クラブアップルの育て方

育てる環境について
クラブアップルは非常に優れた耐寒性を持っているために、育て方に苦労することがないビギナー向けの品種でもあり、マイナス30度の寒気が訪れる厳寒地でも成育でき、冬越しも問題ない樹木として国内でも南から北地方全域に普及の広がりを見せています。耐寒性に優れているものの、真夏の直射日光と同じく、西日が射し込む場所での栽培は避けるのが良く、
日に当たり過ぎることで葉っぱが萎れてしまう場合や枯れ木状態に陥り、果実の付きも悪くなってしまうために半日陰または柔らかな日射しが射し込む場所で栽培管理するのが適しています。クラブアップルは、バラ科でもあるために風通りの良い場所を好み、土壌は耐寒性に優れているため、やや乾燥ぎみの水はけの良い場所が適しています。
さらにバラ科であるゆえに過湿を苦手とし、過湿によるカビなどの病気にかかりやすいために通風性は視野に入れておきたい点です。風通りについては、葉っぱを落としたり、枝を剪定することで過湿環境を打開することが可能であり、通常は葉っぱが落ちる2月から3月に剪定しますが、放置して育てる環境下においては枝の出方が不規則であるため、
間引き感覚での剪定を高温多湿な時期を目安に行います。6月頃からの長雨となる梅雨時期は特に過湿によってうどんこ病などを発生させてしまいやすく、高台や傾斜のある地植えで水はけ良く栽培させるのが最適で、氷点下でも冬越えが可能なため、野生樹として手軽に栽培できます。
種付けや水やり、肥料について
クラブアップルの育て方としては、果実の種子からも育てることが可能ですが、発芽した後、実を付けるまでには数年掛かる場合が多く、長い歳月を掛けずに育てられる株から育てるのが適しています。種子からの場合には果実から種子を取り出し、赤玉土や培養土をポットに入れて種を植え、発芽を促すために日陰で管理します。
生育サイクルとして春先から花が咲き、秋に実を付けて落葉し、冬越しとなります。バラ科としての植物でもあり、肥料不足となると病害虫により枯れ木や枯れ葉、また実付きの悪さに繋がってしまいやすいため、肥料にはリン酸や窒素などのバランスの良い緩効性肥料を土に混ぜあわせて育てますが、窒素過多にならないように注意も必要です。
肥料は新芽に栄養を与えるために春に与えることや、果実を付ける秋に与えるだけではなく、株に栄養を補給させる目的でも施肥は必須であり即効性肥料が適していますが、植え付け時に元肥を十分に与えておき、毎年株元となる周りに有機肥料をすき込みます。水やりでは、表面の土が乾いてからたっぷりの水を与えますが、
地植えで育てる場合には保水性に優れているため、土表面に地割れが見えた段階で水を与えます。枝や株の伸長期や果実の肥大期となる時期には水やりの回数を増やし、落葉後の休眠期は少量の水で冬越へを行います。ヒメリンゴとして盆栽向けとなる低木の品種の場合には、水を含ませた苔を土表面に覆い、苔が乾いてから与えます。
増やし方や害虫について
増やし方としては、果樹や樹木同様に挿し木また接木によって増やすことが可能です。種子から増やすことも可能ですが、上記で述べた通りに実を付けるまでに歳月が掛かるために、挿し木また接木で増やす方法が的確です。クラブアップルを栽培するにあたりネックとなるのが害虫被害であり、バラ科でもあるために毛虫やアブラムシが発生しやすいのも果樹の特徴の1つです。
株に準じて開花前後となる春先に毛虫予防のための防除となる浸透移行性を持つ殺虫剤で、そしゃく性害虫やアブラムシ類などの吸汁性害虫を予防します。枝ぶりが広がり、葉っぱを茂らせる品種や成長具合によって毛虫が大量発生する場合があり、その場合には殺虫剤としての効果として植物の体内に食入する害虫や卵から成虫の各ステージにも高い効果を発揮する殺虫剤を1週間おきに2回程度散布します。
果実を食用として利用する場合には、割り箸などで一匹ずつ駆除する方法が適していますし、枝を揺さぶり振るい落とす方法も適しています。さらに落葉後に関して、枝に枯れ葉が付いたままにしておくことによって食害虫を繁殖させてしまう場合があるため、
取り除いて焼却するのが二次被害に繋げないポイントであり、枝や幹の二股部分に卵が付着している場合にはブラシなどを利用して掻き取っておくことにより、翌春以後の害虫軽減に繋げられます。もちろん、挿し木による仮植えや定植では肥料切れでは幹肌が荒れやすいため、害虫予防に繋げるためには肥料も十分に必要です。
クラブアップルの歴史
科名はバラ科であり属名はリンゴ属、学名をMaluspumilaと言い、和名をヒメリンゴと呼ぶのがクラブアップルです。リンゴの原種に近い品種であり、その種類にはマルス属となる改良された園芸品種も現在では流通し普及しており、マルス属の場合の原産地は主にヨーロッパなどです。クラブアップルの歴史として、
これまで樹木や果樹として栽培されてきたものの、リンゴ原種にもっとも近いことから、1本で結実することのないリンゴの接木台の利用となる受粉樹として原産地では利用されていた歴史が残されています。花木として植栽もされる一方で、原産地となるヨーロッパにおいては球形の果実をつけるため、
観賞用だけではなく果実を加工した利用法も歴史の中に存在しています。生息地においては、野生種となるセイヨウリンゴやエゾノコリンゴなどをクラブアップルとまとめて呼び、生息地を広げた品種改良により花木としての園芸用、果実加工となる果樹用に分けて盛んに栽培されてきた歴史が存在しています。リンゴの歴史は古く、炭化したリンゴが紀元前となる地層から発見されているほどです。
クラブアップルの語源は、その果実を食べると酸味が強く、苦虫を噛みつぶしたような表情となるクラビーな顔が語源の1つです。国内に流通また普及しているクラブアップルは品種改良がされ、和物鉢物として小さな樹丈で小さな実をつけるヒメリンゴの愛称で親しまれており、園芸品種も様々ですが、どの品種も育て方は同じであるため、世界に流通している品種です。
クラブアップルの特徴
クラブアップルは和名をヒメリンゴまた別名にアルプス乙女という名がつけられている小さな果実をつける果樹また園芸樹で、観賞用と果樹の2通りの栽培を可能とする特徴を持ち合わせています。春には品種によって、八重桜などの花形で濃赤色また薄ピンクなどの、大輪となる桜に似た花を付け、直径は大型の物では約5cmに咲き誇ります。
葉っぱの形や大きさも花と比例しており、モスグリーンの淡い色身が特徴で、若葉は柔らかく、落葉樹となる時期には堅い葉へと変化します。9月中旬頃から11月の秋にかけて緑色から赤銅色を帯びる小さな実をたくさん実らせるため、色づく過程を観察する観賞向けとして人気です。上記で述べた通り、クラブアップルは他のリンゴの樹木の受粉樹に適しているだけではなく、
その果実の成分によって他の植物の開花を促す特徴を持つため、他の植物またリンゴの木の近くに定植させて栽培させるのも特徴の1つです。さらに秋口に赤い実を付けるクラブアップルは、生食できる品種も普及しており、肉質は通常のリンゴよりも粗く、酸味が強い実が鈴なりに実るのが特徴です。
小さな実を付ける品種は観賞用であるため、甘味がないものの、ジャムやジュースなどの原料に加工したり果実酒としても楽しめるのも特徴的です。庭樹としても盆栽としての品種がバリエーション豊富に展開されており、樹高は50cm程度となる盆栽向けから2m程度に成長するものまでが展開されています。
-

-
レプトテスの育て方
この花はラン科になります。園芸上においても通常は草花などとなりますが、ランの場合はランに分類されるぐらい特別な存在になり...
-

-
コルディリネ(Cordyline)の育て方
屋内で育てる場合には鉢植えになりますが、葉の色彩を落とさないためにも、日に充分当ててあげることが必要です。5度を超え、霜...
-

-
ホワイトレースフラワーの育て方
この植物においてはセリ科になります。ドクゼリモドキ属となっています。宿根草ですから何年も花をつけることができますが、あま...
-

-
トラデスカンチアの育て方
トラデスカンチアは北アメリカの温帯から熱帯アメリカにかけてを生息地とする植物です。実は日本においても似たような品種の植物...
-

-
なすびの栽培やナスの育て方やその種まきについて
夏野菜の中でもひときわ濃い紫が特徴なのがなすびです。日の光をたくさん浴びて、油炒めにとても合う野菜ですが、家庭でも育てる...
-

-
ヒデリコの育て方
ヒデリコは高さが20~60cmの小柄な植物で、秋には種子を落として枯れてしまう1年草です。湿地や田んぼのあぜなどに生育し...
-

-
キノコ類の育て方
きのこ類の特徴として、シイタケに関してはハラタケ目、キシメジ科、ハラタケ科と呼ばれる種類に属します。それぞれのキノコにつ...
-

-
シュンギクの育て方
キク科シュンギク属に分類されるシュンギクは、20cmから60cmの草丈となる一年草植物であり、春には花径3cmから4cm...
-

-
クコ(キホウズキ)の育て方
この植物はナス科クコ属の落葉小低木ですが、ナスの仲間ということで、その実からは何となく似ているかなという感じですが、色は...
-

-
タチツボスミレの育て方
タチツボスミレに代表されるスミレの歴史は大変古く、日本でも最古の歌集万葉集にスミレが詠まれて登場するというほど、日本人に...




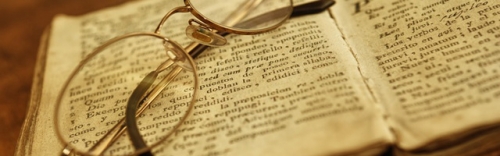





科名はバラ科であり属名はリンゴ属、学名をMaluspumilaと言い、和名をヒメリンゴと呼ぶのがクラブアップルです。リンゴの原種に近い品種であり、その種類にはマルス属となる改良された園芸品種も現在では流通し普及しており、マルス属の場合の原産地は主にヨーロッパなどです。