クラウンベッチの育て方

育てる環境について
地植えでクラウンベッチを育てる場合、何か環境的なことで留意する点があるとすれば、それは増殖しても構わない環境で育てることであります。この植物は本当に増殖力が強いですから、お手入れのできない環境で栽培することは、極力避けた方が良いことになります。基本的に低い気温の環境を好む傾向がありますので寒さに強く、また、暑さに対しましてもそれなりに耐性を備えている適応性の高い植物でもあります。
そしてツルの性質も持ち合せていますので、ツルを様々な場所に伸ばしていきます。伸びたツルはそこに土がありますと根を出して、そこで子株を作り始めます。できた子株も成長するに従いまして新たなツルを伸ばしていき、次なる株を作ります。この連続で次第に勢力を広げていく性質がありますので、
地植えをする場合では育てる環境について、その点への留意が必要になります。その勢いは雑草を押し退ける力がありますから、雑草を防止することにおきましては大いに役立てることができます。ただしそれ故に、栽培する敷地外にツルが出てしまい、野生化することがないように配慮することも大切になります。また、この植物は比較的痩せている土でも育つ場合が多々ありますので、
栽培する場所をそれ程選ばない植物でもあります。それは陽当たりに関しましても同様で、理想的には太陽の光りが良く当たる場所で育てることが理想的になります。しかしそれ程陽が当たらない環境でありましても、ある程度育っていく傾向があります。更にクラウンベッチは、極度に寒冷となる地域以外では、屋外で冬が越せる品種でもあります。
種付けや水やり、肥料について
種付けでありますが、クラウンベッチの種が入手できた場合では、自然界と同様に秋に種をまくことも可能です。また、苗を入手した場合でありますと、春季または秋季に植えることが可能です。そして水やりにつきましては、苗で入手した場合でありますと、まずは水を与えることが大切です。その後植木鉢などに植え付けた場合は、
後日、土の上部1センチ位が十分に乾燥致しましたら、植木鉢の底面から水が出るまで水を与えていきます。もしも水受け皿がある場合では、その水は毎回きちんと捨てることも大切になります。仮に水分が水受け皿にある状態が続きますと、根が腐敗してしまう場合がありますので、水やりでのポイントになります。
また、育て方と致しまして地植えで栽培している場合では、晴天が連続して葉などにハリが無い状態でありますと、水を与えてあげます。その水やりを行う時間帯でありますが、冬季では水が寒さで凍ってしまわないように午前の間に与えることが望ましくあります。夕方や夜では凍ってしまう可能性がありますから、その時間帯は避けることが肝心です。
そして夏季の場合でも、午前の間に与えることが理想的になります。一方、肥料に関してでありますが、この植物では原則的に肥料は殆ど考慮しなくても育てることができます。仮に肥料を与える場合でありますと、即効性のある物は避け、緩やかな効き目のある物が適切になります。また、順調に育っている場合では、肥料は積極的に与えなくても構いません。
増やし方や害虫について
クラウンベッチにおきましては増やし方や害虫についても、それ程難しい点はありません。そもそも増殖力が強い性質を持つ植物ですから、増やし方に関しましては、人為的に行う必要もありません。自然に任せておきますと、余程のことがない限りツルを伸ばして順次増えてくれます。
人為的に行う場合でありますと、伸びたツル先にできた子株を切ることで、株分けによって増やすことも可能です。また、植木鉢で栽培している場合でありますと、植え替えを行うことも大切です。これを行う時期は春季や秋季が良く、少し大きめの植木鉢を用意して植え替えます。そして害虫被害でありますが、この植物では害虫により深刻な被害が出ることは、あまり見受けられない傾向にあります。
中には青虫などが付く場合もありますが、その場合では不要な割箸類を用いて、順次取り除いていくことも対策になります。また、沢山いる場合でありますと、その葉ごとカットして処分することも有効です。一方、薬剤を使用する場合でありますと、葉裏にも潜んでいる場合がありまから、スプレーなどで裏側まで適切に散布することが重要になります。
その他、プランターや植木鉢で育てている場合では、ナメクジが底面から侵入する可能性もあります。その為、用土を入れる前に底面に植木鉢用などの網をセットしてから用土を入れることも、良い害虫対策になります。更に夏季では風通しを良くすることも害虫対策では大切になりますから、蒸れを防止する意味におきましても、ある程度間引くことも良策です。
クラウンベッチの歴史
クラウンベッチはヨーロッパが原産であり、ツルの性質を持つ、マメ目マメ科の多年草です。また、日本におけるクラウンベッチの歴史には、先の太平洋戦争の後、牧場などで用いられる牧草用に導入されたという経緯があります。和名では「玉咲草藤(タマザキクサフジ)」という名称が与えられています。
その他、クラウンベッチはツル性で増殖力が強いことから、緑肥として用いられてきた経緯もあります。これは栽培した後は特に摘み取りや収穫などは行わず、土の中に混ぜ込んで田畑を耕して、そのまま土の肥料にするという活用方法です。こうすることで、農作物などを育てる緑肥としての役割を担い、生産性の向上に貢献してきたという歴史もあります。
そして元々備わっていた高い増殖力から、何時しか帰化植物として日本でも自生するように至りました。現在では北海道の札幌市を始め、本州の千葉県内でもその自生が確認され、日本国内でも生息地の場所を広めています。世界的な分布では、原産地のヨーロッパ以外の北米大陸や、中近東地域などでも外来植物としてその姿が確認されています。
一方、この植物は緑肥の他にも雑草避けとしての活用もされてきた経緯があり、今でもガーデニングなどでは用いられる場合もあります。これらの作用は「アレロパシー」と呼ばれ、現在の農作業におきましても着目されています。そしてクラウンベッチもベッチ類の一つとして、その「アレロパシー」の中に数えられています。
クラウンベッチの特徴
クラウンベッチの特徴と致しまして、茎が真っ直ぐ真上に伸びることはまずなく、斜めに伸びたり、地面を這うように成長していきます。その長さは、概ね1メートル位まで伸びることがあります。また、五月から七月頃にかけて開花する花の特徴は、和名である玉咲草藤の名の通り玉状に咲きますが、見た目の印象はレンゲに近い花を咲かせます。
花ビラは平たくなく、丸みを帯びて膨らんだ印象もあります。色は薄い紫の入ったピンク色の花ビラが上部にあり、その下には白に近い淡いピンク色の花ビラがあります。そしてこの二色が、淡くまばらに美しいコントラストをかもし出しています。見ようによりましては、確かに王冠を連想できる花でもあります。その上、小さな花でもあることから、とても可愛い印象も備えています。
一方、葉の特徴は、先端部に一枚小葉が出ていますから奇数羽状複葉になります。それぞれの小葉は笹の葉にも似た形状を持っておりますが、先端部分はそれ程鋭角ではありません。その為、細長い楕円形の印象があり、その小葉が左右対で生えています。
その他のクラウンベッチの大きな特徴には、繁殖力の強さがあります。定着した場合では、かなり勢いよく増えていきますので、わずか数株植えただけの場合でありましても、気が付けばかなりの広さに渡って覆われてしまう場合もあります。その為この特徴を活かしますと、クラウンベッチはグラウンドカバー用の植物と致しましては、打って付けの存在になります。
-

-
ヤマブキの育て方
春の花が咲き終わる頃になると、濃い黄色の小花をたくさん咲かせ、自然な樹形を保ちやすく、和風な作りの庭などにもよく利用され...
-

-
ナツハゼの育て方
ナツハゼはジャパニーズブルーベリーや山の黒真珠と呼ばれており、原産や生息地は東アジアです。日本はもちろん朝鮮半島や中国な...
-

-
コツラの育て方
この花の特徴はキク科となります。小さい花なので近くに行かないとどのような花かわかりにくいですが、近くで見ればこれがキク科...
-

-
ペンステモンの育て方
ペンステモンが文献に初めて登場したのは1748年のことでした。その文献を書いたのはジョン・ミッチェル氏でした。その当時の...
-

-
モモ(桃)の育て方
桃はよく庭などに園芸用やガーデニングとして植えられていたりしますし、商業用としても栽培されている植物ですので、とても馴染...
-

-
ミズバショウの育て方
ミズバショウの大きな特徴としては白い花びらに真ん中にがくのようなものがある状態があります。多くの人はこの白い部分が花びら...
-

-
木立ち性シネラリアの育て方
木立ち性シネラリア(木立ち性セネシオ)は、キク科のペリカリス属(セネシオ属)の一年草です。シネラリアという語呂がよくない...
-

-
ヘレニウム(宿根性)の育て方
この花に関しては、キク科、ヘレニウム属に属する花になります。花の高さとしては50センチから150センチほどになるとされて...
-

-
きつねのぼたんの育て方
きつねのぼたんはキンポウゲ科の多年草です。分布は幅広く北海道、本州、四国、九州、沖縄や朝鮮半島南部にも存在します。原産は...
-

-
アジサイの育て方
アジサイは日本原産のアジサイ科の花のことをいいます。その名前の由来は「藍色が集まった」を意味している「集真藍」によるもの...




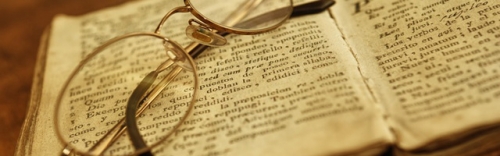





クラウンベッチはヨーロッパが原産であり、ツルの性質を持つ、マメ目マメ科の多年草です。また、日本におけるクラウンベッチの歴史には、先の太平洋戦争の後、牧場などで用いられる牧草用に導入されたという経緯があります。和名では「玉咲草藤(タマザキクサフジ)」という名称が与えられています。