ギリアの育て方

育てる環境について
栽培をするのであればどういった場所で管理をしていかなければいけないかですが、日当たりの良い所です。夏はあまり関係ないので、秋から冬、春、夏先と日当たりのいいところを中心に置くようにすればいいでしょう。この花の特徴としてもある冬の強さですが、どのような寒いところでも対応できるかどうかです。
冬といえば霜がおりるようなところもあります。そのようなところでも大丈夫かどうかですが、霜にはあまり強くありません。せっかく成長したのにも関わらず霜に当たった為に枯れてしまって春に芽を出さないこともあります。寒さが強いところ、霜が降りそうなところに関しては霜対策をするなり、室内で冬を越させて春に表に出すなどをする必要があります。
春と言っても寒い季節があります。そのときに安易に出して霜にやられてしまうことがあります。それも非常にかわいそうなことになりかねません。ですからそのようなことにならないように春に外にだすときには十分に暖かくなってきてからの方がいいでしょう。霜以外に注意が必要なこととしては冷たい風、寒風があります。
霜がなくても日本海側などは冷たい風が吹き荒れるようなことがあります。このようなところはあまり適さないと言えるかもしれません。適さないところでは育てることができないですから、最初から何らかの対策を取る必要があるでしょう。軒下で育てるようにするなどしておくことで寒さに対応することができます。
種付けや水やり、肥料について
育て方において用土としては水はけを考えた土にします。特に配合などのことは気にする必要がなく、一般的な花と野菜の土でも十分育てられるとされています。植木鉢で育てる場合においてはあまり気にする必要が無いですが、庭にまく場合において水はけが悪い時においてはさすがにちょっと調整を施します。行うこととしては赤玉土を混ぜたり、川砂を混ぜたりします。
そうすることによって水はけを良くすることができます。そのまま植えるのではなく、少し環境を整えるだけで育ち方をかえることが可能になります。植え方として寒い地域においては裏技があるとされます。通常は秋まきで冬を越させます。しかし寒い地域は霜が降りることがあり管理が難しくなります。そこで春に植えるようにします。
この植物に関しては直根性があり、移植をあまり好まないとされています。一旦植えたらそこで育てる必要があります。そのことからも、春に地植えをする方法もあることを忘れないようにします。水やりについては少し注意をすることがあります。それは花に水をかけないようにすることです。
水が似合う花などがあり、元気よくさせるために花に水をかけることがありますが、この花は水をかけるとしぼんでしまいます。花が咲いている時に水を与えるときは、植木鉢の横の部分から少しずつかけて花に水が当たらないようにします。もちろん雨も影響してくることになるので、雨がふるようなときは当たらないようにします。
増やし方や害虫について
一年草ですから株分けで増やすことはできません。増やす方法は種まきが最もシンプルで確実になります。花が終わったあとに種を取り、それを植え付けるようにします。芽が沢山出てくるようであれば適度に間引きをしながら育てるようにします。あまり混みあった状態で植えると、たくさんあるようで嬉しいですが、花にとっては非常に育ちにくい環境になっています。
その後根が沢山出てきますし、上の部分でも葉っぱ同士が重なったりすると日当たりなどにも影響してくることがあります。適度な間隔を守るようにすると育ちやすくなります。行っておくといいこととしては支柱を立てることです。種類によって花の高さが異なります。高いものは90センチぐらいになりますが、風などが吹いて折れてしまうことがあります。
そうならないためにも支柱にしっかりと支えさせるようにしておきます。台風の時期ではなくてもちょっとした風が吹いて倒れてしまうことがあります。一度倒れると戻せませんから、先に行っておきます。病気や害虫に関しては特にありません。乾燥に強い、過湿に弱いことを頭に入れて育てるのを心がけます。
植木鉢においては移動ができますが、庭植えの場合は移動が難しくなります。雨は必要ですが、花が開いてからの雨はあまり良くありませんから、屋根をつけるなりも必要になります。雨にあたったから腐るわけではないですが、せっかくの花が早くしぼむのはもったいないので注意をします。
ギリアの歴史
多くの学者がいて、自分の専門分野についての研究をしています。どんどん新しいことが見つけ出せるような分野もありますし、すでに過去の学者などが調べているのでなかなか新しいものが見つけられないケースもあるでしょう。科学技術の分野などなら新たに出せることもあるでしょうが、古くからある学問だとすでに多くのものが発見されています。
植物学に関してだとかなり古くから行われているでしょう。新しい種類が見つけられることはそれ程多くないかもしれません。でも今でもいろいろなことがわかります。元々ある種類だったのが研究によって別の種類になることもあります。これは研究の成果といえるでしょう。ギリアと呼ばれる植物があります。
こちらに関しては北アメリカの西部、カリフォルニアやオレゴンが原産地、生息地の中心となっています。種類としては20種類から30種類近くあるとされています。その中でも主なものとしてはカピタータ、トリコロル、ルテアなどが知られています。この花の名前においては、18世紀のスペインの植物学者の名前が使われているとされています。
その人はギルと言われる人です。ギルが発見などをしたのでそのように付けられたのでしょう。この花については可愛らしい花言葉が付けられています。気まぐれな恋などとなっています。花としては非常に可愛らしい物を咲かせるのでぴったりかもしれません。誕生花の設定もあり、2月の後半から3月の初めに2日設定されています。
ギリアの特徴
種類としてはハナシノブ科になります。別名があり、タマザキヒメハナシノブ、アメリカハナシノブなどの名前が付けられています。草の高さとしては40センチから90センチぐらいになるものもありますが、それ程高くはならないでしょう。耐寒性がありますが、花としては1年草となっています。花が咲くのは5月から7月ぐらいになります。
基本的には秋まきをして、冬を越し、春から夏にかけて咲きます。春まきで咲かせようとすることも種類によってはあります。花の大きさとしては3センチから4センチぐらいになります。発芽をするための温度としては20度ぐらいとされるので、春の4月を超えてくる頃になるでしょう。
育てる上での難易度ではそれほど高くないとされていますからだれでもそれなりに育てることが出来る花と言えそうです。耐寒性があるので冬越はし易いでしょう。耐暑性についてはあまりありません。基本的には花が終わったあとに枯れますからあまり夏越えについては考える必要はないとされています。カピタータと呼ばれる種類はタマザキヒメハナシノブと呼ばれることもあります。
花の色は青、白、紫色などがあります。この種類は比較的高く成長しやすいです。先端に小さな花をたくさんつけることで知られています。トリコロルと言われる種類はアメリカハナシノブと言われることがあります。花茎の先端に1.5センチぐらいの花を数輪咲かせます。同じ種類でも咲き方がかなり異なります。
-

-
トウモロコシ(スイートコーン)の育て方
トウモロコシは夏になるとお店の店先に登場する夏を代表する野菜です。蒸かして食べたり、焼きトウモロコシで食べたり、つぶだけ...
-

-
ボロニアの育て方
ボロニアはミカン科、ボロニア属になります。ボロニアは、3月から4月にかけて綺麗な花を咲かせる樹木になります。ですので、寒...
-

-
クラウンベッチの育て方
クラウンベッチはヨーロッパが原産であり、ツルの性質を持つ、マメ目マメ科の多年草です。また、日本におけるクラウンベッチの歴...
-

-
小カブの育て方
カブは煮物、サラダ、漬物など色々な食べ方が出来る野菜であり、煮込む事で甘みが増すため、日本料理には欠かせない食材となって...
-

-
ゼラニウムの育て方
ゼラニウムの主な原産地は南アフリカです。南アフリカを中心にオーストラリアや中東などの広い範囲を様々な種類が生息地としてい...
-

-
大根の栽培方法を教えます。
日本人の食卓に欠かせない大根は、酢漬けや煮物などで美味しく食べる事が出来ます。特に大根の漬漬けには数多くのバリエーション...
-

-
スイスチャードの育て方
スイスチャードという野菜はまだあまり耳慣れないという人が多いかもしれません。スイスチャードはアカザ科で、地中海沿岸が原産...
-

-
じゃがいもの育て方
色々なアレンジが出来て、老若男女から愛されている野菜が「じゃがいも」です。世界中でポピュラーな野菜であるじゃがいもは、ど...
-

-
二十日大根の栽培方法
二十日大根はその名の通り種まきから一月ほどで収穫できます。家庭でできる野菜の栽培の中でも二十日大根の育て方はとても簡単で...
-

-
ヒイラギナンテンの育て方
ヒイラギナンテンの原産地は中国や台湾で、東アジアや東南アジアを主な生息地としています。北アメリカや中央アメリカに自生する...




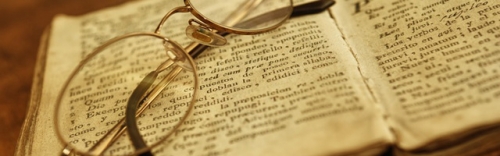





種類としてはハナシノブ科になります。別名があり、タマザキヒメハナシノブ、アメリカハナシノブなどの名前が付けられています。草の高さとしては40センチから90センチぐらいになるものもありますが、それ程高くはならないでしょう。耐寒性がありますが、花としては1年草となっています。