イワレンゲの仲間の育て方

育てる環境について
イワレンゲの仲間は、数年生の植物ですから、上手に育てることができれば、2年目に開花して、枯れるという具合です。葉は白緑色の多肉植物です。秋になると、大きいと20cmにもなる花茎を出して、白くて美しい花を穂状に密生させるという特徴があります。日本固有の種類で、岩上や断崖、石垣の間やわらの屋根などに自生していますが、
今では、自然に生えているものを見ることは、ほとんどない状態です。多肉植物ですから、夏の暑さや冬の寒さが、苦手です。それに、水分過多も枯れる原因になってしまいます。また、日が当たらないと衰退しますから、色んな植物と一緒に繁茂する中では生きていけません。水はけのよさは、他の植物にも必要ですが、
イワサボテンは、周囲の植物のように、水を必要としないため、同じ土壌で育てることはできません。岩場が生息地であった多肉植物ということを考えても、庭先の環境は、他の植物とは違うということを知っておかなければなりません。サボテンと同じような配慮をすると、無事に育てることができます。
肥料や水を不要とする植物は、世話にルーズな人でも育てられますが、ついうっかり一日霜の下に置いてしまったというだけでも弱ってしまいますし、まとめて水をやろうといういい加減さも、腐らしてしまう原因にもなってしまいます。また、葉っぱが萎れかけたりして弱ったときのみ、薄めた液肥を与えるぐらいの配慮が、必要です。その年のうちに花をつけるとは限りませんので、気長にゆっくりと育てる気持ちも必要でしょう。
種付けや水やり、肥料について
イワレンゲは葉が多肉質ですから、他の植物と同じように栽培すると、枯れてしまいます。深めの植木鉢やプランターなどで、人工的に用土を作り、日光や水、風通しなどの管理をします。他の草花と同じ管理をされると、決まって根腐れを起こして枯れてしまいます。多肉植物で一番難しいのは水遣りです。
イワレンゲは、4月から9月の成長期に植え替えと肥料与えをします。植え替えの時の土は、安全でなければなりません。菌に弱い根が腐ってしまいますので、新しいものを購入して、水はけが良いように、砂地と鹿沼土を入れて、植え替えます。しばらくは休ませた後に、植え替え後、最初の水を与えます。
秋までは、屋外で育て、水やりは、植木鉢の土が乾く3日から7日ぐらいの間をあけて行います。雨水が多く当たりすぎるのは良くありませんから、軒下に置くなどの配慮も必要ですが、晴れた日の暑くない季節のころは、日光に当てる必要があります。晩秋になれば、室内で育てます。一年間の管理の仕方次第で開花が決まると言われていますので、
開花は、栽培を頑張った証と言えるでしょう。それも2年ぐらいは待つことになります。それで、その株は枯れてしまいますが、その後に出た新芽を栽培することで、次の年もイワレンゲの次世代を育てることができます。初心者でもできますが、全くの素人では、園芸の常識すら解りませんので、失敗することもあります。タブーな点だけでもチェックしてから、栽培を始めましょう。
増やし方や害虫について
イワレンゲは、病気や害虫などの心配は、殆ど不要だと言われています。けれども、それで安心はできません。多肉植物ですから、日当たりを好みますので、日陰に置く時間が長すぎると、病気になる前に衰退します。また、他の植物でも、多湿のために土に菌が繁殖して、根が腐ったり、葉っぱに白い斑点ができたりと、蝕まれてしまうということがありますが、
イワレンゲは、他の植物以上に菌には弱いですから、そこから病気をもらってしまうということもあります。また、多肉植物には、一般的に虫が付きにくいと言われていますが、栽培した人たちの中には、白い虫に葉っぱや根を食われて、枯れてしまったという体験をした人もいます。鉢をうっかりと雨ざらしにして、黒点病にかかってしまったという経験や、
日当たりや風通しを気にしなかったために、アカダニやアブラムシ、ネジラミやコナカイガラムシなどの害虫にやられてしまったという後悔もあります。けれども、普段から、イワレンゲを観察していれば、全て未然に防げることばかりです。特別な世話をしなくても、特別な気持ちで、毎日観察する愛情を欠かしてはいけません。
その愛情の成果が、数年後に花となります。花茎から多くの花を見せてくれますから、美しく、立派です。さらに、その後には、増やすための新芽を出してくれます。また続けて育てることができる権利をもらうという気持ちになりますから、新たなやりがいが、大いにわいてきます。
イワレンゲの仲間の歴史
イワレンゲの仲間は、ツメレンゲやコモチレンゲなど、葉っぱが多肉状態で、サボテンと育て方と同じ配慮で育てれば、毎年美しい花を咲かせてくれます。原産地は、関東より西の地域であり、日当たりの良い岩の上に生息する植物でしたが、今では、自生するものを見なくなりました。
遠い昔には、岩の上だけでなく、藁屋根の上に、飄々と生きていたりもしました。花茎をにょっきり伸ばして開花しますから、茎が、そのまま花になるという感じです。岩に生えることや葉っぱが蓮のように重なり合っているところから、この名前が付きました。自生種がありませんから、園芸店で購入し、日当たりの良いところに置いて、
通風やみう刷毛の良い粗目の砂を土壌にして育てます。一般的に外で育てますが、水を多く与えるとよくありませんから、雨の多い季節は、軒先など、水分を多く吸わないように配慮する必要があります。また、イワレンゲ周辺の植物が繁茂すると、衰退してしまうことも気を付けなければならないことです。
一般的な植物と、適した環境面で異にすることも多いですから、植木鉢やプランターなどで育てます。庭や軒先に出さないで、日光のよく当たる部屋の窓際に置いて、高温と冬の寒さに気を付けながら育てるというのも良いでしょう。
そうすれば、他に何も特別な世話が必要ありませんから、後は、秋に見られる花茎の出現を楽しみにします。自生種が、ほとんどない植物ですから、春先に新芽を切って、次々と増やしたいという人もいるでしょう。たくさんの花がつくと、とても美しいですから、増やすことは、園芸家にとって、喜びの倍増につながるでしょう。
イワレンゲの仲間の特徴
イワレンゲの仲間は、関東地方より西の四国、九州に分布しており、岩や石垣、藁屋根に自生している多肉植物で、葉に水を蓄えていますから、他の植物が必要とする水や土壌は、不要に近い植物です。けれども、日当たりだけは、必須です。イワレンゲを、庭に植えると、背の高い植物たちに日光を遮られますし、自然の雨水でさえも、
多めであると朽ちる可能性もありますから、植木鉢などで、岩場と同じような環境を整える必要があります。植木鉢で育てるにしても、排水性の良いもので、大きめのものを必要としますし、用土は、多肉植物ということを考慮して、水はけを気を付けなければなりません。
また、根がデリケートで菌に侵されやすいことから、砂と一緒に庭先の土を混ぜるということも、できません。春や秋の陽気には、日に十分当てるようにして、真夏の激暑や梅雨時は軒先、肌寒くなってくるころには室内に入れるようにするなど、その時その時に応じて、場所を移動することも大事です。サボテンを育てている人は、
その土を利用しますが、そうでない人は、園芸店で安心な粗目の砂と鹿沼土を購入するなどして、安全な環境を整えましょう。花を咲かせるために環境づくりを頑張り、栽培に一生懸命になっても、二年か三年は、花を見ることができない植物です。初心者向きの園芸植物といっても、その間、時に応じた配慮ある世話を続けることができるかどうかが重要です。その代り、花が咲いた時のうれしさは、非常に大きいでしょう。
-

-
ヘレボルス・アーグチフォリウスの育て方
特徴としては花の種類として何に該当するかです。まずはキンポウゲ科になります。そしてクリスマスローズ属になっています。属性...
-

-
イレシネの育て方
イレシネは、熱帯アメリカやオーストラリア、ブラジル南部、エクアドルなどを中心に温帯地方に約40~70種類ほど自生している...
-

-
スキミアの育て方
「スキミア」はミカン科ミヤマシキミ属、日本を原産とする常緑低木の一種です。学名は「シキミア・ジャポニカ」、英名を「スキミ...
-

-
サフィニアの育て方
この花の特徴としては、キク亜綱、ナス目、ナス科、ペチュニア属に属する花になります。元々ペチュニアが原種ですが、日本の会社...
-

-
アイノカンザシの育て方
アイノカンザシはユキノシタ科の植物ですが、別名をエリカモドキともいいます。植物の中でも呼び名がとても印象深く、イメージも...
-

-
プテロスティリスの育て方
プテロスティリスは、オーストラリアの南東部が主な生息地であり、ニュージーランドやニューカレドニア、パプアニューギニアと言...
-

-
ブルビネラの育て方
ブルビネラは南アフリカやニュージーランドを原産とする花であり、日本で見ることが出来るようになってきたのはごく最近のことで...
-

-
アニスヒソップの育て方
アニスヒソップはシソ科 カワミドリ属の常緑多年草です。原産は北アメリカから中央アメリカで、森林や比較的降水量の多い高原な...
-

-
パパイヤの育て方
パパイヤはメキシコ南部から西インド諸島などが原産と言われており、日本国内においても熱帯地方が主な生息地になっており、南国...
-

-
エレムルスの育て方
花の特徴では、ユリ科に該当します。花が咲く時期としては4月から7月になります。咲き方としては1年を通して咲く多年草になり...




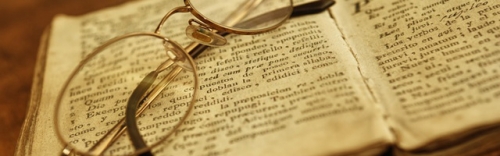





イワレンゲの仲間は、ツメレンゲやコモチレンゲなど、葉っぱが多肉状態で、サボテンと育て方と同じ配慮で育てれば、毎年美しい花を咲かせてくれます。イワレンゲの仲間は、関東地方より西の四国、九州に分布しており、岩や石垣、藁屋根に自生している多肉植物で、葉に水を蓄えていますから、他の植物が必要とする水や土壌は、不要に近い植物です。けれども、日当たりだけは、必須です。