イワコマギクの育て方

育てる環境について
元々が山野草として栽培されているため、耐寒性を持っていることから育てる環境を選ばないのも特徴ですが、氷点下となる地域での育て方としては根っこを張り巡らせるために枯れ葉などを用いり、マルチングして防寒させた環境下で育てる方法が適しており、はり地植えを望む場合に株を充実させることを可能にしています。
育て方のポイントとして、寒さに強いものの日当たりの良い環境を好むため、日陰ではない場所で育てることはもちろん、水ハケの良い土壌環境が必要です。さらにイワコマギクは越冬時の湿度で過湿を嫌う品種でもあるため、土は湿り気や吸収しにくい山野草専用となる土壌環境が最適です。
さらに耐暑性としては高温多湿を嫌う品種ですので、温暖な地域においては多年草としての栽培ではなく、一年草として栽培する方法が適しており、温暖な地域で長く楽しむ場合には光合成を促す昼間に日を当てた後は、半日陰での環境下で育てます。さらに耐寒性においては他の花植物よりも強いため、葉が傷むことがなければ防寒対策の必要性はなく、
花芽分化においては低温栽培法も重要とするので、冬越しさせる場合には暖かい室内で管理してしまうと春に花が咲かないケースも出てくるため、育てる環境には注意が必要です。霜などで枯れる心配がある場合にはプランターなどに移した後、玄関などの冷暗所で管理することで花付きを良くすることが可能で、花が咲き始める頃にプランターから土壌へ植え替えるのが適しています。
種付けや水やり、肥料について
イワコマギクの種付けとして、まず種蒔きに最適となる適期は6月頃から9月頃であり、梅雨に入る前の早めの種蒔きを行うことで株を大きくすることに繋げることができるだけではなく、湿気を嫌う品種であるために梅雨時期を避けた早めの種蒔きで成長を促すことにも繋げられます。晩秋となる時期の種蒔きでは成長を促す気候に左右されやすいため、
翌春に花が咲かない場合があるため、種付け時期には気を付けたいポイントの1つです。種の蒔き方として発芽させるための適温が18度から25度であり、種がうっすら隠れる程度の覆土に留めて発芽させます。約2mm程度の薄い層の土で覆い、発芽までは約一週間程度かかり、本葉が3枚程度になる時期を見計らい浅植えを行います。
この時の株と株の間は20cm程度で、土壌としては上記で取り上げたように水ハケの良い土を好むため、山野草専用となる土が最も適しています。苗が十分育ってからポットに移し、さらに根っこがポット内で十分回ってから花壇またはプランターに植え付けることで定着します。水やりでのポイントは、
水ハケの良い環境を好むことから表面の土が乾いた頃に湿らせる程度の水をあげるのが適しており、肥料は液体肥料を花が咲く前の晩秋時期に一度と、春先に一度与える程度で丈夫に育つのも特徴です。というのも、生息地が山野の過酷な環境下で育ってきたため、追肥などの栄養が少ない土壌でも根付きが良く、肥料を不要とする育てやすい特徴を持っています。
増やし方や害虫について
イワコマギクは多年草であり、増やし方としては花弁の裏側が赤い品種となるタイプにおいては挿し木での増やし方が可能となっており、挿し木での増殖での注意点としては高温時を避けることで、生育がより向上する適時としては秋口に増やすのが適しています。さらに増やし方の1つとしては、花の観賞が終わった後のランナーを挿し芽で行うことが可能です。
さらにイワコマギクは由来となる虫除け草としての機能も持っていることから、害虫をあまり寄せ付けないのも魅力であり、冬越しして赤いつぼみが実る春先以降に一般的に多いアブラムシが付きやすく、春先から定期的にアブラムシ専用となる殺虫剤を土壌と茎部分に散布しておくとアブラムシによる二次被害を防ぐことが可能です。
病害虫に非常に丈夫なのは、山野草として生息してきた環境によるもので、病気にかかりにくい特徴を持っています。イワコマギクはほふく性の植物であるため、梅雨などの雨に弱く、花ボトと呼ばれる灰色カビが付く場合があり、水ハケには注意しておきます。さらに地域によっての害虫被害として、
アブラムシだけではなくウリハムシモドキなどの甲虫が付きやすく、気候や環境によって大量発生する前に殺虫剤で予防することが重要ですが、発生してしまった際には殺虫剤ではなく、手で捕まえて潰すことが適しています。草丈が低いために、周囲に雑草が生えていることで害虫を寄せ付けてしまう場合もあるため、雑草取りも行います。
イワコマギクの歴史
イワコマギクは和名としてだけではなく、原産地となる地中海海岸地方においてはアナキクルスとしての洋名を持つ外来植物であり、宿根草として現在では広く出回る植物です。このイワコマギクは、除虫菊が学名の由来となる歴史が存在しているのも特徴で、原産地でアナキクルスとして発見され、種小名であるpyrethrumは火と群がるに由来し、
根っこ部分は燃焼したようなニオイを発する除虫菊を意味しており、この除虫菊の和名はシロバナムシヨケギクと言われているように、属名がPyrethrumで火を指しています。除虫菊は虫除けとなる殺虫剤にも利用されるピレトリンを含んでおり、このピレトリンは国内では蚊取り線香として使用されており、歴史を紐解いていくと、
かつてイワコマギクは国内でも虫除け目的として盛んに栽培されており、ピレトリン効果による利用法が原産地をはじめ、輸出が行われる古年代から広がる歴史が存在しています。アナキクルスとしての別名を持ち、生息地では薬用植物として採取されており、イワコマギクの根っこを煎じて強壮薬などに用いる利用法が原産地では現在も行われています。
秋口に根っこを収穫する目的での栽培も行われており、観賞用だけではない利用法となる歴史が存在しています。生息地一帯ではピレトリンを含むことから害虫などの被害が少なく、植物の栽培に適していることも重なり、船などで流通目的で物を輸出させる際の木箱の敷き詰め草としても用いられるなどの歴史も虫除け効果の高い植物ならではです。
イワコマギクの特徴
キク科であり、一年草ではなく多年草であるのが特徴の植物であり、生息地は元々山野であったこともこの植物の特徴の1つです。春の芽出しにあわせて花を咲かせると、6月の初夏頃まで咲き続けるために長きにわたり観賞できる植物です。イワコマギクの葉っぱはグレーかかった濃い緑色であり、細かな羽状に切れ込みが入っているのも特徴的で、
放射線状となるマット状に広がる茎によってグリーンガーデンに向いている特徴を持っています。さらに花は、内側が白色の舌状花であるものの、その花弁の裏側は赤色をしています。花径は約3cmで草丈は10cmから30cmとなり、つぼみの時には赤色をしており、黄色の花芯と白と赤のクリスマスカラーとなるコントラストがガーデニング通の間で人気となり、
近年普及率の高い山野草としての特徴も持っています。裏側が赤色の品種や近年では赤に白が混じるストライプの色でも栽培されており、元々は虫除けとなる山野草として普及しているため、鉢植えやロックガーデンに向いており、早春からの鉢花として定着しています。
4月の春先から白い花を咲かせることから庭のグランドカバーに適しており、ガーデニングビギナーな方にも育てやすい品種でもあります。さらに香りの特徴として、除虫菊の仲間でもあることから、強い薬草に近いニオイを発するのが特徴であるため、その花や葉っぱ、茎は芳香目的として利用するのではなく、害虫対策として利用されるのも特徴の1つです。
-

-
フェイジョアの育て方
フェイジョアは1890年にフランス人の植物学者であるエドアールアンドレによってヨーロッパにもたらされた果樹です。元々は原...
-

-
レウイシア・コチレドンの育て方
この植物の特徴は、スベリヒユ科、レウイシア属になります。園芸上の分類としては山野草、草花となることが多くなります。花の咲...
-

-
サルピグロッシスの育て方
サルピグロッシスはナス科サルピグロッシス属(サルメンバナ属)の一年草または多年草です。その名前はギリシャ語のsalpin...
-

-
クンシランの育て方
クンシランはヒガンバナ科クンシラン属で、属名はAmaryllidaceae Clivia miniata Regelとい...
-

-
ノウゼンカズラの育て方
ノウゼンカズラの歴史は古く、中国の中・南部が原産の生息地です。日本に入ってきたのは平安時代で、この頃には薬用植物として使...
-

-
ネムノキの育て方
ネムノキは原産地が広く、日本や朝鮮半島、中国、台湾、ヒマラヤ、インドなどが代表的なものとなっています。このほかにもイラン...
-

-
アサギリソウの育て方
アサギリソウは、ロシアのサハラン・日本が原産国とされ、生息地は北陸から北の日本海沿岸から北海等、南千島などの高山や海岸で...
-

-
ヒヤシンスの育て方
ヒヤシンスは、ユリ科ヒヤシンス属に分類される球根性多年草です。ギリシャなどの地中海沿岸から、イラン、シリア、トルコ、など...
-

-
ベニバナツメクサの育て方
ベニバナツメクサの一番の特徴は、鮮やかな赤色の花です。成長すると茎はまっすぐに伸び、赤い小さな花がまっすぐな茎の先に、円...
-

-
ペペロミア(Peperomia ssp.)の育て方
ペペロミアの原産地はブラジル、ボリビア、エクアドルなどで、主な生息地は熱帯や亜熱帯です。約およそ1400種類もの種類が存...




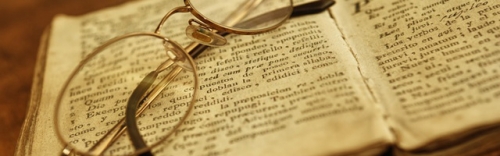





イワコマギクは和名としてだけではなく、原産地となる地中海海岸地方においてはアナキクルスとしての洋名を持つ外来植物であり、宿根草として現在では広く出回る植物です。キク科であり、一年草ではなく多年草であるのが特徴の植物であり、生息地は元々山野であったこともこの植物の特徴の1つです。春の芽出しにあわせて花を咲かせると、6月の初夏頃まで咲き続けるために長きにわたり観賞できる植物です。