イイギリの育て方

育てる環境について
イイギリの育て方というのは、それほど難しいものではありません。これは自生している野生のものを確認するとわかります。公園や庭園はもちろんですが、街路樹にも実際に植栽されています。つまり、育てる環境というのはそれほど条件が厳しくないということです。強いて挙げるとすれば、日当たりが強すぎないところか、
もしくは少し日陰のある湿り気のある用土に移植すると良いです。植栽をすると春頃になれば、葉をつけた幹が縦に伸びます。この伸びは非常に急速なものなのですが、数ヶ月でその伸びは止まります。だいたい夏の6月か7月になると、縦への成長が緩やかになります。そうして縦方向の伸張が止まると、次は葉脈から側枝に向かって水平方向に伸び始めていきます。
この伸張は秋頃から冬頃になると止まります。なぜなら他の樹木と同じように冬になると冬眠活動に入ります。なお、この休眠活動によって本来的に寒さに弱いイイギリが越冬することができる理由でもあります。こうして成長を停止して、春の4月や5月頃になると花を咲かせます。このようにして1年が過ぎるのですが、
その1年間で幹と側脈が非常に伸びるわけです。ちなみに、樹齢確認もこうしたことからわかります。1年間でどのくらい伸びるのかはわかってるので、その伸び具合でだいたいの樹齢が判明します。このように場所はあまり問わず、しっかりと成長してくれますので、庭に植栽したくても育てた経験がないという人でも、心配は不要です。
種付けや水やり、肥料について
栽培方法としてアドバイスするとしたら、いくつかポイントがあります。1つは肥料についてです。樹木の種子を購入したら、播き方を上手く行うことが大切です。適切に播くことができれば、上手く発芽させることが可能になります。播き方を上手く行う上で重要なことは、種まきの場所、用土、水やりの3つが重要になりますが、ここではまずは用土から書いていきます。
イイギリの場合は、特別な用土を用意する必要はありませんが、水はけのよいものが良いです。水はけの良い用土というのは、具体的には、水をそそいだときにしっかりと吸収してくれる用土のことです。これはスポンジに水をあげるときと同じようになると理想的です。反対に、水をかけても、あまり吸収しないものは水はけが悪いということです。
このように水はけがよければ、常に水が保たれているということですから、樹木が水を必要としたときに、根がすぐに水を吸収することができるというわけです。もちろん、水分が多すぎて泥状態になっていると、種子にとっては非常に危険な状態です。なぜなら、種子は水分も必要としますが、酸素も必要です。
常に水浸しの状態であれば、発芽することができないので、その点のみ注意が必要です。そのため、水やりも春から夏にかけて定期的に散水する程度で問題ありません。くれぐれもやりすぎには注意が必要です。種まきの場所としては、なるべく日当たりのよくないところがお勧めです。そうして種から育てると7年前後で花や果実を付け始めます。
増やし方や害虫について
増やし方について述べていきますが、ここでのポイントは種子の性質をきちんと把握することです。イイギリの種子は後熟種子に分類されます。種まきをするときは春頃に行うことがベストです。そのため、春頃まで種子を保管しなければいけません。その保管方法は冷蔵庫がもっとも適しています。
それというのも、乾燥してしまうと発芽率が急激に低下するからです。低温で保管すると発芽率に影響は与えません。このように低温で保管させて休眠状態にさせた後、後に成長させることができる種子のことを後熟種子といいます。後熟種子は他にも、イチョウやシナノキなどがあります。
こうした種子の取り扱い以外にうまく増殖させる方法は、接ぎ木が挙げられます。接ぎ木は早い段階で行うことが重要です。もちろん、実生でも増やすことができますが、非常に時間がかかります。それというのも、イイギリは雌雄異株に分類されるからです。つまり、自分が育てているイイギリが雄木なのか雌木なのかは、花がつくまではわからないというわけです。
しかしながら、種から育てた場合、花や実をつくのに7年前後もかかります。その判定基準は下記のとおりです。もし雄木だった場合は雄しべだけの花が咲き、雌木の場合は雌しべだけがついた花が咲くというわけです。こうしたことから、判定だけで10年近くもかかりますので、雌木から穂木をとって接木することが一般的です。非常に健康的な樹木なので、害虫もよりつかない強い樹木ですので、育てると長期間楽しむことができます。
イイギリの歴史
イイギリは日本原産の落葉高木です。昔から人々に親しまれてきた木ですが、それはイイギリという名称からもわかります。すなわち、昔、イイギリの大きな葉っぱでおにぎりを包んでいたことが、その名前の由来です。ご飯のことを「飯」と書いて「イイ」と言いますが、昔は、今とは異なって徒歩でいろいろな場所に旅にいく必要がありました。
農民であればその土地で生活するので、頻繁に旅にでることはありませんが、商人の場合はいろいろな地方に出かけていく必要性があります。そうした人たちが遠方に出かけにいくときに、おにぎりを包んだのがイイギリの葉というわけです。葉っぱが非常に大きいハート形のため、包みやすかったという利点がありました。
また、別名として「ナンテンギリ」という呼び名も持っています。いずれも漢字で書くと次のようなものになります。イイギリは「飯桐」であり、ナンテンギリは「南天桐」です。両方に共通しているのは「桐」ですが、これは葉っぱが桐の葉っぱに似ていることに由来しています。ちなみに、ナンテンギリの「ナンテン」は果実がナンテンに似ていることが由来です。
生息地としては、本州はもちろん、九州、四国、沖縄とほぼ日本全国に自生しています。これは果実が要因です。鳥にとってこの果実が非常に美味に感じるので、昔から鳥に広範囲に運ばれたわけです。そのように広範囲に自生しているということも人々が親しみを持つ理由になるのですが、桐の代用品としても使われていました。下駄や箱などがその典型例です。
イイギリの特徴
イイギリの特徴についていろいろな視点から書いていきます。原産地は日本です。分布としては本州から四国、九州、沖縄とほぼ日本全国にわたります。ただし、北海道、東北地方、北陸地方といった比較的寒い地域には自生していません。特徴的なのは、その葉っぱです。非常に大きくハートのような形をしています。
桐の葉っぱに似ていることから、イイギリという名前が付けられたほどです。樹高は非常に高く15メートル前後まで伸びます。幹はミズキと似ています。非常に太くかつ曲がることなくまっすぐに伸びます。また、両性花から進化した樹木という他の樹木とは異なる性質も持っています。いわゆる雌雄異株で花をつけます。
時期としては春頃の4月を境にして咲き始めます。雄花は数多くの雄しべを持ち、雌しべは1個だけ持ちます。この特徴は他にはアオハダに見られます。アオハダも雌雄異株です。いずれも両性花から進化した樹木で植物学上、稀有な樹木とされています。果実については、秋頃の10月から成熟しだして直径1センチ程度の実を付けます。
色は赤色で、これはナンテンの実に非常に似ています。この果実が冬の時期の野鳥の貴重な食料になっています。実はイイギリが非常に幅広い分布で自生しているのは、このためです。鳥が冬の間にたくさん摂取することで、分布が広がったというわけです。
ちなみに、鳥が食べる果実の70%以上が赤い果実か黒い果実ということが科学的に立証されています。これは赤色もしくは黒色であることが、その果実が熟していることを示すからです。そういうことからも、イイギリの果実は赤い果実なので、鳥の注意を非常にひきつけます。
-

-
ビヨウヤナギの育て方
ビヨウヤナギの生息地は中国ですが、仲間であるヒペリカム・オトギリソウ属には日本原産種もあります。薬草として用いられるオト...
-

-
いちごの育て方
いちごの歴史は古く、すでに石器時代から食べられていました。南米や北米が生息地になり、野生の果実は甘味が少なく大きさも小粒...
-

-
サルピグロッシスの育て方
サルピグロッシスはナス科サルピグロッシス属(サルメンバナ属)の一年草または多年草です。その名前はギリシャ語のsalpin...
-

-
ミセバヤの育て方
特徴として、バラの種類であることがわかっています。バラ亜綱、バラ目、ベンケイソウ科、ムラサキベンケイソウ属になります。園...
-

-
マンゴーの育て方
マンゴーは、ウルシ科のマンゴー属になります。マンゴーの利用ということでは、熟した果実を切って生のまま食べるということで、...
-

-
植物の育て方について述べる
世の中に動物を家で飼っている人は多くいます。犬や猫、爬虫類などを飼って家族と同然の扱いをして、愛情深く飼育している場合が...
-

-
ベゴニア・センパフローレンスの育て方
ベゴニア・センパフローレンスはシュウカイドウ科ベゴニア(シュカイドウ)属に分類される常緑多年草です。ベゴニアはとても種類...
-

-
ピーマンの育て方
現在は家庭の食卓にも馴染み深いピーマンですが、実はナス科の植物だということはご存知でしたか? ピーマンは熱帯アメリカ原産...
-

-
宿根アスターの育て方
アスターは、キク科の中でも約500種類の品種を有する大きな属です。宿根アスター属は、中国北部の冷涼な乾燥地帯を生息地とす...
-

-
ヨウシュコバンノキの育て方
日光を浴びる事で、成長を促進させないと、葉っぱの白い斑が消えてしまう事があります。白い斑は新芽の間の事なので、しっかりと...




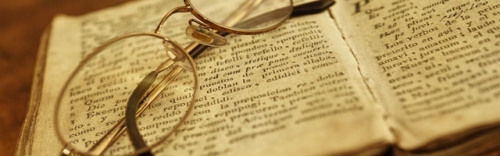





イイギリは日本原産の落葉高木です。昔から人々に親しまれてきた木ですが、それはイイギリという名称からもわかります。別名として「ナンテンギリ」という呼び名も持っています。いずれも漢字で書くと次のようなものになります。イイギリは「飯桐」であり、ナンテンギリは「南天桐」です。