ヨツバシオガマの育て方

育てる環境について
高山植物は標高の高い涼しい環境で育てる場合意外は、その栽培環境を整える事がとても重要になっています。また、ヨツバシオガマは湿気を好みますので、常に湿った環境にし、時には日光を浴びせなければなりませんし、夏の暑い日には涼しい環境にしてあげなければなりません。
季節や環境によって移動させる事ができるように鉢植えなどに植えたほうが育てやすく、できれば専用の環境を整える必要があります。とくに夏の高い気温にさらしますと根腐れをおこして、貴重な芽が枯れてしまう原因になりますので、なるべく涼しい環境に置いてその育成をじっくりと気長に見守ります。
また、シオガマギク属であるヨツバシオガマは半寄生植物ですので、他の植物と一緒に栽培しなければ育つ事が難しく、栽培は不可能とも言われています。寄生植物は他の植物に寄生し栄養分を吸収して生育する植物の総称で、寄生根と呼ばれる特殊化した根で宿主の植物組織と結合して栄養分を吸収して初めて育つ事ができます。
半寄生植物のヨツバシオガマは、光合成によって炭水化物を自分で合成することができますが、宿主となる植物と一緒に栽培しなければ発芽する事はとても難しく、宿主の植物を持たない栽培に成功した例は見られていません。栽培するときはシオガマギク属が主に宿主にするイネ科の植物などと一緒に栽培し、イネ科の植物が常に元気に育つ環境にしておくと、ヨツバシオガマ自信もその養分を吸収して元気な芽を出して成長してくれます。
種付けや水やり、肥料について
ヨツバシオガマは、コスメススキやムツノガリヤスなどのイネ科の植物と一緒に育てていきます。高山植物の多くは根をいじられることを嫌いますので、まずはイネ科の植物が育ちやすい環境に整えて、イネ科の植物が元気に育ってから種をまいたほうが安心です。どうしても植え替えが必要な場合は鉢を抜き取るようにしてあまり根を触らないように行います。
湿気を好むヨツバシオガマですが、水を与えすぎますと、今度は一緒に育てているイネ科の植物が根腐れをおこして枯れてしまいます。ミズゴケなどを置いて乾燥を防ぐ方法もありますが、土の中にピートモスを混ぜますと、保湿しながら通気性のよい環境にする事ができますのでお勧めですし、腐葉土を一緒に入れても良いかもしれません。
化学肥料や植物由来の肥料は一般的な環境で育つ植物に適しているので高山植物には合わない場合があります。液肥なら成長に合わせて利用できますし、根から吸収しやすいですので点滴を打ったように元気に育ってくれます。標高の高い場所に生息する植物が気温の高い環境で育つためには従来の2倍~4倍ものエネルギーが必要となります。
夏場に放置しておくとエネルギーが足りずに根腐れをおこしてしまいますので、たっぷりと肥料を与える事も栽培する上では重要な要素です。栄養となるイネ科の植物も元気に育たなければなりませんので、新しい芽が次々に出るように小まめに手入れをし、新しい種も撒いておきます。
増やし方や害虫について
標高の高い環境では病気や害虫が少ないため、高山植物の多くは害虫などに弱く、一般植物の育つ環境で育てる場合には害虫、病気にも注意が必要です。アブラムシを始めナメクジや小さな青虫、梅雨の次期になるとハダニやアカダニ、カイガラムシが大量発生しますし、湿気を好むダンゴムシやヤスデなど季節ごとに害となる虫が発生するので、見つけ次第すぐに駆除を行なわなければなりません。
駆除するよりも発生する前に定期的に予防措置をとってなるべく根に負担を掛けないようにしたほうが育ちやすいですので、アカダニなどどうしても専用薬剤でなければ駆除できないものにのみ予防措置として使用するとかなり効果があります。また、殺虫剤を使用しすぎると免疫力のある害虫になってしまいますので、適度な量が望ましいとされています。
立ち枯れ病や白絹病などには殺菌剤を季節の変わり目に使用すると病気の拡大を防ぐ事ができます。もしも病気のものを見つけた場合は残念ですが他に移る事を防ぐために処分します。ヨツバシオガマ自体栽培するのが困難ですので、増やしていくのもかなり気を使わなければなりません。
失敗する事が当たり前ぐらいの気構えで、時間をかけてゆっくりと今の環境に適した栽培方法を見つけていきます。気温や湿度の変化、栽培方法などを記録しておくと問題点も見えてきますし、新しい発見があるかもしれません。発芽しない場合は寄生するイネを変えてみたり、水の量を調整する事も必要です。
ヨツバシオガマの歴史
ヨツバシオガマ(四葉塩竈)学名Pedicularisjaponicaは、初夏から夏の、北海道から本州中部の高山の湿地を生息地とする、シソ目ハマウツボ科シオガマギク属ヨツバシオガマ種の多年草の高山植物です。氷河期に日本列島へ南下して来た種が、氷河期に北へ戻れなくなって取り残され、高山などの比較的寒い場所に何とか生存適地を見つけ出して現在に至っているといわれ、
それぞれの高山で遺伝子を交換することなく、独自の進化を遂げていった中の一つとして、日本原産の種と考えられています。北海道や東北地方に分布している大型の種をキタヨツバシオガマと呼び、以前は同属のエゾヨツバシオガマの変種ともされていましたが、DNAなどの比較から別種であることが分かり、現在は分離されています。
ヨツバシオガマの名前の由来は、塩を作るために海岸に立ち並んだ塩釜が浜を美しく彩っている景観を「浜で美しい」と言うことから「葉まで美しい」にかけて名づけられたと言われていますが、地名としての塩竈の浜のどこか寂しげで趣のある景色の事を美しいとして、美しさと趣のある葉の姿から名づけられたとも言われています。
ヨツバという名どおり四枚の葉を輪のように生じさせることでも知られていますが、時おり5~6枚の葉を茂らせている事もあります。変種としてレブンシオガマ、クチバシオガマなどが挙げられますが、はっきりとした位置づけがされておらず、詳しい研究がされています。
ヨツバシオガマの特徴
ヨツバシオガマは高山植物に詳しい方でも他の種との判別が難しい植物です。シオガマ属の中でも多くの場合に四枚の葉を茂らせ、花の色が薄紫色であるのも特徴として挙げられます。よく似た種類のミヤマシオガマなどが岩場などに生えるのに対し、ヨツバシオガマはやや湿った風当たりの強い、高山植物の生息地の中でもやや低い場所を好みますので、
自生している場所も判断材料になります。高さは20~50cmに育ち、名前の由来のとおり、シダのような葉が茎の節ごとに4個ずつ輪を描くように生じます。花期は6月から8月頃に見られ、7月下旬から8月上旬に開花のピークが訪れるので、夏季休暇の間、ハイキングに訪れる登山者の目を楽しませてくれます。
花びらが薄紫色なのもその特徴として挙げられ、花びらは2唇形、上唇の先の部分は濃い紅紫色で鳥のくちばしの様に長く先が垂れ下がり、下唇は大きく3裂して上唇を支える下顎のように広がって垂れ下がります。このくちばし部分の長い種類はクチバシシオガマと呼ばれ、葉が5~6枚となっている礼文産の種はレブンシオガマと呼ばれます。
よく似たタカネシオガマは全体的に少し小さく、花の部分もミヤマシオガマに似ていてヨツバシオガマとは異なるために見分けがつけられます。高山植物ですので気温の高さや害虫に弱く、一般家庭での育て方が難しいとされていますが、自宅で高山と同じ環境を作ることができれば栽培できるため、高冷地ではなくとも栽培に挑戦して見事に花を咲かせることに成功した例もあります。
-

-
ローズマリーの育て方
その歴史は古く、古代エジプト時代の墓からローズマリーの枝が発見されているように、人間との関わりは非常に古くからとされてい...
-

-
タアサイの育て方
中国が原産となるタアサイの歴史は中国の長江付近となる華中で、栄の時代となる960年から1279年に体菜より派生したと言わ...
-

-
オーストラリアン・ブルーベルの育て方
豪州原産の”オーストラリアン・ブルーベル”。白やピンクや青の花を咲かせるきれいな植物です。名前にオーストラリアンと付いて...
-

-
ガマズミの育て方
ガマズミはその名前の由来がはっきりとわかっていません。一説によるとガマズミのスミは染の転訛ではないかというものがあり、古...
-

-
ヤブコウジの育て方
こちらの植物は被子植物、真正双子葉類、コア真正双子葉類、キク類になります。更にツツジ目、サクラソウ科、ヤブコウジ亜科とな...
-

-
ゴーヤ(にがうり)の育て方
ゴーヤの育て方、別名にがうりとも呼ばれています。ゴーヤ栽培は比較的簡単にでき、地植えやプランターでも気軽に出来て、緑のカ...
-

-
コナギの育て方
コナギと人間の歴史は大変古くからあります。特に日本人をはじめ、アジア諸国と古くかかわりを持ってきた植物といえるでしょう。...
-

-
ツリージャーマンダーの育て方
シソ科ニガクサ属で、原産は地中海沿岸西部で、常緑小低木である植物がツリージャーマンダーで、学名はテウクリウムフルティカン...
-

-
サルビア・レウカンサの育て方
サルビア・レウカンサの原産地はメキシコや中央アメリカです。別名を「メキシカンブッシュセージ」「アメジストセージ」といい、...
-

-
ディケロステンマの育て方
ディケロステンマは原産が北アメリカ西海岸のワシントン州西部からカリフォルニア州中部に分布しています。別名をブローディア・...




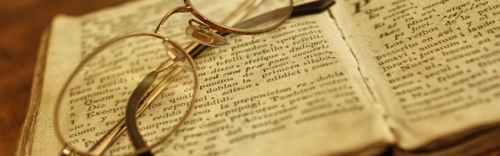





ヨツバシオガマ(四葉塩竈)学名Pedicularisjaponicaは、初夏から夏の、北海道から本州中部の高山の湿地を生息地とする、シソ目ハマウツボ科シオガマギク属ヨツバシオガマ種の多年草の高山植物です。氷河期に日本列島へ南下して来た種が、氷河期に北へ戻れなくなって取り残され、高山などの比較的寒い場所に何とか生存適地を見つけ出して現在に至っていると言われています。