ベニバナツメクサの育て方

育てる環境について
もともと湿気が少ない地域が原産地なので、日当たりや水はけが良い場所を好みます。前述の通り、耐寒性があり、寒さには強いのですが、日本の高温多湿な夏の暑さには弱く、暑さのダメージを受けると枯れてしまいます。そのため、日本では夏を避けて栽培します。種まきは秋ごろ行い、冬を越して春ごろ花を咲かせます。日陰やジメジメした場所は、
栽培する場所としてあまり向いていません。マメ科の植物は、根の部分にチッソを多量に含み、さらに固定する作用があると言われています。そのため、肥沃な土壌に改良することを目的として植えることもあります。マメ科であるベニバナツメクサにも、チッソが含まれています。植えることで土に栄養補給が行なわれ、土壌改良にも繋がります。
集合住宅なら、日当たりの良いベランダでプランター栽培をするのも良いでしょう。もしも庭もベランダもない、と言う場合、手軽な市販の栽培キットを使うという手もあります。風通しが良く、明るい場所を選べば、栽培は可能です。寒さには強いので、基本的には屋外で育てます。庭やベランダがなくても、なるべく外に出しましょう。
風通しが良く日当たりも良い所を選ぶという点は、常に頭に入れておきます。重要な育て方の条件としては、水はけの良さも大切です。ジメジメしていないか、常に土の状態に気を付けて栽培しましょう。寒さには強い植物なので、むしろ多少の寒気に当てた方が、春に花が良く育つとされています。しかし、冷え込みがきつい寒冷地では、霜が付かないようにするなど、ある程度防寒対策をした方が良いでしょう。
種付けや水やり、肥料について
ベニバナツメクサの種付けは、秋に行うのが一般的です。ただ、寒冷地では少し早めに夏の時期から種付けを始めます。しかし通常は9月から10月ごろに行います。種が細かいので、ピートバンと呼ばれる種まき用キットを使うのがおすすめです。種をまく時は、種同士が重ならないよう、なるべくバラバラの場所に行きわたるよう注意します。
種をまいた時の水やりはたっぷりと行います。ある程度育った後は、土がしっかり乾いた後に、水を与えます。本来の生息地に合わせるように、ジメジメ状態にならないよう、最初に水はけの良い土づくりをしておくことも大切です。簡単栽培キットを使う場合は、付属の土や肥料を書いてある通りに使えばOKです。
本葉が3枚から5枚くらいになったら、栽培キットでもそれ以外でも、成長しやすいように広い場所や大きめの鉢、プランターなどに植え替えます。土には、重要な栽培条件である水はけの良さを考えて肥料を与えます。水はけを良くするための肥料として、腐葉土や堆肥があります。栽培キットを利用する場合、付属の培養土に肥料が混ぜ込んであります。
そのため、さらに別の肥料を投入する手間がかかりません。庭で本格的に栽培したい時は、育成予定の土地をよく見極めて肥料を入れ、土壌を適したものに変えます。化学肥料は、与えすぎるとかえって丈夫に育たないとも言われています。ある程度育ったら、基本的にそれほど肥料は与えなくても大丈夫です。手間の少なさから、ガーデニング初心者や、ちょっとした緑や草花を楽しみたい時に向いている植物です。
増やし方や害虫について
春は多くの植物が悩まされる、アブラムシの季節です。ベニバナツメクサも、春になったらアブラムシ対策が必要です。害虫用の薬剤を使用して、アブラムシを防ぐことも対策の一つです。ただ食用として使いたい場合は、殺虫剤などは使わないように気を付けます。しかし元気に育っている様子なら、あまり他に病害虫の心配はしなくても良いでしょう。
春先、多くの虫が出てくる季節に注意しておけば後は安心です。虫が付いていないかどうかは、常に見守っているとより安心です。冬にしっかり根付いた場合は、病害虫被害に遭う確率が減るでしょう。数を増やしたい時は、花が咲いた後に種を採取しておくという方法があります。最初に植えた分が育ち、種が出てきたら、すぐに採取します。
放置しておくと種が成長してしまうので、増やす予定の時は種をすぐに採取します。採取した種は、秋になったら通常通りの方法でまいて育てます。長く花を楽しむには、いったん花が咲いた後、切り戻しという方法を使うことも出来ます。切り戻しは、花が咲いている状態の茎を切ってしまう方法です。切った後には再び成長し、2番目の花が咲きます。
ベニバナツメクサも、切戻しが可能です。種を取っておく場合は、種が出来るまでそのままにしておきます。種から育てる手間を省きたい時は、苗を購入して増やすという手もあります。鮮やかな赤い花が沢山咲いている様子は、庭に彩りを添えてくれます。最初の栽培に成功したら、ぜひ増やしてみましょう。
ベニバナツメクサの歴史
ベニバナツメクサは、もともとアフリカ北部から南ヨーロッパ、さらに西アジアを原産地とする、マメ科シャジクソウ属の植物です。牧畜が盛んなヨーロッパでは、主に牧草として栽培されてきました。英語ではクリムソンクローバーと呼びます。強い赤色の花を咲かせることから、この名前が付いたと言われています。
最近園芸家の間では、種苗会社が名づけたストロベリーキャンドル、またはストロベリートーチという名でも知られています。さらに、オランダレンゲという別名もあります。和名のベニバナツメクサは、漢字では紅花詰草と書きます。同じツメクサでも、漢字で書くと爪草となる物もありますが、こちらは全く違う種類の植物です。
近世にオランダからガラス製品が運ばれてくる時、緩衝材として箱に詰められていた植物に、詰草という名が付きました。詰草ではシロツメクサ、アカツメクサなどが有名で、花の色など見た目で名前が違っています。ベニバナツメクサは、他のツメクサよりも日本に入ってきた時期が遅かったようです。明治時代に西洋から沢山の植物が導入された際、
一緒に入ってきました。最初は牧草として使用する目的でした。しかし今は、どちらかというと観賞用として知られています。シロツメクサなどは日本に入ってきてから野生化し、野原で見かける山野草という雰囲気があります。ベイバナツメクサの場合は、見た目の華やかさ、美しさから、主に庭や鉢植えで育てる園芸用という印象がある植物です。
ベニバナツメクサの特徴
ベニバナツメクサの一番の特徴は、鮮やかな赤色の花です。成長すると茎はまっすぐに伸び、赤い小さな花がまっすぐな茎の先に、円錐状に集まって咲きます。一瞬イチゴの果実が付いているようにも見えるため、ストロベリーキャンドル、ストロベリートーチという名前が付けられました。丈はおおよそ30センチにはなります。
大きなものだと、90センチほども伸びるようです。一本につき、3枚の小さな葉が付きます。葉は小さめなこともあり、赤い花をよく引き立てています。温暖な地域なら4月ごろに、寒冷地では6月ごろに花が咲き始めます。桜に続き、花の季節がやって来たことを告げる植物でもあります。見た目も鮮やかな花の部分は、甘い香りがします。
花の部分を取り、ほぐして食用にすることも出来ます。ほぐした花は、サラダに散らして彩りを添える役割として最適です。葉の部分はゆでて食材として使うことも出来ます。花が咲いたら、切り花にして花瓶に飾るのもおすすめです。咲いた花をメインに残してドライフラワーにすることで、長く室内インテリアとしても楽しめます。
茎がまっすぐなので、ドライフラワーにしやすく、完成後も飾りやすいです。乾燥させた花は、ポプリの材料にすることも可能です。観賞用としてだけでなく、用途がいくつもあるという点も特徴の一つです。本来は寒さに強く、何年も生きる多年草です。しかし高い気温に弱いこともあり、園芸用では一年で寿命を終える一年草として扱われています。
-

-
バーバスカムの育て方
バーバスカムはヨーロッパ南部からアジアを原産とする、ゴマノハグサ科バーバスカム属の多年草です。別名をモウズイカといいます...
-

-
ストレプトカーパスの育て方
イワタバコ科のストレプトカルペラ亜属は、セントポーリアも有名ですが、その次に有名とも言われています。セントポーリアは、東...
-

-
ブロッコリーの育て方
サラダやスープ、炒めものにも使えて、非常に栄養価の高い万能野菜であるブロッコリーは、地中海沿岸が生息地といわれています。...
-

-
ヒヨドリジョウゴの育て方
ヒヨドリジョウゴの特徴は外観と有毒性が挙げられます。外観に関して、白い毛が生えています。現物を見た人や写真を見た人の中に...
-

-
すなごけの育て方
特徴は、何と言っても土壌を必要とせず、乾燥しても仮死状態になりそこに水を与えると再生するという不思議な植物です。自重の2...
-

-
フロックスの育て方
フロックスとは、ハナシノブ科フロックス属の植物の総称で、現時点で67種類が確認されています。この植物はシベリアを生息地と...
-

-
オスモキシロンの育て方
オスモキシロンは東南アジア地域を原産とする植物であり、フィルピンやニューギニアなどでよく見られる植物です。フィリピンやマ...
-

-
ジャボチカバの育て方
ジャボチカバはブラジルを原産地とする常緑性の果樹です。熱帯植物に分類される樹木であり、その大きさは30センチ程度から3メ...
-

-
ハナショウブの育て方
ハナショウブとは6月の梅雨の時期に花を咲かせる花弁の美しいアヤメ科の多年草です。原産は日本や中国などのアジア圏になります...
-

-
ワスレナグサの育て方
そのような伝説が生まれることからもわかりますが、原産はヨーロッパで、具体的には北半球の温帯から亜寒帯のユーラシア大陸やア...




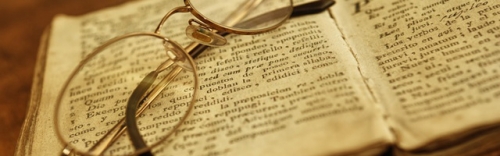





ベニバナツメクサの一番の特徴は、鮮やかな赤色の花です。成長すると茎はまっすぐに伸び、赤い小さな花がまっすぐな茎の先に、円錐状に集まって咲きます。一瞬イチゴの果実が付いているようにも見えるため、ストロベリーキャンドル、ストロベリートーチという名前が付けられました。