ヒメジョオンの育て方

育てる環境について
ヒメジョオンは、北アメリカ原産ですが、日本での栽培には、その環境のギャップを考えなければならないという気遣いは、まったく不要です。繁殖力も強いため、小さなキク科のかわいらしさを、群生して楽しませてくれるところが、魅力的です。初夏から秋にかけて、ダイナミックに咲き誇るヒメジョオンの白い花畑を見て、感動した経験を持つ人は、
少なくありません。小さな庭で、それを楽しみたい場合や広い敷地で花畑を作りたい場合など、その花を持ち帰り栽培する人の気持ちは、様々でしょうが、その目的を果たすためには、この植物が、雑草としての被害を他に与えないことと、どこからどこまで群生させるのかにより、他に広がらないようにすることも大事です。
この植物のために、わざわざ何らかの環境を整える必要はありませんので、育てたい場所が日当たりでも日陰でも構いませんし、肥料や水やりをしなくても育ちます。だから、他の栽培植物を、同じ土壌で育てないことや冬場の越冬時期に、不要な場所は、しっかり刈り取ってしまうなど、生命力において、
共存する植物たちと勝敗ができない環境を整えるように配慮することが大切です。色んな植物を育てている場合は、庭に地植えせずに、プランターや植木鉢で育てたり、見栄えの良い石などで、楕円や円状に囲いをして、他の植物とは全く別に育てるなど、独立した場所を作れば、花が咲くころには、とても見ごたえのある、非常に醍醐味のある庭になるでしょう。
種付けや水やり、肥料について
ヒメジョオンは、雑草としての生命力が、非常に強い植物ですから、特別に水やりや肥料などを与える必要もないという世話いらずです。けれども、それは、自然の中にあってこそということが言えます。自生するのに良い環境を見つけて、根を下ろし、群生するのが雑草です。自然の恵みがある場所で種をまいた場合は、
他の植物への影響に配慮しながら、群生させたい場所を超えさせないように、制限を加えながら育てなければなりません。けれども、野草と言えども、プランターや植木鉢など、人工的な土壌で育てる場合は、水で多湿状態になると根が腐りますし、菌も繁殖し、病気を発症する可能性もあります。水はけのよい土壌にするため、
用土に何をどれくらいの比で混ぜ合わせて、支援に近い良い環境を作るかというのは、とても大事なことです。土が乾いてしまったら、多くなくて良いですから、水やりも必要です。また、日陰でも育つ植物ですが、全く日の目を見ない状況もよくありません。人工の場では、自然環境にある恵みを与えることを忘れてはいけません。
受粉しなくても種子を作りますので、春から夏にかけて急に目立ちだすヒメジョオンの一回り広がった群生に驚くこともあります。種が、風や人間、動物などにより伝播するためです。雑草並みの植物は、こちらの計画に反することがたくさんあります。それを、いかにコントロールできるかで、ただの雑草にしてしまうか、美しい野草としての価値を保つかが決まります。
増やし方や害虫について
育ててもらわなくても、自分で成長しますし、増やし方も気にする必要ないくらいに繁殖するヒメジョオンです。北アフリカから入ってきたときには、貴重で美しい花としてもてはやされましたが、今では、何の値打ちもない雑草として、貧乏草とも言われているほどです。この花の茎を折ると、貧乏になるといういわれからついた名だとも言われますが、
園芸として、手を入れるほどのものではないと評価されがちな植物です。病気もなく、周辺の虫たちに葉を食われても、平気で育つ植物です。大事なことは、庭先に地植えで育てる場合、そのエネルギーで、周囲の植物に勝ち誇った顔の白い花という感じにならないように、今までに作り上げ、育てあげた園芸成果の輝く庭の環境を壊さないように気を付けることです。
でなければ、せっかくのこの美しい野草を、全て刈り取り処分するというような完全な雑草としての存在に追い込むことになります。環境保全のために、荒れた畑などに、この植物だけを育てて、群生を楽しみ、枯れた葉で、土地を肥やすというのも良いかもしれません。家の中やその周囲で楽しむときは、プランターなど、
人工的に作った快適環境の中で育て、軒下や室内に置くというのも、花が咲いた時、家の周囲や室内に癒しが漂うのを楽しめて良いでしょう。ヒメジョオンの場合は、増やし方をいかにコントロールして、花としての価値を持続させるかということが、何よりも大事な園芸の基本になるでしょう。
ヒメジョオンの歴史
ヒメジョオンは、北アメリカが原産の植物で、明治維新で日本が揺れているころに、入ってきて、以来日本中に広がり、色んな家の庭で見られる、おなじみの花となりました。生息地を選ばないと言うところも、この花の良いところで、市街地や農村の庭先や、プランターで見られるのは、もちろんのこと、亜高山帯にまで、
この花が分布しているというのには、驚かされます。茎の高さは、生息している場所により様々で、30cmほどの場合もあれば、1mを超すまでの成長している場合もあります。下のほうの葉っぱは、丸くてギザギザになっています。花は、直径が2cmぐらいで、花弁は白色や淡い紫色です。開花は、6月ごろから9月頃と、長い間楽しめる、かわいらしく、可憐な花です。
見た目は、小さくて愛らしいですが、野に咲く花としても、生きていけるほどの生命力が強い、環境を選ばない植物でもありますから、園芸の手始めとして、庭に植えて、育てるのも、非常にたやすい植物とも言えます。プランターで、門扉周りに置き、来客の気持ちをほっとさせたり、庭先を明るく、
易しく飾る花として利用したりと、珍しくないけれども、愛着がもたれるほど、気軽に育てられる植物です。日本に入ってきた当初は、貴重な花として、園芸人気も高く、もてはやされました。しかし、今では貧乏草と言われるほど、強い雑草的イメージのものとなり、
美しさよりも、環境保全面での配慮が必要と言われるくらいです。しかし、日陰であろうと寒いところであろうと咲きますから、荒庭の環境が良くなくても、ためらわずに選べるというところも、ヒメジョオンの値打ちと言えます。
ヒメジョオンの特徴
ヒメジョオンは、晩秋から後は、地上部は、全て枯れてしまい、根性葉で冬を越しますので、踏みつけられても、刈られたとしても、土の中でぐんぐん成長をして、その存在性をアピールします。種を付けた後は、繁殖力も強いため、風により、種は飛んでいき、どんどん広がりますので、遠くまで拡散し、
知らない間にこんなところにも咲いているということもあります。趣旨による繁殖は、非常に勢いがあり、晩春から夏ぐらいに花を咲かせますが、晩秋にも咲いているものもあり、長い間、色んなところで、小さく白い花を見かけます。雑草の部類ともいえるヒメジョオンですから、わざわざ栽培をする必要もないと言えますが、
日光と良い土壌と風通しの良い快適な場所を用意してやることで、まっすぐ元気に伸びて、観賞にも良い花となりますから、この花を好む人も多いです。ただ、どこででも世話なく育つ代わりに、雑草的な性格の部分に対する世話も必要です。良い環境を与えると、さらに強いエネルギーを持ちます。やたら周囲に広がらないように、
掘り起こして処分をしなければならないこともあります。いくらでも咲き広がらせると、他の植物のエネルギーも奪うことにもなりかねません。ヒメジョオンを育てる時は、その植物の栽培そのものよりも、周囲に対する影響を考える必要があります。秩序あってこその庭先のかわいい花となります。育て方が、簡単な野草ほど、周囲との共存にも配慮することが大事になります。
-

-
ワトソニアの育て方
ワトソニアは草丈が1m程になる植物です。庭植え、鉢植えにも適しています。花の色は、白やピンク、赤やサーモンピンクなどの種...
-

-
パンパスグラスの育て方
パンパスグラスの原産地はアルゼンチン・ブラジル南部とされていて、南米のパンパと言われる地域に自生している事からこの名前が...
-

-
シンジュガヤの育て方
イネ科やカヤツリグサ科などで、日本でも種類は多いのですが注目をあまりされない植物群です。その中でわりと注目されている植物...
-

-
キルタンサスの育て方
キルタンサスの科名は、ヒガンバナ科 / 属名はキルタンサス属になり、その他の名前:笛吹水仙(ふえふきすいせん)、ファイア...
-

-
果物から出てきた種を育てる方法
果物には、中に種が入っているものが多いです。果物によっては、食べながら種を取り出して、それを土に植えることで、栽培するこ...
-

-
アシダンセラの育て方
花の特徴としてはアヤメ科になります。草の大きさとしては60センチぐらいから90センチぐらいになります。花が開花するのは秋...
-

-
ニラの育て方
東アジア原産で、中国西部から東アジアにかけての地域が生息地と考えられます。中国では紀元前から栽培されており、モンゴル、イ...
-

-
カラジウムの育て方
カラジウム/学名・Caladium/和名・ハイモ、カラジューム/サトイモ科・ハイモ属(カラジウム属)カラジウムは、涼しげ...
-

-
プルンバゴの育て方
プルンバゴは、イソマツ科、ルリマツリ属(プルンバゴ属)となります。また、和名は、ルリマツリなどと呼ばれています。プルンバ...
-

-
バンダの育て方
原産地は赤道を挟んだ北緯南緯とも30度の間の国々で主に熱帯アジア、インド、オーストラリア北部、台湾などがあります。また標...




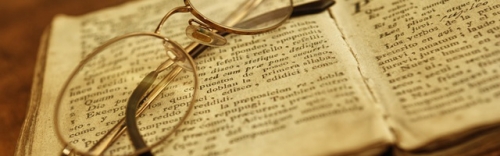





ヒメジョオンは、北アメリカが原産の植物で、明治維新で日本が揺れているころに、入ってきて、以来日本中に広がり、色んな家の庭で見られる、おなじみの花となりました。生息地を選ばないと言うところも、この花の良いところで、市街地や農村の庭先や、プランターで見られるのは、もちろんのこと、亜高山帯にまで、この花が分布しているというのには、驚かされます。