ハハコグサの育て方

育てる環境について
春の七草ということでは、ハハコグサもそのひとつですが、他にはセリ、ナズナ、ハコベ、仏の座と言われるコオニタビラコ、後はカブと大根ということになります。これらを粥に混ぜて食べるということで、なかなか彩りも綺麗になりますし、冬は野菜が少ないので、その意味でも栄養ということでも健康に良さそうです。
歴史的にも元々は中国の厄祓いと、日本の文化が合体してできた習慣のようで、お正月ですし、厄祓い的な意味合いが強いということですが、それはそのまま庭に植えても厄祓いのパワースポット的な植物ということでもそんな役割の植物になるということでもありますし、またそのような歴史がある事自体でも、縁起が良い植物ということになります。
そのような意味からもガーデニングや家庭菜園で栽培するのにも良いということでしょう。またキク科ということですので、花も綺麗で黄色の彩りで、まとまって咲きますので、さすがにキク科だけはあるという感じもします。野草などではキク科もよく見られますので、改めて栽培するのにも、美しい花を楽しめるということになります。
その点でもハハコグサは、野草の中でも選んで面白い植物ということになります。また大きさも30センチぐらいですので、庭でもじゃまにならない大きさです。また日本の冬も越すことができるので、その点でも管理が楽になります。またこぶりなので、広さが限定される庭でも可愛さを演出できるということになります。
種付けや水やり、肥料について
また食用ということでは、昔は餅の中に草餅のように入れていたそうですが、ハハコグサの名前から、臼と杵で打つのはよくないということで、入れないようになり、今ではヨモギになったという話もあります。しかしもともとその頃は、名前も違っていたそうで、多分ヨモギのほうが美味しかったのでそうなったのでしょう。
その歴史的な由来なども、この植物の面白いところです。また名前の由来ということでは、植物全体に短い産毛がありますが、それを母親が幼い子供を抱いで包み込んでいるという様子に見えるので、そのような名前がついたということです。本当に日本人は感性が豊かというか、想像力が豊かということを感じます。
また面白いことに、チチコグサという植物もあり、同じハハコグサ属で親戚ですが、こちらはだいぶ地味で、人間社会の母親と父親の関係に似ていて、これも面白いです。やはり昔から父親よりも母親に対してのインパクトのほうが大きかったのがよくわかります。母親のほうが大切にされて、子どもたちの情も行くということですが、
これは昔から変わらない情関係ということなのでしょう。そのようことも感じられる植物でもあり、非常に印象的な野草ということになります。またそのような利用方法の他にも漢方薬としても使われてきたそうで正式なものではないのですが、干してお茶にするということで、咳止めや内臓などに良い健康茶ができるそうですが、それも試してみたいということになります。
増やし方や害虫について
この植物は、日本でも野草としては非常にメジャーなもので、弁当で言えば定番の玉子焼きのようなものと表現している人もいましたが、まさにそんな感じの植物ということになります。また花言葉は、いつも思っていますとか、親切な人とかで、親子のことは出てきません。また植物としては、
開花期は4月から6月ということですから、春の植物ということになります。また日本のハーブと言っても良い植物ですが、栽培の環境としては、日当たりの良い風通しの良い環境が好みで、乾燥にも強いということですので、都会ではあまり見られないので、庭の隅などで育ててみるのも簡単で面白いということになります。
また花も独特で、明るい黄色の小さな筒状の花がまとまって咲きます。このような花も珍しいので、ガーデニングでも庭が明るくなるというメリットもあります。このように野草ということでも美しい彩りの植物なので、あまり増えすぎないように栽培するということでは注意が必要ですが、それはそのまま簡単に育つということでもありますので、試してみるのも面白いということになります。
またハーブのようにお茶として使う場合には、乾燥させて細かく刻んで、お茶っ葉のようにして保存し飲むということで利用できます。味などもどのようなものか興味もありますが、最近流行りの健康茶としても楽しめるということになります。また非常に強い植物なので、害虫なども心配はなく育てることができます。一度試してみても面白いかもしれません。
ハハコグサの歴史
自然は癒やしを与えてくれますし、その自然を楽しむ方法としてもガーデニングや家庭菜園がありますが、その楽しさの中では、食べられるということも重要です。また見た目も彩りということでも、派手なだけではなく、静かな美しさも必要ですし、バランスも大切になります。
最近では定番の植物ばかりではなく、野草や漢方薬などに利用できる植物なども栽培している人たちも増えてきました。ある程度経験を積んで、今までにない植物を育ててみたい、あるいは収穫してみたいということなどですが、そのような場合には、身近な野草なども面白いということになります。
日本では野草というと、春の七草が浮かびますが、お正月などにお粥にして毎年食べられたりしながら話題にもなります。その中で日本のイメージにあっているのが、ハハコグサです。これは春の七草では、御形と呼ばれていますが、ゴギョウとかオギョウとかとも言われます。
ネーミングのセンスが非常に豊かな日本人ですが、この野草にもハハコグサという名前をつけています。非常に豊かな想像力も感じますし、親子の絆を大切にしてきた伝統も感じで、今の日本にも合っている野草でもあります。ガーデニングの栽培で初心者に扱いやすいのが、日本のどこにでも花を咲かせている野草類ですが、
これらは野草と言っても美しい花を咲かせたりしますし、食べることもできるものが多いので、試しに栽培するのも面白い植物です。また野草なので栽培も手がかからず、誰にでも育てることができ、プランターや鉢植えでも大丈夫なので、ベランダなどでも育てられます。
ハハコグサの特徴
このハハコグサは育て方といっても、日本で自生している野草なので、一般的な育て方で十分で、ガーデニングでも家庭菜園でも、庭の端の方に植えておくだけで、たいがいの環境では育つのではないかということですが、キク科のハハコグサ属ということで、原産地もアジア全般のようです。
中国やマレーシア、インドなどでも生息していて、日本でも生息地ということでは、全国的に普通に見られる植物です。田舎の冬の水田や、あぜ道や道端などで見ることができますので、普通に見られる植物です。また食べられるのですが、茎葉の若いものが食用になるのは、他の野草と同じです。
基本的には、野草なども若い段階で食べるということになります。また歴史的には、古代に外来植物として朝鮮半島から日本に伝わったのではないかということですが、その場合には、今でも田畑の近くが多いので、稲作の伝来の時に、一緒に渡ってきたのではないかとも言われているようですが、
確かな文書などは残っていないので、自然にいつのまにか日本で育っていたということではないかということになります。考えてみればコメも小麦も外来植物ということで、改めて考えてみると不思議に感じます。
そのように日本人とは古いつきあいの野草ということになります。そのような意味でも、その歴史を感じながら、栽培してみても面白い植物です。栽培では日本に自生しているぐらいですから、育てやすいということですが、日当たりや水はけなどを良くすると。増々よく育つということになります。
-

-
あじさいの育て方
あじさいといえば知らない人はいないほど、梅雨の時期に見られる代表的な花です。紫陽花科(ユキノシタ)科の植物で6月から7月...
-

-
シーマニアの育て方
シーマニアは、南アメリカのアンデス山脈の森林が原産の植物であり、その生息地は、アルゼンチンやペルー、ボリビア等の森林です...
-

-
ほうれん草の育て方
中央アジアから西アジアの地域を原産地とするほうれん草が、初めて栽培されたのはアジア地方だと言われています。中世紀末にはア...
-

-
ワイヤープランツの育て方
ワイヤープランツは観葉植物にもなって家の中でも外でも万能の植物です。単体でも可愛くて吊るして飾っておくとどんどん垂れてき...
-

-
アケビの育て方
アケビはまず中国の歴史に現れます。中国で最古の薬物学と書と言われている「神農本草経( しんのうほんぞうぎょう)」という本...
-

-
ベンケイソウの育て方
ベンケイソウは北半球の温帯や亜熱帯が原産の植物です。ベンケイソウ科の植物の種類は大変多く、またその種類によって育て方は多...
-

-
ハナトラノオの育て方
ハナトラノオは北アメリカ東部を原産地とする植物であり40センチから1メートル程度の大きさに育つ多年草の草花です。かわいら...
-

-
マツの仲間の育て方
マツの仲間の特徴としては、環境や種類によって様々に異なってくるものの、マツ属に含まれるものは、基本的に木本であり、草本が...
-

-
シノグロッサムの育て方
シノグロッサムはワスレナグサの仲間でムラサキ科に属する植物です。秋まき一年草で中国南部原産ですが、ワスレナグサ自体はヨー...
-

-
ノアサガオの育て方
ノアサガオなどの朝顔の原産地や生息地はアメリカ大陸で、ヒマラヤやネパール、東南アジアや中国南部という説もあります。日本に...




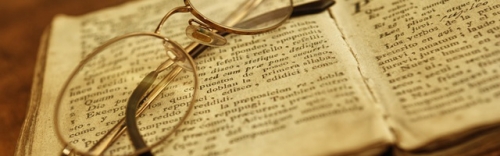





このハハコグサは育て方といっても、日本で自生している野草なので、一般的な育て方で十分で、ガーデニングでも家庭菜園でも、庭の端の方に植えておくだけで、たいがいの環境では育つのではないかということですが、キク科のハハコグサ属ということで、原産地もアジア全般のようです。