ハナトラノオ(カクトラノオ)の育て方

育てる環境について
栽培において育て方において必要な環境は動行ったとところかですが、まず日当たりでの管理を行います。日当たりの場合、夏に弱い植物などがあり管理が難しいことがありますが、この花の場合はそのような心配を余りしなくて良いとされています。夏の暑さにも強いとされているからです。更には冬の寒さもへっちゃらなタイプとされています。
冬についてはどれくらい強いかですが、霜に当たったとしても枯れることが無いとされています。そのために冬にも強い状態の花と言えます。日当たりを好みますが、日陰で育たないわけではありません。完全に日が当たらないとあまり元気良くはなりませんが、半日陰など一定の日当たりがあればそれなりに花を咲かせますし、根の管理も行うことができます。
乾燥しているところでも育ちますが、どちらかと言えば湿り気のあるところの方をより好むとされています。それなりに栄養分があるところでもどんどん繁殖することがあります。湿気があるところと乾燥しているところでは、湿気があるところのほうが花つきが良くなる傾向にあります。
乾燥しているところだと下葉なども枯れやすくなる場合があります。雑草のようにどんどん伸びていくタイプではありますが、全く何もせずにしているといつの間にか花がなくなっている、茎などもなくなっていることになるので適度に管理をしてあげる必要があります。それぞれの環境を考えることで、ベストの花を楽しめるようになります。
種付けや水やり、肥料について
用土においては、水はけと保水を考える必要があります。通常は水はけを重視することがありますが、この植物は生息地から適度な湿り気を好みます。あまり水はけを良くしすぎるのはよくありません。赤玉土に関しては7割、腐葉土を3割り程度にすることで水はけを良くしながらも保水も実現できる状態を作ることができます。
育てる方法としては鉢植えを庭植えがありますが、あまり鉢植えにしない種類とされています。特に移動させる必要がないからです。冬も容易に越すことができますし、夏もそれ程苦手ではありません。庭植えで行った時にはほとんど水やりは不要と言われます。自然においては雨があります。
雨は一度降るとかなり地面で維持されるので、晴れが続いても水やりをする必要性が少ないとされています。肥料については最初に土にいれておけば後は不要と言われています。肥沃なところのほうが良いとはされていますが、成長するにあたってはある程度荒れているところでも育ちます。あえて肥料を入れる必要性が無いともされます。
水やりの考えとしては鉢植えにおいては7月から10月にかけてはしっかりと与えるようにします。つぼみの発育としては梅雨明け以降に進むことがありますが、この時に乾燥するとつぼみができにくくなります。乾燥を抑えるためにもしっかりと与えるようにします。鉢植えにおける肥料については、庭植えに近い考え方です。肥料については多すぎると伸びすぎて倒れてしまう問題があります。
増やし方や害虫について
増やし方では株分け、さし芽、種まきがあります。株分けが行い易いとされています。地下茎をどんどん伸ばして増えていこうとします。これを切り分けるようにすれば増やすことが可能になります。さし木をすることもできます。ただしこれらのことをして増やす必要性があまりないとも言えます。
実際に育てるようになると、増やし方の方法をとらなくてもどんどん増えているからです。場合によっては少し困るぐらいに増えることがあります。わざわざ増やす行為をしなくても勝手に増えてくれます。そこで必要になってくる作業として間引きがあります。まずはこの花について密集しないようにしなければいけません。
狭いところにたくさん密集すると、空気の通り道が少なくなって育ちにくくなります。また他の植物に影響を与えてもいけません。そうならないようにするためにも、必要部分のみ管理をして、その他について間引きを行うようにします。間引き以外に行うといいものとしては一旦掘り返すことです。
そして根の強いものだけを残して後は肥料などにします。病気としてあるのは白絹病があります。水はけが悪い状態になると起きることがあります。この植物は湿った状態を好むだけに水を多く与えすぎることがありますが、それによって発生することがあるので難しいところかもしれません。害虫としては毛虫類がつくことがあります。つぼみを食べられたり、葉っぱを食べられることが多くなっています。
ハナトラノオ(カクトラノオ)の歴史
動物にしても植物にしてもそれなりに住む場所などがあります。陸上で生活する動物に関しては多少泳ぐことができることがありますが、太平洋などを泳げるわけではありません。大陸から日本に単独で泳いでくることも無いでしょう。もし日本の様な島国に大陸にいるような生物や植物がいるとしたら持ち込まれるしかありません。
その後に野生化することがあるかもしれません。凶暴な動物として知られているのが虎です。日本には元々住んでおらず、中国や東南アジアなどで生息しているものなどが観賞用として連れられるぐらいです。動物園で見かけるぐらいでしょう。昔の人にとってはそれ程馴染みはなさそうですが、より馴染みのある猫よりも植物の名前に入っていることがあります。
ハナトラノオと呼ばれる植物があります。別名としてはカクトラノオとなっていることもありますが、どちらにしてもトラノオの名前が入っています。虎のしっぽのような形をしている植物なのでこのように呼ばれています。原産に関してはあまり虎とは関係のないところです。アメリの中でも、北アメリカ東部辺りとされています。
日本に入ってきたのは大正時代に入ってからとなっています。動物園などが徐々にできてきて、その頃から多少は虎の認識があったのかもしれません。そこで付けられたのでしょう。その他にもトラノオとついている花は結構あります。種類が同じものもあれば、全く異なるものもあるようなので間違えないようにしなければいけません。
ハナトラノオ(カクトラノオ)の特徴
種類としては、シソ目、シソ科に属します。多年草の草花で、草丈としては40センチから高くても1メートルぐらいとされています。花が咲くのは7月から10月ぐらいで、花の色としてはピンクであったり紫、白っぽい色の花を咲かせることもあります。耐寒性、耐暑性とも強いですから、日本においては比較的どこででも育てることがし易い花として知られています。
落葉性なので枯れると葉は落ちますが、茎などが残っていますから、次の年にも花を咲かせてくれます。開花期間が長い花として人気のある花になっています。誕生花としても設定されていて、6月20日、7月20日、7月27日、8月19日、10月3日、11月7日などになっています。花言葉では達成や希望などの言葉が入っています。
花の特徴としては、四方に突き出すように花が咲きます。花穂については四角錐のようになっています。見た目としては縦に長いような花に見えますが、実際のところは小さい花がたくさんついて長く見えるようになっています。花の直径については2センチぐらいで、内側には斑点が見えることがあります。
葉っぱの特徴としては披針形になって、対生タイプになっています。葉の縁はギザギザの状態になっています。花が終わったあとには実がなります。花に関しては大体が下から上に徐々に生えていきますそのために上の方の花が咲いていない時に虎のしっぽのように見えるのでしょう。しましま模様があるわけではありません。
-

-
パキラ(Pachira glabra)の育て方
パキラはアオイ科で、原産や生息地は中南米です。現在は観葉植物としての人気が非常に高いです。原種は約77種ほどあって、中に...
-

-
サギソウの育て方
サギソウはラン科サギソウ属サギソウ種の多年草で、日本や台湾、朝鮮半島が原産となっています。日本では北海道や青森などを除い...
-

-
大根の栽培方法を教えます。
日本人の食卓に欠かせない大根は、酢漬けや煮物などで美味しく食べる事が出来ます。特に大根の漬漬けには数多くのバリエーション...
-

-
植物の育て方を勉強する
現在は、家庭菜園などで野菜を栽培している人たちも多く存在しています。自分で手入れをして栽培した野菜を食する事ができるのは...
-

-
ベニバナイチゴの育て方
ベニバナイチゴの特徴としてはまずは高さです。1メートルから1.5メートルぐらいなので決して高くはありません。高く伸びてい...
-

-
ウェストリンギアの育て方
シソ科・ウエストリンギア属に分類され、別名にオーストラリアンローズマリーの名前を持つ低木がウェストリンギアです。別名にあ...
-

-
スノードロップの育て方
真っ白な花に緑色の斑が美しいスノードロップを自宅で育てることができたら、まるでヨーロッパの庭のように美しい景色を作ること...
-

-
ロベリアの育て方
ロベリアは熱帯から温帯を生息地とし、300種以上が分布する草花です。園芸では南アフリカ原産のロベリア・エリヌスとその園芸...
-

-
フジの育て方
藤が歴史の中で最初に登場するのは有名な書物である古事記の中です。時は712年ごろ、男神が女神にきれいなフジの花を贈り、彼...
-

-
ウツギの育て方
ウツギは、ユキノシタ科の植物です。生息地は北海道から九州、奄美大島までの日本の山野や、中国原産のものもあります。落葉性の...




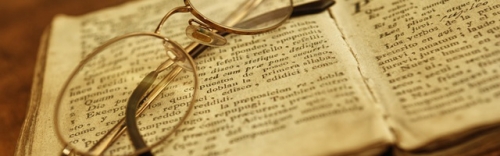




種類としては、シソ目、シソ科に属します。多年草の草花で、草丈としては40センチから高くても1メートルぐらいとされています。花が咲くのは7月から10月ぐらいで、花の色としてはピンクであったり紫、白っぽい色の花を咲かせることもあります。別名としてはカクトラノオとなっていることもありますが、どちらにしてもトラノオの名前が入っています。