ニホンズイセンの育て方

育てる環境について
育て方としてはどういったところがよいでしょうか。環境としてはまずは耐寒性のある植物です。花が咲くのは冬でも最も寒い1月から2月とされます。他の花がまだまだ蕾を固くしている時に咲くぐらいですから、かなり寒さに強いと言ってもいいでしょう。雪が降ったからといって簡単にしおれたりすることはありません。
暑さに関してはどうかですが、夏はこの花は地面の中で休眠をします。花が咲いているのは春先までで、その後は急速に花が枯れて葉っぱなども隠れます。球根が根の下に残りそのまま夏を越すことになります。また涼しくなってきた時に次の季節のための準備を始めます。日当たりについては良い所が好まれます。
海岸などにおいても太陽の日差しが強いところに育っているのがわかります。日差しが強いところに群生していますから、育てるときにおいても日差しを向けるようにしないといけません。土質としてはあまり粘土質の状態は好まれません。海岸においては砂の土地が多くなっています。このような土地で増えやすくなっています。
自宅において砂の質の土壌などを作ることはできませんから、それなりに工夫をして水はけが良くなるようにしておけばいいでしょう。特に夏は休眠をします。水はけが悪いと水が多い時になかなか水が抜けなくなります。休眠中に水などが来るとあまり生育にはよくありません。自宅で育てるときは土の中にそのままにしないかもしれませんが、ある程度考慮するようにします。
種付けや水やり、肥料について
育てる上での土の状況ですが、水はけを重視した土を用意します。庭土だと少し難しいです。通気性も良くしたいため、土をうまく配合して利用するようにします。配合例としては、草花用の培養土が6割、腐葉土が4割程度などです。その他堆肥を少し混ぜる方法もあります。あればそういったものも加えるようにすると育ちやすくなります。
植え付けの時期としては秋になります。この植物は夏には休眠をします。夏に植えて水をあげたとしても育つことができません。あまり水を当てられると球根が傷むことがあります。そうならないように秋ごろに植えて水を与えるようにします。9月から10月ぐらいにかけてうえるようにすれば年内には咲かせることができます。
年内に咲いても1箇月近く咲き続けてくれるので花を楽しむ期間としては長くすることが出来るでしょう。植え付けるときの感覚は20センチぐらいにすることが多いです。植木鉢の時は春に咲いて枯れた後は土から出すことがありますが、地植えにしている場合はそのまま庭に植えたままにすることがあります。
水やりにおいて、庭に植えるときはあまり必要ありません。夏を越しませんから、それ程土が乾くことも少ないです。自然の雨で十分に水分を取ることができます。冬場にあまり雨がふらないようであればその時に水を与える程度で育てられます。鉢植えの時は植木鉢の状態を見ながら行います。水がなくなってくれば育ち方に影響して来るので注意します。
増やし方や害虫について
肥料を与えるのは植えるときに行うようにします。緩効性の化成肥料を利用します。最初に与えた後は目が出た頃の11月ぐらいにリン酸分が多めになっている液体肥料を与えるようにします。花が終わった後にも肥料を与えると良いです。この時にはカリ分の多い液体肥料を与えるようにします。
花が咲いたあとでも球根は生き続けますから、栄養分として与えておくとその次の年以降に良い影響を与えます。将来的に増やすときにも役立ちます。増やす方法としては分球を行います。夏に休眠している球根を掘り上げます。球根がいくつもくっついている事があるので、それを手で割ります。
このようになるので花が終わったあとの肥料が生きてくると言えます。球根に関しては小さい状態の場合は花は咲きません。大きく育つまでしっかりと見守るようにします。急に太らせることはできませんから、じっくりと太らせるようにします。増やすにあたっては花がら摘みも大事になってきます。
花が終わったあとに花茎の付け根から切り取るようにします。葉っぱに関してはそのままにしておく必要があります。病気としてあるのがモザイク病と呼ばれるものになります。葉っぱにその症状が出てくることがあります。
黄色い筋状の模様が入ってきたら注意しなければいけません。この花自体は特に害虫は発生しないものの、この病気はアブラムシが媒介するとされています。そのためにアブラムシの駆除をしっかりとして、病気の元を断つようにします。
ニホンズイセンの歴史
世界にいろいろな品種があるうちに日本にしか見られない、存在しないものがあります。日本固有の種である場合はそのように管理されていくことになります。名前においてもニホンと付けられる事があるかもしれません。ただし必ずしも日本でしから見られないものとも限りません。古く何処かから渡ってきたものが日本で広がった可能性もあります。
水仙に関しては非常に多くの種類が世界において発見されています。水仙そのものの原産地としては主にスペイン、ポルトガルといった地中海沿岸のヨーロッパやアフリカ北部とされています。そこから広がって世界に散らばっているともされています。ではニホンズイセンと呼ばれるものはどうかですが、
こちらについては元から日本にあったものではなく、古く中国から渡来してきたものとされています。非常に美しい花ですから本当のところは日本固有の種であってほしいこともありますが、こればかりは仕方がありません。その後に一定の地域に広まっていったようです。生息地としては主に本州以南とされています。
最初に渡ってきたところとして有力視されているのが福井県で、こちらの海岸においては群落が非常に有名になっています。そのことから県の花になっているぐらいです。その他海岸などにおいて集中して咲くことが多くなっています。自然に咲かせることも増えていますが、近年においては栽培されてることも増えています。自宅においても栽培することが可能です。
ニホンズイセンの特徴
特徴において、種類はクサスギカズラ目、ヒガンバナ科、ヒガンバナ亜科になっています。多年草ですから、一度避けばそのままにしておくことで次の年にも咲かせることができます。咲く季節が少し変わっています。春らしい花なので春も暖かくなった時期に咲き始めるように感じますが、咲く時期はもっと早くなります。
真冬の寒い時期に咲き始めます。海岸沿いといいますとかなり寒い強い風が吹くこともありますが、それらの風に負けないように咲き続けています。それが特徴の一つにもなっています。草丈に関しては15センチ程度から50センチ程度ですが、大体は30センチ程度になることが多いです。特に栽培をしているわけでない群落でもだいたい高さが統一されています。
ですからある花だけが特に成長して高くなりすぎているなどのことはありません。海岸沿いの岸壁などに咲くこともありますが、こちらにおいても均一に咲くことが多いです。茎については外皮に包まれた鱗茎の中にあります。ですから一見茎のように見えるところは実は茎ではありません。
切らない限りには見ることはできない状態になっています。葉っぱは根本から大きく上に伸びる形で生えます。厚みがあり硬いので高く伸びても垂れたりすることは少ないです。葉っぱに艶はあまりありません。葉の間から蕾を付けた花茎が伸びます。伸びきると横向きになり、そこから花が咲きます。ですからは花は上に向かずに横に向いた状態で咲きます。
-

-
果物から出てきた種を育てる方法
果物には、中に種が入っているものが多いです。果物によっては、食べながら種を取り出して、それを土に植えることで、栽培するこ...
-

-
カラジウムの育て方
カラジウム/学名・Caladium/和名・ハイモ、カラジューム/サトイモ科・ハイモ属(カラジウム属)カラジウムは、涼しげ...
-

-
パイナップルの育て方
パイナップルは日本でもよく目にする果物ですが、原産地はブラジルで、代表的な熱帯果樹の一つです。先住民によって果物として栽...
-

-
ヒナガヤツリの育て方
ヒナガヤツリは、カヤツリグサ科カヤツリグサ属の植物です。ヒナガヤツリの原産地は北アメリカですが、主な生息地はオーストラリ...
-

-
シザンサスの育て方
シザンサスはチリが原産の植物です。もとの生息地では一年草、あるいは二年草の草本として生育します。日本にもたらされてからは...
-

-
木立ち性ベゴニアの育て方
木立ち性ベゴニアの科名は、シュウカイドウ科で属名は、シュウカイドウ属(ベゴニア属)になります。その他の名前は、キダチベゴ...
-

-
より落ち着いた雰囲気にするために 植物の育て方
観葉植物を部屋に飾っていると、なんとなく落ち着いた雰囲気になりますよね。私も以前、低い棚の上に飾っていましたが、飾ってい...
-

-
ヘチマの育て方
熱帯アジアを生息地とするインド原産の植物です。日本には中国を通して江戸時代に伝わったと言われています。ヘチマは元々、果実...
-

-
ブラッシアの育て方
ブラッシアはメキシコからペルー、ブラジルなどの地域を生息地とするラン科の植物で、別名をスパイダー・オーキッドと言います。...
-

-
チャボリンドウの育て方
チャボリンドウは、アルプスやピレネー山脈の草地原産の常緑の多年草です。チャボといえば、茶色を基調とした鶏の色をイメージす...




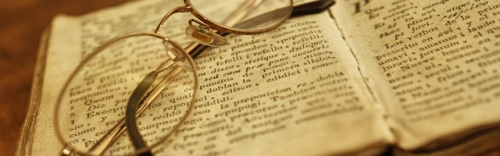





特徴において、種類はクサスギカズラ目、ヒガンバナ科、ヒガンバナ亜科になっています。多年草ですから、一度避けばそのままにしておくことで次の年にも咲かせることができます。咲く季節が少し変わっています。