ツリフネソウの育て方

育てる環境について
上記にある薄暗い場所や湿地帯を好むことからもわかるように、直射日光や明るい場所は好みません。直射日光にあたり続けると花や葉が焼けて痛むことがありますので、基本的には半日陰が適しています。また半日陰でも湿った場所を好むので、日当りの良い場所を好む花が多い中とても特殊ですね。
植物を育ててみたいけれどあきらめていた場所でもうまく育つ可能性があります。庭植えや鉢植えのどちらにも適しており、鉢植えで育てる場合なども軒下など日のあたりにくい場所を探してみましょう。苗自体は一年で終わりますが、種が落ちることで次の年も育ちます。
そのままでも大丈夫ですが、コントラストや配置を楽しみたい場合は、鉢植えの場合は種を収穫して新しい鉢に種をまきましょう。苗の購入時期は春先頃から夏に掛けて出回ります。植えつけは5月から8月が適しています。土などの環境は、市販されている「花の土」や「野菜の土」など花や野菜に使えるタイプの土で育ちます。また自分でブレンドされる場合は、「赤玉土6/腐葉土4」であわせて作りましょう。
どちらの場合も保湿効果の高い土の環境が求められますので、わからない場合は園芸店で確認するようにしましょう。砂などの割合が多い土や何度も使い回している土などは乾きやすくあまりお進めできません。砂質土壌の土を裂けることで育ちやすく、多くの花芽を付けるようになります。基本的にはあまり育て方の難しい植物ではありませんので、初心者向きと言えるでしょう。
種付けや水やり、肥料について
種付けは、花が咲いて実がなりそれが熟すと弾けとんでこぼれ種で次の年に芽が出ます。一度植えてしまえば、その後はほとんど手をかけることなく毎年楽しむことが出来ます。水やりについては少し注意しましょう。乾燥を嫌い適度な多湿を好むツリフネソウは、水やりのタイミングを早めましょう。土の状態を見て乾いていたらたっぷりと水を与えましょう。
また完全に乾いてしまう前よりは、一瞬早く与えるのが水を切らさないコツです。一度水切れさせてしまうとその後の生育が衰えてしまうことがあります。最悪の場合には、生長自体が止まってしまうこともありますので注意しましょう。特に真夏の水やりには要注意で、一日に2回.3回と与える必要もあります。とにかく極度な乾燥には十分注意することが大切です。
肥料は基本的にはあまり必要ありませんが花付きを増やしたり、実の付きを良くしたりと株を豊かにするので適度に必要だと言えるでしょう。春の5月頃や夏には固形肥料を土の上におきましょう。夏前などの生育期などでは液体肥料を1ヶ月の間に2回か3回与えます。10日に一回か15日に一回程度の感覚がベストでしょう。
それを秋まで続けましょう。しかし葉が増えすぎたり茎ばかりが長くなったりするようであれば、栄養が足りすぎている状態かも知れません。その場合は、肥料をいったん中止して様子を見てあげましょう。環境や株の強さ弱さによって肥料の加減が決まりますので、植物を観察することが必要です。
増やし方や害虫について
増やし方については、上記でも書いているように実をつけた果実が種を弾けさせて種を落とします。その方法で毎年増やすことが可能です。しかし種から育てるのは発芽する確率が低いということがあります。ご近所さんから種を分けてもらって育てるのも楽しいですが発芽しなければどうにもこうにもなりませんね。
初心者さんの場合は、まずは園芸店などで苗を購入して育てる方がより確実に成長させることが出来ます。春先になれば園芸店で見かけることが出来ますので、探してみましょう。苗から始めてその年にこぼれた種で、というならツリフネソウにふさわしい環境が整っていると言えますのでかんたんに増やすことができるのではないでしょうか。
害虫についてはあまり被害がないようです。しかし梅雨時になるとウドンコ病にかかりやすいということがあげられます。このウドンコ病にかかってしまうとなかなか治らず、完治するまで時間がかかることがあるので注意しましょう。梅雨が訪れる前に殺虫剤などを散布しておくなど対策を立てておくことも必要でしょう。
またセンチュウに対する抵抗力が非常に弱いことも気をつけなければならないポイントです。センチュウのいる土壌で栽培することはできませんので最大限の注意が必要です。消毒をマメにしておくなど対策を立てておきましょう。センチュウを防ぐためには、マリーゴールドを一緒に植えると効果があるとも言われていますので、気になる方はぜひ試してみましょう。
ツリフネソウの歴史
ツリフネソウは熱帯アジアが原産で日本列島や朝鮮半島、ロシア南東部などを生息地としている植物です。日本で自制しているのを見ることが出来るのは、北海道や本州/九州/四国などの山地です。また明るい日向よりは、日陰の涼しい場所や湿地帯などを好む植物です。
ツリフネソウの花言葉は「心を休める」「安楽」「期待」「詩的な愛」「触らないで」と様々な意味があるようです。近縁種には「ワタラセツリフネソウ」や「エンシュウツリフネソウ」などがあります。ワタラセはその名前からもわかるように渡良瀬遊水地に自生していることから名付けられたようです。
見分けるポイントは、小花弁に点在する黒いシミのような模様が特徴の一つです。「Impatiensohwadae」にある名前は、2005年にワタラセを発見した大和田真澄から付けられました。エンシュウは九州や東海地方の一部で生息していますが、2012年に環境省の定める絶滅危惧IB類に選定されています。また福岡、長野、熊本では絶滅寸前と言われており、
岐阜では準絶滅危惧種に静岡、愛知などでも危惧種に指定されています。日本古来から生息している植物ですので和歌などにも読まれる有名な植物です。季語として使われていますが、季節は晩夏から秋口にかけてを表しています。
ツリフネは「吊船」や「釣船」のどちらの表記も存在します。英語名は「touch-me-not(タッチ・ミー・ノット)」。その由来は、ホウセンカ属であるこの植物が種が出来ると弾けとんで種をまく性質があり、時期が来る前に触れないでねということからついたようです。
ツリフネソウの特徴
ツリフネソウは一年草であり、草の丈は40センチから80センチ程度に成長します。花の開花時期は夏から秋にかけてですが、山地なら8月ごろで低地なら9月から10月などと場所によって少し異なります。特徴は、その花の形にあります。花の色は紅紫色で大きさは3センチ?4センチ程度、花弁は三枚で萼片三個あります。萼片も同じく紅紫色をしているので、花びらのように見えますね。
全体の姿は筒状でさらに先が裂けて出来る形は、くちびるのような形に見えます。そして距が後ろに突き出て渦巻き状になるのでとても個性的な形をしています。くるりと巻いた距の先には蜜がたまるのでたくさんの虫たちが集まります。葉の形は楕円形で交互に生えています。表面はギザキザで細かい鋸歯がある特徴的な葉と言えるでしょう。
茎も少し赤っぽく節が膨らんで見えます。種を落とすのも個性的で、長さが1センチから2センチ程度の果実が熟すと弾けとんで周辺に種を落とします。ホウセンカやインパチェンスなども同じタイプです。ツリフネソウ属の属名である「Impatiens」は”こらえきれない”という意味を持っていることから、
ぎりぎりまで抱え込んでパーンとはじけとばすということがわかります。この植物の場合、種を”落とす”や”撒く”と言うよりは”飛ばす”がふさわしいのではないでしょうか。またこの植物には毒性があります。万が一誤って食べてしまうと嘔吐や下痢また胃腸炎などをひきおこしますので、ご注意ください。
-

-
ドゥランタ・エレクタ(Duranta erecta)の育て方
ドゥランタ・エレクタは南アメリカ原産の植物ですが、日本でも容易に栽培できるのが特徴です。植え付けをする際には肥沃で水はけ...
-

-
バラ(つるバラ)の育て方
バラの種類は、かなりたくさんありますが一般的には世界で約120種類あると言われています。記録によれば、古代ギリシアの時代...
-

-
アローカリアの育て方
アローカリアは日本においては南洋杉と言う呼ばれ方をしています。その言葉の示すとおり南から来た杉の木であると言えます。日本...
-

-
ペトレア・ボルビリスの育て方
ペトレア・ボルビリスは原産地がキューバ・ブラジルといった中南米の常緑蔓性高木です。和名では寡婦蔓(ヤモメカズラ)と呼ばれ...
-

-
キンセンカとハボタンの育て方
冬枯れの戸外で一際鮮やかに色彩を誇るのがハボタンです。江戸時代中期に緑色のキャベツに似たものが長崎に渡来して、オランダナ...
-

-
へらおおばこの育て方
へらおおばこは我が国に在来しているプラントのオオバコの仲間であり、またオオバコに似ているとされていますが、へらおおばこは...
-

-
アボカドの栽培について
栄養価が高く、サラダやサンドウィッチの具材としても人気の高いアボカドですが、実はご家庭で観葉植物として栽培することができ...
-

-
ケイトウの育て方
ケイトウの原産地は、アフリカやアジアの熱帯地方であるとされており、主な生息地としても熱帯アジアインド方面です。日本へわた...
-

-
チューリップ(アラジン)の育て方
チューリップにおいては日本に来たのは江戸時代とされています。その時にはほとんど普及することはなかったようですが大正時代に...
-

-
ブーゲンビレアの育て方
今ではよく知られており、人気も高いブーゲンビレアは中央アメリカから南アメリカが原産地となっています。生息地はブラジルから...




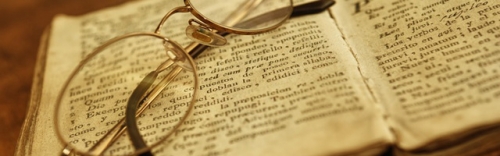





ツリフネソウは一年草であり、草の丈は40センチから80センチ程度に成長します。花の開花時期は夏から秋にかけてですが、山地なら8月ごろで低地なら9月から10月などと場所によって少し異なります。特徴は、その花の形にあります。花の色は紅紫色で大きさは3センチ?4センチ程度、花弁は三枚で萼片三個あります。