リュウビンタイ(Angiopteris lygodiifolia)の育て方

リュウビンタイの向く場所
リュウビンタイは暖かい場所の林内に生育している植物ですから、やや日陰の湿った場所に向いています。家庭では、直射日光があたらずに、レースのカーテン越しのやわらかい日差しがあたるような場所がいいでしょう。暗い所には耐える植物ですが、あまりに暗すぎると、葉の形が崩れてしまいますので注意します。
また、高さがそれほど伸びない代わりに、新芽を伸ばすと横に広がる大きな葉になりますので、幅に余裕を持たせた置き場所を確保してあげましょう。成長は著しく遅く、葉は毎年頻繁に展開しますが、成長点の高さはほとんど変化しません。徐々に基部のかたまりが成長していき、それに応じて葉が大きくなっていきます。
リュウビンタイの年間管理
一般的に園芸店やホームセンターなどで観葉植物コーナーの苗や鉢植えの状態で販売されているものを入手するのがふつうです。選ぶときは、基部のぐらつきがないものや、新芽の動きが確認できるものを選び、鉢に対してややきついくらいの状態のものの方が、植え替えてから時間が経っており、安定した状態のものが多いので、新しい環境にもなじみやすいでしょう。
インテリアグリーンとして近年人気のある植物ですが、東海以西のあたたかい場所では屋外で越冬させることもできます。関東では冬の寒さを越せないので、屋内で管理した方がいいでしょう。湿り気のある場所で自生していて、体内に含まれる水分量が多いことから、水切れには注意が必要です。
表面の土が完全に乾く前に水やりをしますが、その際は基部のかたまりに集中的に水を与えたり、きりふきをしたりと、この部分が乾燥しないように注意しましょう。夏場で、水やりをしていてもあまりに乾いてしまい、葉が垂れてきてしまうような場所で育てる場合は、受け皿に水をためて管理する場合もあります。
同じ水が溜まり続けないように、水やりのたびに受け皿に余っている水があったら交換します。春から秋の成長期は週に1度ほど、葉裏も含めた全体にシャワーをかけてあげると、湿度が与えられてきれいな状態を保てるでしょう。
比較的蒸れには強く、高温多湿の環境には耐える傾向がありますが、あまりにじめじめしすぎると、病気や害虫の発生する原因となりますので、扇風機を回したり風の通り道をつくったりと、空気が動く環境を作ってあげることで予防できます。
寒さには弱いので、最低でも10℃は保ってあげた方がいいですが、寒さに慣れた株は5℃程度でも耐えるようです。それ以下の気温では、枯れないまでも成長が止まってしまう場合が多いようです。そのため、寒冷地の冬場は、なるべく窓から離した部屋の中央付近に移動し、夜間冷える部屋の場合は、花台などを用いて地面から離すか、発泡スチロールなどで保温するようにします。
黄色く変色した葉は、軽く引っ張ると元から簡単に取れます。古い葉をそのままにしておくと、そこから病気が入りやすくなりますので、黄色く変色した時点で取り除いておくようにします。まれにカイガラムシがつくことがありますが、その部分を取り除いておけば大きく状態を悪くすることはありません。
リュウビンタイのふやしかた
リュウビンタイは胞子を飛ばして繁殖するシダ植物ですので、種ができないため、種付けからの栽培はできません。ふやすときは、基部の鱗片を使います。真夏を除いた春から秋が増やす適期で、八重桜が咲き始めた頃から作業ができます。
鱗片を親株から取ったら、あらかじめ一晩水に漬けておき、湿らせたミズゴケを使って包みます。その後、水を切らさないように注意し、明るい日陰で管理しましょう。根が出てきたら、ミズゴケをつけた状態のまま新しい鉢へ移します。根を傷めると失敗しやすいので、なるべく根を傷めずにやさしく植るようにしましょう。
リュウビンタイの植え替え
成長が遅く、頻繁な植え替えは必要ありませんが、鉢が変形するほど大きくなってしまったら植え替えを行います。一般的な観葉植物よりきつめの鉢を用い、やや根詰まり気味に育てた方が失敗しないようです。適期は八重桜が咲き始める頃から真夏を除いた秋までで、冬に入る前に十分に体力を回復させられるように配慮しましょう。
根がいっぱいに成長し、変形してしまった鉢は、叩いても抜けないことが多いので、鋏を使って鉢を切るか、陶器製の場合は割ってしまうかして、根を傷めないように取り出します。根を傷めてしまうと失敗しやすい植物ですので、なるべくほぐさずに、そのままの形で移し替えるようにします。今の鉢よりひとまわり程大きい鉢を用意し、観葉植物用の培養土で植え替えを行います。
鉢底石は入れないか、入れても少なめにしておいた方が、夏場の水切れを防止できるでしょう。植え替え後は鉢底から流れ出るまでたっぷりと水を与え、根付くまでは明るい日陰で管理します。基部のかたまりを乾かさないように注意し、新芽が動いてきたら通常の管理に戻します。
リュウビンタイの歴史
かたまりから葉が四方八方に突き出たようなユニークな形で成長していくリュウビンタイは、その基部が竜のうろこのようであることから名づけられたと言われています。古くは、「竜鱗たい」と呼ばれていたのが変化して、現在のリュウビンタイという呼び名になったと言われていますが、「たい」の字にどの漢字を使っていたか、詳しいことは分かっていません。
「竜鱗(りゅうりん)」の部分に関しては、基部の形状を表しているという説が一般的ですが、たたみ表の竜鬢(リュウビン)に葉脈の形が似ていることから来ているという説もあり、意見が分かれています。
以前は大きく成長することから、家庭での栽培は一般的でなく、植物園などで展示されるのに留まっていましたが、リュウビンタイ本来の耐陰性があり育てやすいという特徴や、他の植物にはないめずらしい形から、現在では家庭や商業施設などでも育てられるようになり人気が高まっています。
リュウビンタイの特徴
リュウビンタイは学名をAngiopteridaceae lygodiifoliaというリュウビンタイ科の植物で、世界に3属110種類の仲間がいる大型のシダ植物です。意外にも日本でも生育している植物で、生息地(植物学上、正しくは生育地といいます。)は伊豆諸島以南の日本南部からオーストラリア、マダガスカルに分布しています。
原産地では葉が1~2mほどにも伸び、巨大化して通年緑の状態を保ちますが、植物学上は大型の草であるとされています。基部のかたまりは、成長すると直径が30cmくらいになり、かたまりに応じて葉も大きくなっていきます。時間が経った葉は、元からポロっと取れますが、葉の取れた痕が丸く残ります。
葉の大きさによって茎の太さが変わるため、大きな株では痕が5cmほどになっているものもあり、特徴的な姿を形作っています。鱗片状のかたまりから、ぜんまい状の形をした新芽を出し、開くと巨大な翼のような葉の形をしていますが、小さな葉を含めた全体が一枚の葉で、このような葉のことを、羽状複葉といいます。
小さな葉のことを羽片といい、大体5~10枚ずつの数が左右対称でついています。水分のたくさん含まれたしなやかな葉で、シダ植物の特徴でもある胞子を出す胞子のうと呼ばれるつぶつぶとした器官が、葉裏の1.5mmほど内側の縁に一列になってつきます。リュウビンタイが含まれるシダ植物は、胞子を飛ばすことで子孫を残していきますので、花や種をつけないという特徴があります。
観葉植物の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ビカクシダの育て方
タイトル:アスプレニウムの育て方
タイトル:フェニックスの育て方
タイトル:ディクソニアの育て方
-

-
ヘリクリサムの育て方
このヘリクリサム、ホワイトフェアリーの一番の特徴は何といってもその触り心地です。ドライフラワーかと思うような花がたくさん...
-

-
コヨバ(エバーフレッシュ)の育て方
マメ科コヨバ属の植物である、コヨバ(エバーフレッシュ)は日本においては、原産地である南アメリカのボリビアから沖縄の生産者...
-

-
アローディアの育て方
アローディアと呼ばれる植物は、マダガスカル原産の植物です。刺のある多肉植物になりますが、歴史はとても古く江戸時代にさかの...
-

-
植物の育て方を勉強する
現在は、家庭菜園などで野菜を栽培している人たちも多く存在しています。自分で手入れをして栽培した野菜を食する事ができるのは...
-

-
ロドリゲチアの育て方
花の特徴としてはラン科になります。園芸上においてもランとしてになります。一般の花屋さんでも見つけることができますが、ラン...
-

-
ハナズオウの育て方
ハナズオウはジャケツイバラ科ハナズオウ属に分類される落葉低木です。ジャケツイバラ科はマメ科に似ているため、マメ科ジャケツ...
-

-
ムシャリンドウの育て方
ムシャリンドウという花は名前を聞けばリンドウの仲間なのではないかと考える人は多いでしょう。ですが実際は、リンドウとは何の...
-

-
イオノプシスの育て方
イオノプシスとはメキシコ〜南アメリカなどを原産地とする多年性草本です。ブラジルから西インド諸島へと分布し、ガラパゴス諸島...
-

-
ルクリア(アッサムニオイザクラ)の育て方
花の種類としてはアカネ科となっています。花が桜に似ていることからバラ科かと考えがちですがそうではありません。桜とはかなり...
-

-
オクラとツルレイシの作り方
オクラは別名アメリカネリといい、アフリカ原産の暑さに強い野菜でクリーム色の大きな美しい花の後にできる若さや食用にしてます...





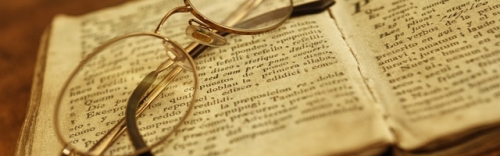





かたまりから葉が四方八方に突き出たようなユニークな形で成長していくリュウビンタイは、その基部が竜のうろこのようであることから名づけられたと言われています。古くは、「竜鱗たい」と呼ばれていたのが変化して、現在のリュウビンタイという呼び名になったと言われていますが、「たい」の字にどの漢字を使っていたか、詳しいことは分かっていません。