クチナシ(実)の育て方

育てる環境について
クチナシの花の育て方ということでは、庭木などで広く栽培されていることや、日本にも多く自生しているということで、初心者でもチャレンジしやすい植物ということになりますが、ちょうど日本でも梅雨の明ける頃から花が咲きますが、そのような花なので植え付けは、4月から5月頃になります。そして開花が6月から7月で、9月から10月でも良いようです。
また剪定は7月から8月に行います。秋以降を想定すると、花芽を枝ごと落とすことになるので、次の年に咲く花が少なくなるというデメリットがあります。それでその前に剪定するということのようです。なかなか初心者にはどうすればよいか迷うところですが、ポイントは風通しや日当たりを良くすることが目的なので、だいたいそのように剪定すれば良いということです。
枝や葉っぱが、込み入ったようなところを剪定するということになります。最近は写真や動画などでも、インターネットで見られますので、それらも参考にすると、剪定もしやすくなりますが、便利な世の中です。また剪定での注意としては、花を楽しむためですので、バッサリと気持ちよく剪定しないようにします。
また植物の特徴としては寒さに弱いということがあります。ですので寒い地方では、冬に枯れてしまうので、温かいところで鉢植えなどやプランターで育てるということになります。また夏の暑さも激しすぎると、地面が乾きすぎてうまく育たないということですので、半分日陰のようなところで育てると育ちやすくなるということになります。
種付けや水やり、肥料について
また育て方では、水やりや肥料も重要ですが、特に寒さに弱く、水分が少なくても枯れてしまう植物なので、寒い地方はむかないということや、乾燥しやすい場所でも、うまく育たないということがあります。また庭などに植える場合には、粘土質の土では育ちにくいので、腐葉土を混ぜるなどして水はけを良くしながら、土を軽くしたところに植えるのが良いようです。
あまり大きくなった苗は育ちにくくなるようですので、できるだけ若いうちに、苗を植えるのが良いそうですが、その他の注意点としては、あまり深く植えないようにして、土を盛るように、ふっくらとしている感じで植えるのがコツです。また水分がないと育ちにくいので、ワラや腐葉土で株を覆って、タップリと水をまいておくのが、植え付け時には必要な作業になります。
鉢植えの場合には、鉢の中が根っこでいっぱいになるので、少し大きな鉢に植え替える作業をします。大きめのプランターなどでも良いでしょうが、その時に根を3分の1ぐらい少なくするということも必要ということです。また植え付けは、春と秋にできますので、春に失敗しても、また秋に挑戦できるということですから、
その点でも初心者向きの植物ということになります。またこの植物の場合には、この植物を好む害虫がいて、その対処も必要になります。オオスカシバという蛾の仲間ですが、幼虫の頃に芋虫になり、葉っぱを食べてしまいます。この植物自体が小さめなので、この芋虫が増えすぎると葉っぱが全部なくなってしまうようになる場合もあるので、注意が必要です。
増やし方や害虫について
このオオスカシバという害虫ですが、蛾の一種で、羽が透けて見えるので、そのような名前がついています。面白いのは、蛾であるにもかかわらず、案外ファンも多くて、蚕の蛾とともに、蛾の仲間では美しいものの中に入っています。蚕の成虫も美しくて、真っ白ですが、なんと口がなく食べ物が食べられないということで驚きですが、自然の中では生きてはいけない成虫ということです。
そのカイコの成虫と人気を二分しているのが、このオオスカシバで、ぬいぐるみにもなっているほどですが、確かに愛らしい、蛾とは思えない昆虫でもあります。また幼虫は、本当に芋虫というような形で緑色をしていますが、愛らしさもあります。他の種類のものもあるので、必ずしも緑色だけではないようですが、綺麗な芋虫でもあります。
しかしクチナシには大敵の害虫ですので、見つけ次第駆除するということが必要になります。このお芋虫はおしりに角のようなものが生えているのでわかりやすい芋虫でもありますが、定期的に殺虫剤を撒いて駆除をするということになります。特にたくさん植えているガーデニングでは、虫も殺されないように隠れますので、
見た目には、いないようでも、駆除をしておくという作業は必要になるでしょう。害虫はガーデニングや家庭菜園では、どうしても必要な作業ですし、しかたがないことでもあります。またこの植物は、寒さや寒い風などや水分にも注意しながら水はけの良い土地で育てるようにするという注意点を守りながら楽しむ植物でもあります。
クチナシ(実)の歴史
クチナシという言葉は何かしらロマンチックな言葉でもあり、何かその言葉の背後には物語があるように想像してしまいますが、ロマンチックな名前でもあります。日本人には馴染みのある植物で、濃い白い小さなかわいい花が咲くことで知られていますが、アカネ科クチナシ属の背の低い植物です。このロマンチックな名前の由来は、あまりロマンチックではなく、
クチナシの木の実が赤い小さなものですが、蛇ぐらいしか食べないだろうということで、そのような名前がついたそうです。要するに口が必要にならないほど小さな実ということです。また漢方薬としても有名なので、歴史は古いということがわかりますが、最近はそれらの花や実が可憐で美しいということで、園芸用に栽培されているということのようです。
ですのでガーデニング等には、もってこいの植物ということになります。また背も低いので扱いやすいということで、日本でもガーデニングをしているお宅の庭などで、よく見ることが出来ます。また蟻が寄ってくる植物なのだそうで、そのことで嫌う人もいるとかですが、その点は本当の話なのかどうかは定かではありません。
多分強い香りが特徴であり、学名もジャスミンのような、という言葉だそうなので、その点からも引き寄せるというイメージがあるのかもしれません。原産地や生息地は、東アジアで、日本にも静岡以西の森林などに自生しているということなので、昔から親しまれている植物でもあるということでしょう。
クチナシ(実)の特徴
クチナシの特徴としては、やはり花の可憐さでしょうが、照り輝く白い色をしていて、まるで和菓子のような感じもしますが、最近はまるでバラのような純白の花を咲かせる品種も園芸用に生まれているので、そのような花を見たいということで、ガーデニングでも人気があるのでしょう。またイメージとしては白なのですが、この植物からは、
青い着色料が取れるということで、和菓子などの青い色付けに使われたりするそうです。また黄色の着色料にもなります。面白いものですが、他には漢方薬にも使われています。山梔子、さんししと読みますが、黄疸に効くそうで、その方面の薬としても使われているということです。なかなか人間の生活でも役に立っているということですが、
ガーデニングでも挑戦してみると面白い植物でもあります。またその花が美しいので、市の花ということでも、日本のいくつかの市の花になっているそうです。またロマンチックな特徴としては、花からのイメージでしょうが、花言葉があり、幸せを運ぶ、清潔、胸に秘めた愛など幸せになれるというイメージと結びついているということですので、
ガーデニングでも栽培しながら、そのようにイメージして育てると、幸せになれるかもしれません。暗示効果ということもあるので、幸せの花に囲まれているというイメージから、良い効果が出る可能性があるからです。けっこう人間は、そのようなイメージの世界で、幸せをつかむことができるものですので、そのような意味からも面白い花でもあります。
-

-
カロケファルスの育て方
見た目からは少し想像がつきにくいですがキク科になります。種類としては常緑の低い木になります。耐寒性としては日本においては...
-

-
にんにくの育て方
にんにくは、紀元前3000から4000年以上前から古代エジプトで栽培されていたもので、主生息地はロシアと国境を接している...
-

-
ジャノヒゲの育て方
ジャノヒゲはユリ科ジャノヒゲ属の多年草植物です。アジアが原産で、日本を含む東アジアに生息地が多く分布しています。亜熱帯気...
-

-
びわの育て方
枇杷(ビワ)は、中国南西部原産で、バラ科の常緑高木です。日本には古代から持ち込まれています。インドにも広がっており、非常...
-

-
ホヤ(サクララン)の育て方
花の名前からラン科、さくらの科であるバラ科のように考えている人もいるかもしれませんが、どちらにも該当しない花になります。...
-

-
マンションで育てて食べよう、新鮮な野菜
皆さんは野菜はスーパーで買う方が多いと思います。とくに都会に住んでいる方はなかなかとれたての野菜を食べる機会は少ないと思...
-

-
キンカン類の育て方
柑橘系果物の一つにキンカンが有ります。一言でキンカンと言っても複数の種類が有り、キンカン類としてはキンカン属が4~6種類...
-

-
カンパニュラ・メディウムの育て方
カンパニュラ・メディウムは南ヨーロッパを原産とする花で、日本には明治の初めに入ってきたものとされています。基本的な育て方...
-

-
スプレケリアの育て方
スプレケリアは別名「ツバメズイセン」と呼ばれる球根植物で、メキシコやグアテマラなどに1種のみが分布します。スプレケリアは...
-

-
サンキライの育て方
英名は「Chinaroot」で科目はサルトリイバラ科です。原産国は日本や中国、朝鮮半島、インドシナ半島などのアジアを主な...




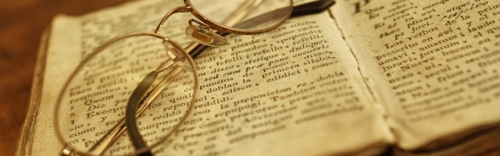





クチナシの特徴としては、やはり花の可憐さでしょうが、照り輝く白い色をしていて、まるで和菓子のような感じもしますが、最近はまるでバラのような純白の花を咲かせる品種も園芸用に生まれているので、そのような花を見たいということで、ガーデニングでも人気があるのでしょう。