クサノオウの育て方

育てる環境について
クサノオウをピンポイントに育てている資料は見つからなかったので、良く似た植物であるヤマブキソウの育て方を参照させていただきます。元々が山野草で、言い方は悪いですが雑草なのであまり神経質に栽培する植物では無いです。綺麗に育てたい人のためのコラムになります。一番大切な事は二つあります。一つ目は日当たり、二つ目は土の質です。
一つ目の日当たりに関してですが、朝日の当たる明るい日陰で育てることが重要になります。日に当たり過ぎるとダメです。あまり日差しの強くないうち、つまり春は一日中日が当たるところで育ててもかまいません。しかし、夏は日陰に移動させて日焼けを防ぐことが必要になっていきます。大体30~40%の日光が当たるように調節して行きます。
二つ目の土の質ですが、庭植えをする場合には、ある程度の湿り気のある落葉広葉樹の下が適します。落葉広葉樹の落ちた葉が腐葉土になる事を期待しての事もあります。そこの土に腐葉土を3割ほど混ぜて植えていきます。砂が多く乾きすぎる場合は黒土などを混ぜ、粘土質で湿りすぎる場合はパーライトなどを混ぜて水はけを調整して行きます。
そして植える場所の土を15cmほど土を盛り上げてから植えつけます。寒さには耐性がありますが、暑さにはあまり強くないので、庭に植える場合には注意が必要です。鉢植えにした場合は、季節によって移動させるなどして直射日光を浴びせないように注意する必要があります。
種付けや水やり、肥料について
種付けや水やり、肥料についてです。種付けは開花を終えた後、つまり6~7月に行ないます。種付けが最も効率よく増やす事が出来る方法です。タネを採取する事が出来たら、すぐに土にまきます。次の発芽時期である春先まで種が乾燥しないように土を3~5mmほどかぶせておきます。発芽をしたあと2年ほどで開花が出来るサイズにまで成長します。
発芽率は良い植物ですから適した環境であれば自然に増えていきます。次は水やりについてです。自生しているところはいくらか湿り気がある場所なので、カラカラに乾燥しないように気を付けるのは鉢植えの場合も庭に植えつける場合も変わりません。鉢植えの場合は、常にある程度の湿り気を保ちます。表面が乾かないように注意します。
ただ水のやり過ぎは根を傷める原因にもなりますので、水のやり過ぎには注意です。また、夏の間は二重鉢にするなり砂床に置くなりして暑さと乾燥から保護します。庭植えの場合も、しおれていたら十分に水を与えます。乾燥には気を付けましょう。肥料についてですが、鉢植えの場合、店から買ってきた後の植え替えの際に、
リン酸とカリウムが多めの化学合成肥料を、3号鉢一鉢当たりで、二つまみ程度施します。大きい鉢に植えた場合にはここから計算して肥料を与えます。そして初春から初秋にかけては週1回、液体肥料を1500~3000倍に薄めて追加で与えていきます。庭に植えた時は、春は鉢植えと同じように肥料を与えますが、夏は必要ありません。
増やし方や害虫について
クサノオウの増やし方ですが、種をまいて育てていく場合と、大きくなった株を株分けして育てていく方法があります。上述しましたが、種をまいて育てていく方法が簡単で効率が良い育て方になると思われます。種の採取方法ですが、少し気を付けなければいけない事があります。種の入っている莢は、熟すと弾けて種を周囲にばらまく習性があるため、
今育てている場所とは別の場所で種から育てたいと思った時には莢にネットなどをかけ、飛んで行かないようにして採取する必要があります。採取した種はすぐに土にまき、薄く土をかけ、発芽を待ちます。春になると芽を出し育っていくことでしょう。大きい株がある場合には、株を分けて増やしていく方法があります。
このときポイントになるのはあまり細かく分けないようにすることです。大きく育った株を2~3個に分割していきます。分割した後、切り口から雑菌が入る事を防ぐためにホームセンターなどで手に入る殺菌をしてくれる薬剤などを塗布しておき、植えていきます。最後に害虫や病気の事です。
元が丈夫な植物であるからか、病気についてはそこまで心配する事はないでしょう。しかし、害虫はどうしても付いてしまいます。主な害虫はアブラムシと小さなクモです。クモはともかくアブラムシが少々厄介です。ウイルス性の感染症を媒介したり、身体が出す「甘露」にアリが集る事がありますので、園芸店などで手に入る殺虫剤を使って駆除しましょう。
クサノオウの歴史
クサノオウは古くから日本に生息している山野草です。聞き慣れない植物ですが、黄色い花を咲かせるヤマブキソウに似ています。ヤマブキソウのほうが聞き覚えがあるという人が多いかもしれません。原産地、生息地はユーラシア大陸一帯とその周辺と広く分布する植物であり、日本には北海道から九州まで分布しています。
なお、クサノオウは「一種一属」で他に種が無いとヨーロッパやアメリカなどでは考えられているようですが、「アジアには数種類あるのではないか」という見解もある面白い植物です。日本では古くから民間療法の薬草として使われていました。つぼみの頃に刈り取った葉や茎を乾燥させたものを白屈菜(はっくつさい)と呼び、
特にいぼ取りや、水虫などの皮膚疾患や傷の手当てに対して使用されていました。また塗るだけでなく、煎じて飲むと胃炎などに対して効果があるとされています。しかし本来は正真正銘の毒草であり、その毒性は非常に高いので安易な使用は避けるべきでしょう。クサノオウの名前の由来はいくつかありますが、
①傷を付けると黄色い液が出てくるので「草の黄」や②怪我・病気に効くことから「草の王」などがあります。クサノオウの別名は「チドメグサ」「イボクサ」「タムシ草」など使用により期待されていたであろう薬効の名前が付いているのが面白いところです。なお、鎮痛作用も持ち合わせているため、古くはアヘンの代用品とされていたこともある植物ですがリスクが高いため今は使われていません。
クサノオウの特徴
日当たりの良い野原や森林、空き地などにも群がって自生している多年草です。秋に地面に落ちた種子はすぐに発芽して葉から成るロゼット(タンポポの葉だけが地面に沿って生えているような状態)を形成し冬を越します。ロゼットを形成している葉っぱは柔らかいです。春になるとまっすぐに空に向かって中が空洞になっている茎を伸ばして行き、
草丈は40-80cm程度までになるまで育ちます。結構大きい植物です。葉には深い切り込みが入るようになり、羽状複葉(鳥の羽のように葉が広がっていく種類の植物)となって約30cmまで伸びます。葉の表面は緑色で、下面には白く細かい毛が生えています。花は直径2cm程度の四枚の花弁をもつ鮮やかな黄色の花ですが、稀に八重咲きの花を咲かせる株があります。
開花時期は5月から7月までの長期間にわたります。花が咲き終わると長さ3~4cmの莢(さや)が上を向いて実っていきます。莢の中には半球状の黒い種子が入っていて種枕と呼ばれる白い脂肪塊のような物が付いています。これをアリが脂肪塊ごと巣まで持ち帰るので、種子が分散され運ばれ、遠くに子孫を残せるようになっています。
植物の葉を傷つけるとたくさんの種類の有毒アルカロイド成分を含む黄色い乳液が流れてきます。これが人の皮膚に触れると炎症を起こします。個人差がありますが、皮膚の弱い人は黄色い液に触れなくても、植物そのものに触れれただけでかぶれる危険があります。
-

-
ナナカマドの仲間の育て方
ナナカマドの仲間は、バラ科の落葉高木で、学名がSorbuscommixta、漢字で「七竈」と書きます。「庭七竈」は、学名...
-

-
レナンキュラスの育て方
レナンキュラスはキンポウゲ科・キンポウゲ属に分類され、Ranunculusasiaticsの学名を持ち、ヨーロッパを原産...
-

-
セッコクの育て方
セッコクは単子葉植物ラン科の植物で日本の中部以南に分布しています。主な生息地は岩の上や大木で、土壌に根を下ろさず、他の木...
-

-
ペンタスの育て方
この花については、アカネ科、ペンタス属となっています。和名の方をとってクササンタンカ属とすることもあります。熱帯植物に該...
-

-
ワスレナグサの育て方
そのような伝説が生まれることからもわかりますが、原産はヨーロッパで、具体的には北半球の温帯から亜寒帯のユーラシア大陸やア...
-

-
シモツケソウの育て方
シモツケソウは日本原産の固有種で、本州の関東地方から九州にかけてが生息地となっています。山地や亜高山の草地、林の縁などに...
-

-
バンレイシの育て方
バンレイシは果実の皮の突起の形が仏教を創設した者の頭に似ているのでシャカトウとも呼ばれているプラントです。ちなみに英語で...
-

-
サヤエンドウの育て方
サヤエンドウの歴史は大変古く、古代ギリシャ、ローマ時代にまでさかのぼります。生息地や原産は中央アジアから中近東、地中海沿...
-

-
マリモの育て方
また日本以外はどうかというと、球体のものは、アイスランドのミーヴァトン湖やエストニアのオイツ湖などで確認をされているとい...
-

-
カンヒザクラの育て方
通常の花といいますと太陽の方に向いて咲く、つまりは上向きに咲くことが多いように感じられます。スズランなど例外的な花もあり...




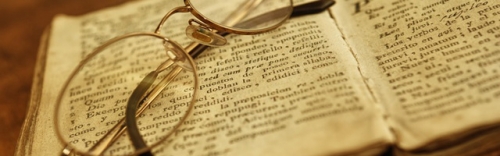





クサノオウは古くから日本に生息している山野草です。聞き慣れない植物ですが、黄色い花を咲かせるヤマブキソウに似ています。クサノオウの別名は「チドメグサ」「イボクサ」「タムシ草」など使用により期待されていたであろう薬効の名前が付いているのが面白いところです。