うばゆりの育て方

育てる環境について
このうばゆりは、育てる環境として整えやすいほうでしょう。手を掛け暇を掛けて育てるというよりは、自然の中で昔から育ってきていますから、そんなにやきになって世話をする必要がありません。地域としては、関東地方の西側から、四国と九州に咲いています。
主に、山に咲く花としての認識が一般的ですから、自宅で苗を買って育てる人はもしかしたらそんなにいないのだと考えられます。育て方に決まった方法はないために、自然と栽培が進んでいくような植物です。山登りが好きな人にとっては、結構なじみのある植物でしょうし、都会の道には咲いてないものですから、物珍しくて持って帰りたい人もいるとは考えられます。
生息地は、日本だけではありません。日本周辺から、日本を抜けて、中国やヒマラヤ周辺までもに生息しています。日本だけでなく他国でも楽しめるお花なので、中国やヒマラヤの人たちとの交流のネタにもなりますよね。その中でも、比較的にきれいなのは、ヒマラヤ周辺が原産地となる、ヒマラヤウバユリと呼ばれる植物が、
とても大きな形でお花自体がすごく美しくなります。そこの周辺の人たちは、少し気を遣って栽培しているようです。普通の物と違ってひと際きれいなら、それは手入れや自分たちの手で栽培をしたくなるものですよね。植物は、時間や愛情をかけてこその花がきれいに咲きます。花がきれいなのは、色々な人の声掛けや愛情の表れという解釈が出来ますよね。分かりやすい指標です。
種付けや水やり、肥料について
一般的に、ここではゆりの育て方について書きます。ゆりは、手間暇かけて育てることで有名な植物です。だからこその、きれいさや凛とした美しさがありますよね。まず、植え付けの時期は、10月から11月といったところです。もう少し後になっても植え付けは可能ですが、球根から出る根っこの発育が少し遅れてしまうために、避けた方がいいです。
根っこの発育が遅れると、花が咲くのが時季外れになったり、せっかくのゆりが、小さい小ぶりのお花になってしまいます。これは可能性の話なので、絶対になるというわけではないので、言いきれません。球根は、水に浸してから植えるといいとされています。そして、うばゆりの場合には、結構深く穴を掘って植える必要があります。
それは、花が成長した時に、高さが出てきますから、あんまりに浅いと、茎が支えきれなくて、折れてしまいます。そうなると、せっかくきれいに咲いたお花も台無しになってしまいます。そうならないためには、植物に対する正しい知識を持っていることが何よりも大切です。自分の未知のせいで、大切な植物の命をなくしてしまったらなんだか悲しいですよね。
水やりですが、土が乾燥しているときにだけ、水をあげれば問題なく育っていきます。毎日のように水やりをしなければならない植物に比べると、手入れや管理ものすごく簡単なような気がします。植物の手入れは簡単な方が、育てる意欲につながりますよね。ほっといても少しは成長していきます。
増やし方や害虫について
お花が枯れたら、土の下にある球根を掘り起こします。その時の注意点は、そっと掘り起こすことです。球根や、生えている根っこを傷つけないようにします。球根を掘り起こしたら、一度消毒をすると安心します。虫に食べられていたら、次がなかなか育ちません。うばゆりは、球根の状態から、もう花になる部分や芽になる部分が決まっていますから、
そこのどこかに傷がついてしまうと、もう次が咲かなくなってしまいます。それだけには気を付けた方がいいでしょう。害虫には、本当に注意が必要です。あぶらむしは、気候が温かくなると植物に飛んできて、茎から大事な汁を吸ってしまいます。その吸った時に、伝染病を移してしまうことがありますから、要注意です。
ナメクジやヨトウムシと呼ばれる害虫は、芽や花やつぼみを、食べてしまいます。あんなに小さいのに、食べてしまうのですから、侮れませんよね。ナメクジの場合、通った後には粘液茎などにべったりと付いてしまうので、すぐに見れば分かります。根切り虫と言う害虫にも注意が必要です。なぜなら、土の中で、球根から生えている根っこをかみ切ってしまうからです。
植物の成長が、極端に途中で止まってしまうようなものなら、まずこの根切り虫の可能性を考えた方がいいでしょう。日光の当たり具合や、水の下限ではなかなかそんなに植物には影響しませんから、害虫と言うのは本当に気を付けた方がいいですよね。せっかくきれいに育てているのですから、ちゃんと様子を見続けることを大切にしたいです。
うばゆりの歴史
うばゆりの歴史ですが、昔この植物を見た人が、ゆりの花が満開にきれいに咲くころには、もう周りの葉っぱが枯れてきてしまうような咲き方の状態を見て、葉っぱを歯として例えられて、歯のない人という意味で、姥という発想をしたらしいです。それから、この植物は、うばゆりと誰もが呼ぶようになったということです。
原産ですが、日本が先か、中国・ヒマラヤ周辺が先かは、あんまり正しい答えははっきりとは分かっていません。どっちにしろ、こんなに可愛い植物を見て、でも周りに全然葉っぱが無い様子を面白おかしく表現したのでしょう。何年も前から、人々に親しまれていますから、もう長い歴史を持っている植物です。
ここ近年の科学技術では、何らかの研究を重ねて、お花の色自体を人工的に決められたり、虹色に変えてしまったりすることが流行しています。そんな科学的な色よりも、うばゆりの生まれ持ったお花のきれいさをしっかりと目に焼き付けてほしいです。目先の欲望にどうしても手を出したくなるのが日本人ですが、自分たちの手で、
植物のきれいな時期を逃していたら、本当にもったいないと考えられます。ゆりも、きれいな人工的な色に変えられてしまう場合もありますが、うばゆりには、自然のままのきれいな染色がありますから、せっかくの自然の宝物を、壊さずに守っていきたいですよね。歴史に残っているままの色や形や、育て方のまま、自然に伝承していくのが本当の歴史だとも考えられます。
うばゆりの特徴
ここでは、うばゆりの特徴について細かく述べます。土より下の部分には、球根があります。この球根とは、いわゆるチューリップなどで考えれば分かりやすいでしょう。球根と呼ばれるものから根っこが生えて、そこから数本が伸びていきます。その植物によって、生え方も本数も全然違いますし、人間と同じように差がありますから、何本生えるというような確実な数字は言えないです。
土の上には、茎が伸びていきます。葉っぱは、長さが割と長いです。数字で分かりやすく言うとするなら、だいたい20センチメートルくらいを想像して下さい。その葉っぱには、よくよく細かく観察すと、網状の脈があります。縦に伸びているような感じから、徐々に開いていくようなイメージです。最後には、一見はハートの形のように見えます。
とても可愛らしい雰囲気になります。その葉っぱには、長い柄がついています。その葉っぱの長い柄は、茎の方に行くにつれて少しずつ太くなるから不思議です。植物の命であるお花の部分は、緑白色で、その長さはだいたい15センチメートルくらいの、細長いようなお花がバラバラに並びます。このばらばらに並ぶ感じが、うばゆりらしくてまた風情があります。
この花が咲く一番きれいな時期は、夏です。月で言ったら、7月から8月にかけてと言ったところでしょう。最近では、地球温暖化が進んでいますから、少し早めに咲くところもちらほらあります。それは、植物全般にも言えることですよね。花が満開にきれいに咲くころに、葉っぱが枯れてくるような咲き方をします。
-

-
シレネの育て方
シレネはナデシコ科のマンテマ属もしくはシレネ属に分類される草場であり、生息地の多くは北半球に在ると言います。また、世界的...
-

-
モクレンの育て方
中国南西部が原産地である”モクレン”。日本が原産地だと思っている人も多くいますが実は中国が原産地になります。また中国や日...
-

-
ホップの育て方
ホップはアサ科のつる性多年草で、和名ではセイヨウカラハナソウと呼ばれています。ビールの原料として有名で、その苦味や香り、...
-

-
失敗しない植物の育て方または野菜の栽培の方法
植物や野菜の育て方は、難しいと思われがちですが、植物や野菜の栽培が初心者だという人には、家庭菜園をお勧めします。プランタ...
-

-
タンジーの育て方
タンジーはキク科の多年生草本で、和名はヨモギギクと言います。別名としてバチェラーズボタン・ジンジャープランツ・ビターボタ...
-

-
ハツユキソウの育て方
ハツユキソウは背丈がおよそ1メートル程の高さに延び、その葉先に小さな花をつけます。白く色づく葉は花の回りにある唇型の葉で...
-

-
センノウの育て方
センノウは鎌倉時代の末か室町時代の初めごろ、中国から渡来したと言われている多年草です。中国名は「剪紅紗花」と書き、センコ...
-

-
シーマニアの育て方
シーマニアは、南アメリカのアンデス山脈の森林が原産の植物であり、その生息地は、アルゼンチンやペルー、ボリビア等の森林です...
-

-
デュランタの育て方
クマツヅラ科ハリマツリ族(デュランタ属)の熱帯植物です。形態は低木です。和名には、ハリマツリ、タイワンレンギョウ、などの...
-

-
ミズバショウの育て方
ミズバショウの大きな特徴としては白い花びらに真ん中にがくのようなものがある状態があります。多くの人はこの白い部分が花びら...




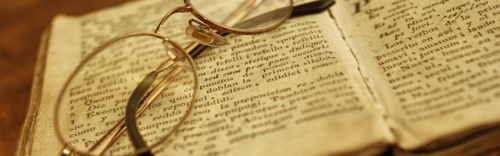





ここでは、うばゆりの特徴について細かく述べます。土より下の部分には、球根があります。この球根とは、いわゆるチューリップなどで考えれば分かりやすいでしょう。球根と呼ばれるものから根っこが生えて、そこから数本が伸びていきます。