ポトス(Epipremnum aureum)の育て方

ポトスの育て方
ポトスは登はん性がある植物です。登はん性とは、木や壁などにへばりついて上に伸びていくと新しく出てくる葉は大きく、つるも太くなることに対して、逆にハンギングなどで吊るす場合には下に伸びていく葉は小さくつるも細くなるという性質をさしています。
タワー仕立てにされているポトスは、よく見ると支柱として黒い木が使用されています。これは「ヘゴ」と呼ばれる蔓性の観葉植物にしばしば使用される植物で、支柱の役割を果たしており、ポトスだけでなくヘデラなどのつる植物を仕立てる際にも利用されています。
ポトスは、仕立て方次第で様々な魅力を感じることができるところが魅力的な観葉植物です。一年を通して、室内の明るい場所で育てることが好ましい環境です。春から秋の成育期には土が乾いてから鉢底からあふれ出るくらいしっかりと水やりをしましょう。
反対に冬は成長が緩慢になるため、夏場と同じ頻度で水やりをすることは避けます。ポトスを栽培するために適した用土は、観葉植物用として市販されている培養土を使用すると便利です。自分で配合したい場合は、赤玉土、腐葉土、少量の川砂を混ぜて使用しましょう。
肥料は、冬をのぞいた生育期に専用の液体肥料を1週間に一回程度与えるといいでしょう。成長しすぎて根詰まりを起こすと、健康な生育に影響を及ぼします。葉が下の方から枯れ落ちてきて、つるの先にばっかり葉がつくような場合は根詰まりが予想されるため、植え替えが必要です。
大きめの鉢ならば2年から3年に一度は植え替えをし、小さめの鉢の場合は1年程度で植え替えるといいでしょう。植え替える際は根についた古い土を落とし、枯れた根を取り除きます。あまり無理に力をくわえると根を傷めてしまうため、根についた土の三分の一程度を落とした方が無難です。
栽培中に注意したいこと
育て方は簡単ですが、置き場所には注意が必要です。いくら簡単に育てられる観葉植物であるといっても、適度な日光がなければいけません。ポトスはかなり日陰でも耐える植物ですが、耐えられるというだけで決して好ましい環境ではありません。
置き場所には注意が必要です。光が差し込む薄手のカーテン越しの窓際が置き場所に適しています。冬場は窓際が低温になり過ぎないように注意が必要です。最低でも置き場所の温度が8度以下にはならないように注意します。あまりにも低温になると、葉が落ちてくるためすぐにわかります。
真夏の直射日光や強烈な西日は避けて、真夏はカーテンのレース越しの光をあてるようにしましょう。強い日光によって葉焼けを起こすと、葉が茶色く変色し表面に穴があいてしまいます。春先の光であれば大丈夫ですが、夏場はとくに注意が必要です。
置き場所を間違うと、最悪の場合は枯れてしまいます。窓際におくことが難しければ普段は部屋の中において、お天気がよいときはベランダなどに出して日光浴させます。室内の湿度がある程度高い方がポトスにとっては好ましい環境です。
空気が乾く冬場は、土に水をあげるというよりは霧吹きなどを吹いて空気中の湿度を上げましょう。冬場の水やりで注意すべき点は、土が乾いてからしばらくしてから与えるようにします。最低でも表面が乾いてから三日程度は間をおきましょう。
水やりの間隔がわからないという場合は、冬場は水を与えずに様子を見て土がからからに乾いてから与えるとよいでしょう。乾燥気味に栽培する方が、ポトスにとって好ましい環境といえます。とくに安全に越冬させたい場合には、耐寒性を高めるためにも水やりはひかえめにしましょう。
注意したい害虫には、ハダニやカイガラムシがあります。放置しておくと植物を弱らせ、最悪の場合は枯らしてしまいます。見つけ次第早急に専用の薬剤を使用して駆除しましょう。他に注意したいこととして、室内で育てる都合上どうしても葉にほこりやちりなどが付着しやすくなります。
時々日光浴をかねて外に出し、葉の上からじょうろで水をまいてやるといいでしょう。水の与えすぎは厳禁のため、その後しばらくたってから通常の水やりを行いましょう。
ポトスを増やす方法
種付けするためには種を採取することが必要ですが、ポトスの種付けは一般的ではありません。種付けするよりも、挿し木で簡単に増やすことが可能です。種付けすることにこだわるよりも、剪定したときに出た葉で手軽にポトスを増やしましょう。
伸びすぎたつるをカットしたときは、捨ててしまわずに水を入れたコップなどに挿しておくと発根します。根が出たら、赤玉土か川砂などに挿しておくと簡単に増やすことが可能です。土に植えなくても、水差しで栽培を楽しむこともできます。
土に植えていたポトスを引き抜いて、根についた土をしっかりと洗い流し、ハイドロカルチャー用の焼いた土の粒などを入れた容器に挿し水を入れます。水は鉢の五分の一程度を入れ、なくなったら適宜追加するようにしましょう。
ポトスの歴史
ポトスの原産地はソロモン諸島だといわれています。原産地のソロモン諸島は南太平洋の島国で常夏の国です。一年を通じて最高気温は32度、夜間でも20度程度は気温があります。もともと、そのような気候の中で自生していたため、温かい場所を生息地としています。
ポトスという名前はスリランカでの呼び名に由来しています。常緑つる植物の多年草として分類されており、黄金蔓(おうごんかずら)という別名を持っています。葉に黄色いマーブル模様が入ることからこの名前がついたと思われます。
観葉植物といえばポトスを思い浮かべる人も多いかもしれません。日本には明治時代に渡来したとされており、観葉植物として長年愛されてきました。沖縄では路地植えで栽培されているポトスも存在しますが、多くの場合室内で育てます。
ポトスを明確に分類することは難しいのか、現在はサトイモ科ハブカズラ属(エピプレヌム属)ですが、長年サトイモ科ポトス属の植物とされていた影響で現在も園芸上はポトスという名で親しまれています。
ポトスの特徴
ポトスの葉は卵型の先をとがらせたような形で、光沢のある葉に不規則なマーブル模様が入っています。つる植物のため、自立することはできず他の大きな木にからまるようにして伸び、熱帯では数十メートルにも育ちます。
葉全体が美しいライムグリーンになる品種「ライム」や、葉に白いマーブル模様が入る「マーブル・クイーン」や、葉の覆輪にクリーム色が大きく入る「エンジョイ」などの品種が存在しています。
半日陰やある程度なら日陰でも耐えることのできる植物のため、室内で管理するために向いているということができます。しかし、いくら日陰に耐えられるからといっても日光を必要しないという意味ではありません。
もともとがジャングルのような環境に自生しているため、鬱蒼と生い茂った樹林の中で日光を求めて這い上がっていく様子が想像できます。丈夫で相当な耐陰性がありますが、ときどきは日光浴させることが健康に育てるためには必要です。
日本で普段観葉植物として様々な場所で見ることのできるポトスの葉はまだ若い葉で、ポトスは大きくなるとまるでモンステラのように葉に切り込みが入ります。しっかりと大きく成長した株でなければ成長した葉をつけることがないため、家庭ではほとんどお目にかかることはありません。
もともとが常夏の国に自生している植物のため、日本の環境下ではそこまで成長させることは難しいのかもしれません。
観葉植物の育て方や色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も参考になります♪
タイトル:クワズイモの育て方
タイトル:モンステラの育て方
タイトル:フィクス・ウンベラタの育て方
タイトル:サンセベリアの育て方
-

-
サキシフラガ(高山性)の育て方
サキシフラガは、ユキノシタ科ユキノシタ属に分類される高山性の植物です。また、流通名はホシツヅリ、別名をカブシア、ジェンキ...
-

-
サフィニアの育て方
この花の特徴としては、キク亜綱、ナス目、ナス科、ペチュニア属に属する花になります。元々ペチュニアが原種ですが、日本の会社...
-

-
ディッキアの育て方
まだまだ我々日本人にとって馴染み深いとは言えない植物、ディッキア。数多くの種を保有する植物群のなかでも、かなり特徴的な形...
-

-
ジゴペタラムの育て方
ジゴペタラムの科名は、ラン科で属名は、ジゴペタラム属となります。また、その他の名前は、紫香蘭(しこうらん)と呼ばれていま...
-

-
アメリカハナミズキの育て方
アメリカハナミズキの歴史について言及していきます。まず、このアメリカハナミズキは原産地が、その名前からわかるとおり、アメ...
-

-
ゴンゴラの育て方
花の特徴としては、ラン科になります。園芸分類はランで、多年草として咲くことになります。草の丈としては30センチ位から50...
-

-
コチョウランの育て方
コチョウランは、18世紀中頃に発見された熱帯植物で、原産地は赤道付近の高温多湿地帯です。インドネシア、フィリピン、台湾南...
-

-
オオバハブソウの育て方
オオバハブソウはオオバノハブソウとも言われ、古くから薬用として珍重されてきた薬草です。江戸時代に渡来した当時は、ムカデ・...
-

-
ローズゼラニウムの育て方
ローズゼラニウムの特徴は、やはりバラのような甘い香りです。クセのある甘ったるさではなく、ミントが混ざったようないわゆるグ...
-

-
マンデビラの育て方
メキシコやアルゼンチンなどの中米から南米などが生息地のつる性の植物です。ディプラデニアという名前で呼ばれていたこともあり...




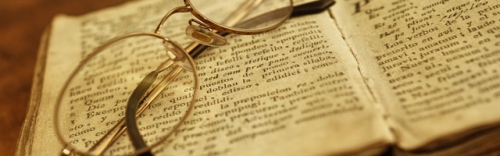





ポトスの原産地はソロモン諸島だといわれています。原産地のソロモン諸島は南太平洋の島国で常夏の国です。一年を通じて最高気温は32度、夜間でも20度程度は気温があります。もともと、そのような気候の中で自生していたため、温かい場所を生息地としています。