リコリスの育て方

育てる環境について
育て方としてはどのような環境かですが、日本において広く分布して咲いているだけにあまり気候などについては考える必要はなさそうです。まずは日当たりについて、日当たりはそれなりに必要になります。冬に霜にあたったりすると弱りますから、それを考慮して半日陰の軒下などに置くことがあります。梅雨や秋の長雨はあまり好みません。
比較的水の近くにを生息地としていることから湿気がある方がいいと考えがちですが、梅雨の行きなどに雨に当たりすぎて球根が腐ってしまう事があるようです。あぜみちなどは比較的水はけが良いので生育しやすいのかもしれません。自宅などであれば屋根がある場所などにしないと腐らせてしまうことがあるので注意が必要になります。
西日本であれば問題はありませんが、北海道や東北となるとかなり冬が寒くなります。そうなると霜の問題が出てきます。土が凍った状態になると球根が枯死してしまいますから、寒冷地においては球根が凍らない対策をしておきます。腐葉土などをまいておくことで対策できる場合があります。
水はけの悪いとこしか植えることができないような場合には高畝にします。そうすることで水は低いところに流れていくようになります。屋根などがない場合にどうしても水はけ問題を解決するときにはそのような方法も必要になってきます。庭の土でも十分育てることができますが、球根なので良い土であればより生育が良くなります。その環境づくりも必要です。
種付けや水やり、肥料について
栽培をするための用土としては、水はけと通気性を考慮して配合した土を使うよいいでしょう。適度な保水性もいります。夏などの長雨などにあったときにあまり水が残りすぎるのはよくありません。流れやすい必要もあります。赤玉の小粒を7割、腐葉土を2割、牛糞堆肥を1割ぐらいにする配合例があります。栄養を少し与えようとする配分になっています。
水やりについてはあまり行わないのが一つのルールになります。乾燥気味に育てるようにします。土が濡れているなら特に与える必要はありません。植木鉢なら乾燥したら与えますが、庭に植えている場合はほとんど乾くことがないでしょうから与える必要がないでしょう。夏においては花茎が現れる頃になると成長のために水が必要になります。
雨が十分降っていればよいですが、雨が少ない年であれば適度に水を与えるようにしておきます。成長の度合いが鈍っている時も水が問題と考えてもいいでしょう。肥料については必ずしも必要ではありませんが、きれいに咲かせようとする場合にいれたほうがいいかもしれません。
リン酸分とカリ分が重要になるとされています。元肥としては、1平方メートルあたり窒素分が10グラム、リン酸が25グラム、かりが25グラムくらいで与えるようにします。植え付ける前に行います。これだけしておけば、それなりに栄養分が行き渡ります。追肥等は必要ないとされます。冬に牛糞堆肥や、化成肥料を与えることもあります。
増やし方や害虫について
増やす方法としては分球があります。6月から8月にかけて葉が黄色に変化してきたら掘りあげてみます。自然に分球している場合があるので、あとはそれらを切り離して植えます。これは植え替えをするときにちょうどいい時期を見ながら行います。植えるときにおいては、球根の底の部分が10センチ位になるように植えます。
かなり深めに植えるようにします。球根の花によってはかなり上に植えるものもありますから、それに比べると少し変わっているかもしれません。行っておきたい作業としては花がら摘みがあります。花が咲き終わったあとに花首のところで花を折ります。比較的最後まできれいな花を咲かせるのでそのまま枯れるまで咲かせてしまうことがありますが、
長く咲かせればそれだけ株に負担がかかります。早めにそれをなくすことで、球根に栄養分が残るようになって次の年の咲き方にも影響してきます。多少のことですが、やっておいたほうがいいでしょう。栽培のサイクルとしては夏植え球根となります。夏に植えて秋に花が咲きます。葉っぱのみの状態が続きますが、夏までには葉っぱも全て枯れます。
枯れていますが球根は残ってます。地上部分がなくなったときに掘り起こして球根を掘り起こします。そして秋になったら植えるのサイクルになります。掘り起こすときに球根が複数できているようならそれを分けるようにすればどんどん数を増やすことができます。害虫などはあまり気にする必要がありません。
リコリスの歴史
秋になると田んぼのあぜみちであったり、川の河川敷などに赤い花が並ぶことがあります。誰が植えたのかと感じるくらいきれいに並んで咲いていることが多いです。おそらくは誰も植えていないでしょう。そこに種となる元があって、そのときに咲く時期になったからたまたま咲いただけと考えられます。
花においてはいろいろな使われ方がしたり、名称が付けられることがあります。そのときにたまたま付けられた名前によって、その花の将来も大きく変わることがあります。その一つがリコリスと呼ばれる花になるかもしれません。日本においてはなんと呼ばれているかといえば主にヒガンバナと名付けられています。
その他にはマンジュシャゲと呼ばれることもあります。田んぼのあぜみちなどに自然に生えていますから、わざわざ購入したりすることはないでしょうし、植えたりすることがないのかもしれませんが、なんといってもヒガンバナと付けられたことによって日本ではあまりいいイメージの花ではないとされています。
他の花にはない美しさがあるにも関わらず、あまり栽培、生産などを行うようなことがありません。主に日本と中国が原産地で生息地になっていますが、その美しさからヨーロッパなどでは珍重されるようになっています。マンジュシャゲの名前については仏典に由来するとされています。リコリスに関しては、ギリシア神話の女神の海の精の一人の名前から付けられたとされます。美しい人の象徴として付けられたのでしょう。
リコリスの特徴
種類としては、クサスギカズラ目、ヒガンバナ科、ヒガンバナ亜科、ヒガンバナ連、ヒガンバナ属になります。園芸上の分類としては草花、球根になります。花の咲き方としては多年草になります。草の丈は50センチぐらいになることが多いようです。花が咲くのは夏の終わりから秋にかけてとされます。
彼岸の日に近いとされていますが、恐らく名前が付けられたのは旧暦の頃でしょうから少しずれるかもしれません。日本でよく見られるのは赤色です。たまに白色を見ることができます。その他に新しい色としては黄色やオレンジ、ピンク、紫色などのものも出てきています。これらはなかなか自然に咲いている様子は無いかもしれません。
日本において毎年咲くことからわかりますが、耐暑性については強いです。耐寒性もそれなりにあります。落葉性なので咲いたあとは茎のほうから枯れますが球根部分が残っていますから次の年にまた生えてきます。こちらについては有毒性があることが知られています。草の部分、花の部分などに有毒物質が含まれています。
花は非常に変わっていて散形花序となっています。基本的な花びらとしては5枚から6枚あります。この花びらが少し細めになっています。花が咲くときはたいてい複数並んで咲くときは同じ方向を向いています。葉っぱに関しては深い緑色になっていて、艶があります。葉っぱに関しては冬の間は出ていることがありますが春になると枯れ、夏になってまた咲き始めます。
-

-
スイカの育て方
栽培スイカの原産地と言うのは、色々な説が在ります。しかし、最も有力とされるのが、1857年にイギリス医療伝道者がアフリカ...
-

-
アプテニアの育て方
この花については、ナデシコ目、ハマミズナ科となっています。多肉植物です。葉っぱを見ると肉厚なのがわかります。またツヤのあ...
-

-
プシュキニアの育て方
プシュキニアはトルコやレバノンの辺りを生息地としている高原に咲く花として知られている花です。球根が取れる花であるという特...
-

-
ヒナガヤツリの育て方
ヒナガヤツリは、カヤツリグサ科カヤツリグサ属の植物です。ヒナガヤツリの原産地は北アメリカですが、主な生息地はオーストラリ...
-

-
クレピスの育て方
クレピスは学名で、モモイロタンポポ(桃色蒲公英)というキク科の植物です。ただし、クレピスの名前で呼ばれることも多いです。...
-

-
マンゴーの育て方
マンゴーは、ウルシ科のマンゴー属になります。マンゴーの利用ということでは、熟した果実を切って生のまま食べるということで、...
-

-
ムラサキサギゴケの育て方
ムラサキサギゴケは、ハエドクソウ科のサギゴケ属になります。和名は、ムラサキサギゴケ(紫鷺苔)でその他の名前は、サギシバな...
-

-
ユリ(百合)の育て方
ユリに関しては、北半球のアジアを中心に広く分布しているとされています。亜熱帯から温帯、亜寒帯にかけても分布されている花に...
-

-
シュンギクの育て方
キク科シュンギク属に分類されるシュンギクは、20cmから60cmの草丈となる一年草植物であり、春には花径3cmから4cm...
-

-
グラプトペタラムの育て方
グラプトペタラムは様々な品種があり日本ではアロエやサボテンの仲間として扱われることが多く、多肉植物の愛好家の間でとても人...




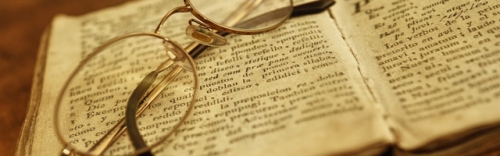





種類としては、クサスギカズラ目、ヒガンバナ科、ヒガンバナ亜科、ヒガンバナ連、ヒガンバナ属になります。園芸上の分類としては草花、球根になります。花の咲き方としては多年草になります。草の丈は50センチぐらいになることが多いようです。