ヤマボウシの育て方

育てる環境について
栽培をする場合にどのような環境を求めるかでは、日当たりの良い場所が好まれる場所になります。1日中日当たりがないといけないわけではなく、午前中優し目の日当たりが当たるようであれば問題はありません。花は小さいタイプのものになり、花がついて実をつけることになりますから、日当たりのいいところに置くことによってそれらを実現しやすくなります。
西日に関してはあまりよくないとされていますから、西日が咲けられるようなところがベストポジションになるかもしれません。土の状態としては乾燥している方がジメッとしている方が良いかではやや乾燥した場所が良いとされています。日本全土で育つタイプです。
日本はそれ程ジメッとしたところはなく、ある程度の日差しがあるところでは地面は乾く状態になることが多くなります。そのことからも少し乾き気味のところが好まれます。やや乾燥気味とは具体的に言えば通気性はあるが、それなりに透水性があることを示します。完全に乾きやすいようなところだと水をあげた時だけ水分があるようなことがありますが、
そうすると頻繁に水分をあげなければならなくなります。保水をしてくれるような土であれば、一度水を与えればそれでしばらく与える必要がなくなります。庭などに直植えをするようなときはほとんど水を与えないとしても土の中に水分が含まれている状態なのでそれ程普段の水を必要としなくなります。良い肥沃な土が良いとされます。
種付けや水やり、肥料について
育て方においては水はけ、水持ちの良い土を利用します。植木鉢の時には特に水持ちが良くなるようにしなければいけません。地植えの場合においては、そのまま植えることもありますが、植えるところに堆肥や腐葉土を混ぜ込むようにして土にエネルギーを与えておきます。鉢植えの時の配合例としては赤玉土を7割、腐葉土を3割にした土を用意しあす。
水はけのよい土に仕立てます。水やりに関しては、地植えにおいては、植えたときにしっかりと水を与えます、根がつくまでは管理が必要になってきますが、一度根がつくようになればそれ以降は水を与える必要はありません。土の中の水、雨水などが常にある状態なので、底から水分を得ることができます。
植木鉢は水を保水する能力が異なりますから水を全く与えないのはよくありません。春から秋にかけて水をしっかりと与えるようにします。土は水はけ重視タイプですから、水が残りにくく、それ程過湿にはならないでしょう。この樹木においては、冬に落葉すると休眠状態に入ります。
成長に関してはストップしますからそのときに水はほとんど必要としません。植木鉢も乾燥した状態を保つようにしておいても育てることができます。肥料については、落葉期に与えるようにすると良いとされます。秋から冬にかけて落ちていきますが、油かすと骨粉を混ぜたものを株元に置きます。植木鉢などなら花の後、落葉直前の時期に化成肥料を置くようにすると生育が良くなります。
増やし方や害虫について
増やし方では種から増やす方法で行うようにします。秋になると果実が実ります。赤く熟したタイプになります。果肉を取り除いてすぐに巻く方法と、保存して次の年の3月ぐらいにまく方法があります。3月まで保存するときは種の保管に気をつけなければいけないとされています。それは種を乾かしてはいけないからです。
乾かしてしまうと発芽する能力が衰えるとされています。最も簡単なのが秋にすぐまく方法となりますが、もし春にまきたいなら湿らせた砂と一緒に混ぜるなどして保管をします。種をまいた後については、発芽まで十分に水を与えるようにします。発芽してきてからも管理を怠らないようにします。本葉が数枚出てくるようになってくれば管理を変えます。
掘りあげて、根の先端部分を切って植えつけるようにします。なぜ大事な根を切るかですが、そうすることをしたほうが水分や肥料の栄養分を吸いやすくなるからです。その後にたくさんの根がつきやすくなるとされます。必ずしないといけないわけではないですが、成長を早めることができます。
種をまいたとして花が咲くまでどれくらいかかるかですが7年から8年とされます。結構長くなりそうです。種から植えたもので2年から3年経ったものに接ぎ木をすることがあります。そうすることで増やすことも可能です。病気としてはうどんこ病の可能性があります。梅雨時期に出やすくなります。害虫としてはテッポウムシに注意しながら育てます。
ヤマボウシの歴史
街路樹としては、かつては見た目の美しさなどが考慮されて選ばれる事があったようです。サクラは春にきれいな花を咲かせて、秋は紅葉します。イチョウは緑の葉っぱ、黄色い葉っぱ、更には銀杏が風物詩になることがあります。しかし両者とも花が落ちたあと、葉っぱが落ちた後が大変です。
とくに葉っぱが落ちた時に両方ともに滑りやすいタイプになっていることから、最近は別の樹木が選ばれることがあります。それはハナミズキとされます。花はサクラよりも少し遅れて咲きますが、サクラのようなきれいな花をつけます。花などは散りますが、サクラに比べると掃除も楽になるようです。
こんなハナミズキに近い植物としてヤマボウシと呼ばれる樹木があります。原産としては、日本を始めとして朝鮮半島や中国もあるので、自生していたのか、ある時期に伝えられたのかはわかっていません。この花については、江戸時代にヨーロッパに渡って鑑賞樹木として栽培されているとの記録があります。
この花にはなんとも人間らしい名前が付けられています。花を見ると4枚の白い花びらがついています。どこかずきんをかぶった法師に見えるような気がするでしょう。そのことからこのような名前が付けられたとされています。その他の名称としてはヤマグルマと付けられていることもあります。この木においては基本的には落葉樹で葉を落としますが、常緑タイプがあります。同属になりますが、種類は異なる気になります。
ヤマボウシの特徴
木の特徴として、被子植物に該当します。ミズキ目、ミズキ科、ミズキ属とされています。サンシュ属とされることもあります。園芸分類においては、庭木であったり、花木として利用されることが多くなります。木においては非常に高くなることがあり、10メートルぐらいから15メートルに達することもあるとされています。
花が開花するのは6月中旬から7月ぐらいとされています。ハナミズキに関しては4月頃を中心に咲く花なので、それに比べると少し後に咲かせることがわかります。名前からして花の色に関しては白が多くなります。その他にはハナミズキのようなピンク色のものや、薄い緑色の花を咲かせることもあります。
耐寒性、耐暑性についてはそれなりにありますから、生息地の日本においては栽培しやすいと言えるかもしれません。常緑タイプもあるとされますが、基本的には落葉性のある植物になります。幹は灰褐色になります。一般的な樹木のように茶色ではありません。葉っぱは楕円形ですが、先端部分がやや細くなる卵円形の種類もあります。
葉っぱの大きさとしては4センチから12センチぐらいになっています。きれいな緑色をした葉っぱです。花は淡い黄色で非常に小さくなります。これは非常に小さいので通常はわかりません。では普段花びらのように見えているのは何かですが、これは総苞片と言われるもので、葉っぱに近い役割をします。確かに葉っぱのような雰囲気があります。果実は9月頃に付きます。
-

-
カラスウリの育て方
被子植物に該当して、双子葉植物綱になります。スミレ目、ウリ科となっています。つる性の植物で、木などにどんどん巻き付いて成...
-

-
レナンキュラスの育て方
レナンキュラスはキンポウゲ科・キンポウゲ属に分類され、Ranunculusasiaticsの学名を持ち、ヨーロッパを原産...
-

-
ツルコケモモの育て方
原産地は北アメリカ、東部で、果樹・庭木・花木として植えられることが多いです。耐寒性は強いですが、耐暑性は弱いです。ツルコ...
-

-
ストロベリーキャンドルの育て方
ストロベリーキャンドルは、ヨーロッパ・西アジアが原産の植物で、自生していました。一年草とされ、蜜を取るためや肥料として、...
-

-
ディサの育て方
ディサは、ラン科ディサ属、学名はDisaです。南部アフリカを中心とした地域が原産で、そのエリアを生息地としている地生ラン...
-

-
アケビの育て方
アケビはまず中国の歴史に現れます。中国で最古の薬物学と書と言われている「神農本草経( しんのうほんぞうぎょう)」という本...
-

-
トリテレイアの育て方
トリテレイアは、ユリ科に属する球根性の多年生植物で、かつてはブローディアとも呼ばれていました。多年生植物というのは、個体...
-

-
レモンバーベナの育て方
レモンバーベナは、クマツヅラ科イワダレソウ属の落葉低木です。軽く触れるだけでもかぐわしいレモンの香りがします。この香り代...
-

-
アイビーゼラニュームの育て方
特徴としては多年草です。基本的には冬にも枯れません。非常に強い花です。真冬においても花を維持することもあります。ですから...
-

-
ハナカンザシの育て方
原産地はオーストラリア西南部で、砂地でよく育ち乾燥を好み自生しています。日本ではドライフラワーなどに良くつかわれています...




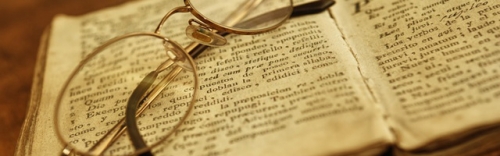





木の特徴として、被子植物に該当します。ミズキ目、ミズキ科、ミズキ属とされています。サンシュ属とされることもあります。園芸分類においては、庭木であったり、花木として利用されることが多くなります。