サンザシの育て方

サンザシの育て方
花、実、紅葉と楽しみどころの多いサンザシは、庭木に迷っているならぜひ選びたい花木です。丈夫な育て方にはいくつかおさえておきたいポイントがあります。基本的な育て方としては、強烈な西日を避けた日当たりがよい場所で育て、土が乾いたらたっぷりと水を与えます。
庭植えにする場合は、夏の時期に極度に乾燥することを避け、みずはけがよく日当たりの良い場所に植え付けます。鉢植えで育てる場合でも通年を戸外に置き、真夏は西日が強烈にあたるような場所は避けて育てます。
鉢植えでの栽培は、根詰まりを起こして生育に影響を与えないように植え替えに気を配る必要が出てきますが、季節や必要に応じて比較的簡単に置き場所を移動できるところが良いところです。
庭植えの場合には水やりは必要ありませんが、夏場に長く雨が降らないような場合は高温で極度に乾燥してしまうことがあるため、あまりにも乾いているようであれば水を与えましょう。サンザシは他の樹木に比べてもそれほど生育が旺盛ではないため、鉢植えで栽培することも充分に可能です。
用土はとくに選びませんが、水はけと水持ちのよいものを使用しましょう。赤玉土、鹿沼土、腐葉土などを配合した用土がおすすめです。肥料は庭植え、鉢植えどちらの場合も3月頃に緩効性肥料や油かすを与えます。植えつけは生長が緩慢になる10月頃か、真冬をのぞいた2月下旬から3月頃に行いましょう。
根鉢の二倍の深さと幅のある穴を掘って植え、掘り出した土に腐葉土を混ぜて栄養をたっぷり与えてから使用します。水をたっぷり与えた後に、細めの棒などでつついて土と根をなじませるとよいでしょう。ぐらつくような場合には、必要に応じて倒れないように支柱を立てます。
栽培中に注意したいこと
サンザシは栽培中に害虫がついたり、病気にかかったりする可能性があります。主に注意したい病気は、うどんこ病、黒星病、赤星病などです。うどんこ病は葉に粉がふいたようになり、美観を損ね株を弱らせます。黒点病は葉に黒い円形の斑点があらわれて、症状が広がると落葉します。
赤星病はさび病の一種で、カイヅカイブキなどのビャクシン類から感染するため、サンザシの近くには植えないようにしましょう。注意したい害虫には、アブラムシ、カイガラムシ、テッポウムシなどがあげられます。テッポウムシは幹の中に入り込み、内部を食い荒らすためにぱっと見では被害に気づきにくいのですが、穴を掘って侵入するため根本のあたりに木くずをまき散らします。
気づいたときには幹の内部がすかすかになっていたという状態にならないためにも、早めの発見が木を守るための鍵となります。害虫は早期発見し、徹底的に駆除することをおすすめします。ブラシや針金などを使って取り除く方法もありますが、専用の薬剤を使用すると便利です。
その他に注意したい点として、生長にともない樹形が乱れることが考えられるため、花が終わった6月頃に剪定を行う必要があります。秋以降に剪定を行う場合には枝先を軽く切る程度にとどめ、花芽を切らないようにしましょう。どんな樹木にもいえることですが、枯れ枝や伸びきった枝をとりのぞき、日当たりと風通しを良くすることが必要です。
サンザシには30cm以上伸びた長い枝には花芽がつきにくく、10cm程度で伸長が止まった枝に花芽がよくつきやすいという性質があるため、長い枝は切り、短い枝は残すやり方が基本的な剪定の仕方です。木が若いうちは、旺盛に枝を伸ばします。
若木のときは花付きよりも樹形を整えることに専念し、ある程度成長してからは定期的に剪定を行います。見た目の問題だけでなく、風通しをよくすることで病虫害を防ぐことにもつながります。花木を健康的に成長させるために、より多くの花や果実をつけさせるために必ず剪定しましょう。
サンザシの増やし方
種付けを成功させるためには種を採取した後、すぐに小粒の赤玉土にまいて、土を1cmほどの深さになるようにかぶせて、乾かないように水やりをします。可能であれば、鉢ごと土に埋めておくと乾燥を防止することができ、発芽率が高まります。
乾かさないように管理することができれば、春になって温かくなると芽吹きます。接ぎ木にする場合は台木を用意することが難しく、さし木にも向いていないため家庭で増やしたい場合には種付けすることが一般的です。
果実ができない種類の場合には接ぎ木をして増やす方法をとります。八重咲きの品種には果実ができません。接ぎ木に適している季節は3月頃です。台木にはマルバカイドウやミツバカイドウの苗を使用しましょう。
サンザシの歴史
サンザシの原産地は中国で、主に北半球の温帯を生息地としています。日本や中国に自生している種類の中には、花や実が美しいものなど多種多様ですが、盆栽などに仕立てられ多くの人々に親しまれています。サンザシはバラ科の落葉低木です。
園芸目的で使われる品種は、大きく分けて中国産のサンザシとヨーロッパを原産地とするセイヨウサンザシの二種類があります。花を楽しむ種類はヨーロッパ産、実を楽しむ種類は中国産として大きくわけることができます。サンザシは山査子と書き、山に実っている実、という意味から名づけられたという説があります。
ヨーロッパではメイフラワーという名称で親しまれ、セイヨウサンザシが街路樹や庭木として栽培されており、別名をホウソーンといいます。日本では主に、白い花を咲かせ赤い果実をつかせるサンザシや、ピンク色の花をつけるセイヨウサンザシが栽培されています。
日本に渡来したのは1734年頃といわれ、果実や種を薬用に用いることを目的として栽培されるようになりました。サンザシの果実と種には整腸作用があるといわれ、漢方にも用いられています。
サンザシの特徴
サンザシの特徴として、花を観賞して楽しむことができることと実を食用にして楽しむことができることの二種類があげられます。サンザシは高さ2メートルほどに成長する落葉性の低木で、春になると白い花を咲かせます。耐寒性が強く、生垣などにも向いている植物です。
寒冷地に自生する樹木ですが、寒さだけでなく暑さにも強く初心者でも栽培しやすいと考えられます。花だけでなく実を楽しむこともでき、落葉樹のため紅葉を楽しむことが可能です。楽しめる部分の多い花木として、多くの人々に愛されてきました。
品種は700種類から1000種類もの種類があるといわれています。バラ科の植物のため、枝にはとげがあるため扱いには注意が必要です。小さな丸い実をつけることが特徴で、9月から10月頃になると赤く色づきます。中国では薬用として果実や種を利用したり、食材として果実酒に使用したり砂糖漬けにしてお菓子として愛されています。
果実が美しい種類のものにオオサンザシがあり、果実は直径2.5cmほどになり、串に刺して水あめをからめたお菓子に利用します。見た目も美しく華やかで、主に中国北部で親しまれているお菓子です。セイヨウサンザシは主に花を観賞することを目的とされ、代表的な品種には八重咲きのポーリーがあります。
庭木の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も参考になります♪
タイトル:アベリアの育て方
タイトル:テイカカズラの育て方
タイトル:サルスベリの育て方
タイトル:カナメモチの育て方
タイトル:ウメモドキの育て方
-

-
アピオスの育て方
アピオスは食材で、北アメリカは北西部が原産地のマメ科のつる性植物で肥大した根茎を食べます。アピオスは芋でありながらマメ科...
-

-
マイヅルソウの育て方
こちらの草花の特徴としてクサスギカズラ目、クサスギカズラ科、スズラン亜科となっています。見た目は確かにスズランに似ていま...
-

-
ツルムラサキの育て方
ツルムラサキがどこに自生していたのかというのは、詳しくは分かっていないのですが、熱帯地域が原産だろうと考えられています。...
-

-
コンフリーの育て方
コンフリーは、日本では様々な文化が海外から入り、人々に受け入れられ始めた明治時代に日本に牧草として元々は入ってきたとされ...
-

-
イイギリの育て方
イイギリは日本原産の落葉高木です。昔から人々に親しまれてきた木ですが、それはイイギリという名称からもわかります。別名とし...
-

-
シャスタデージーの育て方
シャスタデージーの可憐な花は、アメリカの育種家である、ルーサー・バーバンクによって作り出されました。ルーサー・バーバンク...
-

-
トロロアオイの育て方
トロロアオイは花オクラとも呼ばれるアオイ科の植物の事です。見た目はハイビスカスみたいなとても美しい花を咲かせます。この花...
-

-
メカルドニアの育て方
メカルドニアはオオバコ科の植物で原産地は北アメリカや南アメリカですので、比較的暖かいところで栽培されていた植物です。だか...
-

-
ガジュマルの育て方
原産地からもわかるように亜熱帯地方を生息地とする、クワ科の常緑高木です。沖縄ではガジュマルを「幸福をもたらす精霊が宿って...
-

-
オヒルギの育て方
オヒルギはマングローブを構成する植物の種類のうちの一つです。仲間の種類として、ヤエヤマヒルギやメヒルギなどがあります。自...




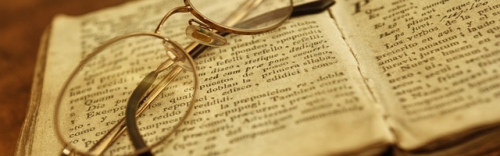





サンザシの原産地は中国で、主に北半球の温帯を生息地としています。日本や中国に自生している種類の中には、花や実が美しいものなど多種多様ですが、盆栽などに仕立てられ多くの人々に親しまれています。サンザシはバラ科の落葉低木です。