ヤーコンの育て方

育てる環境について
栽培をするときにおいてはどのような環境づくりをしていく必要があるでしょうか。まずは日当たりのいいところになります。恐らく育てるとすれば畑のようなところになるでしょう。あまり周りに塀や木などがあるようなところは好ましくないかもしれません。もちろん家庭菜園としても作ることができますが、その時には日当たりがしっかり得られるところを探すようにします。
生育するにあたっての適正温度としては15度から23度となっています。生息地がアンデス地方とあってそれ程高い温度のところではありません。そのこともあってか、日本においてもそのような気候が求められます。春先や秋などであればこのような気温になることがありますが、夏が近づいてくるとすぐに25度を越えますし、冬に近づくと10度を切ることも出てきます。
どちらも該当するところとなると結構難しいかもしれません。問題としてあるのが生育期間です。大体半年ほどかかるとされています。1月に植えたとして6月頃に収穫になります。となるとその間の気温差が非常に大きい状況になります。そこで育てることが出来るかどうかです。
なんとか収穫できたとしてその次に続けて作ることが出来るかどうかですがそうもいきません。連作障害が出ることがあるとされています。ですからうまく作ることができた場合、同じ土地で作るのは少し休む必要があります。2年から3年は間を空けないといけないですから、その環境を探す必要があります。
種付けや水やり、肥料について
育て方としてはまずは土作りからになります。花を楽しむだけであれば花がきれいに咲けばいいでしょう。しかし作物を収穫するのであればそれなりに栄養分などを得た土などが必要になることがあります。土の酸度としては弱酸性が良いとされます。ペーハーであれば5.0から6.0の土壌が良いとされます。
酸度が強くなっている時には石灰をまくことで弱めることができるので調整しておくとよいでしょう。植え付けをする2週間ぐらい前までに行っておきたいのが苦土石灰をまくこと、1週間ぐらい前に葉堆肥や化成肥料をまく作業を終えておきます。土壌改良材を作って混ぜることがあります。
堆肥が2キロに対して苦土石灰が1メートル平方あたり100グラム、化成肥料も同量になります。耕すことができたら畝の中央に20センチの溝を掘って堆肥をまいておきます。水やりについてはまず苗を植えた時にしっかりと与えるようにします。後は土の状態を見ながら乾かない程度に行うようにしていきます。
夏場などの梅雨の時期などは水の調整をしながらまくようにするといいでしょう。肥料については追肥を行うのが良いかもしれません。植え付け後2週間後具合に1回目の追肥を行います。化成肥料を巻いていきます。その後は6週間ぐらい後に同じように化成肥料を追肥します。しっかりと成長させたければ追肥はある程度必要になってきます。様子を見ながら少しずつ行っていく必要があるでしょう。間隔も必要です。
増やし方や害虫について
増やし方としてはまずは土との相談が必要かもしれません。連作障害が出ることがあるとされています。他の作物に比べると出方としてはそれほどないとされますが、せっかく栽培をしてあまりうまくならなかったとしたら連作の影響が出ている可能性があります。増やすのは良いですが、その分次の年に植えるところの確保を考えなくてはいけません。
計画的に行う必要があるでしょう。では増やすときにはどのようにしていくのが良いかです。じゃがいもなどにおいては種芋を用意してそれを次の年に植えて増やすことがあります。この植物は根からは芽が出ないタイプになるのでそのようにして増やすことはできません。芋を収穫したらその後に株から育ってくる新しい芽があります。
その芽を次の年に植えつけることで育てていくことになります。新しい芽が無いのであれば別途購入などをしなければいけませんが、その時には複数に分けることが出来る場合があるので、株数としては増やすことができます。ただし大きくない株を無理に分けようとすると作った芋が小さいタイプになったりするので気をつけないといけません。
しっかり成長した株において、その芋を収穫した後に分けるようにしていけばよいでしょう。この植物においては害虫もあまりつきにくいとされています。無農薬で栽培することも可能な種類です。しかしヨトウムシがつくことがありますから注意をします。増える前に防除することで被害も抑えられます。
ヤーコンの歴史
日本の主食としてはお米になっています。お米を主食としているところは比較的多く、アジアにおいては結構あると言ってもいいでしょう。韓国などでは日本と同じように炊いて食べますから、非常に近いご飯を食べることができます。主食においてはその他には小麦としているところが多いです。
小麦そのものよりもパンやパスタにして食べることが多いようです。形を色々と変えることが出来るのがメリットになるでしょう。その他にあるのがイモ類になります。日本においてもじゃがいも、さつまいもがよく知られています。その他にはサトイモなども煮付けなどにして利用することがあります。
そんな中で新しいイモ類としてあるのがヤーコンと呼ばれる植物になります。こちらについては南米のアンデス山脈地方が原産とされています。こちらの地方の主食として利用されているようです。日本に最初にやってきたのは1970年代とされますから非常に最近の事です。食糧難とは程遠い高度経済成長のまっただ中にやってきたとされます。
それも少し変わった経緯があります。南米から直接伝わったのではなく、アジアのある国を経由しています。なぜそうなったのかはよくわかりません。結局その時は定着せずに栽培されるまでには至らなかったようです。その後1985年にニュージーランドで栽培されているものが入ってきます。現在日本で栽培されているものについてはこの時に輸入されたものとして知られています。
ヤーコンの特徴
特徴としてはまずはキク類、真正キク類、キク目、キク科、キク亜科、メナモミ連、スマランサス属となっています。キクの仲間であることがわかっています。多年草ですから毎年花が咲き、収穫などもすることが可能になります。芋として食べるのは他の芋同様に根の部分になります。この根についてはフラクトオリゴ糖と呼ばれる物質がたくさん含まれています。
そのために甘みがあるとされています。主に食用として使われています。根については塊根型となっています。さつまいものようにどんどん肥大するが、この芋から目が出るわけではありません。その点ではじゃがいもとは少し異なるといえるでしょう。見た目としては非常にさつまいもに似ています。
さつまいもはきれいな紅色をした皮がついていますが、この植物はじゃがいものような土色、砂色の皮になっています。花のダリアと同じような地下茎を持っている特徴もあります。この地下茎が塊茎状に発達することによりどんどん発芽して成長することが出来る場合があります。
この植物については、草丈としては1.5メートルから2メートル近くに伸びることがあります。花が咲きますが、タイプとしてはひまわりに似た花で、同じように黄色の花が咲きます。ですから花を楽しむために咲かせようと考える人がいるかもしれません。じゃがいもなどは白っぽいシンプルな花になりますが、鮮やかな花が咲きますから、芋が収穫できなくてもあまり不満はありません。
-

-
ポリシャスの育て方
特徴としてはまずはウコギ科になります。その中のタイワンモミジ属になります。原産地、生息地においては2メートルから8メート...
-

-
ラセンイの育て方
”ラセンイ”は畳の原料である「イグサ」と同じ種類の植物になります。葉っぱが退化し、くるくるとらせん状にうねうねと曲がって...
-

-
ニンニクの育て方
ニンニクの原産地は中央アジアと推定されていますが、すでに紀元前3200年頃には古代エジプトなどで栽培・利用されていたよう...
-

-
スイセンとシクラメンの育て方について
ここでは、植物の育て方についてお伝えします。秋に植えつけをする花といえば、スイセンやシクラメンがありますね。スイセンとい...
-

-
ニューサイランの育て方
ニューサイランはニュージーランドを原産地としている植物であり、多年草に分類されています。ニューサイランはキジカクシ科、フ...
-

-
じゃがいもの品種と育て方
じゃがいもは、寒さに強い植物です。人気は男爵やメークイン、キタアカリです。男爵は粉質が強いので、じゃがバター・ポテトフラ...
-

-
エマルギナダ(ヒムネまたはベニゴウカン)の育て方
この花についてはマメ科、カリアンドラ属となっています。和名においてネムが入っていますが、基本的にはネムは全く関係ありませ...
-

-
バーバスカムの育て方
バーバスカムはヨーロッパ南部からアジアを原産とする、ゴマノハグサ科バーバスカム属の多年草です。別名をモウズイカといいます...
-

-
ダイモンジナデシコの育て方
ダイモンジナデシコの歴史や由来をたどってみると、ダイモンジナデシコはナデシコ科に属しますが、ナデシコはトコナツの異名をと...
-

-
スネールフラワーの育て方
スネールフラワーの原産地や生息地は中央アメリカから南アメリカの熱帯地域です。ベネズエラであるというのがよく言われているこ...




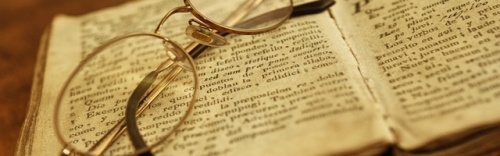





特徴としてはまずはキク類、真正キク類、キク目、キク科、キク亜科、メナモミ連、スマランサス属となっています。キクの仲間であることがわかっています。多年草ですから毎年花が咲き、収穫などもすることが可能になります。