マトリカリアの育て方

育てる環境について
栽培をする時、育て方として良い環境はどのようなところかですが、1年を通して日当たりのいいところを考えるようにします。しかし日本の夏には弱い性質があります。高温多湿にはあまり強い花ではありません。そこで風通しを考えた置き場、場所、環境を作るようにします。風が流れる様なところに置くようにし、風がこもってしまうようなところ、
ジメジメしている様なところは避けなければいけません。耐寒性は強いとされていますが、あまり寒すぎるところは適さないとされています。霜がおりるようなところになると枯れてしまうことがあります。霜対策においては寒いところであっても全くできないわけではありません。簡単に出来る方法としては冬は株元を腐葉土などで覆うようにするばあいがあります。
そうすると冬を越すことができます。鉢植えであれば移動が可能になるので、屋根のあるベランダなどで寒さを抑えるようにします。庭植えの時は環境においては少し考慮をします。毎年同じ場所で育てようとすると生育が悪くなることがあります。これは連鎖障害と言われるものになります。冬においては寒い風が吹くところはよくありません。
北風が吹くと影響しやすいことがあります。そこで備えるような対策ができるところにします。ビニールトンネルなどで防寒をすることができればある程度の環境で対応することが出来るでしょう。長雨が当たらないようにしなければいけまえん。梅雨の時期にも注意がいります。
種付けや水やり、肥料について
種をまく時の用土の状態としてはどういった土を用意するかです。赤玉土の中粒タイプを5割、腐葉土を3割、酸度調整をしているピートモスを2割にリン酸分の多い肥料を適度混ぜた用土にします。水はけ、肥沃な土を好みますから、それに合わせて作るようにします。この植物は酸性土を嫌います。用土1リットルに対して2g程度で苦土石灰を入れるようにします。
そうすることで酸性の状態もある程度は改善されるようになるでしょう。水やりをする時の注意としては多湿にならないようにすることです。あまり水分が多いと根腐れの原因になりますから、乾燥気味に保つようにして水やりをします。夏場は多湿は禁物で、やり過ぎに注意します。肥料については植え付けの時に行うことがありますが、
庭植えにおいては10月から11月、3月から5月に緩効性化成肥料を与えます。鉢植えにおいては10月から11月に緩効性化成肥料を行います。2月から5月においては液体肥料を施すことがあります。肥料については、あまり多すぎるは良くない場合があるので、コントロールしながら行うようにします。
あまり多すぎると茎や葉が大きく茂りすぎることがあります。大きくなりすぎると茎はそれ程太くないので倒れやすくなることがあります。見た目としてもあまり良くありませんから、与え過ぎには十分注意しながら行います。少なめに入れるようにし、足りなそうであれば適宜入れていくようにすれば足りないことは無いでしょう。
増やし方や害虫について
この花の増やし方として種から増やす方法があります。多年草なので翌年も花を咲かせてくれることがありますが、日本の高温多湿の状態に合わずに夏に枯れてしまうことがあります。となると分けるなどのこともできません。種を取ろうとするのであれば、花の後に、種を採取するようにします。種に関しては非常に小さいです。
ですから花が終わりそうな時ぐらいから徐々に種受けの準備をしておきます。小さな紙袋などを用意してそれをかぶせておきます。こぼれたとしてもその中に落ちます。そうすれば確実に種を取ることができ、それをまけば増やすことができます。種まきをするのにいい時期は9月下旬から10月の秋と3月から5月の春にかけてになります。
こういった場合冬越えをさせたほうがいいかどうかがあります。この花の場合は秋まきで冬越をさせ、初夏に花を咲かせる方法が良いとされています。春の種まきだと初夏の段階ではまだ花が付けられない状態で、苦手な真夏に花の時期になってしまいます。それだと楽しめないことがあります。
種については、箱や平鉢などを用意して、発芽したら移し替えていきます。たくさん出てくれば混みあった状態になって管理が困りますから、最も強そうなものを選んで残します。挿し芽での増やし方もよく知られています。病気についてはあまりかかることはありませんが、春から秋にかけては新芽が出る頃にアブラムシが発生することがあるので、捕殺などを試みます。
マトリカリアの歴史
良薬口に苦しと言われることがあります。薬といえば苦いものが多いけども体にきくとするなら飲む必要がありました。体に良いからしかたがないと飲んだのでしょう。人にとって嫌な味などについては毒のこともありますから、あまり安易に知らない植物などについて食べたり飲んだりしてはいけないでしょうが、
ある程度言い伝えなどがあって良いとされるのであればそれらを食べたり飲んだりしても問題ないのでしょう。白い花びらが特徴的な花としてマトリカリアと呼ばれる花があります。原産としては西アジアからバルカン半島にかけて広い範囲でとなっています。日本にとっては少し遠いところですが、ここから中国などに伝わって伝えられることがあります。
属名においてタナケツムがありますが、これはラテン語では不死のことを表すとされます。マトリカリア自体においてはラテン語においては子宮に由来するとされています。これはこれが婦人病の薬として用いられることがあったからとされています。この植物の別名としてはフィーバーフューがあります。これは熱を冷ますことを表します。
女性においてはのぼせや生理痛など体温の上昇に係る病気になることがあったことから、解熱効果に良いとして使われることがあったようです。和名においてはナツシロギクとなんとも美しい名前が付けられています。夏に白い菊のような花をつけることからこのように付けられたとされます。日本人にはこちらのほうが馴染みがありそうです。
マトリカリアの特徴
花の特徴は、キク科のヨモギギク属とされています。タナセツム属に入ることもあります。園芸分類としては草花に属します。形態としては原産地や生息地においては多年草としてになりますが、気候が合わないところなどでは一年草や二年草になることがあります。原産が比較的暖かくて乾燥しているところですから、日本とはかなり違いがあるかもしれません。
花の草丈に関しては15センチから1メートル程度となっています。花が咲く時期は5月から7月の初夏です。夏の真っ盛りや秋に咲くわけではないので、普通の菊などに比べると季節が少し早くなるかもしれません。花の色は黄色もありますが、和名で白菊と入るくらいですから白のタイプが多くなっています。
耐寒性としてはありますが、耐暑性があまりないとされています。そのために夏に弱りやすい花になるかもしれません。常緑性のタイプで、開花時期が長いのも特徴になっています。葉っぱに関しては羽状の状態で、美しい緑が色の特徴にもなっています。花の大きさとしては直径で1センチから2センチで、まさにキクのような花の形をしています。
一重咲きがよく知られていますが、八重咲きもあります。八重咲きになるとまさにその色だけがこんもりと咲くので、可愛らしい様子が伺えます。スノーボール、ゴールデンボールなどの品種もあり、それらは八重咲きの種類になります。まさに小さいボールが茎の上に乗っているように見えることがある花です。
-

-
キンセンカとハボタンの育て方
冬枯れの戸外で一際鮮やかに色彩を誇るのがハボタンです。江戸時代中期に緑色のキャベツに似たものが長崎に渡来して、オランダナ...
-

-
ヤブコウジの育て方
こちらの植物は被子植物、真正双子葉類、コア真正双子葉類、キク類になります。更にツツジ目、サクラソウ科、ヤブコウジ亜科とな...
-

-
シシトウの育て方
程よい辛味があり、あらゆる料理に使用されて人気のあるシシトウですが、その正式名称はシシトウガラシ(獅子唐辛子)であり、そ...
-

-
ローダンセマムの育て方
ローダンセマムの開花時期は春から初夏の間です。一般的な色は、薄く淡いピンク色やホワイトなどがあります。ひまわりのように丸...
-

-
春菊の種まきと栽培の方法とは。
春菊は、キク科シュンギク属の1年草で、原産地は地中海沿岸です。春に黄色の花が咲き、葉の形が菊に似ていることから名前がつけ...
-

-
ムラサキシキブの育て方
この植物の特徴では、シソ目、シソ科、ムラサキシキブ属となっています。英語の名前はジャパニーズビューティーベリーです。日本...
-

-
エケベリアの育て方
エケベリアはその学名を「Echeveria sp」といい、バラ目ベンケイソウ科エケベリア属の植物です。常緑の植物で、多肉...
-

-
クチナシの育て方
クチナシの原産地は日本、中国、台湾、インドシナ、ヒマラヤとされており、暖地の山中に自生し、広く分布しています。主な生息地...
-

-
スパラキシスの育て方
スパラキシスはアヤメ科の秋植えの球根草として知られています。純粋に和名であるスイセンアヤメとも言います。和名が付いている...
-

-
タマシャジンの育て方
タマシャジンとは西アジアからヨーロッパが原産地のキキョウ科フィテウマ属の多年草です。アルプス山脈などの高山地帯の岩場など...




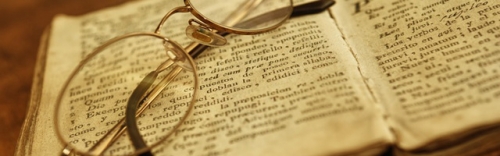





花の特徴は、キク科のヨモギギク属とされています。タナセツム属に入ることもあります。園芸分類としては草花に属します。形態としては原産地や生息地においては多年草としてになりますが、気候が合わないところなどでは一年草や二年草になることがあります。