ロニセラの育て方

ロニセラの育て方
ロニセラは世界中に生息地のあるつる科の植物です。常緑性で開花気が長く、独特の甘い香りのある花で、大変丈夫なため、ガーデニング初心者でも育てやすい植物です。開花期は6月から9月で樹高は3メートルにもなります。
主な原種は日本原産種のスイカズラ、地中海沿岸地域が原産の常緑性のつる植物のハニーサックル、内側が黄色、外側がオレンジ系の紅色でとても香りのよい花をたくさん咲かせるゴールドフレームなどがあります。ロニセラは栽培に土質は特に選ばないのですが、乾燥のしすぎない程度に水はけの良い土壌が向いています。
花を咲かせるためには、午前中は日があたる半日陰または日向で栽培するようにします。冬になると寒冷地ではほとんど落葉してしまうのですが、暖地では葉が傷んでしまうため、冬の乾燥した冷たい風が当たらないような場所を選ぶようにします。
庭植えで楽しむときには水やりは特に必要ないのですが、夏の暑い時期に極端に土が乾燥してしまうようであれば、朝か夕方に水を与えてやる育て方をします。鉢植えで育てる時には枝が伸び始める春から秋まではたっぷりと水を与えるようにします。
ロニセラは乾燥も過湿も苦手とする植物なのですが、適度に乾燥した環境を好みます。真夏には株元のあたりにマルチングをしたり、根元の部分に這う性質の植物を植えてやることで、グランドカバーして、株元の乾燥を防ぐようにする育て方もすすめです。
肥料はロニセラの花が咲く5月から7月にゆっくりと効くタイプの化成肥料を月に一回程度施肥するようにします。鉢植えでロニセラを栽培するときには水もちや水はけがよく、腐植質に富んだ土壌を好むので、細粒の赤玉土を5割、細粒の鹿沼土を2割、腐葉土を3割で配合した用土などを用いる育て方が向いています。
早春に花壇で栽培するときには粒状肥料を与え、鉢植えの場合には土の上にばらまいて施肥するようにします。常緑性のスイカズラの仲間は3月から4月に植え付けや植え替えを行います。
よく肥えた土壌を好むので、根鉢の2倍の深さと幅の植え穴を掘って、そこに腐葉土を掘り上げた土の約3分の一ほどを混ぜて植え付けます。鉢植えの時には2年に一度の割合で、根を3分の一ほどの長さに整理して、一回り大きなサイズの鉢に植え替えるようにします。
ロニセラの殖やし方
ロニセラを増やすときには種付けではなく挿し木で増やします。ロニセラは大変丈夫で旺盛に生長するので、種付けよりも挿し木の方が向いています。種付けをする場合には採取した種を種付け用に日陰につるして乾燥させてから使います。
7月から8月挿し木に適しているのは6月から7月で、つるを2節から3節ごとにその年に伸びてややしっかりとして硬くなった枝を選んで切り、鹿沼土や赤玉土、挿し木用の用土切り取ってさし穂にします。この時に花やつぼみがついていたら切り取っておきます。
切り口を水に30分程度付けた後に、植物成長調整剤を切り口に薄くまぶして挿し木用培養土にさすようにします。大体1か月から1か月半くらいで根が出てくるので、やや深型のポリポットに植え替えます。ロニセラの開花気が長いのは、枝を伸ばしながら次々と花芽を作るためです。
12月に選定をして、太い枝から新しい枝が出るように刈り込むようにします。ロニセラの生育はかなり旺盛なので、環境さえ整えば数年でかなり大きくなって木質化してゆきます。つる性なので選定や誘因は必要で、1月から2月の最も寒い時期に株元をしっかりと支柱などに絡ませるようにして、樹形が乱れないようにひもで縛って固定し、誘引するようにします。
支柱やトレリス、アーチなどにひもやビニールタイなどを使って結びとめるようにします。要らないツルは、この時に切り落としてしまっても大丈夫です。管理をせず放任すると手が付けられない状態になります。そのため、或る程度誘引してから全体の姿を整えるようにする必要があります。
旺盛に枝を伸ばす性質を活用してつるを絡ませられるようにネットフェンスやトレリスなどを活用します。新しく伸びた枝に花を咲かせるため、強めに剪定することで、よりたくさんの花を楽しむことができます。
ロニセラがかかりやすい病害虫
ロニセラの花芽が付き始めるころからアブラムシが発生しやすくなります。アブラムシをそのままにしておくと花芽がアブラムシでおおわれてしまうこともあります。アブラムシを見つけたら殺虫剤を散布して駆除するようにします。アブラムシは尾の部分から出す排泄物がありを誘引したり、すす病を誘発したり、ウイルス病を媒介することがあります。
葉を萎縮させたり湾曲させたり、種類によっては葉に虫エイを作る虫もいます。すす病というのは多くの植物に発生する病気で、植物の表面が黒いすすに覆われたように黒くなります。これは黒いカビによるもので、アブラムシなどの排せつ物や分泌物、植物に付着したほこりなどから栄養を得ています。アブラムシを駆除して栄養源を断つことが重要になります。
ロニセラの歴史
ロニセラは北半球に広く分布するつる植物で、北アメリカの東部や南部が原産地です。初夏から秋まで長期間開花し、半常緑から常緑性で生育が旺盛なためにぐんぐんと枝を伸ばします。和名はツキヌキニンドウですが、これは対生する枝先の葉が基部であわさり、茎が葉を付きぬけているように見えることからツキヌキと呼ばれ、冬でも落葉しないスイカズラを忍冬ーニンドウとも呼ぶことからつけられたと言われています。
学名がロニセラ、またはロニケラと呼ばれ、英名ではハニーサックルなどと言われ、現在さまざまな名称で呼ばれています。日本にも自生し、世界中にその生息地がある大変丈夫なスイカズラ科の常緑つる植物です。日本ではウェルカムガーデンの入り口部分のアーチなどに使われるのがよく見られます。筒のような形になっている花の中のみつを吸って遊んだ事柄にちなんでスイカズラの名称がついたと言われています。
ロニセラの特徴
園芸店などでロニセラという名称で販売されているものには原種を含めていくつかの種類があります。大きく分けるとつる上に生育して花を楽しむ種類で、落葉から常緑のハニーサックルと呼ばれる園芸品種の種類と、常緑低木で刃物として使われているニティダの2種類がポピュラーです。
ハニーサックルは夏の初めから秋にかけて、個性的で変わった形の花を咲かせる植物です。ハニーという名称がついている通り、とても甘い香りがあり、花色が豊富で多色咲きのものもあれば、左記進んでいくうちに変化するものも多数あります。葉は楕円形をしており少し濃い緑色で、株はつる上に生育していき、成長が早く、旺盛に広がってゆくのが特徴です。
落葉から半落葉するのですが、温かい地域では常緑で生育する品種もあります。もう一つのニティダはブッシュ状になって小さな葉が付き、グランドカバーや寄せ植えに活用するのに人気があります。花はあまり目立たないのですが、美しく斑の入った葉が出回ります。ニティダは通常の緑葉もとてもきれいで観賞用にも向きます。
ハニーサックルのように旺盛に成長していくのではなく、成長はやや遅く、樹高もあまり高い丈にはなりません。耐寒性があり、雪の降る地域なら屋外においても冬越しができます。ただし、雪の少ない地域で、寒さで土が凍ってしまうような地域で栽培する場合には、株元に落ち葉や敷き藁を厚く敷くなどの防寒対策が必要です。通常は常緑性のつる植物なのですが、寒冷地では落葉します。
-

-
オリーブの育て方
オリーブの木は地中海地方が原産といわれるモクセイ科の常緑樹です。5万年以上昔の葉の化石があるほど古い植物で、また一説には...
-

-
レモンバーベナの育て方
レモンバーベナは、クマツヅラ科イワダレソウ属の落葉低木です。軽く触れるだけでもかぐわしいレモンの香りがします。この香り代...
-

-
アイスランドポピーの育て方
ポピーというケシ科はなんと26属250種も分布しており、ケシ科ケシ属でも60種の仲間が存在します。ケシ科は麻薬成分モルヒ...
-

-
イブキジャコウソウの育て方
イブキジャコウソウなどのタイムの原産地は南ヨーロッパで、古代ギリシャ時代から薬用や食用として利用されています。紀元前の7...
-

-
ドクゼリの育て方
ガーデニングなどの植物を育てるということは、本来自然にある自生の植物を自分の所有する庭に囲い込み、好みに合わせた箱庭を作...
-

-
エリンジウムの育て方
エリンジウムはセリ科のヒゴタイサイコ属の植物です。同じヒゴタイサイコ属の植物にはE.maritimum やオオバコエンド...
-

-
コマクサの育て方
高山植物の女王とも呼ばれているコマクサは高山に咲く高山植物の一つです。北アルプスなどの山々の中で見ることが出来ますが、比...
-

-
エダマメの育て方
エダマメは「枝豆」と書きますが、ビールには欠かせないおつまみとして人気が高い野菜です。そもそもエダマメと言うのは未成熟の...
-

-
ミルトニオプシスの育て方
花の種類としては、ラン科、ミルトニオプシス属になります。園芸の分類としてはランになり、多年草として楽しむことが出来る花に...
-

-
ヒトツバタゴの育て方
20万年前の近畿地方の地層から、泥炭化されたヒトツバタゴがみつかっています。しかし、現在の日本でヒトツバタゴが自生するの...




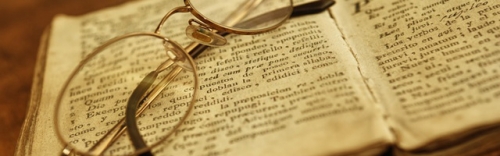




ロニセラは北半球に広く分布するつる植物で、北アメリカの東部や南部が原産地です。初夏から秋まで長期間開花し、半常緑から常緑性で生育が旺盛なためにぐんぐんと枝を伸ばします。和名はツキヌキニンドウですが、これは対生する枝先の葉が基部であわさり、茎が葉を付きぬけているように見えることからツキヌキと呼ばれ、冬でも落葉しないスイカズラを忍冬ーニンドウとも呼ぶことからつけられたと言われています。