ベラドンナリリーの育て方

育てる環境について
栽培をするにあたって、育て方としてはどういった環境が良いかです。生息地としては比較的寒いところでも良いとされています。耐寒性、耐暑性ともにそれなりにあるとされています。凍らせないことを条件にするなら外でも冬越しをすることができます。日本であればあまり無理をさせず自宅の中にいれておいたほうが良いかもしれません。
日当たりを好みますから、生育期においては日当たりの良い所にしっかりと当てるようにします。東北などの寒いところでは冬を外で越すのは難しいとされます。でも西日本であれば十分外で冬越しをすることが出来るとされています。庭植え、鉢植えどちらでも可能ですが、鉢植えであれば移動がしやすくなるので寒い時においても
中に入れて寒さをしのぐことが出来るでしょう。水はけの良い所を選んで植えるようにします。庭植えをするにあたって寒いところで育てる場合においてはそのまま庭においたままではいけません。取り込みをしておいた方が良いとされています。土の状態においてどのようなところを選ぶかがあります。
一般的な庭において植えることが出来るかどうかですが、その他の花を植えたりしてある程度肥えた状態にしているのであれば植えることができます。その他に特に耕したりする必要もなく、そのままの状態で植え続けることが出来る場合があります。あまり草花などを植えていないようなときにおいては、それなりの施しをすることによって出来る場合があります。
種付けや水やり、肥料について
植えようとするときに用土を用意することになります。水はけが重要なので、庭に直接植えるときにおいては庭の土の状態を調べるようにします。鉢植えを行う場合には自分で土の調整をすることができますから良い状態を作るようにします。水はけ、通気性、保水性のあるような土の配合をするようにすれば良いとされています。
赤玉土を4割程度、硬質の鹿沼土を4割程度、腐葉土を2割程度配合するようにするといいとされています。そうすることで水はけ、通気性も良くなります。植え付けにおいては、掘りあげた球根を容易します。7月ぐらいから8月ぐらいに用意しておき、それを植えるようにすればいいでしょう。鉢植えの時にはどのような植木鉢にするかですが、
6号から8号ぐらいの植木鉢に対して球根を一つ位として植えることを考えます。植え方は球根の上の部分が少し土から出るように浅植え状態にします。花によっては土に完全に埋めてしまったりすることがあるので、この方法は少し特殊な部類になるかもしれません。庭に植えるときにおいては球根と球根の間を少し開けるようにします。
20センチから30センチぐらい開けるようにしておけば特に問題はありません。植え付けてすぐに咲いてくれればよいですが場合によってはすぐには咲かないことがあります。それでも根付きを始めていますから、翌年咲くのを期待します。咲かないからといって別の球根でやってみようとしないようにしなければいけません。
増やし方や害虫について
どんどん増やしていくために水やりをする必要があります。生育期においては土が乾いた時にしっかりと与えるようにします。冬においては休眠に入ります。この時にも水を与えるかですが、休眠中は水分などを一切吸収しません。変に水を与えると傷めることになるので水は全く与えないようにします。
肥料については、庭植えにおいて肥沃な場合であれば特に必要ないとされています。植木鉢で育てる場合においては、元肥において緩効性の化成肥料を用意するようにします。花が咲いたあとにも与えるとより元気になります。カリ分が多い肥料を配分すると良いとされています。どのようにして増やしてくかですが、
植え替えなどにおいて掘り返してみると増やせるかどうかがわかることがあります。分球しているときはそれを分けることができます。球根の直径として6センチぐらい、高さが8センチぐらいあるのであれば十分開花できる力のある球根と判断できます。それを目安にしていきます。球根が小さい場合には栄養分を与えて
球根を太らせて花を咲かせられる状態にする必要があります。肥培管理が必要になります。この花については病気であったり害虫に関する心配があまりないとされています。寒さがポイントになりそうですからそれに気をつけていれば毎年のように咲かせることができそうです。しっかり花を咲かせようとするなら花がら摘みをします。花首のところでとってしまうようにすると次の年につきやすくなります。
ベラドンナリリーの歴史
名前がついているものにおいては、正式名称、別の名称、愛称などいくつかついていることがあります。どれで呼ばれているかどうかはそれぞれによって異なりますが、最も印象に残りやすい、発音がし易い言葉などが使われることがあるようです。ですからよく聞く名前の本当の名前を聞いてもそれが何なのかについて分からない事があるかもしれません。
花の名前においてもあまり知られていない名前でいながら、別の名称を聞くとよく聞く、聞いたことがあるもののことがあります。ベラドンナリリーと呼ばれる花があります。この名称を聞いてすぐに頭に想像することができないかもしれません。別の名称としてはアマリリスがあります。
歌にもありますからこちらの名称の方が印象があるかもしれません。原産としては南アフリカのケープ地方とされています。アフリカ大陸においても最も南の地域になります。日本からはかなり離れたところが原産であることがわかります。非常に遠くにある花ですが日本においては比較的古い間に渡ってきているとされています。
明治時代の末期においてはすでに日本に来ていて見られるようになっているようです。近年になって来たわけではなく、それなりに歴史のある花であることがわかります。アマリリスの名前自体は古代ギリシアの詩などに登場する羊飼いから取られているとされています。18世紀ぐらいにヨーロッパに持ち込まれて、そこからいろいろな改良がされたようです。
ベラドンナリリーの特徴
特徴としては、クサスギカズラ目、ヒガンバナ科、ヒガンバナ亜科となっています。ヒッペアストルム連に属するともされています。草丈に関しては50センチから70センチぐらいに達するとされています。主に咲く時期としては晩夏の時期で、8月から9月にかけてきれいな花を咲かせるとされています。育てるときには主に球根から育てることが多くなります。
名称においてリリーとついています。このリリーについてはユリの仲間において付けられることが多い名称ですが、こちらについてはユリの仲間とは異なります。またベラドンナと呼ばれる薬草があります。こちらにおいてはナス科になりますからやはり別の種類の花になります。見た目においてもかなり異なることがわかります。
正式な名称としてはアマリリス・ペラドンナになります。球根に関しては直径が5センチから10センチぐらいになっていてまんまるよりも上部が少し伸びたような球形です。玉ねぎでも先が尖ったような形といったほうがいいでしょう。この球根に関しては葉っぱが肥大したことによって球根状になったタイプになります。
表面は乾いた皮に包まれた状態です。花の咲き方としては、球根から花と茎をどんどん伸ばしていくタイプになります。先端の方に花が咲きますが、10輪前後咲かせることもあります。花の形はリリーと付くだけあってユリに似たような優雅な咲き方をします。色についはきれいな紅色や白、可愛らしいピンクなどもあります。
-

-
レオノティスの育て方
レオノティスはシソ科の植物になります。きれいなオレンジ色の花をたくさんつけるのですが、見た目も鮮やかでパワフルな感じのす...
-

-
ルクリア(アッサムニオイザクラ)の育て方
花の種類としてはアカネ科となっています。花が桜に似ていることからバラ科かと考えがちですがそうではありません。桜とはかなり...
-

-
ヘビウリの育て方
インド原産のウリ科の多年草で、別名を「セイロン瓜」といいます。日本には明治末期、中国大陸を経由して渡来しました。国内では...
-

-
ゴーヤーともよばれている健康野菜ニガウリの育て方
ゴーヤーは東南アジア原産の、特有の苦味があるつる性の野菜です。沖縄では古くから利用されており郷土料理”ゴーヤーチャンプル...
-

-
ドクダミの育て方
ドクダミは、ドクダミ科ドクダミ族の多年草であり、ギョウセイソウやジゴクソバ、ドクダメとも呼ばれています。
-

-
ハンネマニアの育て方
ハンネマニアはケシ科ハンネマニア属の多年草です。別名、メキシカンチューリップポピーとも呼ばれています。名前からも分かると...
-

-
カロケファルスの育て方
見た目からは少し想像がつきにくいですがキク科になります。種類としては常緑の低い木になります。耐寒性としては日本においては...
-

-
ぶどうの育て方
ぶどうの歴史には、その品種の多さゆえに諸説あり、最も古いものは紀元前8000年頃のヨルダン遺跡から、初期農耕文化における...
-

-
コウバイの育て方
楽しみ方としても、小さなうちは盆栽などで楽しみ、大きくなってきたら、ガーデニングということで、庭に植えるということもでき...
-

-
トケイソウの育て方
原産地は、北米、ブラジルやペルーなどの熱帯アメリカです。パラグアイでは国花とされています。現在、園芸に適した品種として知...




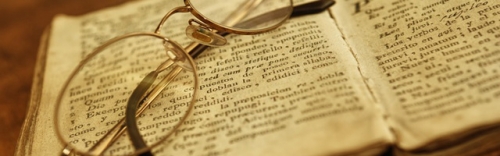





特徴としては、クサスギカズラ目、ヒガンバナ科、ヒガンバナ亜科となっています。ヒッペアストルム連に属するともされています。草丈に関しては50センチから70センチぐらいに達するとされています。正式な名称としてはアマリリス・ペラドンナになります。球根に関しては直径が5センチから10センチぐらいになっていてまんまるよりも上部が少し伸びたような球形です。