ヘディキウムの育て方

育てる環境について
ヘディキウムの栽培に適している場所は半日陰で湿った場所を好みます。暑さにも寒さにも比較的強いですが、寒すぎると地上部が枯れてしまうので、腐葉土や落ち葉などで防寒してあげれば寒い冬でも越えることができます。冬でも室内で管理していけば寒さにより葉を傷つけることがなく、
緑色を保ったまま冬を越すことができます。強い霜が降りることで凍害を受けてしまい、葉の色が緑色から茶色に変色してしまう恐れがあります。気温が下がりすぎる地域で育てる場合は、球根が凍ってしまわないように11月には球根を堀り上げると良いでしょう。
球根は乾いたバーミキュライトと一緒にビニール袋に入れておきましょう。こうすることで球根を霜や凍ることから避けることができます。比較的気温が下がりにくい場所では、霜で葉は傷んでしまう恐れはありますが、地下部は生き残ったまま冬を越すことができます。
屋外ではなく室内で管理する場合も、球根の場合でも寒さから守ろうと暖房で暖まっている部屋での管理はしないように注意しましょう。ヘディキルムの生息地は東南アジアで亜熱帯植物ではありますが、直射日光は苦手です。庭植えでも鉢植えでも育てることはできますが、直射日光が当たらない場所を選んで育てましょう。
日差しが強まる西日が当たるような場所も避けたほうが良いでしょう。また大きく育つ植物なため、強風が吹くと葉を傷めてしまったり、風により株元から倒れてしまうこともあります。強風から守ってあげるためにも風が吹きさらすような場所も避けた方が良いでしょう。
種付けや水やり、肥料について
ヘディキウムを庭植えにし、屋外で冬を越させるためには、春(4月~5月)に植え付けを行いましょう。日差しが強い場所は避けた方が良いですが、日当たりの良い、湿り気のある場所に深さ15㎝ほどの穴を掘り、春に植え付けを行うことで、冬までに根をしっかりと張らせることができます。
また植え付けを行うときには、腐葉土や堆肥を多く土に混ぜ込むことが大切です。鉢植えする場合の赤玉土小粒と腐葉土の7対3に配合された土で水はけの良い土が適していますが、普通の草花用培養土で大丈夫です。春から秋の成長時期には、窒素・リン酸・カリの三要素を等量に与えるか、
リン酸がやや多めの化学肥料を置き肥として与えると良いでしょう。7月~9月頃には追肥として1週間に1回程度、液体肥料を与えるとより育ちやすくなります。根詰まりしてしまうと、成長しにくくなってしまうので、1~2年くらいに1回は植え替えを行うようにしましょう。
水やりは暖かい時期には土が乾燥したら、たっぷりと水を与えてあげましょう。冬の寒い時期にはやや乾かし気味にしておきましょう。冬は休眠期になるので、断水しておくのが好ましいです。鉢植えの場合は、土の表面が乾いてからたっぷりと水を与えましょう。
特に夏の時期は土が乾きやすいの水切れしないように注意が必要です。ただし、乾きやすいからと鉢皿に水を溜めたりしないようにしましょう。そんなに考えすぎずに、一般的な観葉植物と同じ程度の水やりでも育ちやすい植物です。
増やし方や害虫について
植え替えを春に行う際に、株分けも行うことでヘディキウムを増やしていくことができます。その時の注意する点として、細かく株分けをし過ぎないことです。分けすぎてしまうと、成長が遅れてしまうので注意しましょう。育つ年数が増えるごとに大きくなりやすいので、
広い面積が必要となります。2株以上植える場合には40㎝~50㎝ほど間隔をあけて植えてあげるとしっかりと成長しやすくなります。花が咲いた後は、花茎を切り取りましょう。しかし開花時期である春から夏に切り取ってしまうと、花が咲かなくなってしまうので注意が必要です。
切り取りを行う場合は、3月から4月、11月から12月の間に行うようにしましょう。また植え替えの時に球根を切り分けてあげるとヘディキウムを増やしやすくなります。球根を植え付けた年は、どうしても根が少なくなってしまうので、花が咲きにくくなります。
植え付け年は花が咲きにくいものと考え、焦らないようにしましょう。根が増える2年目には開花しやすくなります。ヘディキウムには害虫はほとんど見られませんが、葉の裏や花の芽にハダニやアブラムシが発生する場合もあります。発生してしまった場合には、素早く駆除する必要があります。
害虫はつきにくいですが、安心しきらずに念のために葉の裏を見ておくと良いでしょう。ヘディキウムの増やし方・育て方は簡単な植物ですが、植え替え時期や増やす時期を寒い時期に行ってしまうと腐敗の原因となってしまうので気を付けましょう。
ヘディキウムの歴史
ヘディキウムは東南アジアを中心に約50種類が分布されています。花が美しいものが多く、種間交雑により育成された品種もあります。ヘディキウムは和名はシュクシャと呼ばれているショウガ科シュクシャ属(ヘディキウム属)の植物です。姿などからショウガに似ていると言われていますが、
香料などに使うショウガとは違い、ヘディキウムは花を楽しむことを目的とされています。原産地はインド・マレーシアの東南アジアで、日本には江戸時代に薬用として渡来して以来、花の美しさから鑑賞用もなりました。主に花を楽しむための植物で、庭先などに植えられることも多い植物です。
東南アジアでの栽培はもちろん、日本では沖縄や植物園の温室で栽培されることが多い植物で、和名でシュクシャと呼ばれる他に、ジンジャーやジンジャー・リリー、またはガーランド・リリーと呼ばれることもあります。ヘディキウムは成長すると1m前後程大きく育ち、
多年草の大型種でもあります。葉や根茎がショウガそっくりです。ヘディキウムはギリシャ語でヘディス(甘い)とキオン(雪)からきています。ヘディキウムには「コロナリウム」「コッキ二ウム」「カルネウム」という品種があり、
それぞれ花の色が違います。江戸時代に日本に入って着たものはコロナリウム種が最初だとも言われています。また、カルネウムは園芸品種として日本で改良されたものが多く存在します。特に有名なものは、香川県の小山実一さんが育種したものです。
ヘディキウムの特徴
ヘディキウムの特徴は花が美しいものが多く、花の色が豊富なのが特徴ともいえます。花の色は白・黄・朱紅・赤橙などがあります。大きな花茎を伸ばし、その先に沢山の花を咲かせます。花の大きさは8㎝を超えるものありますが、1㎝ほどの小さな花を咲かすこともあります。
ヘディキウム属は品種が豊富で「コロナリウム」は見た目は豪華ながらも清らかで美しい雰囲気をもっており、ユリの花のような甘い香りがします。園芸種としては白蘭、真珠があります。「コッキニウム」は鮮やかな花の色をしており、花つきの良さもあります。
ベニバナシュクシャとも呼ばれる品種です。他に夕映や源平があります。「カルネウム」は豪華に咲き、香りが良いのが特徴です。キバナシュクシャと呼ばれています。金閣は鮮やかな色が特徴です。夏の終わりころから10月にかけて花を咲かせ、100~150㎝ほどの花茎に、
20㎝ほどの長さがある楕円形の総状花序に香りのある花を咲かせます。先が尖った葉の長さはおよそ60㎝あり、葉の裏面は綿毛に覆われています。また虫媒花なので夜行性の昆虫を呼び寄せるために、夕方から夜にかけて香りを強く放ちます。ヘディキウムは観賞用の花として楽しむだけでなく、
ショウガに似た根茎からは精油がとれるため、それを鎮痛用の薬として用いられることもあります。また食用にできる品種もヘディキウムにはあり、氷砂糖と焼酎などでつけてジンジャー酒としても楽しまれることもあります。香りの良さから香水やポプリなどにも使用されることも多いです。
-

-
スピロキシネの育て方
こちらについてはキンバイザサ科になっています。別にコキンバイザサ科に分類されることもあります。園芸分類としては球根になり...
-

-
スズランの育て方
春を訪れを知らせる代表的な花です。日本原産のスズランとヨーロッパ原産のドイツスズランがあります。ドイツスズランは、草姿お...
-

-
エリデスの育て方
エリデスは観賞用のものとして用いられるランの一種です。最近では日本でも有名になってきていますが、もともとはインドシナ半島...
-

-
キンギョソウの育て方
キンギョソウはもともとは多年草ですが、暑さで株が弱り多くが一年で枯れてしまうので、園芸的には一年草として取り扱われていま...
-

-
スキミアの育て方
「スキミア」はミカン科ミヤマシキミ属、日本を原産とする常緑低木の一種です。学名は「シキミア・ジャポニカ」、英名を「スキミ...
-

-
モミジバアサガオの育て方
モミジバアサガオは和名をモミジヒルガオといい、日本で古くから親しまれてきたアサガオの仲間です。日本へ伝来したのは今から1...
-

-
コカブの育て方と種まきの時期
コカブは球の直径が4から5センチのカブで、葉にはビタミンA、Cが多く含まれています。コカブの栽培は、虫の食害にだけ気を付...
-

-
ゲットウの育て方
ゲットウの特徴ですが、南国の植物でショウガ科に属し、葉は生姜の葉と同じ形をしています。葉の幅約15センチ程度、長さが40...
-

-
ミヤマホタルカズラの育て方
ミヤマホタルカズラはヨーロッパの南西部、フランス西部からスペイン、ポルトガルなどを生息地とする常緑低木です。もともと日本...
-

-
ヒナソウの育て方
ヒナソウは、北アメリカ東部が原産の草花で毎年花を咲かせる小型の多年草です。日本に入ってきたのは昭和時代の後期に園芸植物と...




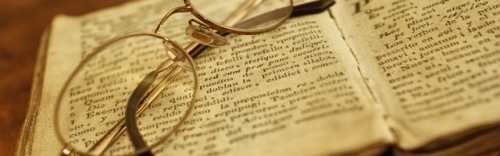





ヘディキウムは東南アジアを中心に約50種類が分布されています。花が美しいものが多く、種間交雑により育成された品種もあります。ヘディキウムは和名はシュクシャと呼ばれているショウガ科シュクシャ属(ヘディキウム属)の植物です。