フルクラエアの育て方

育てる環境について
育てる環境については年間を通して日光がよく当たる場所ならばあまりその他の環境についての制限がないのですが、寒さに弱い植物なので、冬の寒い時期には室内で栽培をすることでこの植物を枯れさせるなどの失敗を防ぐことができます。
基本的には多肉植物の一種なので乾燥については強いのですが、寒さに関しては寒冷地に分布している植物ではないので、あまり強くないので、寒い場所に何日も放置していると全体が枯れてしまうこともあります。しかし管理は非常に簡単なので初心者でも十分に育てることができる品種であるとされています。
この植物は多年草なのであまり世話をしていなくても普通に何年も室内で鑑賞できることがあるのですが、見栄えの良さを追求する場合には植え付けや植え替えなどの世話をしなければなりません。花は10年に1度程度咲くのですが、黄色い花が咲いた後には
その株が枯れてしまうので残された無数の小さな子株から育て直すことになります。開花時期は不定期とされているのでいつ咲くのかがわからないのですが、真ん中の部分が成長してくるので花が咲く数日前には開花時期を予想することができます。
常緑性なので基本的には黄色に変色することがないのですが、風通しの悪い場所で育てると湿気がこもってしまって栄養状態が悪くなるので葉が変色してしまったり、根の部分が傷んでしまうこともあるので注意が必要です。しかし多少体力が衰えたとしても十分に栽培ができる状態が保たれます。
種付けや水やり、肥料について
水やりに関しては春から秋は鉢の表面の土が乾燥したら水を与えるようにして、冬はあまり水分を必要としていないので完全に乾燥してから与えるようにします。肥料は緩効性の化成肥料を春と秋に1回ずつ与えるようにすると生長を促すことができるので、葉を大きくすることができます。
しかし冬に水や肥料などを与えてしまうと過剰な栄養素などが土の中に残ってしまうので、暖かい時期になってからあまり生育しなくなってしまいます。これは冬の間に水分などを与えすぎたことで根の部分が弱ってしまって、春から秋にかけての生長に影響を及ぼしているのが原因です。
庭植えで育てる場合には夏の暑い時期には直射日光に気をつける程度で十分育つのですが、冬は霜が降りる場所では栽培しないように気をつけたり、北風が直接当たる場所などの場合には囲いを付けるなどの工夫が必要になります。基本的には冬の寒い時期には室内で観賞することが多いので、
明るい窓辺においておくだけで十分に栽培することができます。主な作業としては下葉取りがあるのですが、これは下の葉が黄色くなってきたら、それを切り戻すという作業のことで、これをすると栄養が健康な葉に行き渡るので、
コンディションを良好に保つことができて、見栄えも良くなるので観賞用に育ててる場合にはこの作業は必要になります。植え付けなどをする場合には5月の中旬から8月の下旬までの期間に行うようにして、株の生育状態に合わせて行うようにします。
増やし方や害虫について
増やし方は株分けが一般的になっていて、適期としては5月の中旬から8月の下旬が良いとされているのですが、株元の部分に子株が出てきたら、葉の数が4枚から5枚程度になっているものを外して植え付けを行います。また花が咲いてしまった後には無数の子株が作られるので、
それを入手して植えつけることもできます。鉢植えの場合にはよ用土として水はけの良い腐植質の土を使うと良いとされていて、赤玉土小粒と腐葉土などを配合した土の中に植え付けを行います。フルクラエアに多い病気としては炭そ病があるのですが、
病気に感染した部分を除去するだけで回復させることができるのであまり深刻な症状になることはありません。カイガラムシは年間を通して発生するので、見つけたら早めに歯ブラシなどで除去する必要があります。基本的にはカイガラムシは風通しの悪い鉢植えなどに寄生する虫なので、
配置を工夫するなどして風通しを良くすると被害を減らすことができます。炭そ病は葉の部分に発生するのですが、小さな斑点ができているのを放置してしまうと葉に大きな穴が開いてしまうので、観賞用に栽培をしている場合には見栄えが非常に悪くなってしまいます。
高温多湿を好む細菌なので雨が多い季節に感染することの多い病気です。フルクラエアなどを室内で育てていても水やりの時に水滴の跳ね返りなどがあると底から感染が広がることがあります。予防するには室内で栽培するときに風通しの良い場所を選ぶとこの病気になりにくくなります。
フルクラエアの歴史
フルクラエアはリュウゼツラン科の植物で原産地は熱帯や亜熱帯地方の乾燥地帯なので日本には自生していません。またこの品種にはリュウゼツランなどの多肉植物などもあるので、庭木や観葉植物として栽培されているものが多くあります。
フルクラエアはリュウゼツランに似ている植物で長さが2メートルを超えることもあります。葉の中央部には黄色と白が混ざったような斑点が入っているのが特徴の植物で黄色の縦縞が入るものなども園芸品種として育てられています。またフルクラエアは繊維植物としても利用されることがあります。
歴史的には熱帯アメリカで栽培が始まったのでこの地域を生息地としている品種が21種類あります。観葉植物として世界中で流通しているものとしてはフルクラエア・フォエティダやメディオピクタなどがあります。葉が大きく成長した場合には自生地によっては
2.5メートルにもなることがあるのですが、鉢植えなどで育てる場合には30センチから1メートル程度で収まってしまいます。育て方によって、成長する大きさが全く違うのもこの品種の特徴で、10年以上育て続けていると株の中心部分から長い花茎を伸ばして
たくさんの花が咲くのをみることができるのですが、花が咲いてしまうとその株は枯れてしまいます。しかし残った植物の中に小さな株が無数にあるので、それをもう一度鉢植えなどして育てるという楽しみ方もあります。育てられている環境としては鉢植えの他に花壇などがあります。
フルクラエアの特徴
フルクラエアの特徴としては多肉植物であるということですが、多肉植物というのは葉や茎、根の部分が肥大化することでその部分に水分を蓄えることができるように進化を遂げた植物のことで、地面からの水分がなくなったとしても葉の部分が空気中の水分を吸収するので
乾燥地帯でも生育することができる植物のことです。フルクラエアの原産地は南米なのですが、多肉植物はアフリカ南部や北米の南部地域やマダガスカル島などにも分布しています。この地域では多くの種類が自生をしているので、栽培をしていなくても森や林の中などで
普通に見つけることができます。フルクラエアなどの多肉植物の良さとしては形が個性的なので栽培をしている愛好家にとってはとても大切な世界でただ一つの植物のように感じられる場合もあります。また品種によっては生きている宝石などと呼ばれて高値で取引されるものなどがあるので、
比較的栽培が簡単であるとされているフルクラエアを育てることによって、少しずつ難しい多肉植物の栽培をしていくと、様々な形の植物の生態を知ることができます。日本でもサボテンなどの多肉植物の人気は高くなっていて、室内のインテリアやデスクの置物などの
用途で利用されている場合もあります。基本的には水分などをあまり必要としないので、管理が簡単であまり枯れることがないのが魅力で、また品種によっては非常に安価なものがあるので、気軽に手に入れて、それをたくさん飾る女性もいます。
-

-
センブリの育て方
センブリはリンドウ科センブリ属の二年草です。漢字で「千振」と書き、その学名は、Swertiajaponicaとなっていま...
-

-
ハンカチノキの育て方
ハンカチノキはミズキ科ハンカチノキ属の落葉高木です。中国四川省・雲南省付近が原産で、標高1500~2000m位の標高の湿...
-

-
インゲンの育て方
豆の栽培は農耕文化が誕生したときから穀類と並んで始まったと言われています。乾燥豆は品質を低下させずに長い期間貯蔵できるこ...
-

-
ゴメザの育て方
ブラジル原産のラン科の植物です。属名がなんども変えられた歴史を持っています。最初はSigmatostalix(シグマトス...
-

-
クレソン(オランダガラシ)の育て方
クレソンは、日本では和蘭芥子(オランダガラシ)や西洋ぜりと呼ばれています。英語ではウォータークレスといいます。水中または...
-

-
クテナンテの育て方
クテナンテは熱帯アメリカ原産の植物で、葉の色や模様などが特徴的な種類が多いことから観葉植物として栽培されています。熱帯ア...
-

-
アレカヤシ(Dypsis lutescens)の育て方
アレカヤシという観葉植物をご存知でしょうか。園芸店などでもよく見かける人気のある植物です。一体どのような植物なのでしょう...
-

-
コクリュウの育て方
コクリュウは日本や中国など東アジアに生息地がある植物で寒さにも非常に強く、冬の間も黒っぽい葉を落とすことがありません。似...
-

-
マルバノキの育て方
木の種類としては、マンサク科、マルバノキ属となっています。別の名称としてベニマンサクと呼ばれています。園芸分類としては庭...
-

-
ドゥランタ・エレクタ(Duranta erecta)の育て方
ドゥランタ・エレクタは南アメリカ原産の植物ですが、日本でも容易に栽培できるのが特徴です。植え付けをする際には肥沃で水はけ...




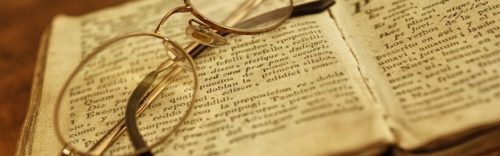





フルクラエアはリュウゼツラン科の植物で原産地は熱帯や亜熱帯地方の乾燥地帯なので日本には自生していません。またこの品種にはリュウゼツランなどの多肉植物などもあるので、庭木や観葉植物として栽培されているものが多くあります。