デュランタの育て方

育てる環境について
日光がよく当たる場所が適所です。日光が不足すると花の付きが悪くなるので注意しましょう。ただし、真夏に直射日光に当ててしまうと葉焼けして黄色くなってしまうことがあります。特に観葉植物用に改良されたあライムの品種は葉に光沢があり明るい色をしていることから、葉焼けしやすいです。
また、斑入りの葉も葉焼けしやすいので注意しましょう。熱帯原産の植物なので耐寒性は劣りますが、5℃程度あれば枯れる心配はありません。霜のない暖地、一部の平地では露地栽培で越冬可能です。鉢植えで育てる場合には、寒風、霜、凍結、が避けられるような場所に移動させてあげると良いです。
庭植えにする場合には、水はけの良い場所を選んであげると良いです。水はけが悪いと、開花が遅れることがあります。用土には、水はけの良い土を作るために、小粒赤玉土:腐葉土=7:3の割合で混合土を作ると良いです。
この割合で混ぜた土は、他の植物を育てるときにもほとんど応用可能です。他にも、小粒赤玉土:腐葉土:川砂=6:3:1の割合で混ぜた土でも良いです。海外ではアメリカのフロリダ州〜ブラジルを原産としており、やや暑いくらいの気候を好みます。
日本では沖縄が適所で、この地方ならば常緑樹として一年中葉を楽しむことも可能です。真夏には葉が焼けないように管理するために、半日陰に置いてあげると良いかもしれません。冬は寒風、霜、凍結にさえ注意してあげれば、比較的寒い地域でも育てられます。
種付けや水やり、肥料について
生育が大変旺盛なので、育て方では植え替えがポイントになります。植え替えをしないでいると根詰まりを起こし、生育が悪くなってしまいます。また、花付きも悪くなります。だいたい1〜2年を目安にして植え替え作業を行うようにしましょう。
鉢から移植する場合には、植え替えの1週間前から水やりを通常よりも控えておくと、根が乾燥して鉢から抜けやすくなります。植え替えの時には根を傷めないように優しく扱いましょう。水やりは、鉢の土が乾いたら与えるようにします。
ただし、冬はあまり水を必要としないので乾かし気味で大丈夫です。開花期(6〜10月)や成長期(春〜秋)では普段よりもたくさん水を吸うので、乾燥しないように注意します。特に7〜9月の天気の良い日は土が乾きやすいので、毎日水をあげるようにします。
庭植えの場合には根が張れば水やりはほとんど必要ありません。ただし、雨が降らないようならば適度に与えるようにします。肥料は、春〜秋の成長期に緩行性化成肥料を与えるようにします。規定量を置き肥として施せば良いです。夏場に窒素分の多い肥料を施してしまうと、枝や葉だけが大きくなり、
花が咲きにくくなってしまうので注意しましょう。窒素性の肥料にはもともと、葉を大きくする作用があります。これに対して、リンは花、カリウムは根の成長を促進する作用があります。窒素分の多い肥料は夏場は避けて、春〜秋の成長期の段階に緩行性化成肥料でバランス良く栄養分を与えてあげるようにしましょう。
増やし方や害虫について
挿し木で増やすことが可能です。可能なのは春〜秋にかけて可能です。本年伸びた枝を先端から5〜10cmほど切り取り、30分ほど水に挿して吸水させてから、清潔なバーミキュライト(蛭石)や鹿沼土などに挿してあげましょう。根が出るまでは半日陰で管理して、根が乾燥してしまわないようにします。
挿し木の時期の注意点がひとつあります。夏に行っても良いですが、夏は根が出る前に枯れてしまう可能性が高いので、できるだけ避けるようにします。種まきでも増やせますが、一般的には挿し木が確実な方法です。病気は特別ありませんが、気温が高く、湿度が低い環境ではハダニが発生することがあります。
ハダニは葉の裏側について吸汁する小さな害虫です。湿気が苦手という弱点があるので、高温で乾燥している時には葉に霧吹きなどで直接水をかけてあげると良いです。霧吹きを使うことにより、葉から水が蒸散しづらくなり乾燥を防ぐ効果が得られますし、同時にハダニ駆除も行えます。
やり方としては、葉を少し持ち上げて、下から霧吹きで水を噴射してハダニを飛ばすようにします。普段からこの作業を行っていれば、ある程度予防が可能です。他には、新芽の付近にアブラムシが発生することがあります。
アブラムシは繁殖力が強く、放っておくとどんどん数を増やしてしまうので、見つけ次第駆除スプレーなどで駆除するようにします。ハダニと違い、べっとりとした体をしているので、霧吹きなどで飛ばすことは出来ません。
デュランタの歴史
アメリカのフロリダ州〜ブラジルが原産地の熱帯植物です。藤色や白い小花が集まり、房状に垂れ下がって咲きます。日本に渡来したのは明治中期頃と言われています。現在では夏の鉢物として出回っていることが多いです。一部には観葉植物として品種改良されたものも出回っています。
日本では沖縄などの熱帯地域の生垣としてもよく使われています。名前の由来は、ローマ法王の侍医兼植物学者であった「デュランテス」という人名からです。デュランタの仲間は普通、南アメリカが主な生息地で、約30種類が知られています。
ただ、普通デュランタと呼ばれて栽培されているのは、デュランタ・レペンス(エレクタ)という種類です。これはフロリダのキーウェスト島〜ブラジル・西インド諸島に分布している熱帯性の花木で、育つと6m近くもの大きさになります。和名ではハリマツリとも呼ばれ、
そのほかにタイワンレンギョウなどの別名もあります。植物学上の分類では常緑樹とされていますが、日本で栽培すると秋〜冬にかけての低音により落葉してしまうことが多いです。現在出回っている品種で多いのは、花びらに白い縁取りが入る「タカラヅカ」という品種です。
観葉植物では、葉が光沢を帯び、明るい黄緑色をした「ライム」という品種もあります。ライムは花よりも、葉を楽しむために作られた品種です。最近のデュランタの使い方として多いのは、寄せ植え、花壇の縁どり、生垣、庭木、などとなっています。
デュランタの特徴
クマツヅラ科ハリマツリ族(デュランタ属)の熱帯植物です。形態は低木です。和名には、ハリマツリ、タイワンレンギョウ、などの呼び方があります。花色は白や藤色で、小花が集まり、その重みで房上に垂れ下がった形で花を咲かせます。鉢物や観葉植物用の品種が一般的に出回っています。
基本的に熱帯原産の植物なので、耐寒性は弱いです。日本でも育てることは可能ですが、常緑樹でありながら秋〜冬の寒さで葉を落としてしまいます。日本でも沖縄などの熱帯性気候では年中葉を茂らせているものもあります。また、生垣としても用いられています。
日本の温帯地方ならば、霜にさえ気をつければ戸外で越冬させることも可能です。暖地ならば庭木としても適しています。開花期は6〜10月で、開花期が長いです。耐暑性も高いので、初心者でも比較的簡単に育てることが出来ます。生育が旺盛なので、枝が伸びたら剪定作業が必要になります。
一般的な植物と同様に、日当たりの良い場所を好みます。日照不足だと花付きが悪くなることもあります。耐寒性はそれほど高くはないものの、5℃くらいの気温があれば育てることは可能です。病気も比較的少ない植物なので、庭木として挑戦するならば
初心者でも扱いやすいでしょう。ただし、ハダニやアブラムシなどの害虫がつくことはあります。日本では藤色の美しさや、白い縁どりの入ったタカラヅカという品種の存在により、園芸庭木として人気が高い植物です。
-

-
クルミの育て方
クルミは美味しい半面高カロリーである食材としても知られています。しかし一日の摂取量にさえ注意すれば決して悪いものではなく...
-

-
ハゲイトウの育て方
熱帯アジア原産の植物である”ハゲイトウ(葉鶏頭)”。暑い地域を生息地とし、春に種をまくと秋頃には枯れてしまう一年草になり...
-

-
ヒマラヤ・ハニーサックルの育て方
ヒマラヤ・ハニーサックルは、スイカズラ科スイカズラ属の植物です。落葉性の低木です。原産はヒマラヤ山脈で、中国西部からチベ...
-

-
パンジーゼラニウムの育て方
パンジーゼラニウムはフロウソウ科のテンジクアオイ属の植物です。品種改良によって、南アフリカ原産のトリコロル種とオウァーレ...
-

-
果物から出てきた種を育てる方法
果物には、中に種が入っているものが多いです。果物によっては、食べながら種を取り出して、それを土に植えることで、栽培するこ...
-

-
白菜の育て方
白菜は、アブラナ科の野菜で、生息地は他のアブラナ科の野菜類と同様に、ヨーロッパの北東部からトルコ にかけての地域でだと考...
-

-
シャコバサボテンの育て方
現在観葉植物として流通しているシャコバサボテンはブラジルのリオデジャネイロを原産地とする観葉植物であり、標高1000~1...
-

-
ウメモドキの育て方
ウメモドキは、日本の本州、四国、九州、そして中国原産の落葉低木です。モチノキ科モチノキ属に分類され、生息地は暖帯の山間部...
-

-
ヌスビトハギの育て方
ヌスビトハギの仲間はいろいろ実在していて、種類ごとに持っている特質などに違いが見られ、また亜種も実在しています。例に出し...
-

-
カカオの育て方
そんなカカオの特徴はどのようなものなのでしょうか。前途のように、チョコレートの原料として使われるので樹そのものよりも、果...




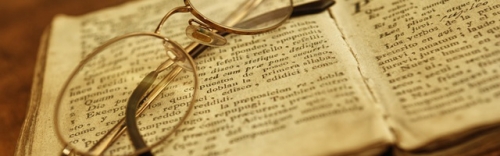





クマツヅラ科ハリマツリ族(デュランタ属)の熱帯植物です。形態は低木です。和名には、ハリマツリ、タイワンレンギョウ、などの呼び方があります。アメリカのフロリダ州〜ブラジルが原産地の熱帯植物です。藤色や白い小花が集まり、房状に垂れ下がって咲きます。日本に渡来したのは明治中期頃と言われています。