アッツザクラの育て方

アッツザクラの育て方を知ろう
アッツザクラは花が咲くまではできるだけ日当たりが良い場所で育てるのが良いです。ただし高温多湿は苦手ですから梅雨時になれば直射日光があたらない風通しの良い場所に置いておきます。秋になると葉が枯れて休眠状態に入っていきます。凍らせないようにする必要はありますが、ある程度の寒さにあたらないと花芽をつけないという性質があるので、あえて屋外で栽培したままにしておくのが育て方のコツです。
冬は5度から8度ほどの温度にあうのがベストですから、屋内には入れないようにするのがいいです。もしどうしても室内に置くとしても10度以上にはならない環境においてあげることで花芽をつけるようになります。庭植えのままですとさすがに凍ってしまう恐れがあるので、その場合は球根を掘りあげておがくずなどを入れて球根が乾燥しないように凍らない程度の低温の場所に保管します。
暖かい土地などで凍る心配がなければあえて球根を掘りあげる必要はありません。栽培する上で土は水はけの良いものが適しています。鉢植えであれば小粒の赤玉土を5、腐葉土を3、ピートモス2の割合で混ぜたものか市販の草花と野菜の土などを使うといいです。水は生育期間であれば土が乾いた時にたっぷりと与えるようにします。
秋頃から休眠に入ってくれば水は与える必要はありません。肥料はそれほど多くあげなくてもいいのですが、葉が枯れるまでは1、2か月に1回の割合で固形肥料を施すようにするといいです。害虫は春になるとアブラムシが大量に発生しやすくなるのでそこは注意が必要です。アブラムシは1匹いればすぐにたくさんの幼虫を生んであっというまに増えてしまいます。
アッツザクラの育て方のコツ
アッツザクラは鉢植えで栽培しているとどんどん根がはってきて根詰まりを起こしてしまう恐れがあります。また用土も何年もそのままでは劣化してしまいますので、毎年早春の頃にでも植え替えをするのが良いです。植え替えしないと芽がたくさんになりすぎて球根の太りが悪くなってしまいますし、花の数も少なくなってしまいます。
ですからこの作業は忘れないようにしましょう。またアッツザクラは球根性なので水のやりすぎなどで水はけが悪かったりすると、せっかく栽培していても球根が腐ってしまうことがありますので植える場所だけは気をつけるようにしたほうがいいです。あとはそれほど育て方も手間はかからない植物ですから安心です。
種付けはできるのか?
基本的には球根で栽培するので種よりは増えてくる球根を分けるなどして増やすほうが簡単です。早春か開花直後に株わけするような要領で分けてから植えつけると良いです。1球ずつにするよりはいくつかの塊に分けるのがコツです。球根を掘りあげたらまずは古い土を落としてしまい、それを大まかに分けてしまいます。
植える時には球根同士の間隔をあけ過ぎないように植えます。あまり間隔をあけすぎてしまうと花が咲いた時に寂しい感じになってしまうので1cmほどの適当な間隔で植えるようにするのが良いでしょう。ポイントは球根同士がくっつかない程度の間隔にすることです。土をかぶせる時は球根の高さくらいにするのがちょうどいいです。
12cmほどの鉢植えを使う場合で球根は10球までとしておくのが目安です。球根は自然と増えていきますから何年もこの作業をしていないと窮屈になってしまうので毎年行なうようにします。種付けをする場合もありますが、その時には種付けされたものが落下して発芽することもあります。
しかし見栄えなどのバランスを気にするのであれば種付けされたかどうかは花が咲き終わる頃にチェックするようにして種も下へ落ちないように採取するのが良いです。種はかなり小さな種なので採取する時には気をつけましょう。植える時も土はほとんどかぶせなくても大丈夫です。
アッツザクラにはいくつかの品種があります。同じピンク色でも微妙に濃さが違ったりして楽しむことができるのでいくつかの品種を植えてみるのも良いでしょう。白い花にうっすらとピンク色がかっている白鳥、濃いピンク色の花が咲き、白いかすりが入る都鳥、ピンク色の覆輪花の千代鶴、都鳥を薄くしたピンク色の折鶴、赤い色の花で八重先のルビーの輝きなどがあります。
庭植えにして群生させるとかなり美しく、庭を彩ってくれます。丈夫で育てやすいのでいろんな品種の栽培に挑戦してみるのもオススメです。ちなみにアッツザクラにも花言葉は存在しており、可憐という見た目そのままなものがあります。
また無意識や愛を待つ、はかない恋という花言葉もあります。1月23日の誕生花でもありますから、その日が誕生日の方に鉢植えか苗をプレゼントしても喜ばれるでしょう。草丈もそれほどありませんから世話をしやすいですし、それなりに増えてくれば世話をする楽しみも増します。英名はローズグラスやレッドスターといいます。
アッツザクラの歴史
アッツザクラはアッツという名前はつきますが、アッツ島にあるものではなく、原産や生息地は南アフリカです。ではなぜアッツザクラという名前がつけられたのかといいますと、当時まだアッツ島の日本の守備軍が玉砕をした記憶も生々しく残っている頃に山野草の専門店で売り出された桜だからということが伝えられています。
そのお店がアッツザクラと名付けていたのです。こういう経緯があったので実際のアッツ島とは全く関係はありません。現在では属名であるロードヒポキシスという名前でも販売されています。日本に渡来したのは実はアッツザクラと名付けられた時代のはるか昔である1921年(大正10年)の頃だといわれています。
この植物は発見されて以来主に英国で園芸品種が作り出されていますが、近年では日本でも品種改良などが研究されています。ロードヒポキシスとはギリシャ語でバラの花という意味があるrhodonとヒポキシスという植物が語源になっています。さくらと名付けられてはいますが、桜の仲間でもありません。
キンバイザサ科といわれていますが、高山に咲く多年草です。開花は4月から6月頃になります。茎は細くて白い産毛のような毛が生えており、白やピンク、紫色の花を咲かせます。
アッツザクラの特徴
花の直径は2、3cmほどで6枚の花びらから成り立っています。3枚ずつ2段になっていて草丈は10cmから15cmほどです。小鉢など鉢植えでよく植えられることがあります。球根は直径1cmほどしかありません。南アフリカが原産なだけに暑さには非常に強いですが、逆に寒さには弱いので対策をしておく必要があります。
ただしある程度の寒さにあわないと翌年花が咲きませんので、その辺りも考えておく必要があります。比較的、初心者の方でも育てやすいです。草丈があまり高くないことからグランドカバーとして植えられることも少なくありません。春植え球根として扱われることが多く、冬の間は葉が枯れてしまい、休眠状態になります。
球根は掘りあげて乾燥させてしまうと枯れてしまうので、乾燥させないようになるべく掘りあげないようにして冬の間もできれば多少は湿り気を感じさせておくほうが良いでしょう。冷蔵しておいた春先の芽を出す前の球根を植えることで秋にも花を咲かせようとすればそれも可能となります。黄花アッツザクラという名前で売られているものもありますが、これは同属ではあるものの、アッツザクラの一種ではありません。
-

-
ヒコウキソウの育て方
ヒコウキソウ(飛行機草)はマメ科、ホオズキバ属(クリスティア属)の植物で、東南アジア原産です。別名コウモリホオズキハギと...
-

-
びわの育て方
枇杷(ビワ)は、中国南西部原産で、バラ科の常緑高木です。日本には古代から持ち込まれています。インドにも広がっており、非常...
-

-
イチゴの育て方について
イチゴは粒が大きくて甘味が強いのが当たり前だと思っている人が少なくありませんが、スーパーの店頭などで売られている栽培イチ...
-

-
フェイジョアの育て方
フェイジョアは1890年にフランス人の植物学者であるエドアールアンドレによってヨーロッパにもたらされた果樹です。元々は原...
-

-
なたまめの育て方
中国では古くから漢方と用いられてきました。中国の歴史的な著書には「なたまめは腎を益し、元を補う」とかかれています。人とい...
-

-
キアノティスの育て方
キアノティスは熱帯アジアと熱帯アフリカを生息地とする植物です。原産の地域では高さが10センチから40センチくらいになりま...
-

-
ワサビの育て方
ワザビの色は緑色をしており、香りは大変爽やかになっています。しかし何と言っても最大の特徴はあの抜けるような辛みでしょう。...
-

-
ポトス(Epipremnum aureum)の育て方
ポトスの原産地はソロモン諸島だといわれています。原産地のソロモン諸島は南太平洋の島国で常夏の国です。一年を通じて最高気温...
-

-
ヒビスクス・アケトセラの育て方
ヒビスクス・アケトセラが日本に入ってきた年代は詳しく知られていないのですが、本来自生しているものは周種類であるとされてい...
-

-
トサミズキの育て方
トサミズキの生息地は、四国の高知県です。高知県(土佐)に自生することからトサミズキ(土佐水木)と呼ばれるようになりました...




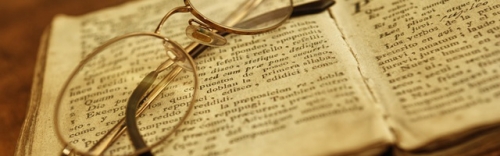





アッツザクラはアッツという名前はつきますが、アッツ島にあるものではなく、原産や生息地は南アフリカです。ではなぜアッツザクラという名前がつけられたのかといいますと、当時まだアッツ島の日本の守備軍が玉砕をした記憶も生々しく残っている頃に山野草の専門店で売り出された桜だからということが伝えられています。