木立ち性ベゴニアの育て方

育てる環境について
ベゴニアの野生種はオーストラリア大陸を除く世界の熱帯、亜熱帯地域に広く公布しています。また、熱帯とはいえ乾燥や酷暑の続く場所ではなく、標高が高く寒暖差が小さい山地なので、多くの種類は厳しい暑さと寒さが苦手です。また、うっそうと茂った森林でつるになって、
樹幹に絡みついて伸びたり、河畔などに生えており、強い日差しの当たらない、湿度が高い場所を好みます。なので、日本で栽培する際、注意が必要です。特に冬の時期です。熱帯、亜熱帯地方原産の木立ち性ベゴニアにとって、凍るような寒さは枯死をもたらします。
室内に取り込み、保温して冬越しをします。その際、日光不足になりやすいため、葉が黄化したり、間のびする株も出てきます。一方、温室やサンルーム、夜間でも一定の温度が保てるマンションで四季咲き性の品種を育てている場合は、花数は少ないですが開花が見られます。
逆に夏では、熱帯夜が続く最も過酷な真夏を迎え、少々夏バテ状態です。ベゴニアは、熱帯、亜熱帯が原産といっても、標高の高い山地に自生するので、日本の酷暑と乾燥はベゴニアにとっては過酷な環境下です。また、この時期には根腐れや水切れなどの
症状が出ていないかチェックも必要です。なので、屋外の風通しのよい明るい半日陰で育てます。家の東側や北側で朝日が当たる程度の場所、木漏れ日の下、あるいは南側であれば50%くらい遮光します。強い直射日光が当たると葉焼けを起こすので注意してください。
種付けや水やり、肥料について
苗を購入する際、苗は株元がぐらぐらせず、茎がしっかりしている株を選びます。見た目で「大きいから」と、つい茎が長く伸びた株を選びますが、このような株は「徒長」と言って、高温、日照不足、蒸れなどが原因で、柔らかくひょろひょろと間のびした生育不良株ですから、選ばないようにします。
また、葉色が黄ばんでいたり、下葉が枯れていたり、葉の大きさがまちまちなものは悪い株です。花だけを見て選ぶのではなく、これからよい花を咲かせる株かどうかという事を念頭においてください。ポット苗の場合は、根の状態をチェックするとよいでしょう。
次に培養土ですが、排水性、通気性に富み、適度な保水性のある土が適しています。例を挙げますと、赤玉土5、腐葉土2、ピートモス2、パーライト1の割合で配合します。ピートモスを用いるときは、酸度調整済みかどうかを確認し、未調整であれば苦土石灰を加え、pH(土壌酸度)を5.5~6.5にします。
次に肥料については、一般的に野生種は多肥を好みませんが、園芸品種を立派に咲かせるには肥料が欠かせません。ベゴニアは春と秋に生育が活発になるので、植え付け時には元肥として、用土1㍑あたり緩効性化成肥料(N窒素-Pリン酸-Kカリウム=6-40-6など)を5g程度、
花が次々に咲いているときは化成肥料を置き肥するか、あるいはリン酸分が多めの液体肥料(N-P-K=6-10-5など)を10日から2週間に1回の割合で施します。最後に水やリですが、株の生育が衰える真夏や真冬には水やリを控えめにします。この場合、「水やリの回数」を減らすのであって、
「1回の水やリの量」を減らすのではありません。通常の水やリの基本は「鉢土が乾いたら、鉢底から水が流れ出るほどたっぷりと与える」です。少量の水を頻繁に与えることを繰り返すと、細根が深く伸びていかずに地表近くに集まってしまうため、鉢土が少しでも乾くと萎れやすくなります。
増やし方や害虫について
ベゴニアの育て方は簡単にしたが、増やすのも簡単で、挿し木が一般的です。そのやり方をお伝えします。挿し木は20℃前後の時が最も発根しやすく、5月は挿し木の適期です。良いさし穂の取り方は1本の枝からでも数本のさし穂をとることができますが、さし穂をとる部位に注意が必要です。
太い茎や、茎の下の方の木質化した部分からは初根しにくいうえ、元気のよい芽も出にくいので茎の先端から7cmくらいで切り離し、さし穂にします。また、葉っぱは蒸散を抑えるため大きな葉を半分に切り落とします。そして、無肥料のみずはけのよい清潔な培養土を用意します。
まず、さし穂を30分くらい水に差し込み、次に、培養土を入れたポットに挿し、そのあと、たっぷり水やリをします。作業後は、水やリを控えめにし、直射日光の当たらない場所で管理をする。さし穂の下の方の節に葉芽があれば、地際から芽が出て株立ちがよくなる。
5月にさした挿し木苗を7月になったら、ひとまわり大きな鉢に植え替えます。その際のポイントは、根鉢を崩さず、新しい用土で植え替えします。その後水をたっぷり与えます。約3ヶ月後の秋には立派に花が開花します。ベゴニアの病害虫についても対策が必要です。春になって暖かくなるとアブラムシが発生しやすくなるので、
日頃から新芽や葉をよくチェックします。また、高温になりやすい夏の時期はダニ類がよく発生します。ダニ類による症状を見つけたら、直ちに専用の殺ダニ剤で駆除します。なお、ダニ類は乾燥条件で多発する反面、水を嫌うので日頃から時々葉裏を洗い流すように水を与えたり、葉水をかけて湿度を保つなど、予防するとよいでしょう。
木立ち性ベゴニアの歴史
ひと口にベゴニアと言っても、いろいろな種類があり、野生種だけでも約2000種、交配種にいたっては約1万5000品種で今もなお新種が次々と発見されています。そんなベゴニアは、茎の形態に着目して分類すると、木立ち性ベゴニアと球根性ベゴニアと根茎性ベゴニアの3つに分けられます。
また、ベゴニアのもともとの生息地は熱帯や亜熱帯地域に公布しています。日本でも、西表島から石垣島にかけて、コウトウシュウカイドウとマルヤマシュウカイドウという2種の根茎性ベゴニアが自生しています。日本で古くからよく見られるシュウカイドウは実は日本国有の植物ではなく、
中国が原産である球根性ベゴニアで、江戸時代に初めて長崎に渡来したと言われています。また、木立ち性ベゴニアにはブラジル原産のマクラタやシュミティアナなどの品種があり、ニューギニア島原産のブレウィリモサ、中国原産のマソニアナ、西アフリカ原産のプリスマトカルパなど世界各国で栽培されています。
突然ですが、ベゴニアの花言葉は何だとご存じですか。ベゴニアの花言葉は「片思い」とか「不調和」です。清楚な花に反して、イメージのあまり良くない花言葉がつけられているのはなぜでしょう。それは、ベゴニアの葉が主脈を中心にして
左右の大きさが同じでないことに由来しています。つまり、二人の心が同じでない「片思い」というわけです。鉢植えで楽しむ多年草のなかでもひときわ異彩を放つ存在である、木立ち性ベゴニア。シャンデリアのような豪華な花房を楽しむのもいいですね。
木立ち性ベゴニアの特徴
1万5000種を超えるベゴニアは茎の形態に着目して分類すると、次の3つに分けられます。一つ目は地下に球根を作らず、茎が立ち上がって伸びるタイプの木立ち性ベゴニアです。二つ目は地下または地際に球根をつくるタイプの球根性ベゴニア。
三つ目は節間がつまり、多肉質の太った茎が地下や地表面を這うタイプの根茎性ベゴニアの3つのグループに分けられます。さらに、木立ち性ベゴニアは茎の形状により次の4つに分けられます。茎が堅く、節の部分が矢竹のように少し太くなり、
木立ち性ベゴニアのなかでも最も園芸品種の数が多い「矢竹型」と、茎は柔らかい草質で、地際から茎が多数伸びて灌木状に生い茂る「叢生型」と、茎が細く、垂れ下がったり、這い上がったりする「つる性型」と、茎は多肉質で太く、直立して伸びて、節間が短く、
あまり枝分かれしない「多肉茎型」の4つにグループに分けられます。木立ち性ベゴニアは地下に球根を作らず、茎が立ち上がって伸びるタイプで、株が古くなると、茎の基部が茶色く木のようになりますが、ベゴニアは草本植物であり、木立ち性といっても年輪ができる樹木にはなりません。
シャンデリアを思わせる豪華な花房が特徴で、主として花を観賞するベゴニアです。四季咲き性の品種が多く、暑さ寒さに比較的強くて育てやすいことから、多くの愛好家たちの間で親しまれています。また、ベゴニアの花は雌雄異花同株でキュウリやカボチャやスイカなどと同じく、雄しべだけを持つ雄花と雌しべだけを持つ雌花が同じ株に存在します。
-

-
チョコレートコスモスの育て方
チョコレートコスモスは、キク科 コスモス属の常緑多年草です。原産地はメキシコで、18世紀末にスペインマドリードの植物園に...
-

-
ズッキーニの育て方
アメリカ南部付近、メキシコあたりまでが生息地であり原産地ではないかといわれています。本格的に栽培が始るのがヨーロッパに入...
-

-
シャクヤクの育て方
シャクヤクの最も古い記述については、中国で紀元前五世紀には栽培されていたという記録が残っており、宋の時代には品種改良が行...
-

-
トマトの栽培における種まきや植え付けの時期及び育て方について
トマトは世界一の需要量を誇る野菜で、日本でも比較的良く食されています。気候的にも栽培に適する事から、家庭菜園レベルであっ...
-

-
マツバギクの育て方
原産地が南アフリカなどの砂漠地です。日本には明治の初期に暖地で広がりました。マツバギクは葉が松葉のような形をしてサボテン...
-

-
アメリカテマリシモツケの育て方
アメリカテマリシモツケは、北アメリカが原産だと考えられており、現在テマリシモツケ属の生息地はアジア東部や北アメリカ、メキ...
-

-
アエオニウムの育て方
アエオニウムはアフリカ大陸の北西の北アフリカに位置するカナリー諸島原産の植物です。生息地は亜熱帯を中心に多くく見られる植...
-

-
コトネアスターの育て方
コトネアスターはほとんどがインド北部またはチベットを原産としています。生息地はこれらの国に加えて中国まで広がっています。...
-

-
食べ終わったアボカドを観葉植物として栽培しよう
最近、美容にとてもいい効果があるとしてハリウッド女優やモデルがよく食べているというアボカドは、栄養価が高く質のいい不飽和...
-

-
アイスランドポピーの育て方
ポピーというケシ科はなんと26属250種も分布しており、ケシ科ケシ属でも60種の仲間が存在します。ケシ科は麻薬成分モルヒ...




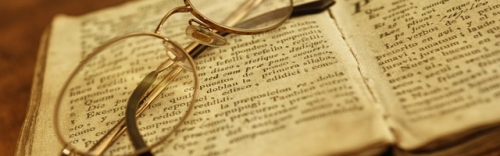





木立ち性ベゴニアの科名は、シュウカイドウ科で属名は、シュウカイドウ属(ベゴニア属)になります。その他の名前は、キダチベゴニア、コダチベゴニア、木立性ベゴニアと呼ばれています。ひと口にベゴニアと言っても、いろいろな種類があり、野生種だけでも約2000種、交配種にいたっては約1万5000品種で今もなお新種が次々と発見されています。