エピデンドラムの育て方

育てる環境について
エピデンドラムは中米から南米の熱帯、あるいは亜熱帯地区を原産地としている植物であり、様々な色の花をつけることを特徴としている花です。原産地の気候に似た環境では長く栽培することが出来ますが、寒さに弱いという性質がありますので冬に寒い地域では
室内で栽培するなどの対応が必要になるケースもあるでしょう。常緑性の植物であり観葉植物にも適しています。比較的育てやすいという特徴もありますので初心者にも扱える植物であると言えます。なお、花は不定期に咲きますので時期を問わずに楽しむことが出来る植物であると言えます。
このエピデンドラムは育てる上で剪定などを行う必要はあまりありません。原種の様に大きく育つことを目的にしたものは減り、植木鉢で育てることが出来る大きさで成長を抑制するのが一般的な対応です。形を整える場合などには好みに合わせて切ってみるのも良いでしょう。
それよりも日課になりそうなのは花がら積みです。この花の開花時期は非常に長く、その間ずっと同じ花が咲いたままでいることはできません。そのため古い花は徐々に茶色く枯れて行き、最後には散ってしまうのです。そうなる前に手で取り除いて、
花の部分を綺麗なボールの形に保たせてあげることが出来れば最良であると言えるでしょう。望ましい環境hあ日当たりのよい場所です。夏の時期に日差しが強すぎるケースを除いて殆ど全ての日は日向におくべきでしょう。夏は戸外、冬は屋内になってしまうケースが多くなって行きますので注意しましょう。
種付けや水やり、肥料について
エピデンドラムの植え付けや植え替えは2年に一回程度の頻度で行うようにしましょう。鉢植えで育てている場合には少し大きな鉢に移すか、株分けをして十分なスペースを確保すると良いでしょう。その様な場合にはあまり細かくし過ぎないようにするのがコツです。
茎が多いほど花が咲いた時に見事な見た目になりますのであまり小さくまとめてしまうとエピデンドラムの見事な咲きっぷりを楽しむことが難しくなってしまいます。水やりは植え込みが乾いてきたタイミングを使ってたっぷりと与えるようにしましょう。
夏の気温が高い時期には鉢植えが濡れていても新鮮な水を与え続けるようにしましょう。一方で冬の時期にはやや乾かし気味での管理が推奨されます。株が大きくなってくると気根を出すようになりますので水やりの際には空中にある根にも水をかけて挙げると良いでしょう。
肥料に関しては綺麗で立派な花を咲かせたい場合には用意すると良いでしょう。春には緩効性化成肥料を鉢植えの大きさに合わせた適量を施すと良いでしょう。それ以後は液体肥料を週に一回程度施すことが必要になります。この様な対処をすることでエピデンドラムは
美しい花を非常に多く咲かせるようになるでしょう。この肥料や水やりに関しては必要なタイミングで必要なだけ行う様にすることが重要であり、植物と接するのに対して育て方を学ぶ必要があるのは何が何でも水と肥料をまけば良いというものではないということを理解することが必要なのです。
増やし方や害虫について
エピデンドラムを増やすのであれば最も一般的な方法は株分けと呼ばれる作業です。この株分けの最適気は4月であり、鉢植えから取り出したエピデンドラムの根鉢を丁寧にほぐして分けることが出来そうな場所でほぐして行くのが主な方法です。
手で分けることが難しい場合にはハサミを利用するのも一つの手ですが、上手に分けることが難しいあ愛には鋏を使用するのも一つの手段です。なお、鋏を利用する場合には消毒をしておくことが推奨されます。万が一カビなどの胞子が付着していた場合には、
刃物で切った断面等は非常に感染しやすい場所であると言えます。そのためその様な病気にも注意しておく姿勢は重要です。幸いエピデンドラムには深刻な害を出す病気の存在は確認されていません。そのためある程度は安心することが出来ます。しかしながら害虫の被害は多数報告されています。
エピデンドラムに就くことがある虫としてはアブラムシが一般的であると言えます。アブラムシは多くの植物についてしまう虫ですが、植物の汁を吸うことで植物本体を枯らしてしまう恐れもあると言われています。そのためアブラムシが付き始めたら早めに何らかの対処をするようにしましょう。
後回しにしているとあっという間に相当な量のアブラムシが闊歩するようになりますので早めの対応は非常に重要です。大量発生してしまうと周囲の環境にも悪影響を及ぼしてしまうため特に注意して駆除しておくことが重要であると言えます。
エピデンドラムの歴史
エピデンドラムはラン科の植物であり、日本においては観葉植物としてその地位を安定させています。この植物の本来の生息地はメキシコから南アメリカにかけての地域であるとされています。観賞用として盛んに品種改良がおこなわれた結果、
400種類から1000種類を超えるという極めて多くの品種を持つ植物になりました。しかしながら日本で主に流通している物はその中の本の一握りであり、世界的には同じ種類の植物の仲間であっても日本においてはその他の洋ランと一括りにしてしまうことも少なくありません。
日本におけるエピデンドラムと言う花は世界におけるそれに比べてやや狭い範囲の花を示す言葉であると言えるでしょう。歴史的にはそれなりに長いものを持っていますが、観賞用に品種改良が繰り返されている関係から交配種の方が流通するようになり、
歴史のある新しい花と言う顔を持つようになってきました。完全に観賞用に特化しているものが多く、日本国内では冬の時期を室内で迎えさせなければならないケースも少なくありません。そのため本来の生息地では非常に大きな気になるのが一般的ですが、
日本においては植木鉢で育てることが出来るサイズでとどめておくスタイルの花が人気を高く持つようになってきました。多くの人にとってこの花の名前は聞きなれないものですが、切り花としての普及が進んでいますので知らず知らずのうちに花束の中に入っていることも珍しくありません。
エピデンドラムの特徴
エピデンドラムは中南米に広く分布しているランの仲間です。日本においても流通している花になりますが、その様なエピデンドラムはリードステムエピデンドラムと呼ばれる種類の交配種であるのが一般的です。野生のエピデンドラムは1メートルから数メートルと
いう非常に大きく育つ細長い茎を持っていますが、その頂点にドーム状に小さな花が多数咲くという特徴を持っています。このエピデンドラムはそのままでも十分に美しい花ですが、株が長く延び過ぎてしまうと飾ることが出来る環境が限られてしまうという物理的な問題から、
近年では茎が短くなるような交配種が生まれるようになってきています。そしてその様なエピデンドラムは鉢植えで育てることが出来る園芸用の植物として一般的な存在になってきています。エピデンドラムの花は元々はオレンジ色が主流でした。
しかし品種改良が進むにつれて様々な色が姿を現すようになってきました。例えば赤や黄色、ピンクや白と言った似た系統の暖色の花を咲かせる品種が数多く生み出されてきたのです。最近では色とりどりの花を楽しむことが出来るようになりました。鉢植えで育てることによって
長く楽しむことが出来るのですが、エピデンドラムと言う花は切り花にしたり生け花での活用も増えてきています。実際にエピデンドラムと言うと様々な形状と色が存在していますが、日本においては株の頂部にボール状の花を咲かせる品種のことを言い、それ以外は原種ランという括りで扱われるのが一般的な対応となっています。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:エランギスの育て方
-

-
シペラスの育て方
シペラスは、カヤツリグサ科カヤツリグザ(シぺラス)属に分類される、常緑多年草(非耐寒性多年草)です。別名パピルス、カミヤ...
-

-
ベゴニア・センパフローレンスの育て方
ベゴニア・センパフローレンスはシュウカイドウ科ベゴニア(シュカイドウ)属に分類される常緑多年草です。ベゴニアはとても種類...
-

-
コカブの育て方と種まきの時期
コカブは球の直径が4から5センチのカブで、葉にはビタミンA、Cが多く含まれています。コカブの栽培は、虫の食害にだけ気を付...
-

-
ミニトマトの育て方について
ナス科のミニトマトの育て方について、ご紹介します。ミニトマトは、ビタミンCとカロテンを豊富に含んでおり、そのままでサラダ...
-

-
ブラックベリーの育て方
ブラックベリーの始まりは古代ギリシャ時代までさかのぼることができるほど古いです。このブラックベリーは人々から野生種として...
-

-
アジサイの育て方
アジサイは日本原産のアジサイ科の花のことをいいます。その名前の由来は「藍色が集まった」を意味している「集真藍」によるもの...
-

-
モクビャッコウの育て方
日本では、神の島「久高島」の浜辺に群生していることで知られています。また日本では古くから南西諸島や硫黄島などに自生が見ら...
-

-
ヒコウキソウの育て方
ヒコウキソウ(飛行機草)はマメ科、ホオズキバ属(クリスティア属)の植物で、東南アジア原産です。別名コウモリホオズキハギと...
-

-
バイカカラマツの育て方
バイカカラマツとはキンポウゲ科の植物で、和風な見た目やその名前から、日本の植物のように考えている人も少なくありませんが、...
-

-
ムスカリの育て方
ムスカリは、ユリ科ムスカリ属の球根植物で、ヒヤシンスの近縁とも言える植物です。約30~50ほどの品種があるといわれ、その...




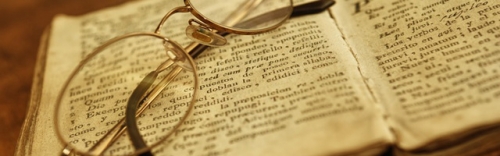





エピデンドラムはラン科の植物であり、日本においては観葉植物としてその地位を安定させています。この植物の本来の生息地はメキシコから南アメリカにかけての地域であるとされています。観賞用として盛んに品種改良がおこなわれた結果、400種類から1000種類を超えるという極めて多くの品種を持つ植物になりました。