セツブンソウの育て方

育てる環境について
セツブンソウは、特に石灰岩質の礫地を好む傾向にありますが、乾燥することをあまり好みません。育て方としては、開花するまでの時期は雨があたらない日のあたる場所で育てていくことがおすすめです。花が咲き終わった後は、地上部が枯れてしまい休眠にはいるまでは
半日陰の場所で管理していくようにしましょう。鉢植えで育てていく場合には、芽が出始める頃から花が終わって結実する4月下旬頃までは、午前中の間は日のあたるような場所で栽培していくようにします。葉が伸びきって結実する頃からは、半日陰に移してあげることで
葉が傷んでしまうことを防ぎましょう。夏の厚いシーズンは、気温がとても高くなり乾燥しやすくなります。地温が上昇すると地中の球根が暑さで傷んでしまうことがありますので、枯れてしまうこともあります。基本的に耐暑性の弱い植物だとされていますので、
夏の暑さはには弱いです。逆に寒さには非常に強いという性質を持っていますので、霜などで枯れてしまうという心配をすることも少ないです。冬の生育期間には、できるだけ日光のあたる場所で管理していくようにしましょう。葉が枯れて落ちてしまっている場合には、
軒下などの比較的涼しい場所へ移動してあげることがおすすめされています。庭植えをして育てていくような場合は、落葉樹の下などが好ましいとされています。少し傾斜地になっているような場所が理想的で、石のかたわらなどに植えてあげることによって水はけをよくすることができます。
種付けや水やり、肥料について
芽が出て花が咲く頃は土の表面が乾いたら株元に水を与えてあげるようにしますが、多湿にならないように注意してあげることが大切です。葉は自然に枯れてくるまで傷めないようにするために、休眠期に入っている場合は少し乾かし気味にすることがおすすめされていますので
水をあまり与えません。ただし、完全に乾燥させ過ぎてしまわないように多少湿っている状態にしてあげましょう。夏は気温が高くなってしましますので日中に水やりをすることはおすすめできません。夕方など比較的涼しくなってくる時間帯になってから、
地上部が枯れた頃を目安に水やりしてあげるようにしてください。夏場は乾燥しやすいシーズンですので、たっぷりと水やりをしてしまいたくなりますが過湿には注意しましょう。庭植えをしている場合には、基本的に自然の雨で生育していくことができますが、
開花シーズンに入ると乾燥しやすくなってきますので水やりをしてあげてください。セツブンソウは、あまりたくさんの肥料を必要としませんが、生育期間が短いので施肥は大切なポイントでもあります。鉢植え、庭植えでも芽出しのころに1回置き肥をし、成長期には2週間に1回液体肥料を施します。
花が終わってから地上部が枯れる夏前までは、2000倍に薄めた液体肥料を週1回くらい与えます。休眠期には肥料は施す必要がありません。水はけ良いことが大切で、石灰質を含む土壌を好みますので軽石砂と赤玉土を等量に混ぜたものか、軽石砂を主体に赤玉土や鹿沼土を2、3割ほど混ぜた用土が適しています。
増やし方や害虫について
セツブンソウは、球根の分球がほとんど見られませんので球根の分球やタネまきで増やしていきます。4月頃に果実が割れたらタネをとり細かめの培養土にまきますが、この時に細かい緩効性化成肥料を元肥として少し入れておくと効果的だとされています。
セツブンソウの場合は、タネを保存しておくと発芽率が落ちますので、タネを採取してすぐにまく「とりまき」が基本になります。種を蒔く土はバーミキュライトや赤玉土、植え付けに使用する用土などでも生育することができます。まいた後は乾燥を防ぐために細かい土を
古いなどを使ってあげるとよいでしょう。セツブンソウの主な病気には、軟腐病、炭そ病、連作障害などがあります。多湿になることで発生する軟腐病は、地上部が腐ることが多くありますので注意するようにしましょう。植え替えを何年もおこなっていない場合は、
連作障害を起こしてしまいやせてきますので植え替えをおこなってください。植え付けや植え替えをするのに適しているシーズンは、8月末頃から9月中だとされています。葉のある時期には茎が弱いため控えてください。セツブンソウに発生する害虫には、
ナメクジ、ヨトウムシ、アブラムシなどがあります。ナメクジやヨトウムシは食害をしてしまいますので、発見をしたら専用の殺虫剤などを散布するなどして対策を施してあげましょう。アブラムシなども多くついてしまうことがありますので、見つけたら拭き取りをするなどして取り除いていくことが大切です。
セツブンソウの歴史
節分の頃に花を咲かせるセツブンソウは、キンポウゲ科セツブンソウ属の多年草のことを言います。日本原産の植物で関東地方以西に分布し、石灰岩地域や落葉広葉樹林の林床、山地のブナ林などが生息地となっています。キンポウゲ科というのは、2枚の初期葉もしくは
子葉をもつ植物の双子葉植物キンポウゲ目に属する科です。草本または自らの剛性で体を支えるのではなく、他の樹木を支えにするつる性などが多いとされています。開花するシーズンは2月頃から3月頃となります。セツブンソウの仲間のエランティス属は、
ヨーロッパからアジアなどの温帯に7種類ほどが生息しています。レッドリストに掲載される希少種で絶滅危惧類に指定されていることから、保護しているところも多いとされています。近畿地方では、伊吹山、鈴鹿山地や兵庫県北部の石灰岩地などに生息しています。
セツブンソウの根の部分には有毒成分のアコニチンがあることから嘔吐、頭痛、麻痺などの中毒症状を起こしてしまうとされています。セツブンソウと花色がよく似ている植物には、韓国原産のヒナマツリソウがあります。その他にも、ヨーロッパ原産で
黄色い花を咲かせるキバナセツブンソウやオオキバナセツブンソウなどもあります。種から育てられますが花が咲くまではおよそ3年以上くらいかかるとされています。英名では、ウインター・アコニットと呼ばれているのですが、アコニットというはトリカブトのことを言います。
セツブンソウの特徴
セツブンソウの草丈は、およそ5センチメートルから15センチメートルくらいになり地面から花茎を伸ばして茎頂に複雑に裂けた総苞葉をつけます。細かく切れ込んだ葉っぱを開きますが、総苞葉には柄がありません。大きな切れ込みがある苞葉の先端部分に、
およそ2センチメートルくらいの可憐な白い花を1輪咲かせます。花びらに見える部分は萼で基本的に5枚あり、6枚以上の花もよくあります。花の芯周辺にある黄色の部分の花びらは、筒状のような形をしていて先端部分がおよそ2から4本くらいに分かれて
蜜腺は蜜腺があり筒のくぼみに蜜が入っています。名前の通りあまい蜜を出す器官で、雄しべの先端に付いている花粉が入った葯も紫色で鮮やかです。雄しべの中心部分には、およそ2から5本くらいのピンク色の雌しべがあります。球根の大きさは径およそ1.5センチメートルほどで、
先端の尖った球形をしています。4月の終わり頃から5月初め頃には、袋果から種子を播き落としていきます。セツブンソウは、スプリング・エフェメラルと呼ばれる春植物の1つで、可憐さからとても人気があります。セツブンソウは、寒い冬のシーズンに芽を出して
花を開花させます。その後に葉を茂らせて木々の新緑がまぶしくなる春の終わり頃には茎葉が枯れて地下の球根の状態で秋まで休眠期に入ります。根は秋頃から地下で伸び始めるのですが、セツブンソウが地上に顔を見せ始めるのは春の3ヶ月くらいだとされています。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:カラマツソウの育て方
-

-
サルビア・レウカンサの育て方
サルビア・レウカンサの原産地はメキシコや中央アメリカです。別名を「メキシカンブッシュセージ」「アメジストセージ」といい、...
-

-
アッツザクラの育て方
アッツザクラはアッツという名前はつきますが、アッツ島にあるものではなく、原産や生息地は南アフリカです。ではなぜアッツザク...
-

-
コンロンカの育て方
コンロンカの科名は、アカネ科で属名は、コンロンカ属となります。また、その他の名前は、ムッサエンダなどと呼ばれます。コンロ...
-

-
ツタ(ナツヅタ)の育て方
ツタはナタヅタともいい、ブドウ科ツタ属のツタ植物です。古くから存在していて、日本でもよく使われている植物の一つです。昔か...
-

-
ショウジョウバカマの育て方
ショウジョウバカマは日本から南千島、サハリン南部を原産地とするユリ科ショウジョウバカマ属の多年草です。北は北海道から南は...
-

-
トウミョウの育て方
エンドウ豆の歴史は古く、紀元前7000年の頃には南西アジアで作物としての栽培が始まっていました。その痕跡はツタンカーメン...
-

-
ミヤマホタルカズラの育て方
ミヤマホタルカズラはヨーロッパの南西部、フランス西部からスペイン、ポルトガルなどを生息地とする常緑低木です。もともと日本...
-

-
マツカゼソウの育て方
松風草は、一般的には、マツカゼソウと表記され、ミカン科マツカゼソウ属に属しており、東アジアに生息するマツカゼソウの品種と...
-

-
ヒメシャガの育て方
ヒメシャガはアヤメ科アヤメ属の多年草でシャガよりも小型になります。シャガとよく似ており絶滅危惧植物に指定されている耐寒性...
-

-
ヒコウキソウの育て方
ヒコウキソウ(飛行機草)はマメ科、ホオズキバ属(クリスティア属)の植物で、東南アジア原産です。別名コウモリホオズキハギと...




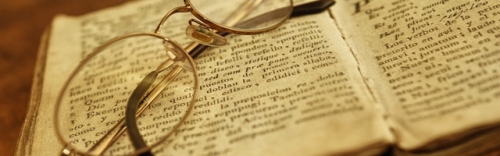





節分の頃に花を咲かせるセツブンソウは、キンポウゲ科セツブンソウ属の多年草のことを言います。日本原産の植物で関東地方以西に分布し、石灰岩地域や落葉広葉樹林の林床、山地のブナ林などが生息地となっています。