コンボルブルスの育て方

育てる環境について
育てる環境については基本的には庭植えですが、マンションのベランダなどで鉢植えにして育てることもできます。比較的暑さには強いのですが、直射日光を避けるようにしないと花が早い段階でしおれてしまうことがあるので、ベランダなどの場合には日当たりに関して注意が必要です。
栽培をする環境として適しているのは温暖な気候で日照量が比較的多い地域で関東地方などでも十分に育てることができます。また地中海沿岸が原産地なので比較的乾燥した土地を好む性質があるので、梅雨の間の管理をしっかりとしておかないと株が弱ってしまうので、
初夏から夏の時期の開花に悪い影響を及ぼすこともあります。栽培をする場合に気をつけておくことは水はけと風通しで、冬は氷点下5度程度まで耐えることができるのですが、それ以下になる場合には室内に置くなどの対処を必要とします。
乾燥している土地ならば元気に育つのがこの植物の特徴なので、乾燥している状態ならばある程度の寒さまで耐えることができます。また直根性の植物なので一度植えたものを他の場所に植え替えてしまうと株が弱くなってしまうので、植え替えるときには土などに特別な注意を払うことが重要です。
土は鹿沼土や軽石などを配合しているものが適していて、市販されている山野草向けの用土と使うことで簡単に栽培することができます。また水はけがいい場所ならば一般の草花用の培養土でも十分に栽培ができるので、初心者にも育てることができます。
種付けや水やり、肥料について
水やりに関しては与えすぎてしまうと根腐れを起こしやすいので用土が乾燥してから水やりをすることが大切で、根腐れというのは細菌が繁殖してしまう状態なので、乾燥状態を一定の期間保つことができれば防ぐことができます。アサガオの栽培などの場合は毎日のように
水やりをしていたのですが、その感覚でコンボルブルスを栽培すると根腐れが起きるので株全体が傷んでしまうことになります。肥料に関しては春の成長期と秋に化成肥料を施すと美しい花を咲かせることができるのですが、日本の夏は高温多湿なので、肥料の成分が
夏にまで残らないように気をつけなければなりません。一年草の品種を育てる場合には定期的に液体肥料を与えることで花を長持ちさせることができます。用土は鹿沼土を基本としてその中に軽石などを混ぜたものと使い、市販されている野草向けの用土でも十分に育てることができます。
水はけには注意が必要で、悪い場合には根腐れの原因にもなります。4月から5月にかけてと9月の下旬から10月の上旬くらいまでが植え付けや植替えに適した時期であるとされていて、コンテナや吊り鉢、石垣の表面などに植えることができます。必要な作業としては
伸びすぎた部分を切除することや切り戻しをして形を美しく整えることなどが必要なのですが、庭植えをしている場合には大きさなどが制限されていないので、これらの作業をあまり必要としません。つる性のものは必要に応じてつるを誘引しなければなりません。
増やし方や害虫について
増やし方に関しては品種によって様々な方法があるのですが、多年草の場合には挿し芽をして増やすことが多く、時期としては9月から10月が良いとされています。一年草は基本的には種まきによって増やすことが多くなっていて、通常の場合は4月から5月に種をまいて育てています。
また暖かい地方では秋にまくこともできるのですが、ポットで育てるか、花壇などに直播きをして育てるかのどちらかなのですが、根を切らないように注意をしないと株を枯らしてしまう場合があります。また品種が多いので中には株分けをすることで増やすことができるものもあります。
害虫については太陽の光がある場所で水はけが良ければ病気になることはなく、害虫などもほとんど見られません。栽培するときに失敗する主な原因としては用土を必要以上に湿らせてしまって、この状態が長く続くことによって、土の中の水分が過剰になることで
細菌が増殖してしまって、根の部分が腐敗してしまうことです。用土に関しては必要以上に湿らせないようにして、ある程度の乾燥状態を維持するように管理をすると開花が長続きします。原産国の地中海沿岸の気候を考えると、乾燥した風が一年中吹いていて、
湿気があまりないので、この気候条件を参考にするとコンボルブルスをコンディションの良い状態で育てることができます。またつる性の品種を育てる場合にはつるの部分をしっかりと誘導しないと伸び放題になって景観を損ねてしまいます。
コンボルブルスの歴史
コンボルブルスは地中海の沿岸を中心とした地域で200種くらいが自生しているとされていて、品種によって一年草や多年草、低木と様々なタイプのものがあります。またつる性の植物の場合もあるので、日本においてはセイヨウヒルガオが帰化植物として扱われています。
花の形は朝顔によく似ていて、花の寿命が2日から3日程度で雨が降っていて陽の光がない状態だと花が閉じているので、日本ではヒルガオとして扱われてしまうこともあるのですが、歴史的に見ると品種が異なっているので、サンシキアサガオなどと呼ばれて栽培されることが多くなっています。
原産地は地中海沿岸ですが、様々な場所を生息地としているので、育て方も品種によってさまざまになっています。日本では一年草の栽培が盛んに行われているのですが、多年草として人気のあるものとしては平面的に生長をする品種やつる性のものなどが数多く栽培されていて、
花壇やコンテナ、ロックガーデンなどに利用されています。花の色は品種によって異なるのですが、白やピンク、青などが多く見られるのですが、中には3色が混じりあったものなどもあるので、好みによって使い分けたり、寄せ植えをするときに使用することもできます。
開花時期は5月から7月の暑い時期で品種によって耐寒性や耐暑性がちがいますが、基本的には暑さに強い品種が多くなっています。開花の時期はその地域の気候によって異なっていて、長い場合には9月の下旬まで花が咲いている場合もあります。
コンボルブルスの特徴
コンボルブルスの特徴としては品種によって様々なタイプのものがあるということで、基本的には日本でも多く自生しているヒルガオ科に属しているのですが、多年草や一年草、つる性のものなどバリエーションがかなり多いので、1つの種類として扱うのには多少無理があるので、
栽培をする場合にはそれぞれの品種によって育て方を変えなければなりません。花はアサガオの花を小さくしたような感じで、様々な品種が開発されていて、好みによって色を選ぶことができます。白や紫、青などの一色だけの花色の品種もあるのですが、
白と青のものや紫とピンクが混ざっているものなどもあるので、色を組み合わせて花壇などに寄せ植えをするととても美しくなります。また用途に応じてつる性の品種を使うこともできるので、フェンスの周辺で育てる場合にはつる性の品種を選ぶとフェンスを利用して栽培することができるので、
庭などを花で美しく飾り付けることができます。一株につく花の数が非常に多いのですが、それぞれが3日程度の寿命しかないので、次々に花がさかないと美しさを堪能することができません。日本人には馴染みのあるアサガオによく似た花なのですが、
五角形のものなどたくさんの品種が販売されているので、庭に植えるなどすると横方向に生長をしていくので、庭の広い地域を覆うことができます。鉢植えにする場合には鉢の大きさよりも広がって育つことが多いので、植え替えを行う必要があります。
ツル性の植物の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ダイコンドラ(ディコンドラ)の育て方
-

-
ソープワートの育て方
ソープワートは、ナデシコ科サポンソウ属で別名をシャボンソウやサボンソウで、学名はSaponaria officinali...
-

-
スナップエンドウの育て方
スナップエンドウは若くてみずみずしい食感を楽しませてくれる春の食材です。このスナップエンドウはグリーンピースとして知られ...
-

-
ユズ(実)の育て方
ユズの実の特徴として、成長して実をつけるまでの時間の長さが挙げられます。桃栗八年とはよく聞くことですが、ゆずは16年くら...
-

-
セイヨウタンポポの育て方
セイヨウタンポポは外国原産でそういうところから持ち込まれたタンポポであり、今では我が国を生息地として生えているタンポポで...
-

-
サルビア・レウカンサの育て方
サルビア・レウカンサの原産地はメキシコや中央アメリカです。別名を「メキシカンブッシュセージ」「アメジストセージ」といい、...
-

-
植物を元気いっぱいに育てるには
どれを選ぼうか迷うほど園芸店などにはたくさんの植物が並んでいます。好みの花色や珍しさで選ぶとうまく育たないこともあり、植...
-

-
サルピグロッシスの育て方
サルピグロッシスはナス科サルピグロッシス属(サルメンバナ属)の一年草または多年草です。その名前はギリシャ語のsalpin...
-

-
ハオルチアの育て方
ハオルチアはもともと南アフリカ地域の原産のユリ科の多肉植物で、水分が多くなると生育できないことが多いので日本で栽培をする...
-

-
ポリシャスの育て方
特徴としてはまずはウコギ科になります。その中のタイワンモミジ属になります。原産地、生息地においては2メートルから8メート...
-

-
ヒメシャガの育て方
ヒメシャガはアヤメ科アヤメ属の多年草でシャガよりも小型になります。シャガとよく似ており絶滅危惧植物に指定されている耐寒性...




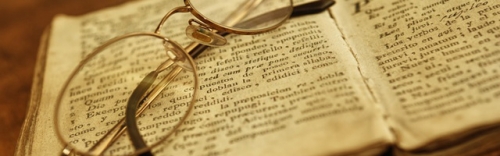





コンボルブルスは地中海の沿岸を中心とした地域で200種くらいが自生しているとされていて、品種によって一年草や多年草、低木と様々なタイプのものがあります。またつる性の植物の場合もあるので、日本においてはセイヨウヒルガオが帰化植物として扱われています。