キリンソウの育て方

主な原種や品種について
園芸ショップなどでも取り扱いされることが多くなってきていますが、主な種類としていくつか挙げられますのでご紹介していきたいと思います。エゾノキリンソウは、北海道やカムチャッカ半島、朝鮮半島北部、中国東北部などに分布しています。カムチャッカ半島とは、ユーラシア大陸北東部にある半島のことを言います。
比較的草丈が低くおよそ10センチメートルほどです。ホソバノキリンソウは、山地の草原に生息することが多く、主に中部地方やシベリアから極東ロシア、モンゴル、朝鮮半島などに分布しています。葉が細長く茎は間隔を置いて出てくるという特徴があります。ヒカリダケキリンソウは、テカリダケとも呼ばれています。
南アルプスの南部で栽培されています。日本国内では長野県、静岡県などが原産となっています。亜高山帯に生えることが多く高さは低めでいよそ10センチメートルほどとなります。また葉の部分が赤みを帯びてくるという特徴があります。
キリンソウの育て方
キリンソウの栽培方法ですが、種付けは2月下旬頃から3月下旬頃までにおこなわれます。種付けをおこなう際には、土に肥料を混ぜていく必要があります。肥料には土に活力を与えてくれるだけではなく腐植酸が肺配合されているため、元気な育て方としての重要なポイントとなります。種付け時の土に使用する肥料は粒状肥料として販売されています。
鉢植えなどで栽培する場合には、土が乾いてしまわないように水を十分に与えるように注意が必要です。花壇で栽培される場合や冬場などは、種付けをおこなう場合以外はお水は控えめにするようにしましょう。キリンソウの育て方として日当りのよい場所がおすすめされています。
栽培しやすい品種ですので必ずしも日当りがよくないと生育できないというわけではありません。日当りが悪過ぎるような場所は葉の色が悪くなってしまう可能性がありますが、半日陰の場所でも生育することができるとされています。品種によっては寒さにとても弱いものがありますので、育て方に注意しましょう。
挿し木で増やしていく場合は夏の初め頃におこなわれます。切り口部分を水につけておくようにしてください。2週間ほど経ってくると根が伸び始めてきます。4週間ほど経ったらポリポットへと植え替えていきましょう。このタイミングで株分けをおこないます。キリンソウを育てる場合には、病害虫に悩まされるということがほとんどありません。開花は5月上旬くらいからでキレイな黄色い花を咲かせます。
キリンソウの色々な利用方法
有効成分をすり潰して虫さされや切り傷などの患部に塗って使用することができます。すり潰す生葉は水洗いをしてから使用します。外用として用いられている他にも食用として利用されることがあります。食用として利用する場合には、塩茹でをしたり胡麻和えとして食べたりされています。
若芽を食べる場合には、よく茹でてアク抜きをしてから和え物や汁物の具材として使用されてください。アク抜きが十分におこなわれていない場合は、下痢などお腹の調子が悪くなってしまう可能性がありますので注意が必要です。その他にもカラシマヨネーズを付けて食べるのもおすすめされています。
古い時代には茹でた葉を日干しにして乾燥をさせることによって保存食にしていました。乾燥をさせたものを漢方として利用されていますが、これを一枝黄花と呼びます。この漢方は、風邪による頭痛や喉の痛み、利用作用や膀胱炎などに効果が期待されています。
緑化目的で使用されることがありますが、屋上に土の負荷がかかりますが断熱効果によって建物への熱による負荷を少なくする効果があります。ストレート屋根の場合には緑化をすることが難しいですが、屋上緑化は音を吸収して騒音を抑える効果も期待されています。その他にも壁面緑化、法面緑化などで常緑キリンソウが利用されています。
湿気や乾燥に強いこともあり、日本の風土に適した植物だと言われているのです。自然の雨水で生育することができますので、特別に水を撒くような装置を取付ける必要がありません。定期的に刈り込みをおこなうという手間がありませんので、ローメンテナンスの植物としても知られています。寒さに強いことから霜の厳しいような地域でも生育することが可能で、一年を通して緑の景観を保つことができます。
キリンソウの歴史
キリンソウとは、ベンケイソウ科に属している多年草のことです。生息地は、シベリア東部や中国、朝鮮半島などが挙げられます。タケシマキリンソウは、離島竹島が原産とされています。タケシマキリンソウは東京大学の植物分類学者によって、1917年に採集されました。形状や性状の変位が多く、直立性や匍匐性の系統などがあります。
そのため、複数の系統が存在しているのではないかと考えられています。また、一般的には休眠芽で冬越するところを秋に出芽したものが越冬するため冬でも緑があります。日本国内では、北海道や本州、四国、九州などの山地や海岸の乾いた岩場など日当りのよいところに生息しています。
一年中緑を保つことができるように改良された品種に常緑キリンソウがあります。日本国内で常緑キリンソウとして農林水産省で公式に認められているものは、トットリフジタ1号、2号で正規品取り扱い店舗から購入することができます。和名では、茎葉頂き部に黄色い小さな花が輪のように密集して咲くということから黄輪草と表記されています。
別名でキジンソウやキジグサと呼ばれることがありますが、これが転訛してキリンソウになったとも言われています。その他にも名前の由来として、中国の古書に登場している伝説上の動物の麒麟が関係しているという説もあります。中国の植物図鑑には中国名で費菜と記載されています。
キリンソウの特徴
花は茎の先端部分に5ミリメートルほどの鮮やかな黄色い小花です。下の方へいくに連れて枝分かれしているため、全体的な印象は円錐形です。星のような形をした小さな花は、10から30輪ほど水平についています。和名は黄輪草ですが、麒麟草とも呼ばれ俳句などでは夏の季語として用いられています。花はベンケイソウ科に属しているマンネングサに似ています。
この植物も盛んに枝分かれをして開花シーズンには黄色や白い花を咲かせます。茎の部分は太くて葉の部分は長楕円形で肉厚なのが特徴です。茎の高さはおよそ5から50センチメートルほど、葉長は2から7センチメートルほどになります。 花は茎の先端周辺で集まって小さな黄色い花を咲かせます。花弁は5枚で、蕚片も5枚で緑色をしています。
雄しべは10本、雌しべは5本となります。実の部分は熟してくると果皮が自然に裂けて種子を放出するという特徴を持っています。春から夏に黄色い花を付けていきます。ベンケイソウ科は、多肉質の葉や茎を持ち水分を貯蔵することができるという特徴があります。水の少ない乾燥した南アフリカなどの地域で多く生息しています。
省力型の緑化植物としても知られています。株型の大型タイプと匍匐型の小型タイプの系統を組み合わせることによって、高い緑比率を得ることができます。また単独で使用すると株の間に空間ができてしまうため雑草が生えやすくなってしまいますが、株型と匍匐型とを上手く組み合わせて使用することで、雑草が生えてしまうのを抑制する効果が期待されています。
多肉植物の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:セダムの育て方
タイトル:イカリソウの育て方
タイトル:金のなる木の育て方
-

-
カキの育て方
カキは日本の文化にも深く根ざした樹木で、たとえば正月になると干し柿を鏡餅に飾ること空も分かると思いますし、若にもたびたび...
-

-
キンバイソウの育て方
キンポウゲ科キンバイソウ属に属する多年草で、その土地にしか生えていない固有の種類です。過去どのような形で進化してきたのか...
-

-
ストケシアの育て方
この花は被子植物門、双子葉植物綱、キク亜目、キク目、キク科になります。タンポポ亜科になるのでタンポポに近い植物であること...
-

-
アーティチョークの育て方
アーティチョークの原産地や生息地は地中海沿岸部や北アフリカで、古代から栽培されているキク科のハーブです。紀元前から高級な...
-

-
マロウの育て方
マロウは、アオイ科のゼニアオイ属になります。マロウはヨーロッパが原産地だと言われています。生息地としては、南ヨーロッパが...
-

-
ソープワートの育て方
ソープワートは、ナデシコ科サポンソウ属で別名をシャボンソウやサボンソウで、学名はSaponaria officinali...
-

-
フッキソウの育て方
フッキソウは日本原産のツゲ科の植物です。北海道から九州まで日本のどこでも見つけることができます。フッキソウは半低木で、そ...
-

-
ブルビネラの育て方
ブルビネラは南アフリカやニュージーランドを原産とする花であり、日本で見ることが出来るようになってきたのはごく最近のことで...
-

-
アデニウムの育て方
アデニウム/学名・Adenium/キョウチクトウ科・アデニウム属です。アデニウムは、南アフリカや南西アフリカなど赤道付近...
-

-
クレソン(オランダガラシ)の育て方
クレソンは、日本では和蘭芥子(オランダガラシ)や西洋ぜりと呼ばれています。英語ではウォータークレスといいます。水中または...




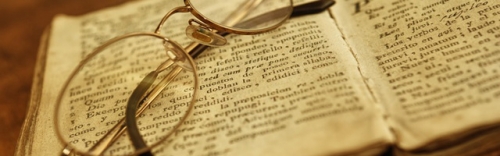




キリンソウとは、ベンケイソウ科に属している多年草のことです。生息地は、シベリア東部や中国、朝鮮半島などが挙げられます。タケシマキリンソウは、離島竹島が原産とされています。タケシマキリンソウは東京大学の植物分類学者によって、1917年に採集されました。形状や性状の変位が多く、直立性や匍匐性の系統などがあります。