西洋オダマキの育て方

育てる環境について
西洋オダマキの栽培に適しているのは10度から20度になり、もともとは涼しい高地に生息していた植物なので、高温多湿に弱い性質があります。日陰で育てることもできますが、なるべく明るい場所で栽培するようにしてください。育て方としては葉やけを防ぐため、
夏場は直射日光に当てないように半日陰で管理するようにします。その他の時期には午前中は日の光に当てておき、午後からは明るい日陰で管理するようにして、西日に当たらないように注意します。庭に植える際には西側に木や建物などがあり、夕方から木陰になるような場所が適しています。
冬は冷たい風が当たらない場所に置き、表面の草は枯れてしまいますが、根を守るため気温が低くなる頃には藁やバークチップなどを敷いて霜よけの対策を施します。ただし冬場に暖かい場所で管理してしまうと、花芽分化が起こらなくなってしまうことがあるので、10度以下になる場所で管理します。
花が終わった後は種を採取します。種の採取は7月頃になりますが、西洋オダマキの種まきは翌年の2月以降になるので、採取した種は冷蔵庫で保管するようにしてください。種を採取する必要がない場合には、咲き終わった花がらは、
こまめに摘み取るようにするとたくさん花が咲くようになります。花が終わった時には、花が付いている下の部分を茎ごと切り取ります。そして株の花がすべて咲き終わったら、株元の葉を残して短く切りとっておき、涼しい場所に置いて管理します。
種付けや水やり、肥料について
西洋オダマキは、前年に採取した種を2月から3月頃にまきます。種はとても小さいのでバラまきして薄く覆土しておきます。発芽に最適な15度から20度になり、種をまいてから発芽までは大体1ヶ月くらいかかります。本葉が2枚から3枚になったら鉢上げをします。
温度は用土は水はけの良い赤玉土、腐葉土などを配合したもの、または市販の草花の土、山野草用の土を利用します。庭に植える際には20cm程度盛り土をしたところに植えるようにして、弱酸性の土を好むので苦土石灰を混ぜ込んで中和しておきます。
水やりは鉢植えの場合は表面の土が乾いてきたら与えるようにして、夏場の乾燥しやすい時期には朝と夕1日2回、鉢の中の水分温度が上昇しないように涼しい時間帯に水やりを行います。秋に近づき気温が落ち着いてきたら水やりの回数を徐々に減らしていきます。
庭植えの場合はそれほど頻繁に行う必要はありませんが、乾燥していたり天候が良く雨がなかなか降らなかった時に水やりを行います。肥料は生育が活発になる3月から9月の間は2000倍程度に薄めた液体肥料を週1回の割合で与えるようにします。株が弱りやすい夏場はさらに薄めたものを与えます。
また植え替えの時期にリン酸とカリウム分が多く配合された緩効性の肥料を与えるようにします。西洋オダマキは太い根が生えていて、根を傷つけてしまうと生育不良や枯れてしまう原因になるので、植え替える際にはこの根を傷つけないように十分注意してください。
増やし方や害虫について
西洋オダマキは種で増やす方法と株分けする方法があります。株分けを行う際には、芽が生長する3月前に行うようにしましょう。根を見て自然に分かれている部分をナイフなどで切り分けした後、切った部分に殺菌剤を塗っておきます。
ただ、西洋オダマキは株分けしても芽が出てこないことがあるため、確実に増やしたいときには種から苗を育てる方法が一般的になります。西洋オダマキによく付く害虫には、ヨトウムシ、アブラムシ、ハダニなどがあります。ヨトウムシは夜行性で、昼間は株元や土などに隠れているのですが、
夜になると出てきて葉を食害します。アブラムシやハダニは大量に発生するので見た目も悪く、植物の汁を吸ってしまうため葉が変形したり変色したりします。害虫は見つけた時に駆除するか、薬剤を散布して対策を施します。病気ではうどんこ病や灰かび病にかかる心配があり、
共にカビが原因の病気で、春先から梅雨にかけて、または気温が低くなりはじめる秋口から冬にかけて多く発生します。うどんこ病が発生すると葉などに粉をまぶしたような状態になり、灰かび病になると花や葉に斑点ができて次第に腐り、
やがてカビに覆われていきます。温度が低く湿度が高い環境で多く発生するため、植物同士の風通しを良くする、枯れた部分や終わった花がらはこまめに摘み取るなどの対策が必要になります。被害が表れた部分は切り取って除去するようになりますが、範囲が広い場合には薬剤を散布して対処するようになります。
西洋オダマキの歴史
西洋オダマキはキンポウゲ科オダマキ属の多年草です。生息地はヨーロッパ、北アメリカ、アジアなどの広範囲に広がっています。オダマキ属にはたくさんの種類があり、西洋オダマキは主にヨーロッパが原産となっているアクイレギア・ブルガリスと北アメリカ原産の
アクイレギア・カエルレア、アクイレギア・クリサンタなどその他の種類を掛け合わせてできた園芸用品種になり、交配しやすい品種であるためさまざまな色や形が存在します。同じオダマキ属で日本に自生しているものに、ミヤマオダマキとヤマオダマキがあり山間部などに生息していますが、
ミヤマオダマキは一部の地域では個体数が少なくなってきたため、絶滅危惧種に指定されています。名前のオダマキとは、麻などの糸を中心が空洞になるように巻いた物のことで、中心にある花びらの状態が似ていたことが由来となっています。オダマキには
「糸繰草」(いとくりそう)という別名があり、属名の「Aquilegia」アクイレギアはラテン語で鷲という意味を持つ「Aquila」からきていて、尖った距の部分が鷲の口ばしに見立てたことが由来となっています。
植物の中には毒となる成分を持っているものがありますが、オダマキ属もその中に該当しています。オダマキ属にはプロトアネモニンという成分があり、液が皮膚に付いてしまうと炎症を起こして水泡ができたり、誤って食べてしまった時には胃腸炎や心臓麻痺が起こる場合があります。
西洋オダマキの特徴
西洋オダマキの花は、中心に端がカーブして筒のようになっている「距」という5枚の花弁があり、その外側に先端が尖って星のように見える五枚の花弁があります。実はこの外側の部分も花のように見えますが花弁ではなく、花を支える役割を持つ「がく」になります。
この距の形が西洋オダマキの特徴となっていますが、種類によっては距のないものもあります。草丈は30cmから70cmほどになり、葉の色は単色の緑です。花の大きさは4cmから6cmほどで花の中央には複数の雄しべと先端に小さな5本の雌しべがあって、開花時期は4月から6月になります。
さまざまな品種の交配によって改良されてきたため種類はとても豊富にあり、白、黄色、赤、ピンク、オレンジ、紫などたくさんの花色が選べて、花の形もシンプルな一重のものから八重咲き、大輪のものなどバラエティーに富んでいます。
多年草なので毎年花を咲かせてこぼれ種でも増えるのですが、西洋オダマキの株はおよそ3年から4年ほどで寿命がきて立ち枯れを起すこともあるので、できれば新しく苗を植えて更新していくようにします。西洋オダマキは交配しやすいという特徴があるため、
近くに種類の異なる品種を植えておくと色や形が混ざり合って、翌年は原型と異なるさまざまな色や形の西洋オダマキが育ってしまうことがあります。特にこだわりがない場合は問題ないのですが、もともとの色や形をそのまま保って育てたい場合は、近くに別の種類の西洋オダマキを植えないようにしてください。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:セツブンソウの育て方
タイトル:イチリンソウの育て方
-

-
アセロラの育て方
アセロラの原産国は西インド諸島や中央アメリカなど温かい熱帯気候の地域です。別名「西インドチェリー」とも呼ばれています。そ...
-

-
プリムラ・オブコニカの育て方
プリムラ・オブコニカはサクラソウ科サクラソウ属に分類される植物で、和名は常磐桜と呼ばれています。中国西部が原産の多年草に...
-

-
ルエリアの育て方
ルエリアはルエリア属キツネノマゴ科の多年草で生息地はアメリカ、アジア、南アフリカの熱帯地域などです。その名前は、フランス...
-

-
シモバシラの育て方
学名はKeiskeaJaponicaであり、シソ科シモバシラ属に分類される宿根草がシモバシラと呼ばれる山野草であり、別名...
-

-
イースターカクタスの育て方
ブラジル原産の多肉性植物で、4月初旬の頃のイースター(春分後の最初の満月の後の日曜日)に開花するカクタス(サボテン科)で...
-

-
西洋クモマソウの育て方
原産地はヨーロッパ北部といわれています。漢字で書くと雲間草で、ユキノシタ科の植物です。雲に届きそうな高い山間部に生息する...
-

-
ホタルブクロの育て方
ホタルブクロの特徴として、まずはキキョウ目、キキョウ科であることです。花の色としては真っ白のものがよく知られていますが、...
-

-
セントーレアの育て方
セントーレアの歴史は、古くやギリシャ時代にまでさかのぼります。今現在、一般的に使われているセントーレアという属名は、ギリ...
-

-
フラグミペディウムの育て方
フラグミペディウムは常緑性のランの仲間であり、メキシコからペルーやブラジルなどを原産としており、これらの生息地には15種...
-

-
ドラゴンフルーツの育て方
サンカクサボテンの実の事を総称してピタヤと呼びます。ピタヤはベトナムから輸出する時の商品名であり、日本に輸入される時には...




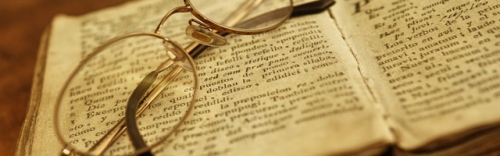




西洋オダマキはキンポウゲ科オダマキ属の多年草です。生息地はヨーロッパ、北アメリカ、アジアなどの広範囲に広がっています。オダマキ属にはたくさんの種類があります。