アスクレピアスの育て方

育てる環境について
育て方に基づいた、育てる環境としては、水はけがなるべく良く、尚且つ栄養(肥沃)な土を、この花は望みます。そして尚且つ腐葉土が多くあると更によく、通常の土と半々か、おおよそ通常の土や赤玉土が6で、腐葉土が4の割合のレベルで花壇を整えるといいです。
そしてアスクレピアスは日当たりの良い場所でないと育ちにくい特徴もあります。そして暑さにもそれなりに強く、広めの花壇などの真ん中に種を撒いて、周辺環境の住宅や塀などで陽射しを遮る日陰などが覆い被さったりしない様にしていくのも必要になります。
これはクラサヴィカ種とツベロサ種はほぼ同じで、ツベロサ種は寒さに強いのにクラサヴィカ種と然程変わらないぐらいの耐暑性を種として保有しているので、種蒔きさえ間違えなければ比較的気にせずに、陽射しの当たりさえよければ順調に育てていく事が可能となります。
ただ、病害虫においては日本ではアブラムシなどがクラサヴィカ種などでは種蒔きの時期が春頃なのもあって、頭を悩ませる要因となりやすくなります。その為、防虫剤を散布するか、防虫剤を散布したくないならば唐辛子や牛乳やお酢、そして水とで割って混ぜた虫が嫌う臭さとなる液体を、
土にこまめに定期的に染み込ませていく事で、常日頃からアブラムシなどが近寄りたくない環境を形成していく事が大切となります。放置していると蕾などにアブラムシは繁殖しやすく、タネも残せずに枯れてしまう場合もあるので注意が必要です。
種付けや水やり、肥料について
ツベロサ種はおおよそ9月から10月、そしてクラサヴィカ種はおおよそ3月から4月に種蒔きをするのが良いと前述にて記載しましたが、これは一度花壇に植えて育てたアスクレピアスの花から出てきた種などの場合ですと、なるべくはその種を残そうとする花の本能に沿って、種を放置するのも1つの手とされています。
クラサヴィカ種の場合ですと、水やりは春から夏までの合間のスパンがある為、その分水気が乾きやすい傾向がある為、土が潤うぐらいの水やりをしてあげるとクラサヴィカ種は喜びます。対してツベロサ種の場合ですと、秋から冬以降にかけてですので土は朝霧や結露などで水気を含んでいやすいので、
程ほどな水やりをしてあげるのが良いと言えます。そして肥料を与える場合においては、家庭菜園用の液体肥料などを10日から15日ぐらいのスパンで与えていくのが良いです。液体肥料などを使いたくない場合などにおいては、何かしらの魚を出汁にした煮汁などを冷やした後に与えてあげたり、
または冷蔵庫の中で忘れてしまっていて、しぼみすぎて使えなくなったトマトなどを鍋に水を入れて一緒に煮込んで溶かし、それを冷やしてアスクレピアスの茎や花や葉っぱを傷つけない様に撒いてあげるのが良いです。これは自然由来の古くからある肥料の与え方の1つであり、生ゴミなどでは土が栄養の消化に時間がかかったり、生ゴミに虫が繁殖したりするのを防ぐ水分主体の栄養の与え方になります。
増やし方や害虫について
アスクレピアスの増やし方は、冠毛の習性をなるべく利用する必要があります。アスクレピアスは冠毛により、次世代の命の種を大地へと落とす場合は、あまり遠くへは飛ばさず根元周辺の大地に種を産み落とす傾向があります。その為、アスクレピアスの種蒔きをしてから複数の芽が近く合わせの形で出始めた場合には、
なるべく早めに植え付けの替えをするか、株分けを行っていき、別途の土に冠毛の纏わり付いた種が産み落とされる様にする必要性があります。もし、こうしなければ次世代の種が一箇所に集まりすぎて、逆に芽が出にくくなり、性質が悪い形になると芽が絡まってしまうケースもあります。
害虫はアブラムシなどにかかりやすいと前述しましたが、それ以外にもアスクレピアスのクラサヴィカ種においては夏頃に虫が非常に活発になる事からも、アブラムシ以外の夏の害虫などにも気をつける必要があります。前述にて防虫剤が嫌ならば、
唐辛子や牛乳やお酢に水を混ぜた物を使う手段について記載しましたが、これがあまり効果の無いケースとなるのがゴキブリなどの生命力が強く、臭いもあまり気にしない害虫の類になり、もし土に魚の骨などの生ゴミを撒いていて土の栄養としている場合などですと、
ゴキブリが土の上を歩く場合や蟻の繁殖が凄い事になる場合もあり、それが原因でアスクレピアスの種が傷つけられる、または食べられてしまうという場合もあり、クラサヴィカ種においては防虫剤を用いるのも苦渋と言えど選択する必要の場合もあります。
アスクレピアスの歴史
アスクレピアスという花は、その色合いが赤とオレンジの色合いが綺麗に混ざり合い、その為に太陽などと引き合いに出される事もある、ヒマワリとある種の意味で似た花です。この花はどこが生息地、もとい原産地なのかと言うと、原産地は北アメリカとアフリカにあり、
いわく暖かいや熱いと言われる様な土地と、カナダ圏などの寒い土地などで生息している花でもあります。その為、その歴史は片や太陽との引き合いに出され、片や雪との引き合いに出される花でもあります。この花は日本ではトウワタという名前の方が知られていると言えます。
これは和名です。日本では1842年、天保13年の年にトウワタが渡来したと言われています。アスクレピアスの名前の由来は定かとは言われていません。ギリシャ神話に出てくる医学の神のアスクレーピオスなどの名前が由来の説や、紀元前ローマの医師のアスクレピアデスなどの名前が由来とする説などの、
多数ある説が存在している名前由来に関しては不確かな特徴的な歴史のある花でもあります。アスクレピアスにはクラサヴィカ種とツベロサ種というのがメジャーに栽培されている花であり、クラサヴィカ種は寒さに弱く、ツベロサ種は寒さに強く、それぞれの環境の違う土地で、
命を育んで紡いできた歴史のルーツの違いのある、近親ながら枝分かれした歴史のある花です。日本に渡来してきたのがどちらなのかも定かとは言われておらず、現時点ではまた違う種のアスクレピアスが渡来してきた可能性も説として存在します。
アスクレピアスの特徴
アスクレピアスの特徴は、太陽になぞらえられる様な、赤色やオレンジ色で映えた綺麗な色合いがまず1つです。そして、この花は、クラサヴィカ種の場合だとアフリカなどが原産地であり、暑かったり暖かい土地で生息する種の為、、日本での開花時期で言えば6月から9月と、夏真っ盛りの時期に花を咲かせる特徴があります。
ただ、ツベロサ種も似た開花時期であり、花の枯れる時期に違いがあるという感じです。クラサヴィカ種は5度辺りになると直ぐに枯れてしまい、対してツベロサ種の場合だとマイナス10度を越えても枯れずにいる違いがあるという訳です。夏ごろに種を大地へと産み落とし、
次の命へと繋げる生命活動をしているのも、この花の特徴の1つです。形での特徴を言えば、アスクレピアスは高さが数十センチから、高い物で1メートルに達するぐらいの背丈となり、長い茎を持つのが特徴です。この部分もある意味で太陽になぞらえられるヒマワリなどの花と似ていると言えます。花の形はバトミントンの羽の先のゴム部分が破裂したかの様な形をしており、
その破裂している様な部分から種を落とします。そして種を落とす時は冠毛という白い糸が種にくっついて同時に吐き出されます。これはタンポポなどの種を運ぶ胞子と類する部分があり、和名のトウワタのワタの部分の「綿」という漢字になるのは、この部分が由来していると言われています。和名を漢字で正しく記載すると「唐綿」となります。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:アストランティアの育て方
-

-
ロシアンセージの育て方
ロシアンセージはハーブの一種です。名前からするとロシア原産のセージと勘違いされる人も多いですが、それは間違いです。原産地...
-

-
アグラオネマ(Agleonema)の育て方
アグラオネマはアジア原産の熱帯雨林が生息地のサトイモ科の多年草です。インドから東南アジア、中国南部にかけて約50種類が生...
-

-
シャコバサボテンの育て方
現在観葉植物として流通しているシャコバサボテンはブラジルのリオデジャネイロを原産地とする観葉植物であり、標高1000~1...
-

-
ウメモドキの育て方
ウメモドキは、日本の本州、四国、九州、そして中国原産の落葉低木です。モチノキ科モチノキ属に分類され、生息地は暖帯の山間部...
-

-
リビングストーンデージーの育て方
リビングストーンデージーは秋に植えれば春頃に花が咲きます。しかし霜には弱いのでなるべく暖かい場所に移動させるか、春に植え...
-

-
シネラリアの育て方
シネラリアはキク科の植物で、早春から春にかけての代表的な鉢花のひとつです。原産地は北アフリカの大西洋沖に浮かぶスペイン領...
-

-
エンレイソウの育て方
エンレイソウは、ユリ科のエンレイソウ属に属する多年草です。タチアオイとも呼ばれています。またエンレイソウと呼ぶ時には、エ...
-

-
エンコリリウムの育て方
パイナップル科に属しており日頃よく口にするパイナップルの原種から派生したとも考えられています。乾燥地に生息していた事もあ...
-

-
ピーマンの栽培方法
ピーマンは夏を代表する野菜となっています。小さな子供は苦手と言うことが多くなっていますが、その苦みがうまみを増やすという...
-

-
さつまいもの育て方
さつまいもは原産が中南米、特に南アメリカ大陸やペルーの熱帯地方と言われます。1955年にさつまいもの祖先に該当するイポメ...




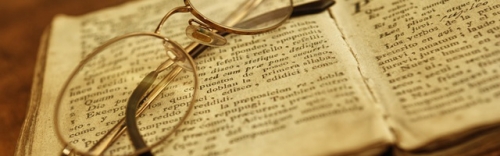





アスクレピアスという花は、その色合いが赤とオレンジの色合いが綺麗に混ざり合い、その為に太陽などと引き合いに出される事もある、ヒマワリとある種の意味で似た花です。