ポーチュラカの育て方

ポーチュラカの育て方
育て方はとても簡単で、園芸初心者にも向いています。カラフルな花が次々に飽きることなく咲いてくる様子は、真夏の暑い時期の園芸を賑やかに盛り上げてくれます。乾燥に強いのでうっかり水やりを忘れてしまった、という場合でもそれほど心配することがありません。
暑さに強いため、他の植物では日当たりが強すぎる場所などに植えるなど植え場所に工夫するといいでしょう。ポーチュラカは花壇植えの他、プランターや鉢植えでも栽培が楽しめます。日が当たらない場所では花を咲かせることができないため一日中日当たりが良い場所が好ましいですが、鉢で育てる場合には時間によって日当たりの良い場所に移動させるなど工夫しましょう。
ポーチュラカの葉は通常つやのある緑色の葉をしていますが、種類によっては斑入りの模様を楽しめる品種のポーチュラカもあります。葉だけを楽しむカラープランツとしても魅力的です。葉のふちの部分が白~紫や赤に変化する葉は美しく見ごたえがあります。葉の色を楽しむタイプの斑入りポーチュラカの場合でも日光は必要です。
一日中効率よく日の当たる場所が確保できない場合でも、日当たりのよい場所を見つけて日光浴させてあげることで丈夫に育ちます。1鉢だけでも充分に魅力的ですが、寄せ植えにすることでポーチュラカの魅力をより楽しむことができます。寄せ植えにする場合は同じ暑さに強い植物と相性がよく、育てやすいです。
同じ鉢の中に相反する性質の植物をいれないようにすれば、うまく育ちます。へら状の形の葉を持つため、針状の形の葉やこんもりと丸くなる種類の多肉植物等と合わせると互いの魅力をより引き出しあうことができます。用土は水はけと肥料持ちに適したものを好みますが、水はけが良ければとくに心配することはありません。赤玉土に腐葉土を混ぜ込み、排水性を高めるためにパーライトを混ぜてもいいでしょう。
市販の草花用培養土でも育てることが可能です。肥料は緩効性肥料をきらさないようにしようしましょう。次々に花が咲く植物なだけに、肥料の消費は早くなります。また、雨などが多いとそれだけ肥料も雨水と一緒に流出してしまうことがあります。梅雨時期にも盛んに育ちます。肥料切れになると花付きが悪くなる場合があるため注意しましょう。庭植えの場合には肥料は必要ありません。
栽培中の管理で注意したいこと
とても丈夫で暑さにも強いので夏の時期には重宝する植物ですが、栽培中に注意したい点がいくつかあります。ポーチュラカの分厚い葉は水分を充分に蓄えておくことができます。水のやりすぎが根腐れを招いてしまうことがあるため、真夏にいくら暑いからといっても与え過ぎは禁物です。
暑い時期は土の表面がかさかさに乾いてから、たっぷり水を与えるようにしましょう。
低温時は水切れするまで放置すると立ち枯れを招いてしまいますので、水をあげすぎない方がいいといっても土の乾き具合に気を配ることが上手な育て方のコツです。庭植えの場合には水やりをしなくてよいですが、プランターや鉢植えの場合は水が底面からしたたるくらいたっぷりと与えます。
日当たりと水はけのよい場所であれば非常に成長旺盛なため、成長しすぎて邪魔になってしまうことがあります。伸びすぎたら適度に剪定してしまいましょう。成長が盛んな暑い時期に、月に一度程度切り戻しをするとわき芽が増えてたくさんの花を咲かせることができます。より多くの花を咲かせたいときには切り戻しが欠かせません。
どんな植物の育て方にも通じることですが、徒長しきった姿はどこかだらっとした印象を与えがちです。暑い時期に根元から半分程度の長さまで思い切って切ると、よく広がって花をつけます。病虫害としては栽培中にアブラムシがつくことがあります。虫がついてから慌てないように、アブラムシ対策にあらかじめ専用の駆除剤を用土に混ぜ込んでおくと安心です。
ポーチュラカの増やし方
低温では発芽しないため、充分に温かくなってから種付けをしましょう。種付けに適した時期は5月頃です。種付けするためには種を採取する必要がありますが、越冬に成功できれば前年にこぼれた種が自然に増えることもあります。種付けのほかにも挿し木をすることができ、簡単に増やせます。
発根するまで水をいれたグラスなどに入れておいて、それから土に植えても構いませんし用土に直接さしてもそこで根をおろすことが可能です。挿し木するには成長旺盛な6月~9月の高温の時期に行います。高温の時期であればあるほど根付きやすくなります。まだ時々肌寒いかな?と、いう時期よりも暑さを感じる季節の方が発根しやすいです。
初めて育てる、あるいは簡単に育てたいという場合には種から育てるよりも園芸店で苗を購入することをおすすめします。5月頃から園芸店で苗の取り扱いが始まります。開花時期が長いため、苗や鉢でも充分に花を楽しむことができます。気温が低いうちはあまり花が咲かず、それほど成長もしません。充分に温かくなってから苗や鉢を購入する方が育てやすいでしょう。
ポーチュラカの歴史
ポーチュラカの原産地はメキシコや南アメリカといわれています。日本には1980年代にドイツから入ってきたとされています。高温で強い日光があたる場所を生息地としており、高温多湿の日本の夏に向いている植物です。ポーチュラカはスビリヒユ科の非耐寒性多年草で、別名をハナスベリヒユといいます。
スベリヒユとマツバボタンがかけあわさって変異した種ではないかといわれています。スベリヒユは雑草として有名ですが、ポーチュラカはカラフルな花色が美しく這うように伸びることから、花壇などのグラウンドカバーとして使用している人が多いです。雑草との違いは、美しくつやのあるカラフルな花をたくさん咲かせてくれるところです。
花は日照不足だと咲きにくくなり、曇りの日や雨の日は咲かないこともあります。冬の寒さに弱いため、寒風にあててしまうと越冬が難しく一年草として扱われることもあり、厚みのある葉にしっかりと水分をたくわえることができるため暑さと乾燥に強い夏向けの植物といえます。
マツバボタンとよく似た姿をしていますが、見分け方としては松葉ボタンは葉が棒のような形になることに対して、ポーチュラカはへらのような形になるため、葉を見て見分けるといいでしょう。ポーチュラカは1990年の大阪花博でその存在を広く認知され、園芸店等で幅広く取り扱うようになったといわれています。
ポーチュラカの特徴
花色は多彩で、白、赤、オレンジ、黄色、ピンク、紫などがあり、絞り状に2色が咲く品種もあります。一重咲きと八重咲きがありますが、一般的に広くみられるのは一重咲きの方です。花色が豊富なため、夏の花壇やプランターに彩りが欲しいとき利用するといいでしょう。
地面を這うように伸びるため、草丈は10cm~20cmとそれほど高くなりません。適度な乾燥を好むため、水を与え過ぎると徒長して間延びしてしまうことがあり、環境によっては30cm~40cmまで伸びてしまう場合もあります。初夏から秋にかけての気温が高い時期に盛んに花をつけ、花壇植えにすればまるで花畑のような景観を楽しむことができます。
花壇で楽しみたい場合は水はけと日当たりの良い場所を選びましょう。天気の良い日以外は花は咲かず朝咲いた花は午後になると閉じてしまいますが、天気の良い日はほとんど毎日次々に花が開いてきます。近年になって夕方まで咲き続けることのできる種類が出回るようになりました。
花を育てることに興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:イレシネの育て方
タイトル:ストロベリーキャンドルの育て方
タイトル:ノゲイトウの育て方
-

-
ノウゼンカズラの育て方
ノウゼンカズラの歴史は古く、中国の中・南部が原産の生息地です。日本に入ってきたのは平安時代で、この頃には薬用植物として使...
-

-
サルビア・レウカンサの育て方
サルビア・レウカンサの原産地はメキシコや中央アメリカです。別名を「メキシカンブッシュセージ」「アメジストセージ」といい、...
-

-
クチナシの育て方
クチナシの原産地は日本、中国、台湾、インドシナ、ヒマラヤとされており、暖地の山中に自生し、広く分布しています。主な生息地...
-

-
キャットテールの育て方
キャットテールは別名をアカリファといい、主にインドが原産地で、熱帯や亜熱帯地方を生息地としている植物でおよそ300種類か...
-

-
イキシアの育て方
イキシアはアヤメ科の植物で、原産地は南アフリカになります。また、別名として「ヤリズイセン(槍水仙)」、「コーン・リリー」...
-

-
セキショウの育て方
元々はサトイモ科に属していました。しかし実際の姿とサトイモの姿とを想像してみても分かる様に、全くサトイモとは性質が違いま...
-

-
ゴーヤーの育て方について
一昔前までは、ゴーヤーと聞いても何のことだかサッパリわからないという人が大半でしたが、ここ10年位の間に全国的な知名度が...
-

-
ブルーキャッツアイの育て方
ブラジル原産の多年草である”ブルーキャッツアイ”。日本では観賞植物として栽培されています。別名はオタカンサスと呼ばれる花...
-

-
イワコマギクの育て方
イワコマギクは和名としてだけではなく、原産地となる地中海海岸地方においてはアナキクルスとしての洋名を持つ外来植物であり、...
-

-
ケラトスティグマの育て方
中国西部を原産としているケラトスティグマは明治時代に日本に渡ってきたとされています。ケラトスティグマの科名は、イソマツ科...




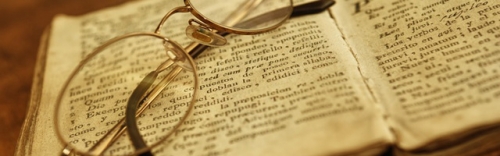





ポーチュラカの原産地はメキシコや南アメリカといわれています。日本には1980年代にドイツから入ってきたとされています。高温で強い日光があたる場所を生息地としており、高温多湿の日本の夏に向いている植物です。ポーチュラカはスビリヒユ科の非耐寒性多年草で、別名をハナスベリヒユといいます。