パンジーの育て方

パンジーの種付け
パンジーを種から育てる場合、3cmくらいのプラスチックトレーに種を蒔きます。種まき用の用土を用意し、トレーいっぱいに入れます。パンジーの種付けの場合、種の上に1ミリほど土をかぶせればOKなので、土を入れた後、軽く指の腹で押し込むだけでも大丈夫です。基本的には一つの区画に対し、一つの種を蒔きます。
種付けした後、初めは半日陰に置き、徐々に日光に慣らしていくようにします。次に苗から育てる場合、苗を購入する時期は秋から春頃にかけて購入します。この時、葉の色が濃く、元気な苗を選ぶようにしましょう。
最適とされているのは10月頃で、理由は寒くなる前に十分に土に根を張らせることで、暖かくなった頃からの生育がよく、花を楽しむ期間も長期間期待できます。土は草花用の用土を使用しますが、小粒の赤玉土と腐葉土を混ぜ合わせたものでも育てることができます。
パンジーの育て方
品種改良の末、たくさんの種類ができたパンジーですが、育て方は品種に左右されることなく、ほとんど変わりません。種付けが終わり、発芽が揃ってきた段階で半日陰の場所へ移します。日陰に置いたままにして置くと、間延びしてしまし、逆に突然炎天下の直射日光に当ててしまうと、枯れてしまう原因になります。
水やリは土の表面が乾いてからたっぷりと与えますが、過湿は避けるようにします。他の花とパンジーの育て方の違いは、水やりの量です。ほとんどの花は冬の間成長が止まってしまいますが、パンジーは冬の間も花を咲かせ続けるので、他の植物と同じような間隔で水をあげると、水分が不足してしまうこともあります。
日光を好むので、日の光を当てることで成長も早く、花もたくさんつけます。夜間の冷え込みが厳しい冬場は土が凍ってしまうので、その場合は午前中のうちに済ませておきます。花が咲いている期間が非常に長いパンジーなので、植え付けの前はもちろん、発芽した後も3月頃までは10日に一回くらいの頻度で液体肥料を与えるようにします。
冬の間は液体以外の肥料は与えないようにしましょう。種まきから2ヶ月が過ぎる頃になると、花jを咲かせるものも出てきます。この頃から定植を始めるとよいでしょう。苗を植えるときには根を軽くほぐしてから植えます。プランターに植える場合は60センチのもので、5本~10本、鉢植えの場合は直径12センチの鉢に対し1本、花壇に植える場合は、間を約20センチくらい空けるようにします。
その後花が枯れてくると実がなりますが、実ができる事で栄養が多く実に逃げてしまうので、こまめにチェックし、枯れた花を摘むようにします。この時、枯れた花びらの部分だけを摘むのではなく、軽く花茎を引っ張るようにし、付け根から摘むようにします。
栽培する上での豆知識
育て方も簡単で初心者向きのパンジーですが、栽培のコツがあります。まず、苗を購入した時に根がぐるっとまわってしまっていた場合、下半分の土を指でほぐしてから植えます。その他にも蕾や花が付いてしまっていた場合は摘み取り、少しでも早く根を張れるようにします。
栽培していて、成長が遅いなと感じた時には、以下の何点かを確認します。まず肥料を与えすぎていないかを確認します。パンジーの根はとても繊細なので、肥料jをあげ過ぎることで、上手く栄養素を吸い上げる事ができなくなっている場合があります。次に、水のあげすぎも原因として考えられます。
それでも解決しない場合は病害虫にかかっていないかを確かめましょう。発生する確立が高く、暖かい時期に特に若い芽につきやすいのがアブラムシです。アブラムシが発生した場合はウイルス病も持ち合わせていることがほとんどなので、アブラムシを退治する事はウイルス病を予防する事にも通じています。
ウイルス病にかかりひどくなってしまうまでほっといてしまうと元気がなくなるだけでなく、生育も止まってしまう事もあります。気温が高くなってくるとアブラムシが発生しやすいので、気温が上がる前の2月頃には株元に市販されている粒状の殺虫剤を散布します。その後は栽培しながらアブラムシの状況jを見て散布するようにしてください。
この他にもダニが発生する場合もあります。ダニは乾燥時期に葉の裏に発生します。葉の表面に黄色の小斑点が出たら要注意です。特攻薬は殺ダニ剤ですが、続けて使っていると耐性がついてしまうので、他の薬剤も用意し、交互に使用するようにしましょう。
水のやりすぎや肥料の与えすぎ、排水の悪い場所で栽培すると立ち枯病も発生します。春は特に注意が必要で気温の上昇、多湿になる事により白いフェルト状の斑点が発生するうどんこ病にも気をつけましょう。
うどんこ病にかからないようにするには、事前に市販の殺菌剤を散布したり枯葉や花がらなどを早めに摘み取ることで風通しをよくしておきましょう。かかってしまった場合には硫黄を含んだ薬剤を使用します。それでも解決しない場合は早めに処分します、処分する事で元凶であるアブラムシを完全に防除する事ができます。
パンジーの歴史
パンジーの原産はヨーロッパで、生息地は世界世界各国に広がっています。パンジーは交雑によって作られた植物です。その初めはイギリスの園芸家により1813年ごろビオラ・トリコロルを元に掛け合わせてものが始まりとされています。他にもビオラ・ルテア、ビオラ・アルタイヤ、ビオラ・カルカラータなどが挙げられます。
19世紀末頃になるとオランダ・ドイツ・フランスでも改良がされる様になり、20世紀に入る頃にはアメリカやスイスが品種改良をリードするようになり、大輪で花の色もカラフルなものになってきました。そして20世紀後半、大輪種が大量に作られました。その後、時間の流れからか大輪のものは求められなくなり、現在では小・中輪で、花をたくさん咲かせるものが主流となっています。
日本には江戸時代末に入ってきましたが、戦後から、一般に普及し、栽培されるようになりました。種苗会社が本格的に育種を開始したのは昭和40年代に入ってからで、現在では日本がパンジーの改良をリードしています。
パンジーの特徴
パンジーの花は晩秋から次の年の初夏まで咲き続ける事がら、花期が非常に長い事でも知られています。花の特徴は根から伸びている5枚の花びらの花をひとつつけます。花柱の頭の部分は球状に膨らみ額片の付属体は台形に膨らみます。
花の種類は品種改良の豊富さが影響し、幾つかの系統に分けられますが、特殊系といわれるものはその中でも更に数種類あり、春に咲くものが多く、花弁が緑で、フリンジしたシャロン。秋から開花し、フリンジが緩やかなカンカン、強いフリンジが特徴で色幅も楽しめるオルキブルーシェード、そして花の色が黒い、スプリングタイムブラック、オレンジの花に紫色の覆輪の入ったジョリージョーカーなどがあります。
花の大きさの特徴でも分けられていて、花の直径が4~5センチ程度の小輪系と呼ばれるものはビオラの多花性、開花期間の長さとパンジーの豊富な色、優れた性質を兼ね合わせたものです。次に、中輪系と言われるものは、花の直径が7~6センチで、花色の豊富さとバリエーションが非常に豊富で花数も多いところから一番人気があります。
そして大輪系と呼ばれる花の直径が8~9センチのものは暖かくなっても株の乱れが少なく、その姿もコンパクトにまとまっていて、単植、寄せ植えなどが楽しめるもの。この他にも、一輪だけでも非常に見ごたえの、花の直径が12センチ以上のものまであります。葉は大きく葉状や羽状のものがあります。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:パンジーゼラニウムの育て方
タイトル:マンデビラの育て方
-

-
桃の育て方
桃の歴史は紀元前にまで遡り、明確な時期は明かされておりませんが、中国北西部の黄河上流が原産地とされています。当時の果実は...
-

-
ヘリオプシスの育て方
特徴としてはこの花は1年草になります。キクイモモドキの名前の元になっているキクイモに関しては多年草ですから、その面では異...
-

-
シバザクラ(芝桜)の育て方
シバザクラは北米を原産とするハナシノブ科の多年草です。春先にサクラによく似た可愛らしい花を咲かせますが、サクラのような大...
-

-
ゲラニウム(高山性)の育て方
高山性ゲラニウムの学名は、ゲラニウム・ロザンネイです。別名でフクロウソウとも呼ばれている宿根草で、世界にはおよそ400種...
-

-
植物の栽培、育て方のコツ。
植物を育てるのは生き物を飼うのよりはだいぶ気楽にできます。動かないので当然といえますが、それでもナマモノである以上手を抜...
-

-
モクレンの育て方
中国南西部が原産地である”モクレン”。日本が原産地だと思っている人も多くいますが実は中国が原産地になります。また中国や日...
-

-
パキラ(Pachira glabra)の育て方
パキラはアオイ科で、原産や生息地は中南米です。現在は観葉植物としての人気が非常に高いです。原種は約77種ほどあって、中に...
-

-
ホウセンカの育て方
ホウセンカは、ツリフネソウ科ツリフネソウ属の一年草で、東南アジアが原産です。中国では、花を鳳凰に見立てて羽ばたいているよ...
-

-
ルバープの育て方と注意点とは。
ルバープは和名をショクヨウダイオウといい、シベリア南部地方原産のタデ科の多年草です。大型の植物で高さは1メートル以上にな...
-

-
ベニバナの育て方
ベニバナに関しては見ると何の種類か想像しやすい花かも知れません。見た目には小さい菊のように見えます。実際にキクの仲間にな...




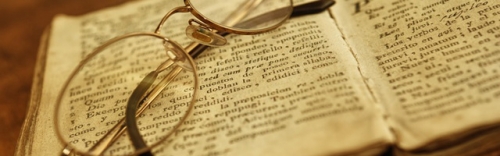





パンジーの原産はヨーロッパで、生息地は世界世界各国に広がっています。パンジーは交雑によって作られた植物です。その初めはイギリスの園芸家により1813年ごろビオラ・トリコロルを元に掛け合わせてものが始まりとされています。他にもビオラ・ルテア、ビオラ・アルタイヤ、ビオラ・カルカラータなどが挙げられます。