ネメシアの育て方

ネメシアの育てる環境について
ネメシアは鉢植えで育てることが出来る草花です。鉢植えで育てる場合には一年を通じて戸外に置くようにするのが良いでしょう。九月から六月にかけては日向に置き、七月から八月の暑い時期に関しては風通しの良い日陰を選んで置く様にするとよいでしょう。
ネメシアの仲間は暑さに弱いため、通常の環境では夏を越すことが出来ないケースもあるのです。そのため少しでも暑さを逃れることが出来る環境づくりを大切にしましょう。一月から二月の冬の時期に関しては北風を避けることが出来る南向きの軒下など暖かい場所を選んで置くようにしましょう。
夏に雨に充てると傷みやすいため、夏の時期には雨に晒さないようにすることも夏越しさせるための工夫であると言えます。鉢植えではなく庭の花壇等に植える場合には日当たりが良くて水はけのよい場所を選んで植えるようにしましょう。例ずドベッドやロックガーデンにも適している品種であると言えるでしょう。
いずれにしてもネメシアにとって苦手とされる環境をできるだけ避けて上げる配慮がネメシアを栽培する上で重要な要素になってくると言えます。育て方についてはそれほど特別なものはありませんが、長く花を楽しみたいと考えているのであれば、
ネメシアを理解した環境づくりを考えるようにすると良いでしょう。土は特別なものは必要ありませんが、水はけのよい環境を作ると良いでしょう。有機石灰を混ぜ合わせて中性からややアルカリ性の土壌にすると育ちが良くなります。
ネメシアの種付けや水やり、肥料について
ネメシアの植え付けや植え替えに関しては春と秋のに買いが適切な時期であると言えます。植え替えは状況を見ながら年に一回程度行うと良いでしょう。根鉢を軽く崩してやり、一回り大きな鉢に植え付けるという処置をすることでより成長できるようになると言えるでしょう。
庭に植える場合には秋に彫りあげて元肥を施し、軽く耕してから植え直しを行うと育ちやすくなると言えます。ネメシアに対する水やり葉鉢植えであれば土の表面が乾いたらたっぷりと水をやるという対応で十分です。もしも庭に植えているのであれば余程乾燥する場所でもない限りは水を撒く必要はありません。
しかし環境で気に全く雨とは無縁の場合には適切な水やりが必要になる場合もあります。屋外の場合には適度な雨が水やりの代わりとなるのですが、その様な雨が全く降らない場合には注意をしておくようにしましょう。鉢植えの場合、肥料に関しては九月から一〇月、
三月から六月の二回に薄めた液体肥料を二週間に一回の頻度で与えると良いでしょう。薄めずにあまりに濃い肥料を与えてしまうと根が傷んでしまうことになりますので注意が必要です。植物の場合には濃ければ良いと言うものではないということを知っておく必要があります。
庭植えの場合には植え付けのタイミングで緩効性化成肥料を元肥として施しておけば追加の肥料は必要ありません。夏越しさせた株に対しては涼しくなってくる九月以降に緩効性化成肥料を追肥するという対応を取るのが良いでしょう。
ネメシアの増やし方や害虫について
ネメシアの増やし方として一般的なのは種まきです。最もスタンダードな増やし方であり、一〇月頃が最適な時期であると言えます。種は高温環境では発芽しにくいという特徴があるため、涼しくなってからまくのが大切なポイントであると言えます。
種をまいた後で土を被せるケースが少なくありませんが、ネメシアの場合にはごく薄く土を撒く程度で十分です。種が見える程度が最も条件の良いものであると言えます。もう一つの増やし方としてさし木があります。このさし木を行うのであれば三月から六月、
または九月から一〇月が最適な時期であると言えます。葉をつけて2~3節切った茎を肥料の少ない清潔な用土にさしておきます。それから三週間もすれば移植も可能な株が出来るようになるでしょう。害虫に関してはアブラムシ対策が必要であると言えます。
それ相応に虫が付きますが、それでも適切な対処を取れば恐れるものではありません。しかし病気に関しては注意すべき点はやや多くなっています。例えば灰色カビ病やウイルス病等は広く知られている疾患になっています。
風通しが悪くなるとこの灰色カビ病になりやすいため、適切な環境づくりに力を入れることが予防につながるでしょう。一方ウイルス病に関しては灰色カビ病とは異なり、風通しを良くするなどの環境改善だけでは不十分です。
周囲の植物にも移ってしまう可能性がありますので対応には注意しなければならないと言えるでしょう。この病気が疑われる場合には早めに抜き取って処分しましょう。その際にはさみを使用するとそれを原因として伝染する場合もありますので注意が必要です。
ネメシアの歴史
ネメシアは日本においてはウンランモドキとも呼ばれており、園芸用の植物として愛されてきている品種です。最近では2000年にアメリカウンランモドキと呼ばれる品種が見つかっており、一部は自生している植物になっています。
元々日本においては夏を越すことが出来ない草花である一年草として知られていたのですが、近年の品種改良技術によって夏を越すことが出来るのは勿論、夏の時期以外はずっと花をつけると言う特徴を持つネメシアも生まれました。この様に品種改良が盛んに行われている園芸用の植物としての歴史を持っているのです。
そのため現代では単にネメシアと言っても一年で枯れてしまうものもあれば夏を越して複数年咲き続けるものまで沢山の種類が存在しています。これらは全く同じ品種と言うわけではなく、付ける花の色に関しても様々な違いを持っているのが特徴として知られています。
実に様々な種類がありますので一般的にネメシアと言ってイメージできる花の種類にも様々なものがあるでしょう。その様なバリエーション豊富な草花は今でも多くの種類が研究開発されており、新しい園芸用の草花として世の中に出る日を待っている状態であると言えるでしょう。
原産地である南アフリカとは異なる環境の日本において、日本に適した品種が生まれるのもそれほど先のことではないと言えるかもしれません。既に年中花を咲かせる品種が生み出されており、非常に高い評価を受けているのです。
ネメシアの特徴
ネメシアは南アフリカを原産とする多年生の植物です。草花の類であり、10センチから40センチほどの大きさに育ちます。花の色は青、白、ピンクと多彩であり、美しい観賞用の花を咲かせるのが特徴です。咲いてからすぐに枯れてしまう植物もある中でネメシアの花は開花時期が長く、
良い香りがするのが特徴として知られています。開花時期は夏の7月8月を除いてそれ以外の全ての時期が対象になります。そのため花が咲く期間の長さに関しては非常に優れた特徴があります。本来の生息地である南アフリカと日本の気候には様々な違いがありますが、
日本の気候にもそれなりに順応してくれるという特性があり、暑さには弱いですが寒さに対してはそれ相応の耐性を持っています。かつては秋から春にかけて種をまいて育てるストルモサと呼ばれるネメシアの仲間の一年草が栽培され、長年楽しまれてきました。
しかし近年になって-3度と言う寒さにも耐えることが出来る品種が生まれ、苦手な夏越しもできる品種として宿根ネメシアと呼ばれる品種が多く流通するようになってきました。この宿根ネメシアはカエルレア、デンティキュラータといった品種から改良されて、
作られた四季を通じて咲くと言う特性を得ることが出来ました。三度以上の気温があれば夏の時期を除いてずっと咲いているという特徴がある花として知られています。この様にネメシアには大きく分けて二種類の草花が存在していると言えるでしょう。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ネリネの育て方
-

-
ベッセラ・エレガンスの育て方
この花については、ユリ科のベッセラ属に属します。花としては球根植物になります。メキシコが生息地になっていますから、暑さに...
-

-
フロックスの育て方
フロックスとは、ハナシノブ科フロックス属の植物の総称で、現時点で67種類が確認されています。この植物はシベリアを生息地と...
-

-
タマガヤツリの育て方
タマガヤツリはカヤツリグサ科の一年草で、湿地帯に多く見られます。生息地は日本においてはほぼ全土、世界的にみても、ほぼ全世...
-

-
ジギタリスの育て方
ジギタリスの原産地は、ヨーロッパ、北東アフリカから西アジアです。およそ19種類の仲間があります。毒性があり、食用ではない...
-

-
ヤナギランの育て方
花の特徴としては、まずはフトモモ目、アカバナ科、ヤナギラン属の種類となっています。多年草なので1年を通して葉などをつけて...
-

-
トケイソウの仲間の育て方
トケイソウの仲間は中央アメリカから南アメリカにかけてが原産地とされています。生息地は熱帯地域が中心で、現在では世界中に数...
-

-
ヘデラの育て方
ヘデラは北アフリカ、ヨーロッパ、アジアと広い地域を生息地とする非常に人気がある常緑性のつる植物です。非常に様々な品種があ...
-

-
ワレモコウの育て方
この植物においてはバラ目、バラ科になります。ひと目見たところにはバラにはとても見えそうもありませんが、よく見てみるとたし...
-

-
三尺ササゲの育て方
三尺ササゲは別名ジュウロクササゲ、長ササゲともよばれるマメ科ササゲ属ササゲの亜種で見た目はインゲンのようですが別の種類に...
-

-
フィクス・ウンベラタ(フィカス・ウンベラータ)(Ficus ...
フィクス・ウンベラタとは、フィカス・ウンベラータとも言われていますが、葉がとても美しいだけでなく、かわいいハートの形をし...




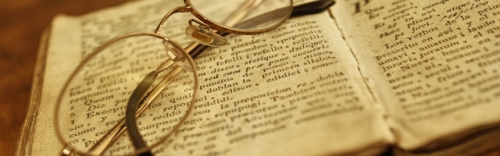





ネメシアは日本においてはウンランモドキとも呼ばれており、園芸用の植物として愛されてきている品種です。最近では2000年にアメリカウンランモドキと呼ばれる品種が見つかっており、一部は自生している植物になっています。