ニンジンの育て方

ニンジンの育てる環境について
ニンジンの育て方は少し気を遣うかもしれません。まず、発芽の適正温度は15~25℃にします。そして生育の適正温度は18~22℃となります。12以下になってしまうと、根の着色が悪くなります。栽培は涼しい気候が適していますが、苗の段階では気温が高くてもさほど問題はありません。
土が酸性になると成長が遅れ、根が避けてしまう恐れがあるので、酸度は弱酸性~中性に保つ事が必要です。他の野菜に比べて肥料をたくさん必要とする為、雑草も増えやすくなるので、苗の成長が妨げられてしまわないよう、除草はこまめに行うようにします。
そしてニンジンを育てるにあたって大切なのは、適度な湿度と土の質です。有機性に富み、排水や保水に優れ、通気性があり、強い雨が降った後も表土が崩れにくい土質が理想といえます。土壌の水分はおよそ70%~80%程度がいいとされています。
しかし、湿度が高すぎると逆に根元の部分が荒れてしまい、更にひどい場合は根が腐ってしまうこともあります。逆に乾燥していても、根の伸びが悪くなり、成長が阻害されてしまいます。色の付きも悪く、ひげ根が多くなってしまいます。どんなに水や肥料を与えても、
肝心な土台である土の状態が良くないと当然、育ちも悪くなってしまいます。土壌の水分や湿度を適度に保ち、日光を浴びせながら育てていくことが大切になります。畑や菜園だけでなく、プランタでミニニンジンを育てる場合も同じように考えてあげるといいでしょう。
ニンジンの種付けや水やり、肥料について
種を撒く2週間ほど前に、苦土石灰を菜園や畑に散布した後、やや多めにまんべんなく耕します。そしてその一週間後に肥料を散布し、こちらも同様に土に混ぜて丁寧に耕しましょう。生育期間が長いので、ここでは緩効性の肥料を用います。種を植えてから2カ月ほど経過すると肥料の吸収がよくなるので、
その頃までは肥料は与えすぎないようにします。また、土が乾燥していると種の吸収力が弱いので、雨が降った後などに種を撒くのがよいとされています。種を撒いた後は発芽するまで土を乾燥させないようにしましょう。新聞紙や不織布、もみ殻などをかけ、毎日の水やりも欠かさないようにします。
これらは、発芽した際には取り除き、発芽した後は土が乾いた時に水を与える程度で大丈夫です。収穫は種を撒いた後、およそ100日~120日が目安です。株の根の直径が4~5cm程になったら根元を掴み、一気に引き抜きましょう。
収穫のタイミングが遅れてしまうと、大きくなりすぎてしまい、根が避けてしまう恐れがあります。一番よい大きさは12~13cmとされています。ミニプランターでミニキャロットを栽培する場合、収穫は種を撒いた後およそ70日と、
通常と比べて早い場合1カ月ほど早く収穫することが出来ます。ニンジンはもともと成長が遅く、ゆっくりと育っていく野菜なので、早く成長させたいからといって必要以上に水や肥料を与えてはいけません。焦らず、丁寧に育て、収穫のタイミングをしっかりと見極めて育てていきましょう。
ニンジンの増やし方や害虫について
葉と葉が重なり合う時期になると、間引きをする必要があります。間引きとは名の通り、葉と葉同士が触れ合って成長を妨げないように間隔をとってあげることをいいます。まず一回目の間引きは、本葉が1~2枚になった頃、2cmほど株間を空けます。
2回目の間引きは、葉が3~4枚になった頃、3~4cmほど株間を空けます。この時、一株あたり3~5g程度追肥をし、苗がぐらつかないようにする為の土寄せを行います。そして葉が5~6枚になった頃、3回目の間引きをします。株間を10cmほどにし、不要な苗は根元から撤去しましょう。
この時にも2回目と同様、追肥と土寄せを行います。最終的な株間は10~15cmとなります。そして、害虫からも苗を守ってあげなくてはいけません。主にアオムシ、ネキリ虫、ヨトウガといったアブラムシが多いのですが、これらの害虫がついた場合、食品成分を使用した殺菌殺虫剤などを散布して、退治しましょう。
また、かかりやすい病気からも守る必要があります。かかりやすい病気として、軟腐病、根腐病、黒班病、黒葉病などがあります。軟腐病や根腐病は土の排水の状態が悪いとかかりやすいので、排水をよくする事を心がけましょう。
また黒班病や黒葉病は15℃以下、35以上では発生しにくいので、適した環境を作り上げていくことが大切になってきます。もしもこれらの病気にかかってしまった場合は、それぞれに適した専用の殺菌剤を使い、治療しましょう。
ニンジンの歴史
ニンジンはセリ科の一種であり、この名前の由来は朝鮮人参に形が似ていることからつけられたものですが、朝鮮人参はウコギ科の植物なので、ニンジンとは品種も生息地も異なります。茎はおよそ1メートル、葉は細かく裂けています。原産地はアフガニスタン周辺にあり、
それに横する山脈、ヒンドュークシで栽培が始まったのがきっかけで、ここから世界各地に広まるようになりました。オランダからイギリスへ西方に伝わりながら品種改良されたものを西洋系ニンジン、中国から東方へ伝わりながら品種改良されたものを東洋系ニンジンといいます。
西洋系ニンジンは太短く、それに対して東洋系ニンジンは細長いのが特徴になります。どちらも主に薬や食用として古くから栽培されてきました。古代ギリシャで薬用として栽培されていたニンジンは根が枝分かれした、刺激の強いものとなっていました。
日本にニンジンが伝わったのは16世紀と言われており、江戸時代は東洋系が主流でしたが、この品種は栽培が難しい為生産が少なくなり、明治時代頃には西洋系が主流となったのです。今よく目にするオレンジ色をしたニンジンは、
17世紀~18世紀にオランダで品種改良され、栽培されたものといわれています。現在の日本での主な産地は北海道、千葉県、徳島県となっており、もっとも多く栽培されている地域は北海道で、その割合はおよそ30%を占めています。続いて、千葉県、徳島県、その他地域といった順となります。
ニンジンの特徴
よく見られる一般的なニンジンは15~20cm程度のものが多く、綺麗なオレンジ色をしています。以前は独特な香りや風味があったのですが、近年では品種改良により、においも少なく、食べやすいのが特徴となっています。このオレンジ色のニンジンには100グラムに対し、
およそ8600mcgものBカロテン、240mgのカリウムを含みます。風邪予防、がん予防、高血圧予防、心筋梗塞予防、脳梗塞予防、動脈硬化、老化予防などといった数多くの健康維持の他、Bカロテンは体内でビタミンAに変わり、免疫力の向上、抗酸化作用、粘膜の健康維持、視力の保持なども期待できます。
この他にも様々な種類のニンジンがあります。京ニンジン、金時と呼ばれるものは濃赤色で、細長く長さは30cm程度。東洋系ニンジンの代表品種ともいわれており、香川県や岡山県で栽培されています。11~3月頃までが旬といわれています。
紫ニンジンは糖度が高く、視力によいとされるアントニシアンを含むものです。生食でも食べる事ができ、野菜ジュースなどに使用しても美味しく摂取できます。黄ニンジンは沖縄で栽培されており、ごぼうのように細長く、繊維が多いのが特徴です。
やわらかく甘みもあるので、生でも食べられます。丸型のミニキャロットという10cm程度の小さく可愛らしいものもあります。皮が薄くてやわらかく、甘みも強いので生でも食べられます。プランターでの栽培も容易に出来ます。
-

-
アラマンダの育て方
アラマンダはキョウチクトウ科 Apocynaceaeのアリアケカズラ属 Allamanda Linn. の植物です。原産...
-

-
チグリジア(ティグリディア)の育て方
チグリジアは別名ティグリディアとも呼ばれるユリに似た植物ですが実際にはアヤメ科の仲間になっています。チグジリアの仲間アヤ...
-

-
ダボエシアの育て方
ダボエシアは学名でDaboeciacantabrica’bicolor’といいますが、分類で言うとツツジ科ダボエシカ属に...
-

-
ナンテンハギの育て方
ナンテンハギはマメ科でありますが、他のマメ科の植物がツルを使って他の植物に頼ることで立つ植物であるのに対して、そうしたツ...
-

-
ユーフォルビア(‘ダイアモンド・フロスト’など)の育て方
ユーフォルビア‘ダイアモンド・フロスト’などは小さな白い花のようなものが沢山付きます。だからきれいで寄せ植えなどに最適な...
-

-
ビカクシダ(Platycerium ssp.)の育て方
ビカクシダは年間を通して日当たりが良い場所で育てるのが基本です。日陰では株が弱ってしまいます。土は腐植質で水はけのよいも...
-

-
スカビオーサの育て方
別名を西洋マツムシソウといいます。英名ではピンクッションフラワーやエジプシャンローズ、スイートスカビオスなどあります。ス...
-

-
コリウスの育て方
コリウスはシソ科の植物で、和名は金襴紫蘇、別名はニシキジソといいます。ただし金襴紫蘇の名前で呼ぶ人は渡来した当時はたくさ...
-

-
ヘレニウム(宿根性)の育て方
この花に関しては、キク科、ヘレニウム属に属する花になります。花の高さとしては50センチから150センチほどになるとされて...
-

-
モナデニウムの育て方
モナデニウムは日当たりのいいところで栽培をします。そして育て方は土が乾いたらたっぷりの水を与えてあげます。塊根タイプの植...




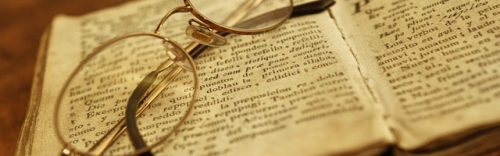





ニンジンはセリ科の一種であり、この名前の由来は朝鮮人参に形が似ていることからつけられたものですが、朝鮮人参はウコギ科の植物なので、ニンジンとは品種も生息地も異なります。