トリトマの育て方

トリトマの育てる環境について
トリトマは植え付けを3月から4月にかけて行い、開花は6月から10月頃になります。また、肥料は3月から9月頃に施し、花が一通り咲き終わると肥料を与えるのを止めます。尚、花が一通り咲き終わった後には枯れた花穂が残りますので、
そのままつけたままにしておくとあまり見栄えもよろしくありませんので、花の下の方から切り取ります。また、茎や葉などの部分もこまめに取り除いておくと良いです。育て方や育てる環境ですが、日当たりを好むため、日当たりが良い環境に植え付ける事がポイントです。
また、日陰の状態では育ちが悪くなってしまい、花つきが悪くなります。南アフリカや熱帯アフリカと言った場所が原産であるため、耐暑性は強く光を好みますので、日当たりはとても重要な要素となります。因みに、トリトマと言う植物は耐暑性が強いだけではなく、耐寒性も強いのが特徴です。
しかも、開花時期が6月から10月頃までと長いため、初心者の人も環境を作り出してあげる事で比較的容易に栽培が出来ますし、開花期間が長いので黄色や赤色と言った花を長く楽しめるなどのメリットも有ります。日当たり、水はけのよい場所が育てる環境に適しており、
このような環境の場所に、水はけや通気性に富んでいて、適度な保水性を持つ土を用土とします。例えば、市販されている草花用培養土、赤玉土を6、腐葉土もしくは堆肥を4の割合で混ぜて用土を作って栽培を行う事で、花つきを良くしてくれます。
トリトマの種付けや水やり、肥料について
水やりについては土の表面が乾燥をしてきたら行う事になりますが、庭植えの場合などでは、根が活着したら場合は殆ど不要になりますが、鉢植えの場合は、鉢の中の土が乾いた場合はたっぷりと水をあげます。肥料については、植え付けを行う時や、植え替えを行う時など元肥として、
ゆっくり効き目が出る粒状の肥料と有機配合肥料(例えば、油かすや骨粉を配合した肥料など)を混ぜ込んで用土を作り上げる方法も有ります。また、庭植えの株の場合は、春時期と秋時期などに株の周囲に化成肥料を与え、鉢植えの株に対しては、
開花中や定期的に緩効性化成肥料を置き肥したり、液体肥料を利用して肥料を与えてあげます。また、追肥として初夏から秋にかけて2回ほど化成肥料を与える事で花つきを良くしてくれますし、元気な花を咲かせることが出来ます。尚、追肥については月1回程度与えて行っても良いです。
日当たりを好み、日陰では育ちが悪くなり、花が咲きが悪くなると言う特徴が有りますが、トリトマは耐寒性が強いため、特別防寒対策を行う必要は有りません。しかしながら、寒冷地などで栽培を行う場合には、土壌はガチガチに凍りついてしまうため、
腐葉土などを土壌の上を覆って凍結を防止する事が大切です。尚、トリトマを植えたままの状態にしておいても良いのですが、そのままにしておくことで生育が衰えてしまったり、株が大きくなり過ぎてしまうため、株分けが必要になった場合などに、3月頃に植え替えを行っておきます。
トリトマの増やし方や害虫について
増やし方は株分けと種まきを行う事で増やすことが出来ます。株分けを行うのに適しているのは3月であり、春先になって新芽が伸びる前に株分けの作業を行うのがコツです。株分けを行う時には、掘りあげた株を、1つの株に3芽以上付けた状態で切り離して植え付けを行います。
種については市販されていない事が多いため、栽培をしている中で採取した種を使って増やして行きます。尚、採取した種は涼しい場所で保管をし、3月に入った時に鉢にまいておきます。種をまいたあとは土をかぶせ、たっぷりと水を与えておきます。発芽の後に本葉が出て来た段階で、
大きめの鉢に植え替えを行いますが、トリトマは大株になりますので大きめの鉢を用意しておくと良いでしょう。尚、上手に栽培をしてあげれば翌年の初夏などの季節になった時に開花させることが出来ます。また、庭植えを行う場合も、間隔を60センチほどとって株を植えて上げる事が大切で、
横にも大きく広がってきますので、隣との間隔を十分の考慮しておくことが大切です。トリトマの害虫と言うのは主にアブラムシなどが発生します。春から秋にかけてアブラムシは発生しやすく、葉や茎、花穂などにアブラムシが発生しやすいため、1か月に1度の割合で薬剤を散布して予防を行っておきます。
また、アブラムシが発生した時も、薬剤を散布して駆除を行い、蕾が出来た時にアブラムシがついても薬剤を散布する事で防除が可能です。尚、トリトマは大型で横にも良く伸びますので鉢植えよりも庭植えの方がお勧めです。また、庭植えを行う場合には日当たりが良く、水はけが良い環境で栽培する事がコツです。
トリトマの歴史
トリトマは、クニフォフィアと言う別名を持つ草花であり、以前はトリトマと呼ばれていましたが、最近ではクニフォフィア属(シャグマユリ)に分類されており、正式にはクニフォフィアと言います。生息地と言うのは標高が1000メートルを超える高地であり、
主な原産地と言うのは熱帯アフリカや南アフリカなどになり、野生種の多くは南アフリカの高地に自生していると言います。日本国内で栽培されているものは、ヒメトリトマと呼ばれる品種で、蕾の段階ではオレンジ色をしていますが、開花する事で色を黄色に変化させると言う特徴が有ります。
育て方などもそれほど難しい草花ではないため、古くから園芸用の草花として栽培が行われており、その多くは赤い花をつけると言う、オオトリトマなどの品種であり、日本国内においては2つの色の品種の栽培が可能になっています。尚、南アフリカの高地などが主な生息地と言う事になりますが、
南アフリカの高地には多数の動物が生息をしており、真っ赤に彩られたトリトマと動物たちが生息する風景と言うのは不思議な世界と言えます。これは、トリトマの草丈が1メートルにも及ぶと言う事からも、野原を駆け巡る動物と真っ赤な花を咲かせるトリトマの
コラボレーションは絵になるとも言われており、古くから栽培が行われていたと言います。何本も伸びる花茎の先には赤い色の花が咲き、一つの株から複数の花茎が伸びる草花でもあり、家の花壇などで栽培をする人が多い人気種です。
トリトマの特徴
トリトマは旧属名であり、現在ではクニフォフィア属もしくはシャグマユリと言った呼び名になっていると言います。但し、昔からトリトマと呼ばれていた事からも今でもこのように呼ぶ人が多いのです。熱帯アフリカ、南アフリカなどには約70種類が分布しており、
その多くは標高が1000m以上の高地に分布しているものが多いと言います。日本で栽培されているものと自生しているものは異なる品種ですが、その様相などは同じものであり、背丈においては1メートルを超える物も有ると言います。細長い茎の先端には縦長の花を咲かせるのが特徴で、
大半を赤色に染める花弁が有り、茎の近くだけ黄色いものや、日本の中で主流となっている黄色のものは、蕾の時にはオレンジ色をしており、花が開く事で黄色に変わると言う特徴が有ります。尚、トリトマはユリ科もしくはススキノキ科の植物であり、和名はシャグマユリ、漢字では赤熊百合と書きます。
赤い熊のようなユリ科の植物から、このような漢字で表現されていると言う特徴も有ります。また、特徴の中で外せないのが花の大きさです。一つの株から複数の茎が伸びており、その先端部分には長さ約20センチの大きな花序を立てており、
花は下向きに密生し、下部分から上方向に向かって咲き上がると言う特徴が有ります。そのため、徐々に花の部分の色が変化すると言う面白さを持つ事からも、海外や日本の中で栽培する人が多いと言う特徴が有ります。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ニーレンベルギアの育て方
-

-
アカザカズラの育て方
夏になると、近年は省エネが叫ばれ、電力の節約のためにさまざまな工夫がなされます。つる性の草のカーテンもそのひとつだと言え...
-

-
ヒメツルソバの育て方
ヒメツルソバは原産国がヒマラヤの、タデ科の植物です。姫蔓蕎麦と書くことからも知れるように、花や葉が蕎麦の花に似ています。...
-

-
オーストラリアビーンズの育て方
オーストラリアビーンズは学名をCastanospermumaustraleといい、マメ科になる植物です。名前にもビーンズ...
-

-
チョウノスケソウの育て方
植物の特徴としては、被子植物、双子葉植物綱になります。バラ目バラ科バラ亜科なのでまさにバラの仲間の植物といえるでしょう。...
-

-
ゼノビアの育て方
ゼノビアは日本国内ではスズランノキという名前でも呼ばれる北米を原産地とする植物です。同様にスズランノキという名前で呼ばれ...
-

-
にらの育て方
にらの原産地は定かにはなっていませんが、中国西部から東アジアにかけての地域生息地ではなかったかと考えられています。モンゴ...
-

-
シンジュガヤの育て方
イネ科やカヤツリグサ科などで、日本でも種類は多いのですが注目をあまりされない植物群です。その中でわりと注目されている植物...
-

-
カンパニュラの育て方について
カンパニュラは、釣り鐘のような形の大ぶりの花をたくさん咲かせるキキョウ科の植物です。草丈が1m近くまで伸びる高性タイプの...
-

-
ヤツデの育て方
ヤツデは学名がファツシア・ジャポニカということでジャポニカとありますから、日本固有の種類ということがわかりますが、ウコギ...
-

-
長ねぎの育て方
長ねぎの他、一般的なねぎの原産地は中国西部あるいはシベリア南部のアルタイル地方を生息地にしていたのではないかといわれてい...




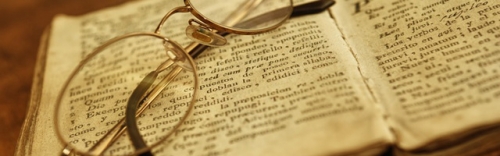





トリトマは、クニフォフィアと言う別名を持つ草花であり、以前はトリトマと呼ばれていましたが、最近ではクニフォフィア属(シャグマユリ)に分類されており、正式にはクニフォフィアと言います。