アサガオの育て方

アサガオの種を栽培する
アサガオの育て方はまず種付けから始まります。種付けする時期は5月の中旬から下旬が適しています。発芽適温は20度から25度であるため、まだ寒い時期の種付けは厳禁です。種付けを行ったあとは厚みを1cmから2cmを目安に土で覆ってください。直まきはもちろんのこと、苗を移植して植えつける方法でも可能です。
先述のように種皮が硬いことから、まく前にヤスリなどで種皮を削っておき、芽が育ちやすいようにする工夫を凝らす育て方もあります。その際は尖った部分の内側にあるへそに、傷を付けないよう注意しながら削ってください。市販のタネであれば硬実処理がすでに施されているものも多いので、初めて種付けを行う場合はそれを利用すると簡単です。
または、種を一晩水につけ、膨らんだら蒔くという方法でも芽が育ちやすくなります。種を予めポリポットで育苗した場合は、底穴から白い根がわずかに見えた頃が目安です。根を切らないように気をつけて植えましょう。
その都度ホームセンター等で種や苗を購入するのもよいですが、開花時に株を2つ用意し、それらで人工受粉を行って種を作り、次年度も栽培可能にするとコストの面で節約できます。受粉が成功してできたタネは、次の種付け時期までは紙袋などに入れて冷暗所に置き、乾燥保存しましょう。
育った苗を植え付けする
次はある程度育った苗を植え付けする方法です。基本的には花壇や庭など、直接地面に植える育て方が望ましいですが、場所に余裕がない場合はプランターでも可能です。但し土の容量が大きいもので行いましょう。30cmから50cmの株間で植えて下さい。庭に直接植えるの場とプランター栽培では、育て方も変わってきます。
まず庭に直接植える場合ですが、アサガオを植えつける2週間ほど前に、苦土石灰を1平方メートルに対して100gの割合で混ぜ、更に植えつけ直前に腐葉土を1平方メートルに対し2kg、粒状肥料を平方メートルに対して150gになるよう混ぜるのです。この肥料の混ぜ方によって育ち方も異なるのでしっかり行いましょう。
一方プランター栽培の場合ですが、土によって準備が異なります。市販の草花培養土などを使う場合、それに加えて完熟牛ふん堆肥と川砂を、それぞれ全体1割程度の量を加えて、更に粒状肥料を用土1?に対し5gの割合で加え、混ぜたあとで苗を植えるのです。
栽培中の注意点
アサガオはその特性から、朝日がしっかりと当たる場所で育てるのが望ましいです。水やりは花が咲くまではやや控えめに行い、花が咲き始めてから初めて、土を乾かさないようにたっぷりと行ってください。特に真夏は、庭に植えたの場合でも朝夕の水やりが必要となります。根気よく土の中に水が十分しみ込むまで与えましょう。
また真夏の時期は午後からの強い日ざしで葉がしおれることがありますが、夕方に水やりをすれば回復します。この点でも、朝夕の水やりが重要なことが分かります。アサガオは短日植物ですから、夜間に照明が当たると翌朝に花が咲きにくくなってしまいます。朝日が当たる場所であると同時に、夜間の照明の位置以外の場所にしましょう。
自宅の照明だけではなく、道路の街灯の位置にも注意してください。日々の手入れでは、下葉が枯れ落ちることが多いため、初期段階で摘心、株の下のほうの枝数を増やす形状にすると良いです。また咲き終わった花を摘み取りも必ず行いましょう。早朝に開花して午前中にはしぼんでしまうので、お昼にはつみ取りが可能です。
花がら摘みをしないでいるとタネがつき、株が早く老化してしまうのです。育成中は元肥として粒状肥料を1平方メートルに当たり150gを土に混ぜておくこと、定植後に10日に1回ぐらいの間隔で、窒素分が少ない液体肥料を水やり代わりに行うとより大きく育ちます。8月をすぎれば成長も少なくなるため、施肥を中止して構いません。
緑のカーテンの仕立て方法
アサガオをカーテンにする場合は、事前に支柱とつるもの用ネットを準備します。ネットの両端には丈夫な支柱や金属パイプを通して固定し、カーテンとして活用できるようにするのです。ネットの場合はつるが真っすぐに成りにくいため、まっすぐにのぼらせたい場合はネットの代わりに麻ひもを用意してください。
支柱やネットを立てる目安は、本葉が7、8枚開いた時で、併せて摘心します。2階建ての家であれば、2階のベランダまで伸ばすことも可能なので、行いたい場合は支柱やネットもそこまで届く長さにしましょう。あんどん仕立ての場合は1本の芽だけを残す形ですが、カーテンの場合はわき芽を全て残してそれぞれを誘引する語りにします。
仕立て準備としてはこれで完成ですが、カーテンの内側に黄色くなった枯れ葉が目立ってくるので、適宜取り除くことと、横方向に誘引する場合は伸びたつるを一旦解き、ネットやひもに誘引し直すことを忘れないようにしてください。
アサガオの歴史
日本で古くから親しまれている日本で最も発達した園芸植物です。それは小学校の教材でも用いられる程で、育成の容易さも示しています。原産地は熱帯アジアやヒマラヤ山麓で、日本には奈良時代末期、遣唐使がその種を薬として持ち帰ったのが初めとされています。しかしこの時期については平安時代であるという説もあり、具体的には定かではありません。
何が薬になるのかというと、アサガオの種の芽になる部分に下剤作用のある成分が多く含まれており、粉末にして下剤や利尿剤として活用されたのです。奈良時代、平安時代においては薬用植物として扱われていました。また古典園芸植物として歌に詠まれる等の側面も持っています。しかし万葉集などで朝顔と呼ばれているものは、アサガオ本種でなく、キキョウやムクゲ等を詠んでいるとも言われています。
その後、江戸時代に2度、朝顔ブームが起こり、それをきっかけに品種改良が進んだ結果、現在のような観賞用植物となりました。この時、江戸を中心に流行ったのが変化朝顔と呼ばれる種類です。また江戸以外では熊本藩の武士たちによる園芸が盛んであり、朝顔も花菖蒲や菊、芍薬、椿、山茶花と共に愛好され、独自の文化を形成しています。
こちらは肥後朝顔と呼ばれており、後に大輪朝顔と呼ばれる種類の祖先とも言われています。明治時代以降は変化朝顔が発展しつつも、現在に近くなるにつれて大輪朝顔の方が持て囃されるようになってきました。戦後にはほぼ大輪朝顔が主流となっています。現在では江戸時代の品種の再現等の試みが行われており、品種改良も続いています。
アサガオの特徴
分類上はヒルガオ科サツマイモ属の一年性植物であり、生息地は日本では全国と行っても過言ではないほど広く分布しています。花は、日が射す方向に向いて咲くという特徴があり、それが朝顔の名前の由来にもなっています。
つる性の1年草で、つるの生育はとてもおう盛であり、育てば硬くて丈夫なつるが3m以上に長く伸びます。アサガオのつるは、下から見て左巻きになっているのが特徴です。タネは硬実種子と言われており、比較的硬い性質を持っており、成長が早くて育てやすい植物の一つです。
鑑賞形態はあんどん仕立ての形式が広く知られていますが、つるの性質から、日避けを目的として緑のカーテンに仕立てることもできます。西洋アサガオや曜白アサガオ、そして垣根アサガオと呼ばれる種類が特にカーテンに適しています。
下記の記事も緑のカーテンを作ることが書いてあります♪
タイトル:なたまめの育て方
タイトル:ミニカボチャの育て方
タイトル:モミジバアサガオの育て方
タイトル:インパチエンスの育て方
タイトル:ヨルガオの育て方
タイトル:ノアサガオの育て方
タイトル:ムクゲの育て方
-

-
ブルークローバーの育て方
ブルークローバーはマメ科パロケツス属の常緑多年草です。原産はヒマラヤやスリランカ、東アフリカなどで、主に高山帯を生息地と...
-

-
小かぶの育て方
原産地を示す説はアジア系とヨーロッパ系に分かれており定かにはなっておりません。諸説ある中でも地中海沿岸と西アジアのアフガ...
-

-
ハナビシソウの育て方
盃のように大きく開いた花の形で、鮮やかなオレンジ色の花を咲かせます。カリフォルニア原産の小型種で淡い黄色の花がたくさん咲...
-

-
銀葉アカシアの育て方
まず歴史的にもミモザという植物は、本来は銀葉アカシアなどの植物とは違う植物です。もともとミモザとはオジギソウの植物のこと...
-

-
スイートマジョラムの育て方
スイートマジョラムは、ギリシア神話の愛と美の女神アフロディーテが創り出し、太陽の光をよく受けて育つように山の上に植えたと...
-

-
コウバイの育て方
楽しみ方としても、小さなうちは盆栽などで楽しみ、大きくなってきたら、ガーデニングということで、庭に植えるということもでき...
-

-
クルクマの育て方
クルクマは歴史の古い植物です。原産としての生息地がどこなのかが分かっていないのは、歴史が古すぎるからだと言えるでしょう。...
-

-
アレカヤシ(Dypsis lutescens)の育て方
アレカヤシという観葉植物をご存知でしょうか。園芸店などでもよく見かける人気のある植物です。一体どのような植物なのでしょう...
-

-
柑橘類(交雑品種)の育て方
柑橘類は遡ること3000万年という、はるか昔の頃から、インド東北部を生息地として存在していたものです。中国においては、4...
-

-
ブルーハイビスカスの育て方
ブルーハイビスカスは別名をアリオギネ・ヒューゲリーやライラック・ハイビスカスといいます。属名はギリシャ語の結合したや分割...





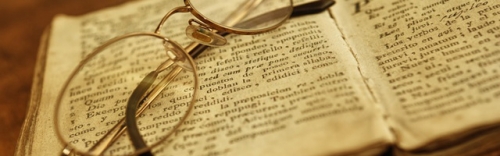





日本で古くから親しまれている日本で最も発達した園芸植物です。それは小学校の教材でも用いられる程で、育成の容易さも示しています。原産地は熱帯アジアやヒマラヤ山麓で、日本には奈良時代末期、遣唐使がその種を薬として持ち帰ったのが初めとされています。しかしこの時期については平安時代であるという説もあり、具体的には定かではありません。