チオノドクサの育て方

育てる環境について
可憐な花を咲かせるチオノドクサを育てるときには、出来るだけ寒い地域で地面に埋めるのが最適な環境です。高山植物であることから、水はけのよい土を選び、夏の照りつけるような直射日光はできるだけ避けることが必要です。赤玉土が6割、腐葉土が3割、川砂があれば1割加えると黄金比率となります。
暑さが気になる地域では、最初から地面に植えるよりも鉢植えにして、夏の時期は冷房の効いた室内で球根が休めるようにした方が安全です。暑い時期を乗り切ってから、秋口の風邪が冷たくなったころに地面に植え替えるのも球根に優しい育て方です。
育てるときには水はけが良い土を選んだ方が良いですが、球根を植え替えたり保存する場合には球根自体を乾燥させないようにすることが必要です。ある程度の湿り気を持たせながらも、乾燥してしまわないように土を完全に取り除かないようにすることが大切です。
年中気温の上がらない地域に生息する高山植物であることを念頭において、高温に留意することも重要です。高山地域、北海道や東北といった、夏でも快適な涼しい地域では、地面に植えっぱなしでも来年に向けて花を咲かせるようになりますが、
連日最高気温が30℃を超える地域では、鉢植えや球根を地面から掘り出して涼しいところに保管する必要があります。放っておくと球根が腐ってしまい、春に花を咲かせたばかりの球根がダメになってしまうため、暑い時期をどう乗り越えるかがカギを握っています。
種付けや水やり、肥料について
チオノドクサは高山植物の一種であるため寒さに強く、日本では雪がちらつく前の寒さを感じ始める10~11月が種付けの時期になります。北海道や東北など雪の時期が早い時期には、秋の気配を感じ始めたら植えるのが適当です。庭などに直に植える際には地面から2センチの深さ、
5センチ程度の間隔をあけて植え、鉢植えの場合には軽く土がかかる程度の地面すれすれに、球根同士が窮屈でない程度の間隔をあけて植えます。暑さに非常に弱いので、まだ暑いうちに植える時には日陰を選んで、日ざしを遮る葉っぱが生い茂る樹木が近くにある場合にはその木陰が一番最適です。
鉢植えを選ぶ際には、鉢がすっぽりと埋まるまで土をかぶせて守ると夏の暑い時期も乗り切ることができます。秋から春の時期は日差しの良いところで根腐れをおこさないように見守ることが大切です。水やりは、地面の表面が乾いてからたっぷりと与えます。
水の与えすぎは球根が腐ってしまうので、土が乾いてなければ毎日水やりをする必要がありません。よほど土が痩せた場所や極寒の地で地面が凍らない限り、肥料も基本的には不要です。一般のホームセンターで販売されている腐葉土や堆肥などの、
有機質の肥料を一種類だけ少し混ぜるか、寒さをしのぐために地面にかぶせるように保温するだけで構いません。肥料の与えすぎも球根が腐ってしまう原因となるため、基本的に水も肥料も足りなくなった分を少しずつ与えることが大切です。
増やし方や害虫について
チオノドクサは生命力が強く、球根を掘り出して大き目に分割して、土から取り出した球根が完全に乾かないうちにまた土に戻すと、次の年にはどんどん増えていきます。種でも小さい球根からでも増やすことは可能ですが、最初から自分で育成すると花を咲かせるまで数年はかかるため、
気に入った花でおうちを彩りたい方には、ある程度育った大きな球根を分割したり、新たに球根を追加購入することが勧められています。増やすのに適した時期は、種付けと同じ秋の時期が適当です。球根が休眠状態に入る夏の暑い時期を過ぎて、来年の春に向けて栄養を蓄え始める秋に行うと、
分割した球根も大きさを増していき奇麗な花を咲かせるまで成長していきます。分割した球根の育て方も、種付けの時と同じように水やりと適度な肥料で十分です。基本的にチオノドクサは球根で地面に埋まっているため、害虫はつきにくい植物です。
暖かくなって芽吹いてくと家庭菜園の天敵であるアブラムシが付くことがありますが、早い段階の場合には木酢液などで対処できます。あまりにも増えてしまった場合には、殺虫剤の使用が効果てきめんです。最近では有機野菜にも使えるタイプ、
家庭菜園にも使える天然成分由来タイプの殺虫剤も販売されているため、安心して花を守ることができます。土に混ぜるタイプの殺虫剤は球根の根腐れを起こす可能性があるため、できればスプレータイプを選んで、早めに害虫に対処することが必要です。
チオノドクサの歴史
チオノドクサという植物は東地中海クレタ島やトルコの高山が原産で、現在ではヨーロッパの山々を生息地とする高山植物の一種です。ギリシャ語の雪を表す「チオン」と、輝きや栄光を表す「ドクサ」を組み合わせた言葉が示すように、ヨーロッパでは非常に古くから愛されてきた花となっています。
日本にこのチオノドクサが入ってくるようになったのは、昭和初期のことです。和名でユキゲユリ(雪解百合)と言われるように、軽井沢や北海道などの雪深い地域で多く栽培されるようになり、春の雪解けとともに白や青といった小さい可憐な花をつけて各地の観光客を楽しませています。
特に雪深い北海道では公園や学校の庭園などといった公共施設でも多く植えられていて、短い春に彩りを添えています。以前は栽培する方も少なく専門店でないと球根を購入できなかったのですが、最近では大手ホームセンターや通販、種苗を扱う店舗から様々な種類の球根が購入可能です。
定番の小さい花をつける白や青の球根だけでなく、最近ではピンクの花をつける大型の球根も人気を集めています。特に通販では気に入った花の球根を20球などといった大口販売をしていて、格安で購入できます。
球根を植える時期が秋になっているため、球根の頒布は9月からが多くなっており、色の良い花の球根は売り切れが予想されるため、夏ごろから頒布に留意しておくとより良い球根を手に入れられて、庭や家の周りに彩りをくわえることができます。
チオノドクサの特徴
チオノドクサは小さな星形のような可憐な花を咲かせる植物です。単色の花を咲かせることもあれば、白と青のグラデーションに見える花もあるため、育てる楽しみが非常に大きい植物でもあります。球根から育つのですが、チューリップなどいった大きな球根を深く埋める必要もなく、
堆肥を大量に混ぜたりホースで水を撒くような重労働も要らないことから、ガーデニングを趣味をする非力な女性にも植えやすい植物でもあります。鉢植えにも適した4センチほどの球根であることから、室内で育てることも可能です。雪の溶けてきた時期に芽吹くことから、
花の最盛期は2~5月上旬までとなっています。この時期に芽吹く植物が少なく、しかもビニールハウスといった人工に育てる場所以外で自然に育成する植物が少ないことから、春の花として非常に珍重されています。多年生であるため、毎年同じ時期に同じ場所で花が咲くことも特徴です。
花を咲かせた後の夏は、また球根に戻って休眠と呼ばれる時期に入ります。高山植物であるため、日本の夏の高温多湿の環境は苦手です。土の中で涼しいところに置いて、過酷な時期を乗り切って、今度は秋という過ごしやすい時期を迎えます。
秋から冬は、球根に栄養を蓄える時期です。他の花や樹木が色づいて華やかな時期に、チオノドクサはじっと花をつけるために土の中で力を養っています。人間には過酷な冬を乗り越えて雪解けの時期に芽吹き、春の訪れを知らせてくれます。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:チランジアの育て方
タイトル:チゴユリの育て方
-

-
キウイフルーツの育て方
キウイフルーツは、中国にある長江中流地域の山岳地帯から揚子江流域を原産地とする植物です。1904年に中国からニュージーラ...
-

-
より落ち着いた雰囲気にするために 植物の育て方
観葉植物を部屋に飾っていると、なんとなく落ち着いた雰囲気になりますよね。私も以前、低い棚の上に飾っていましたが、飾ってい...
-

-
レウコフィラムの育て方
レウコフィラムという花は一昔前は珍しい花の一つでした。もともとアメリカのテキサスからメキシコにかけての原産の花で非常に乾...
-

-
アロンソアの育て方
この花については、ゴマノハグサ科、ベニコチョウ属になります。多年草になります。生息地である中南米においては多年草として知...
-

-
ウメモドキの育て方
ウメモドキは、日本の本州、四国、九州、そして中国原産の落葉低木です。モチノキ科モチノキ属に分類され、生息地は暖帯の山間部...
-

-
ヒノキの仲間の育て方
ヒノキは原産として日本と台湾にのみ分布する樹木です。アメリカにおいては似ているものとしてアメリカヒノキがあり日本にも輸入...
-

-
ベロニカの育て方
特徴として何の種類かですが、シソ類、シソ目、オオバコ科となっています。ルリトラノオ属に該当するともなっています。多年草と...
-

-
ユリオプスデージーの育て方
特徴として、キク科、ユリオプス属になります。南アフリカを中心に95種類もある属になります。園芸において分類では草花に該当...
-

-
アリウムの育て方
原産地は北アフリカやアメリカ北部、ヨーロッパ、アジアなど世界中です。アリウムは聞きなれない植物かもしれません。しかし、野...
-

-
カランセの育て方
カランセはラン科エビネ属の多年草です。日本が原産地となっているエビネ属の花もありますが、熱帯原産のものを特にカランセとよ...




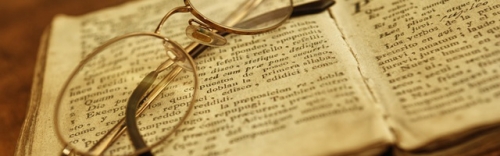





チオノドクサという植物は東地中海クレタ島やトルコの高山が原産で、現在ではヨーロッパの山々を生息地とする高山植物の一種です。ギリシャ語の雪を表す「チオン」と、輝きや栄光を表す「ドクサ」を組み合わせた言葉が示すように、ヨーロッパでは非常に古くから愛されてきた花となっています。