エンドウの育て方

エンドウを育てる前の準備について
エンドウを育てる場所は数年間野菜などを栽培していない場所を選んで、プランターで栽培する場合には少し深めの30センチの容器を用意します。直射日光から野菜を守ることが出来るように、日陰へ楽に移動することが出来る軽い素材のプランターを選びようにします。
土を購入する場合には野菜用やエンドウ用の培養土を選び、必要な成分がバランス良く含まれている土を購入するようにします。エンドウ用の培養土を使えば、必要な成分を手軽に取り入れることが出来ます。古い土を再利用する場合は1か月以上直射日光に当てて消毒をして、さらに古い土を再利用する液体や土を混ぜ込むようにします。
堆肥などの有機物と共に苦土石灰を少し多めに施して、pHの調整をします。排水が悪い場所では育て方にも影響を与えるので、高めに畝を作ります。野菜を鳥や害虫から守るためにも、ネット類を用意します。防虫ネットは土や株に害虫がつくのを防ぎ、エンドウにも大変有効です。不織布は、害鳥から守ります。豆類を育てるときには支柱が必要で、植え付けのときには仮支柱を取り付けます。植え付けや種付けのときに土に肥料が入っていない場合は、事前に肥料を混ぜ込んでおきます。
エンドウの育て方について
育て方の一番のポイントは、連作障害に注意することです。マメ科であるエンドウは野菜の中でも連作を嫌う品種なので、5年以上は野菜などを作ったことがない土地や土を選ぶことが大切です。種付けの時期は10月中旬ごろですが、寒い地域は10月の下旬、暖かい地域では10月の上旬に行います。植え付けも同じように、10月から11月ごろに行います。
生育の適温は10度から20度で、若い苗のうちは低い気温でも耐えることが出来ます。温度管理は難しいことはないですが、大株は真冬の気温に弱いので注意が必要です。冬越しをさせるためには10センチから20センチになるように、種付けの時期をずらして育てるようにします。早い時期に種付けを行うと大きくなりすぎるので、種付けや植え付けの時期には十分注意する必要があります。
一つの穴に対して3粒ほどの種を蒔いたり植え付けをして、発芽してから間引きを行います。エンドウは冬を越す野菜なので、敷き藁や黒いビニールマルチなどを使って寒さ対策をしておくことが大切です。春先を越えることが出来たら間引きを行い、株間30センチに対して1本になるようにします。
ツルが上手に伸びるように、ネットと支柱をセットしておきます。間引きした若い茎は食べることができ、中華料理などに応用することが出来ます。ここからだんだん膨らみ始めて、エンドウになるのです。
エンドウの栽培のポイントや育て方のコツ
エンドウは酸性の土に弱いので、石灰を混ぜてpHをきちんと調整することがポイントです。石灰を1平方メートルあたり150グラム、堆肥2キロと化学肥料120グラムを混ぜます。畝は60センチ幅で、高さ15センチに整えます。畝に40センチほどの間隔で穴を開けて、くぼみに3粒に種を入れて軽く土をかぶせるようにします。発芽したら育ちがいいものを2から3株だけ残して、間引きを行います。
本葉が3枚になったら、株元に土寄せをしておきます。また種を植えるのを早くしてしまうと上手く冬を越えることが出来ずに凍結してしまうので、必ず秋の時期に種まきや植え付けをするようにします。真冬の時期には冷え込みが激しくなるので、北側から西側にかけて、風よけのための柵を立て掛けておきます。プランターなどで育てている場合は暖かい場所に移動して、凍結を防ぐようにします。
栽培を始めてから冬を越し、2月ごろになったら1か月おきには追肥を行います。タイミングが分からないときは1回目はツルが伸びてきたら、2回目は花が咲き始めたら追肥を行うようにします。種付けや植え付けを行ったあとにはたっぷり水やりをして、表面の土が乾いたら水やりをするようにします。あまり水をあげ過ぎると根腐を起こすので、注意が必要です。さらにツルが伸びたら支柱を立てて、上手く誘導させます。
混み過ぎたら孫ヅルを摘み取るようにして、日当たりの妨げにならないようにします。ネットを使わない場合は両サイドに支柱を立てて、上手く誘導させてあげます。種まきから180日後が収穫の時期で、実が膨らみ始めたときに収穫します。上に向いている莢が下向きに垂れれば、収穫期です。遅い時期に収穫してしまうと皮が固くなってしまいますが、中の実は食べることが出来ます。
春先には葉に白い粉で線を描いたような模様があったら、ハモグリバエの幼虫なので注意が必要です。葉の表に潜って、葉を食い散らかした後がそのサインです。大きな穴を開けたりすることはないのですが、収穫に影響が出てしまうことがあるので薬剤を散布するなどして対策を行います。また食害を予防するためにも種まきのときに、薬剤を蒔いておいても予防することが出来ます。
エンドウの歴史
古代エジプトの王の墓から発見されたというエンドウは、地中海地方と中国が原産地や生息地とされています。日本には10世紀のころに穀物として伝わり、江戸時代になると野菜として知られるようになります。庶民に広く普及したのは、明治時代になってからです。スナックエンドウはグリンピースを莢ごと食べられるように品質改良したもので、1970年代にアメリカから伝わったのです。
人類は1万年前からエンドウを食べていたとされ、スイスの湖上住居の跡や新石器時代の農民からはエンドウを使った食事の残りが遺跡として発見されています。昔に食べられていたエンドウは固いでんぷん質のもので、現代のものとは全くの別物のようだったのです。丸ごと食べるのではなく、焼いたりしてから皮をむいて豆を食べていたのです。
中世では乾燥させて使うのが一般的で、長く保存したりスープやおかゆに使われていたのです。イングランド人の料理家も1660年に発表された自身の本で、エンドウを使ったスープのレシピを紹介しています。ミントの束と一緒に煮る調理方法で、でんぷん質の独特な淡白な味を和らげるためにミントが使われていたのです。
エンドウの特徴
えんどう豆には莢ごと食べることが出来る「さやえんどう」や熟してから莢をむいて食べる「グリンピース」、豆を乾燥させてから食べる「青えんどう」と「赤えんどう」があります。さらに「スナップえんどう」はグリンピースを莢ごと食べられるようにしたもので、莢が柔らかく甘みが強いのが特徴的です。主な栄養素はタンパク質と炭水化物で、ビタミンB群が豊富です。特にビタミンB1が多く含まれていて、疲労回復に効果的です。
カロテンや食物繊維も含んでいるので、血糖値の安定や老化防止にも効果があります。特にカロテンには発がん防止や動脈硬化の予防にも役立つので、生活習慣病などの病気の予防にもなります。品質改良して生まれたグリンピースにはタンパク質や糖質、ビタミンB群やビタミンCが含まれています。疲労回復だけでなく、肌荒れや風邪の予防にも役に立つのです。
栽培だけでなく輸入品も増えているので、年間を通して市場に出回っています。福島県や鹿児島県、愛知県産の出荷のピークは3月から6月です。炒めものや煮物に多く使われ、その色鮮やかな見た目で様々な料理に彩りを添えています。料理が引き立つ野菜として、幅広い料理に活用されているのも特徴的です。
エンドウ豆の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も詳しく書いてありますので、凄く参考になります♪
タイトル:スナップエンドウの育て方
タイトル:サヤエンドウの育て方
タイトル:つるありいんげんの育て方
タイトル:さやいんげんの育て方
-

-
ペンツィアの育て方
特徴としては、種類はキク科のペンツィア属になります。1年草として知られています。花が咲いたあとに種をつけて枯れますから次...
-

-
ネジバナの育て方
もともと日本では江戸時代に栽培されていた植物です。別称であるモジズリ(捩摺)は、かつて都で重宝された絹織物シノブズリ(忍...
-

-
カルーナの育て方
カルーナはヨーロッパや北アフリカなど、地中海の周辺に生息する植物です。カルーナという言葉は「掃く」という意味に由来します...
-

-
ワレモコウの育て方
この植物においてはバラ目、バラ科になります。ひと目見たところにはバラにはとても見えそうもありませんが、よく見てみるとたし...
-

-
タアサイの育て方
中国が原産となるタアサイの歴史は中国の長江付近となる華中で、栄の時代となる960年から1279年に体菜より派生したと言わ...
-

-
ショウジョウバカマの育て方
ショウジョウバカマは日本から南千島、サハリン南部を原産地とするユリ科ショウジョウバカマ属の多年草です。北は北海道から南は...
-

-
オニバスの育て方
本州、四国、九州の湖沼や河川を生息地とするスイレン科オニバス属の一年生の水草です。学名をEuryaleferoxと言いま...
-

-
アグラオネマ(Agleonema)の育て方
アグラオネマはアジア原産の熱帯雨林が生息地のサトイモ科の多年草です。インドから東南アジア、中国南部にかけて約50種類が生...
-

-
シネラリアの育て方
シネラリアはキク科の植物で、早春から春にかけての代表的な鉢花のひとつです。原産地は北アフリカの大西洋沖に浮かぶスペイン領...
-

-
シモバシラの育て方
学名はKeiskeaJaponicaであり、シソ科シモバシラ属に分類される宿根草がシモバシラと呼ばれる山野草であり、別名...




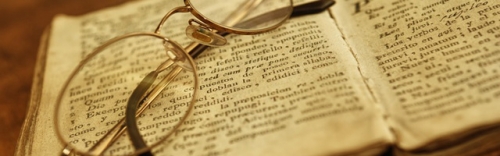





古代エジプトの王の墓から発見されたというエンドウは、地中海地方と中国が原産地や生息地とされています。日本には10世紀のころに穀物として伝わり、江戸時代になると野菜として知られるようになります。庶民に広く普及したのは、明治時代になってからです。スナックエンドウはグリンピースを莢ごと食べられるように品質改良したもので、1970年代にアメリカから伝わったのです。