葉ネギの育て方

葉ネギの基本的な情報
葉ネギを育てる上で、まずは基本的な情報を把握しておきましょう。葉ネギはユリ科の植物です。基本的な育て方はありますが、どちらかというと育ちやすいために、特に凝った育て方をする必要はありません。まず、日当たりの良いところで栽培するのが育て方の基本です。
暑さや寒さには強いですから、温度の変化によって生育が悪くなると言ったことは考えにくいでしょう。ただ、湿度には弱いという傾向があります。乾燥には強いですが、多湿になると少し生育が悪くなる傾向がありますから、栽培する場所を選ぶ際には、この点に注意しましょう。
栽培に適したPhは5.7から7.4となっていますから、ごく普通の土壌でも生育は可能ですし、必要であれば土壌のPhを改良することによって栽培できるようになるでしょう。発芽に適した温度は15度から25度くらいですから、かなり幅広いと考えられます。この範囲以外では発芽しに合いというわけではなくて、1度から3度くらいの低温でも発芽しますし、30度を超えても発芽することがありますから、地域によってはいつでも発芽できます。
収穫に適した時期を探すと言うよりも、十分に育てば収穫するというようにすれば良いです。葉ネギですから、50センチから60センチくらいまでに生育すれば、その時点で収穫をするのが良いです。小ネギとして用いることもできて、その場合にも20センチから30センチくらいになれば収穫するといった形で、時期を選ぶと言うよりは大きさで判断していけば良いです。
連鎖障害が指摘されていて、毎年同じ場所に同じものを植えていると育ちが悪くなってきます。ですから、収穫をすればすぐに種付けをするのではなくて、1年から2年は間隔を開けた方が良いです。1年から2年は別のものを植えるというようにして対応していきましょう。
葉ネギの種付けから収穫の時期
葉ネギは育ちやすく、栽培できる時期も長いですから、栽培時期によって違いがあります。どの時期に栽培しても良いわけですが、時期としては春まきと秋まきの二パターンが用いられることが多いようです。葉ネギは、春まきとと秋まきで時期が異なります。春まきの場合、3月から4月の間に種付けを行います。7月から9月には大きく成長して収穫できるようになります。
秋まきの場合、5月から7月くらいに種付けを行います。そして収穫は10月頃です。これが基本的なもので、どちらの場合にも大きく成長し、葉の部分の味を楽しむことができるでしょう。薬味用に小ネギとして栽培したいのであれば、3月から9月頃までに種付けをします。2ヶ月から3ヶ月くらいでちょうど良い大きさになりますから、収穫時期としては5月から12月の間になります。必要な時期に応じて種付けをすると良いでしょう。
葉ネギの育て方の注意点
葉ネギは酸性土壌に弱い傾向があります。ですから、土壌をややアルカリ性にしておくと良いのですが、そのためには苦土石灰を散布しておくのが良いです。種付けをする前に、苦土石灰をまいておくと、土壌の問題は解決されるでしょう。これをしなかった場合、生育が悪くなることがありますから注意が必要です。
苗床にはすじ蒔きをすれば良く、蒔けばすぐに発芽しますが、間引きは必要です。5センチくらいの大きさになれば、間引きを始める時期です。この時期には、密集している部分を少し間引いてやります。そして、10センチくらいになったときには、2センチから3センチの株間にすれば生育が良くなります。20センチから30センチくらいまで育ったら、畑に定植すると良いです。これも時期と言うよりは大きさで判断するのがよいですが、春まきの場合には5月から6月頃になるでしょう。
定植についてですが、これは深さ5センチから10センチくらいの溝を掘っていけば良いです。土をかけすぎないように注意しなければならず、葉が分かれている部分よりも下までに土をかけるようにしましょう。太さは調節でき、細くしたい場合には密集させて植え、太くしたい場合には間隔を開けて植えれば良いです。こうすることで好みの太さのものを選ぶことができます。
50センチくらいになれば収穫に適した時期だと言えるでしょう。このときには、根元から株ごと収穫するのも良いですが、繰り返し収穫したいのであれば、少し株元を残しておきましょう。3センチくらい残しておけば新しい葉が伸びてきますから、時期が良ければ何度か収穫することができます。
プランターでも十分に育ちますが、密集させすぎると育ちが悪くなります。一般的なプランターなら5ヶ所くらいに植え付けるのが基本で、密集しすぎていれば間引きをすると良いです。種付けをしてそのままにしている光景を見かけることがありますが、そのままにしておくと育ちが悪くて小さいものしか収穫することができません。間引きをして適当な株間にしてやれば、育ちは良くなります。
葉ネギの歴史
ネギの原産地はアジアの北部だとされています。元々の生息地はこのあたりで、中国の西部、あるいはシベリアあたりのものが栽培されるようになったは紀元前だと考えられています。栽培が始められたのは現在の中国あたりで、北部では白ネギが主に栽培されていたのに対して、葉ネギはどちらかというと中国の中部から南部だったと考えられています。その後、世界各国へで栽培されるようになります。
欧米にも広まりましたが、すでにタマネギが普及していたために、特別珍しいものではなく、タマネギの一つの種類として認識されていたようです。欧米では、どちらかというとタマネギがメジャーなものとなっていて、葉を食べるという文化自体はそれほど広がらなかったようです。
奈良時代になると、大陸から日本に伝えられ、そして平安時代にはすでに栽培がなされていて、この時期にはすでにポピュラーな野菜となっていました。たとえば九条ネギはその時代から京都で栽培されていたと考えられます。ネギという言葉は、根が広がりやすいということから名付けられたと考えられています。
葉ネギの特徴
葉ネギは、葉の部分を食べるのが特徴の一つです。葉の部分というのは、ネギの緑色の部分を指します。緑色の部分を薬味にするなどの方法で利用することが多く、関西地方では元々このように使われていました。光の当たった部分が緑色になりますが、この部分を増やすためには全体的に光を当てることが必要となります。光が当たると、光合成をするために緑色の色素が作られるのです。
白ネギは、色を緑にしないようにするために土寄せが必要となりますから、かなり手間がかかるのですが、葉ネギは土寄せの必要がありません。土寄せをすると、逆に緑色の部分が減ってしまいますから、むしろ土寄せをしてはいけないのです。この作業がありませんから、栽培するのに手間がかからないという特徴があります。この点は白ネギに比べるとメリットの一つだと言えるでしょう。
九条ネギや博多ネギなど、いくつかの品種があって、耐暑性や耐寒性はそれぞれで異なります。ですから、葉ネギを栽培しようと思ったときには、その地域で成長しやすい品種を選ぶのが良いです。こうすることによって、栽培に失敗しにくくなりますから、始めて栽培する人でも成功しやすいと考えられます。選び方は簡単で、栽培したい地域に近い場所で主に栽培されているものを選べば良いわけです。
野菜の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:タマネギの育て方
-

-
エボルブルスの育て方
エボルブルスは原産地が北アメリカや南アメリカ、東南アジアでヒルガオ科です。約100種類ほどがあり、ほとんどがアメリカ大陸...
-

-
ひまわりの栽培やヒマワリの育て方やその種まきについて
夏になると太陽の方向を向いて元気に咲くひまわりが目につきます。このひまわりを自分で育てることができます。ひまわりの栽培方...
-

-
ヒイラギナンテンの育て方
ヒイラギナンテンの原産地は中国や台湾で、東アジアや東南アジアを主な生息地としています。北アメリカや中央アメリカに自生する...
-

-
シロタエギクの育て方
シロタエギクの原産地は、地中海に面した南ヨーロッパの海岸地帯です。現在ではイギリス(連合王国)南部を含むヨーロッパの広い...
-

-
ユーフォルビアの育て方
ユーフォルビア、別名、ユーフォルビアダイヤモンドフロストは、トウダイグサ科ユーフォルビア属の植物です。生息地は世界の熱帯...
-

-
クコ(キホウズキ)の育て方
この植物はナス科クコ属の落葉小低木ですが、ナスの仲間ということで、その実からは何となく似ているかなという感じですが、色は...
-

-
バナナの育て方
バナナの歴史は非常に古く紀元前10000年前には既に人間に認知されており、栽培もされていたと言われています。現在我々が口...
-

-
ヤマイモの育て方
ヤマイモとナガイモは、よく混同されますが、まったく別の種類で、ナガイモは元々は日本にはなく、海外から入ってきた芋というこ...
-

-
ヤマジノホトトギスの育て方
ヤマジノホトトギスはユリ科の植物です。そのため、ユリのように花被片があり、ヤマジノホトトギスの場合は6つの花被片がありま...
-

-
花壇や水耕栽培でも楽しめるヒヤシンスの育て方
ユリ科の植物であるヒヤシンスは、花壇や鉢、プランターで何球かをまとめて植えると華やかになり、室内では根の成長の様子も鑑賞...




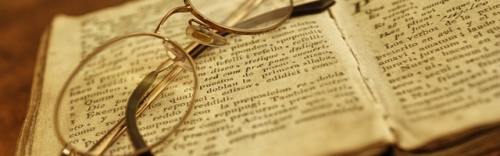





ネギの原産地はアジアの北部だとされています。元々の生息地はこのあたりで、中国の西部、あるいはシベリアあたりのものが栽培されるようになったは紀元前だと考えられています。栽培が始められたのは現在の中国あたりで、北部では白ネギが主に栽培されていたのに対して、葉ネギはどちらかというと中国の中部から南部だったと考えられています。その後、世界各国へで栽培されるようになります。