サンダーソニアの育て方

育てる環境について
サンダーソニアは球根から育てる園芸向きの植物であり、大きくなっても50~70センチ程度です。そのため園芸に向いている植物であると言えるでしょう。南アフリカの植物と言うこともあり、日本の気候に必ずしも順応しておらず、寒さや暑さにはやや弱いという傾向があります。
そのため栽培には中程度の難易度があると考えておくと良いでしょう。開花の時期は6月から7月が基本にはなりますが、室内での栽培等温度調節が出来るのであれば球根を植える時期を調節することで開花時期を変えていくことは可能です。
そのためかなり自由に楽しむことが出来る花であると言えるでしょう。サンダーソニアで注意したいのは高温と過湿です。これらの環境には弱いため、夏の時期は半分日陰で管理したり、水やりも表面の土が乾いてからにするなどの配慮をすると良いでしょう。
花が咲いた後は球根が取れますが、秋に掘り上げた球根の場合はまず乾燥させた上で冬を越させるとよいでしょう。その際に注意しておきたいのはあまり暖かい部屋で保管しないようにすることです。およそ10度くらいの温度の場所で保管することで健全な状態が維持され、
春に植えた時に芽吹きやすくなります。保管している間にあまりに暖かい環境に置き続けていると春になっても芽吹きにくくなってしまうという特徴があります。植物であっても寒暖のメリハリが付いた方が動きやすいという事情があるのかもしれないと思わせる特徴です。
種付けや水やり、肥料について
サンダーソニアの植え付けは3月から5月にかけて行います。球根の先端から芽が出ますので、その部分を下にして植え付ければよく成長するでしょう。植える時点でどう芽が出るかわかりにくい場合には寝かせて植えておくとよいでしょう。その様に置くことが結果的にはい方向に働くことが期待できます。
早く芽を出させようとする場合には、3月頃に湿らせたバーライトに球根を埋めてビニールで覆い、室内の日当たりのよい場所で可能な限り暖かい環境を維持してあげると良いと言われています。この様な調整によって開花時期をある程度コントロールできるのもサンダーソニアの魅力の一つであると言えるでしょう。
水やりに関してはあげ過ぎないことも重要です。庭に植える場合にはほとんど必要はないと言えるでしょう。鉢植えの場合には土が乾いてきたら十分に上げることが必要となりますが、葉が黄色くなってきたらあげ過ぎですので水やりをやめて土を乾かす必要があります。
肥料に関してはかわいらしい花を多く咲かせたい場合には必要になります。4月から6月にかけて液体肥料を施すことが推奨されます。サンダーソニアは暑さにやや弱い特徴がありますので夏になると成長が衰えます。
そのため猛暑になる前の段階で十分な肥料を上げて育てていくと良いでしょう。その意味では肥料を必要とするのは短期間であると言えます。庭に植える場合も同様であり、比較的涼しい時期に球根を大きくさせる対応が求められます。
増やし方や害虫について
サンダーソニアは球根を使って増やす方法と種を使用する方法の二種類で増やすことが出来ます。種まきをする場合にはまずは種を入手しなければなりませんが、冬の時期に寒さに晒しておかなければ目が出ないという特徴がありますのでその点に関しては注意が必要です。
秋に戸外にまいておけば春には芽吹くと言った感じになるでしょう。しかしながら種を使用した増やし方は種の入手が容易ではないためにあまり一般的ではありません。それよりも文久による増やし方が主であり、3月から5月にかけて良く成長した球根を見ると茎を、
中心として二又に分かれへの字になるのが一般的です。この球根を折れ曲がった部位で切り分けてに建つにすることが出来るのです。芽は茎であった方向とは別の方向から出てきますので、向きに気をつけて植えておけば立派に成長するでしょう。
育て方について病気や害虫の心配をする必要があるのが一般的ですが、サンダーソニアに関しては病気の心配はほぼありません。その代わり害虫には相応の注意が必要となります。具体的にはアブラムシとナメクジが害虫であり、早めに防除することが必要になります。
アブラムシは春先に、ナメクジは梅雨時に出てきますが、小さな新芽や花芽を好んで食べてしまいますので適切に処理しておかないと鼻を楽しむことが出来なくなってしまいます。ナメクジは日中は隠れていて夜になると出てくる性質がありますので夜に見回ると見つけやすいでしょう。
サンダーソニアの歴史
サンダーソニアは南アフリカのナタール地方で発見された花で、1851年に発見されたイヌサフラン科の多年生植物として伝えられています。非常に特徴的な花を持つ品種ですが、品種改良による多品種の製造は行われておらず、一種類しか存在していない花として知られています。
またサンダーソニアの名前の由来は発見者であるジョン・サンダーソンにちなんで名づけられたものであり、日本でも人気の高い種類になっています。その後、日本に入ってきたのは比較的最近であり、1980年代以降に球根がニュージーランド経由では言ってきたのが栽培の始まりであるとされています。
葉の先には巻きひげがあり周囲の物にからみついて上に伸びて行く性質があります。風鈴の様な形であることからクリスマスベルと呼ばれることもありますし、英名にはチャイニーズランタンリリーと言う名称も使われるようになってきています。
花言葉は「愛嬌」「祈り」「共感」「望郷」「祝福」「福音」「純粋な愛」であり、贈り物にも用いられる花として広く普及しています。原産地である旧ナタール共和国では開発が促進しており野生での花を見ることはやや困難になってきています。
しかしニュージーランドを中心として栽培は盛んにお粉輪rているため、生け花やフラワーアレンジメントの素材として非常に高い人気を博しています。そのため主要な消費国としての日本の存在感は非常に大きなものがあると言えるでしょう。
サンダーソニアの特徴
サンダーソニアはオレンジ色の花を提灯の様に咲かせる花であり、つやつやとした葉の間に堂々とぶら下がる様が非常にかわいらしいと人気があります。鮮やかなオレンジ色と葉の緑のコントラストが美しく、観賞用の花として人気があります。
南アフリカのトランスバール南東からスワジランド、ナタール、ケープ東部当たりを生息地としている植物であり、南アフリカ原産の植物として知られています。サンダーソニア属の植物の種類は非常に狭く、サンダーソニアオーランティアカと呼ばれる一種類しか存在していません。
地中に細長い指の様な形状をした塊茎を作る性質があり、そこから芽を出す仕組みの植物です。そのためその部分を傷つけてしまうと目がでなくなってしまうという特徴がありますので栽培をする場合には注意をしなければならないと言えるでしょう。
誤って傷つけてしまうだけでも育たなくなってしまうという繊細なものであると言えます。春に目を出して花を咲かせたら秋には球根として流通するようになりますが、植え付けの時期をずらすことで開花の時期を調節することが可能な花であるために1年を通じて栽培することが可能です。
サンダーソニアの特徴的な魅力を飾り花としたい人には嬉しい特徴であると言えるでしょう。なお、この花は食用にはなりません。特に球根にはコルヒチンが含まれていますので誤って食べてしまうと中毒を起こしてしまうことが知られています。その点は注意が必要です。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:チゴユリの育て方
タイトル:ジニアの育て方
タイトル:シーマニアの育て方
-

-
ハベナリアの育て方
ハベナリアはラン科の植物で、草丈は15cmから60cmほどになります。洋ランの中でもその品種が非常に多い植物でもあります...
-

-
トックリラン(Beaucarnea recurvata)の育...
トックリランは、スズラン亜科の常緑高木でトックリランという名前は、幹の下部が徳利のような形に膨らんでいることが由来してい...
-

-
ディサの育て方
ディサは、ラン科ディサ属、学名はDisaです。南部アフリカを中心とした地域が原産で、そのエリアを生息地としている地生ラン...
-

-
シュウメイギクの育て方
シュウメイギクは中国が原産とも言われています。中国では根を解毒・解熱に使用されてきました。日本でも古くから本州、四国、九...
-

-
サギゴケの育て方
サギゴケは日本を原産とする多年草です。本州、四国、九州などが生息地です。日本以外だと、台湾や朝鮮半島南部で見ることができ...
-

-
ほうれん草の育て方について
ほうれん草は日常の食卓にもよく出てくる食材なので、家庭菜園などで自家製のほうれん草作りを楽しんでいる人も少なくありません...
-

-
スイスチャードの育て方
スイスチャードという野菜はまだあまり耳慣れないという人が多いかもしれません。スイスチャードはアカザ科で、地中海沿岸が原産...
-

-
マダガスカルジャスミンの育て方
一般的なジャスミンはモクセイ科になります。キンモクセイなどと同じ仲間です。同じような香りをさせています。一方この植物に関...
-

-
ナツメ(実)の育て方
この植物は繁殖している地域も、日本中何処ででも見られますので、その点でも栽培では、初心者に適していますが、味の方も食べる...
-

-
ヤマハギの育て方
植物の中には生息地が限られている物も珍しくありません。しかしヤマハギはそういった事がなく、日本全土の野山に自生しています...




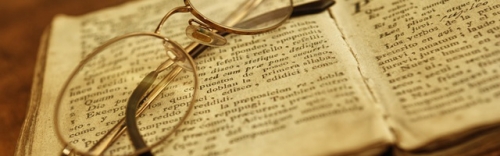





サンダーソニアは南アフリカのナタール地方で発見された花で、1851年に発見されたイヌサフラン科の多年生植物として伝えられています。非常に特徴的な花を持つ品種ですが、品種改良による多品種の製造は行われておらず、一種類しか存在していない花として知られています。