サギソウの育て方

サギソウの育てる環境について
サギソウは日当たりの良い場所を好み、光が不足してしまうと葉が黄色くなることがあるため、一年を通して日が当たる風通しの良い所で管理します。ただし日差しの強い夏場は、ネットなどを利用して30%位まで遮光しておきます。気温が30度以上になる猛暑日には50%以上遮光するようにして、
高温で蒸れないように気をつけます。花が開いている時は夕方の日差しに花をあてないようにすると長持ちします。冬になって気温が下がると表面の葉や茎は枯れてしまいますが、凍結や霜が降りないように気をつけて室内で管理して、球根を越冬させます。
表面の枯れた部分は丁寧に取り除いて、乾燥しすぎないように冬の間も球根に水やりを行います。球根の耐寒温度はマイナス3度ほどで、比較的寒さには強い方ですが凍らせないように注意して、気温が下がりそうな時は段ボールや発泡スチロールの箱などを利用して防寒対策をしておきましょう。
サギソウは湿地帯に生息する植物なので、植付け用の土は保水性の高い水ごけを使用します。水ごけは痛みやすい性質があるので、植え替えする時に取りかえるようにしてください。悪くなった水ごけをそのまま使用し続けていると球根が痛んで枯れてしまうことがあります。
水ごけと土と混ぜて使うときには、赤玉土や鹿沼土などの通気性の良い土を混ぜて使うようにしますが、水ごけだけで栽培しても問題はありません。乾燥に弱いので、水ごけが乾かないように確認しながら水やりをします。
サギソウの種付けや水やり、肥料について
サギソウの植付けは鉢に2cm位間隔を空けて球根を植えます。1cmから2cmほどの厚さに土をかぶせて、土が乾かないように気をつけて風通しの良い場所に置きます。植付けは1月から3月くらいの時期に行い、鉢はあまり深くない物を選びます。水ごけが傷んだりして植え替えをする場合は、
葉が枯れてから行うようにします。11月から4月くらいの時期が適していて、それ以降でも植え替えはできますが、葉が出ている時に行うと根などを傷つけるおそれがあるので注意してください。発芽してきたら日当たりの良い場所で管理するようにします。
水は切らさないようにして、表面の水ごけが完全に乾かないうちにたっぷりと水を与えるようにします。夏は水切れをしやすいので水ごけの様子を見ながら、朝夕の1日2回水やりを行います。ただしいくら水が好きな植物といっても、過度に水を与え過ぎてしまうと枯れる原因になってしまうため注意してください。
暖かい地域では水ごけが腐りやすくなるので、土の分量を多くしておくと手入れがラクになります。サギソウは肥料がなくても育ちますが、球根を大きくしたり花付きを良くするために与えるようにします。
開花前の5月と6月に液肥を2000倍~3000倍に薄めた物を月1回与えます。水ごけよりも土が多く使っている時には1000倍以上の濃度にしておきますが、肥料を多く与え過ぎてしまうと却って弱ってしまうこともあるので、適量を与えるようにしてください。
サギソウの増やし方や害虫について
サギソウは球根から地下茎が伸びて、その先に新しい球根が育ちます。環境や条件が揃っていれば1年でおよそ2~3個の球根が採取できます。新しくできた球根は、植え替えの時期に取り分けて新しい鉢に植えます。よく発生する害虫に、ナメクジがあります。
ナメクジはサギソウの葉やつぼみ、花ばかりでなく水ごけや球根まで食べてしまいます。ナメクジが多く発生する時期は3月から11月になり、湿気ある場所によく出てきます。駆除には誘発剤を使ったり薬剤を散布するなどの方法があり、
ナメクジが好むチャービルなどのコンパニオンプランツを近くに植えておき、そちらに誘導しておく対策もあります。病気ではウイルスにかかりやすくなっていて、この場合はカビや細菌などで感染する病気と異なり、薬剤などでは対処できません。ウイルスに感染してしまうと、
生育が遅くなり茎がねじれ、葉がまだら模様になったり縮れて小さくなってしまうといった状態になります。感染した株を見つけた場合は、ただちに抜きとって処分するようにします。ウイルスは軽く触れたり同じ道具を使うだけで簡単に他の株に感染してしまうので、
発症を防ぐことは難しく、自生のものや市販のものでも多くの株がウイルスを所有しています。株が健康な状態であれば、ウイルスの症状が強く出てきて枯れてしまうことも少なくなるので、日常の管理に注意を払って栽培していくことが、ウイルスの症状を抑える有効な手立てになります。
サギソウの歴史
サギソウはラン科サギソウ属サギソウ種の多年草で、日本や台湾、朝鮮半島が原産となっています。日本では北海道や青森などを除いた地域の湿地が生息地になり、自生地では個体数が減少しているため、環境省によってレッドリストに指定されています。
地域によっては野生種が絶滅してしまっているところもあり、湿地帯などで自生しているサギソウを見つけたとしても採取は禁止されています。サギソウの名前の由来は花びらが翼を広げたシラサギに似ていることから名付けられました。シラサギは日本ではとてもなじみ深い鳥になり、
浮世絵などの日本画でも描かれています。1992年は発行された平成切手では、日本国内の自然をテーマとした図柄が使われ、190円切手にサギソウが描かれていましたが、この切手は現在では販売終了となっています。サギソウの栽培の歴史は古く、
1965年の江戸時代に伊藤三之丞によって書かれた園芸書の花壇地錦抄(かだんちきんしょう)には、鑑賞用の花としてサギソウの育て方が記載されています。また明治から昭和にかけて活躍した俳人の高浜虚子はサギソウをテーマとした句を詠んでいて、希少種となった現在と比べて、
当時の人たちにとってはサギソウはとても身近な植物でした。大正時代ごろまでは東京都内でも田んぼなどの湿気の多い場所に咲いていたのですが、都市開発が進み、田んぼや湿地帯が少なくなってくるとサギソウの生息地も限られるようになり、数自体も減少してしまったのです。
サギソウの特徴
サギソウは蘭の一種でありとてもデリケートな植物で、花が咲いても4日から5日で終わってしまいます。茎はまっすぐと伸びて、草丈は20cmから大きい物では50cmほどになり、茎の先端に直径3cmほどの糸状の切り込みが入った白い花が咲きます。
ホームセンターや園芸店などで購入できて、花の色は白のみになりますが、葉は単色のものと白や黄色などの斑が入る品種などがあります。サギソウにはたくさんの品種があり、市場に多く流通している銀河・飛翔、香りの良い武蔵野・香貴、黄味がかった斑の入る金星・輝、散り斑種の、
天の川・残月、大きな花を咲かせる玉竜花・雅、形の変わった飛翔・おぼろ月など、それぞれ花の切り込み具合や開花の時期などが微妙に変わってきます。サギソウの主な開花時期は7月から9月までになるので、花が咲き終わったらこまめに花がらを摘むようにすると、
養分が他の茎にまわるため次の花が咲きやすくなります。爽やかな印象を与える白色と細かく切り込みの入った花びらがとても涼しげな印象をあたえるため、暑い時期の鑑賞用の植物として最適です。乾燥に気をつけて水分量を保っておくようにします。
学名は「Hebenaria radiata」(ハベナリア・ラディアタ)、英名は「egret flower」(イーグレットフラワー)または「white egret flower」(ホワイトイーグレットフラワー)「fringed orchi」(フリンジドオーキッド)などと呼ばれます。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:サンダーソニアの育て方
-

-
インドゴムノキ(Ficus elastica)の育て方
日本でも一部の温暖な地域では戸外で育ちますが、寒冷地では鉢植えで育てます。ミニサイズの鉢から大型のものまで、様々な趣のあ...
-

-
ヘゴの育て方
ヘゴ科ヘゴ属のシダ植物です。野生種は最大7〜8m近くにまで伸びる熱帯性の植物です。日本では一般的には沖縄や鹿児島などの南...
-

-
トキソウの育て方
ラン科トキソウ属の山野草です。和名は朱鷺草(トキソウ)で、別名には朱鷺蘭(トキラン)などがあります。日本の本州や北海道を...
-

-
アデニウムの育て方
アデニウム/学名・Adenium/キョウチクトウ科・アデニウム属です。アデニウムは、南アフリカや南西アフリカなど赤道付近...
-

-
ブラサボラの育て方
ブラサボラはカトレアに近い仲間でカトレア属やレリア属などの交配にも使われる植物で原産地は中央アメリカやカリブ海沿岸、南ア...
-

-
サクラソウの育て方
サクラソウとは、サクラソウ科サクラソウ属(プリムラ属)の植物で、学名をPrimula sieboldiiといいます。日本...
-

-
雲間草の育て方
日本の園芸店で市販されている雲間草は、一般的に「西洋雲間草」、「洋種雲間草」と呼ばれているヨーロッパ原産のものです。元々...
-

-
びわの育て方
枇杷(ビワ)は、中国南西部原産で、バラ科の常緑高木です。日本には古代から持ち込まれています。インドにも広がっており、非常...
-

-
コバンソウの育て方
コバンソウはイネ科の植物で、大振りの稲穂がしなだれているような姿をして居ます。四月の終わりから七月ごろにかけて徐々に開花...
-

-
ヘレボルス・アーグチフォリウスの育て方
特徴としては花の種類として何に該当するかです。まずはキンポウゲ科になります。そしてクリスマスローズ属になっています。属性...




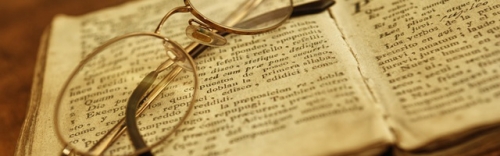





サギソウはラン科サギソウ属サギソウ種の多年草で、日本や台湾、朝鮮半島が原産となっています。日本では北海道や青森などを除いた地域の湿地が生息地になり、自生地では個体数が減少しているため、環境省によってレッドリストに指定されています。