ナスの育て方

ナス栽培のための土作り
どのような野菜でも土の中に根を張るので、根を広く土中に伸ばすためにも深く畑を耕すことです。深く土を耕せば柔らかさが増し、大きなすき間を増やすことが出来ます。空気をたくさん含むすき間を作ることで自由に根を張ることができ、ナスの生育にも良い影響を与えるのです。
畑を作る場所は日当たりが良い場所を選び、数年以上前にナスを植えた場所か、一度も植えたことがない場所を選びます。ナスは同じ畑で連続して栽培すると生育に影響を与え、枯れてしまう可能性があります。以前に寄生していた病害虫が土の中に残るので、同じ種類の野菜を植えないように注意します。
粗起こしのときには堆肥や苦土石灰を多めに混ぜて、酸性濃度を調整します。幅が12センチの畝を立てて、早く栽培したい場合には一度雨が降ってから黒ポリマルチをして、土の温度を高めておくことが大切です。種付けをする場合は苗になるまでに時間が掛かるので、早めに準備します。
種付けから苗になるまで約80日程度かかるので、早めに蒔いておくことが大切です。初心者や植え付けから時間がない場合は、種付けは行わずに苗から育てるようにします。苗から育てるためには、苗を購入してから3日間日当たりの良い場所で慣れさせてから植え付けをします。
植え付け用の穴は大きめに開けて、根鉢の表面が見えるくらい浅く植えるようにします。植え付けをしたらたっぷり水やりをして、株元を落ち着かせて仮の支柱を立てておきます。仮の支柱を立てておけば、苗が倒れることを防いでくれます。
ナスの育て方
ナスの育て方のポイントは、水やりです。乾燥に弱い野菜なので、水やりはたっぷり行うようにします。暑さには強いので、乾燥に注意することが大切です。夏場の時期には乾燥を防ぐために、藁を敷いておくと乾燥を簡単に防ぐことが出来ます。
水やりのタイミングは土の表面が乾いてきたら、十分に水を与えるようにします。夏場は土の温度が低い早朝に、かん水をするのがポイントの一つです。たっぷりの水を与える必要があるので、土が剥げてきてしまったら上から新しい土を被せるようにします。
整枝や誘引は1番花が開花したころに行い、主枝と1番花の下から出てくるわき芽とそれぞれから出てくるわき芽を選んで、3本から4本仕立てにします。選んだわき芽より下の側枝は早めに取り除いて、3本から4本の主枝から出てくる側枝は第1花の上の葉を全て摘心します。
さらに第2、第3のわき芽も取り除いて、4本の主枝は150センチ以上に延びたら摘枝します。嫡花は成長の様子を見て、摘み取るか判断します。生育が悪いときには様子をみて、1番花は摘み取って負担を軽減させます。収穫するときには基部2節まで切り戻して、第1葉に残しておいたわき芽が伸びている場合は花の上の葉を残して摘心します。
側枝が長くなってしまった場合は風通りが悪くなってしまうので、注意する必要があります。追肥は種付けしてから苗になり、苗を植えてから1か月間は必要なく、1番花が膨らみ始める時期に行います。定植してから1か月程度経ったあとに、株の周りに肥料を蒔きます。ナスは肥料をたくさん必要とする野菜なので、肥料切れを起こさないためにも実をつけ始めたら定期的に追肥をします。
栽培や育て方のポイントや注意点
育て方のポイントは、インドが原産地のため日中の温度が20度以上になったら植え付けを行うようにすることです。高い気温が安定してから、夜の時間帯でも15度以上の高温多湿の時期に育てるようにします。苗を選ぶときには茎が太くて、節間の詰まった苗を選びます。植え付けをするときは無風で、気温が高い時期に行うことがポイントです。
ナスは害虫に好かれやすいので、定期的に薬剤を散布するようにします。夏の時期に葉っぱが黄色くなるのはハダニで、葉の裏から水やりをして吹き飛ばすようにします。水やりをしても居なくならない場合には、薬剤を使って対策を行います。葉っぱを食べられてしまったら、すぐに散布しておくことも大切です。
葉の裏や茎を注意深く見て、害虫を発見したら対策を行うようにします。育てている最中は人間が日焼けするくらいの日光を必要とするので、長時間強い光が当たっている場所で育てるようにします。出来るだけ古い葉は取り除いて、葉で影が出来ないようにしておきます。水や肥料を十分に与えているのに元気がないときや、収穫量が低いときは日光が原因と考えます。
プランターで栽培している場合は場所を移動したり、工夫する必要があります。畑の場合は移動することが出来ないので、何か遮っているものがないか注意して観察することが大切です。収穫は花が咲いてから2週間から3週間後に行って、丸みを帯びていたら収穫するようにします。いくら待っても大きくならないものは諦めて、早めに収穫することが大切です。他の実に十分な栄養を与えるためにも、大きくなったら早めに収穫するようにします。
ナスの歴史
インドが原産の植物といわれ、中国でも古くから伝わる植物でもあります。栽培の歴史は数千年を超え、農業に関する世界最大の古典である斉民要術には栽培方法や採種方法などが詳しく記載されているほどです。インドが生息地と言ったのはスイス人の男性で、1886年に栽培植物の起源という本の中で明言しています。
ローマ人やギリシャ人はナスのことを知らず、ヨーロッパの植物学者もナスのことを知らないけれど、インドでは古くから栽培されていたと言っているのです。この本がきっかけとなり、インドが原産地という説が広まったのです。それからヨーロッパでナスの栽培が始まり、13世紀になってようやく栽培されるようになったのです。それまでのヨーロッパでは鑑賞用に作られ、17世紀になって食用になったのです。
日本に伝わったのはかなり古い時代で、最古の記録では東大寺正倉院文書に天平勝宝2年にナスが献上されたという記録があります。この記録によって、日本では奈良時代に食べられていたことが分かるのです。
ちなみに正倉院文章ではナスのことを、なすびと書かれています。平安時代になってもなすびとして記録され、宮廷に置ける規則や風習を記している文書には畑でなすびやきゅうり、ねぎが作られていたとされています。栽培方法だけでなく、漬物の作り方など加工についても記載されています。
ナスの特徴
植物学での分類では、被子植物門のナス科に所属している潅木性多年草です。日本で栽培すると草ですが、熱帯地方では木に実がなるのが一般的です。日本では栽培の歴史がとても長いので、各地方に色々な品種が残っているのが特徴です。海外のものと比べると色は紫色で実の部分は白ですが、形は様々です。
加茂のように大きいものから東北の小なす、また大根のように細長い長なすもあります。用途や使い方に合わせて品質改良がされて、様々な品種が残っています。現代では一年中なすを手に入れることが出来ますが、秋冬は施設で作られたものや夏秋は露地で作られたものが占めています。
なすの旬は夏の季節である6月から9月で、この季節のなすは味がよく、値段が安いのが特徴です。煮たり焼いたり、炒めたりと幅広い料理に応用することが出来るのも大きな魅力です。カロリーも低く油を吸収しやすいので、ダイエットにも効果的です。油となすは味覚的にも相性がいいので、ダイエット中でもカロリーを気にせず食べることが出来るのです。
-

-
ミントブッシュの育て方
シソ科の常緑低木の中でブッシュ状に茂る植物がミントブッシュであり、固有の原産・生息地となるのが豪州いわゆるオーストラリア...
-

-
タアサイの育て方
中国が原産となるタアサイの歴史は中国の長江付近となる華中で、栄の時代となる960年から1279年に体菜より派生したと言わ...
-

-
レウカデンドロンの育て方
「レウカデンドロン」は、南アフリカ原産の常緑低木で熱帯地域を中心に広く自生しています。科目はヤマモガシ科レウカデンドロン...
-

-
リカステの育て方
この植物の特徴としては、キジカクシ目、ラン科、セッコク亜科になります。園芸の分類においてはランになります。種類としてもラ...
-

-
ミニカボチャの育て方
ミニカボチャをはじめとするカボチャの原産地は、インド地方やナイル川の沿岸地域、南米大陸北部のペルー、アンゴラなど様々な学...
-

-
ユキモチソウの育て方
ユキモチソウ(雪餅草)は非常にユニークな花を咲かせます。名前からも分かるように、真っ白な平皿に真っ白な餅が載せられている...
-

-
キアネラの育て方
キアネラの特徴について書いていきます。キアネラの原産地は南アフリカを生息地としています。ケープ南西部に9種のうち8種が生...
-

-
サボテンの育て方
サボテンといってもその名前が指す種類はとても幅広いです。一つ一つ特徴も異なることでしょう。しかし、一般の人々がサボテンと...
-

-
野菜の栽培野菜の育て方野菜の種まき様々な方法があります
野菜の栽培といえば、日本で一番多く栽培されているのは、主食のコメでしょうか。野菜の育て方で調べてみると、多くの情報には、...
-

-
クサギ(ソクズ)の育て方
こちらは被子植物、真正双子葉類です。シソ目、シソ科に該当します。クマツヅラ科に該当するとの話もあります。栽培上においては...




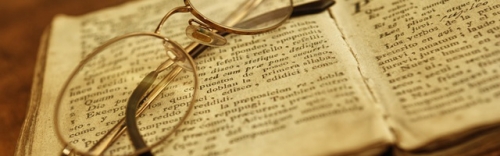





インドが原産の植物といわれ、中国でも古くから伝わる植物でもあります。栽培の歴史は数千年を超え、農業に関する世界最大の古典である斉民要術には栽培方法や採種方法などが詳しく記載されているほどです。インドが生息地と言ったのはスイス人の男性で、1886年に栽培植物の起源という本の中で明言しています。