ケストルムの育て方

ケストルムの育てる環境について
ケストルムは開花をしている期間が比較的長いのですが、基本的には日陰の土地で育つ植物なので、強い日差しの中で放置すると花の咲いている期間が短くなるなどの悪影響があります。基本的には寒さに弱い植物なのである程度の寒さならば耐えることができるのですが、
非常に寒い土地で育てることは難しいとされています。また湿った土を好むので、乾燥する土地を避けるようにして植えると元気に育ちます。冬に関しては注意が必要で北風が長い時間当たり続けてしまうと生育環境が悪化してしまいます。
また熱帯の植物なので日当たりの良い場所で育てるのが基本なのですが、日陰でも十分に育つので霜や寒さに注意をするだけで育てる環境は十分に整えることができます。ケストルムはアメリカの熱帯地帯で自生している植物なので暑さには非常に強いのですが、
寒さに関してはある程度までは耐えることができるのですが、日本の北海道や東北地方などの寒冷地の寒さに関しては耐えることが難しいとされているので、鉢植えの場合には太陽が出ている時間には外に置いて、寒くなりそうな場合には家の中に置くなどの工夫が必要となります。
また種類によっては生息地が異なっているのですが、すべて熱帯地帯の国々が原産国となっているので、乾燥には強いのですが、霜などの冷たい水分を含んでいる土壌には弱いので、注意が必要です。とくに冷たい北風が当たる場所に置いてしまうと地中の水分が冷やされて霜になるので、避けなければなりません。
種付けや水やり、肥料について
ケストルムは基本的には熱帯地方で自生している植物なので庭に植えている場合には水やりをする必要は全くありません。しかし植え替えをした場合には水分を必要とするので必ず水を含んでいる土を使う必要があります。鉢植えで育てている場合には根が吸収している栄養素や水分には限度があるので、
土の表面が乾いた時には多めの水分を与える必要があります。また冬に関してはあまり水分を与えてしまうと地面が冷えてしまう場合があるので、乾燥状態で維持することが良いとされています。植え付けや植え替えをする場合には古い土を3分の1程度入れ替えてから新しい土を足すのですが、
比較的暖かい時期の5月から6月に行うのが良いとされています。肥料に関しては窒素、リン酸、カリが同じ割合で含まれているものを使ったり、リン酸が多めに含まれている置き肥を使う方法などがあります。生育期にこれらの肥料を与えることで開花の時期に美しい花を咲かせることができます。
また開花の時期が非常に長いのですが、花に水を与えることで根腐れや葉の変色などを引き起こすことがあるので、水やりのし過ぎには注意が必要で、吸収することができない水分による弊害を考えるとある程度乾燥してから水分を与えることが重要です。
熱帯地方で自生している植物は昼間の暑さに非常に強くできているので、ある程度乾燥したとしても悪影響はほとんどありません。しかし熱帯地方では土地が湿って、霜が降りるなどの現象は起きないので、植物にとっては大敵となります。
増やし方や害虫について
増やし方に関しては枝を5センチ程度に切って、それを赤土などの土地に挿すことで自然に生育していきます。季節的には4月から9月の比較的暖かい時期が良いとされていて、あまり寒い季節に枝を地面に挿しても失敗してしまう確率が高いので、
熱帯地方の植物であることを考慮して増やすことが重要です。害虫としてはアブラムシやカイガラムシであるとされていて、アブラムシは直接被害としては新しく出てきた芽や葉の裏側に寄生することで、栄養分を吸い取ってしまうので生育環境が悪化する恐れがあります。
アブラムシは1匹だけの場合にはなんの心配もないのですが、数が多くなってくると葉が変色してしまうなどの影響が出てくるので注意が必要です。また関節被害としてウイルス病などを媒介することも知られているので、見つけたら早めに駆除をする必要があります。
駆除をするための薬剤はホームセンターなどで手に入れることができるので、それらを使うと駆除することができます。カイガラムシは直接的には茎の部分から栄養分を吸い取ることで生育に悪影響を及ぼすので、数が増えてしまうと枯れてしまう場合があります。
間接的な被害としては排泄物に細菌が繁殖してしまうことですす病になって光合成ができなくなるので、生育が著しく悪くなることがあります。カイガラムシにはいろいろな種類があるのですが、茎などに白い斑点や赤い斑点などが付着している場合は駆除を考える必要があります。
ケストルムの歴史
ケストルムはアメリカの熱帯地帯でよく見られる常緑樹でその中でも園芸用の品種として栽培されているのは10種類程度であるとされています。基本的には原産地はメキシコやチリ、西インド諸島などの熱帯の地域であるとされていて、それらの国々からアメリカの熱帯地域に広まったと考えられています。
なかでもヤコウボクとキチョウジが有名で世界で最も普及している品種となっています。その他にもメキシコ原産のものやチリ原産のものがありますが、日本国内には大正時代に渡来してきたと考えられています。ケストルムに限って言えば熱帯アメリカを原産地としているので、
アメリカから世界に広まったと考えられているのですが、この地域は南米の国々と比較的近いことから、種子が風などに運ばれたり、様々な輸送手段を使うことで種子が運ばれてそれぞれの国で自生していると考えられています。ケストルムは西インド諸島ではヤコウボクという種類が有名で、
樹木の高さは3メートルほどになる低木です。夜になると芳香を周囲に放つことからヤコウボクと呼ばれていて、グアテマラなどにもキチョウジという品種が自生しています。この品種は樹木の高さが1.5メートルほどの低木となっていて、
つるのある低木なので他の品種と少し異なっている特徴があります。花の色はオレンジ色で果実は小さな白いナスにような姿をしていて、この品種は明治初めの日本に渡来してきたとされていて、この時期から栽培が始められたという歴史があります。
ケストルムの特徴
ケストルムの特徴としては小さな白い花の形状などがあるのですが、これは日本ではナスなどに似ているとされています。もともと熱帯地帯で自生している品種なので暑さには強く、寒さや乾燥にも比較的強いことから園芸用に品種改良されて世界各地の愛好家に楽しまれているのですが、
霜や凍結に弱いという性質があるので、日本の寒い地域で栽培する場合には生育環境に注意が必要です。寒さや乾燥に強いとしても熱帯に自生している植物なので、この地域気候の特徴をよく考えて栽培をしなければ、きれいな花や芳香を楽しむことが難しくなってしまいます。
初心者にとっては栽培が難しいとされていますが、ある程度の知識があれば十分に栽培が可能と鳴っています。とくにヤコウボクなどは一般にかなり普及しているので、ホームセンター等でも育て方の説明を受けることができるので、様々な情報を収集することが可能です。
またケストルムは鉢植えで育てるのが一般的であるとされていて、寒い地域で栽培する場合には日中は外で陽の光に当てておいて、気温が下がる夜の時間帯は屋内で育てるなどの方法があります。花の特徴としてはやや垂れ下がっていて、赤紫色の筒状の花が特徴的ですが、
花自体の大きさは3センチ程度と小さく、香りがあまりないのですが、ベニバナヤコウカという別名があるので、夜になると芳香を楽しむことができる品種となっています。ケストルムはナス科の植物なので淡い色の花をつける品種が多くあります。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:コマクサの育て方
タイトル:コバイモの育て方
タイトル:皇帝ダリアの育て方
-

-
レティクラツム・オウァリウムの育て方
この花についてはキツネノマゴ科、プセウデランテムム属となります。園芸上の分類としては熱帯植物です。また暖かいところに生息...
-

-
ヒメツルソバの育て方
ヒメツルソバは原産国がヒマラヤの、タデ科の植物です。姫蔓蕎麦と書くことからも知れるように、花や葉が蕎麦の花に似ています。...
-

-
ヒイラギナンテンの育て方
ヒイラギナンテンの原産地は中国や台湾で、東アジアや東南アジアを主な生息地としています。北アメリカや中央アメリカに自生する...
-

-
ミヤコワスレの育て方
ミヤコワスレ日本に広く生息している花ですが、もともとはミヤマヨメナという植物を指しています。日本では広く分布している植物...
-

-
イチゴを種から育てる
甘酸っぱい味わいが特徴のイチゴの栽培方法として、市販されている苗からの育て方が一般的ですが、種から育てる楽しさも子供たち...
-

-
へらおおばこの育て方
へらおおばこは我が国に在来しているプラントのオオバコの仲間であり、またオオバコに似ているとされていますが、へらおおばこは...
-

-
セアノサスの育て方
セアノサスはカナダ南部や北アメリカにあるメキシコ北部が原産となっています。花の付き方が似ているという理由から、別名をカリ...
-

-
パンジーの育て方
パンジーの原産はヨーロッパで、生息地は世界世界各国に広がっています。パンジーは交雑によって作られた植物です。その初めはイ...
-

-
柑橘類(交雑品種)の育て方
柑橘類は遡ること3000万年という、はるか昔の頃から、インド東北部を生息地として存在していたものです。中国においては、4...
-

-
パセリの育て方
その歴史は古く、紀元前にまでさかのぼります。特徴的な香りにより、薬用や香味野菜として使われてきました。日本には、鎖国時代...




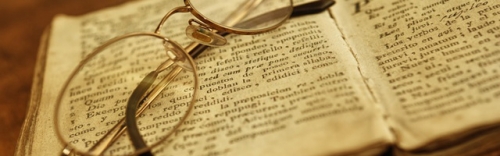





ケストルムはアメリカの熱帯地帯でよく見られる常緑樹でその中でも園芸用の品種として栽培されているのは10種類程度であるとされています。基本的には原産地はメキシコやチリ、西インド諸島などの熱帯の地域であるとされていて、それらの国々からアメリカの熱帯地域に広まったと考えられています。