クロッサンドラの育て方

育てる環境について
クロッサンドラは熱帯植物なので、基本的に夏に非常に強い品種なので、ジメジメとしていて高温である日本の夏にも対応することができますが、直射日光を浴びすぎると、葉焼けをしてしまうこともあり、また、直射日光が原因で株が弱くなってしまうこともあるので、
夏の間だけでも半日陰の場所に移動させることが望ましいです。しかし、暑いところが好きな品種なので完全に日陰の場所はあまり好ましくなく、また風通しの良いところに置く必要はないほど、湿気には強い品種なので、夏以外の季節であれば、日当たりの良いところを条件に置く場所に困らない品種です。
湿気にも強いですが、冬の乾燥にも強く、花は咲かないながらも温度にさえ気を配り、過度な冷えを防ぐことで、また夏に向けて花を咲かせる準備をきちんと行ってくれます。しかし、8度以下の環境に置くと、花はしぼみ、咲かなくなってしまうので、
寒さに厳しい日本では一年草として扱われることも多くあります。花がしぼんでしまった際には、茎ごと切り取ってしまうのが望ましいです。切り取らなかった場合、そのしぼんだ花を修復しようと栄養がその花ばかりに集中してしまい、
株への栄養が後回しになり結果、株が悪くなってしまう原因になってしまうので、定期的にしぼんでいる花がないかのチェックをし、茎ごと切り取るという作業をし、翌年に向けて花が綺麗に咲く環境を整える育て方をすることで長い年月咲かせることができます。
種付けや水やり、肥料について
植え付けは花が咲く6月~10月に向けて、4月から行うことができます。肌寒くなってきたり、直射日光が当たるのを避けるために7月までには植え付けを終わらせるのが望ましいです。土はあまり他の種と変わらず、赤玉土6~7:3~4腐葉土の割合で配合した水はけの良い土を使います。
使い回しの土では育ちが悪くなることがあるので、必ず新しい土を使用することが大切です。冬を越した株も、春先には3分の1から半分ほど土を新しいものに入れ替える必要があります。水やりは土が乾いてきたらあげる程度の基本的な水やりの仕方で構いません。
しかし、梅雨の時期は多湿になりすぎてしまう傾向があるので、水やりを少し控えることで多湿により根枯れを防ぐことができます。鉢植えの場合は、受け皿に水が溜まっていれば、必ず捨てるようにしてください。受け皿に長時間水が溜まっていることにより、
過度な多湿の環境に似た環境になるので、それも根枯れの原因になってしまいます。肥料は春から秋の成長期、具体的には4月~7月、間をあけて9月~10月に月に3回ほどのペースで緩効性化成肥料の置き肥をあげることが望ましいです。追肥をすることで、
花付きがよくなるので、葉の存在感に負けない大きめの花が咲く確率があがります。それでもやはり個体差が激しい花なので、小さめの花になってしまうこともありますが、それは個体差の問題であり、育て方になにか間違いがあったわけではありませんので、心配しないでください。
増やし方や害虫について
寄せ植えをすると見栄えのする花なので、最初から市販の株を多めに買って寄せ植えをする方も多いと思います。クロッサンドラは、さし木で増やすことも可能な花で、5月~9月にかけて、茎を2節ほど残して切り、切り口から出る白い乳液を流して清潔にしてから新しく清潔な水はけの良い土にさしてください。
さし木は立ち枯れを起こしやすいので、1~2年に1度はさし木で株を更新していくと良いです。さし木の株は成長が早いとされ、親株よりも早く花を咲かせることが多くあります。理由としてはさし木の子株は、そのさし木をした場所の気候に合わせて順応するので早いという説があります。
しかし、やはり花の数や大きさは親株の方が多かったり大きかったりなど、長所短所が分かれます。害虫については、虫が多くなる時期に咲く花なので、カイガラムシが多くつく場合があり、温室などの温かい環境で育てていればオンシツコナジラミという虫が葉につきます。
カイガラ虫は殺虫剤は防虫剤などの通常の虫対策で追い払ったり防ぐことができますが、オンシツコナジラミは殺虫剤などに強いので、ハエトリ紙などで直接取り、駆除していくことが求められますが、やはり株が多きなってくると手間になるので、
あらかじめ親株を買う際には、市販されているものの中でも適用害虫にオンシツコナジラミが書かれているものと書かれていないものがあるので、書かれているもののほうを選んで買うことで、少しは防ぐことが可能です。
クロッサンドラの歴史
クロッサンドラは、促音を抜いたクロサンドラとしても呼ばれ、その名前の由来はギリシャ語で房飾りを意味する「Krossos」と雄を意味する「aner」が語源となっています。他にも夏のろうそくという意味でサマーキャンドルともよばれており、熱帯性の植物で原産は南インド地方です。
日本には大正時代の1912年にやってきたので、日本で見られるようになってから100年以上の割と長い歴史を持つ花です。クロッサンドラの種類は大変豊富で、園芸用によく使われている低木だと50種類以上もあり、ほかにも多年草として扱われます。
主な品種としては、良く流通しているものですと、橙色の花を咲かせるトロピックフレームです。橙色のものは他のものと比べ花付きも良いので、園芸用として見栄えがするので重宝されています。また、黄色の花を咲かせるトロピックイエロースプラッシュ、イエローバタフライ、プンゲンスなどの品種があり、
花としては珍しく翡翠色の花を咲かせるリフレブルー、他にも通常のものよりも大輪を咲かせることができるスーパーキャンドルなど多種多様な品種が出回っています。翡翠色のクロッサンドラの中の一部は、実際はクロッサンドラではない花であるエクボリウムという花であります。
エクボリウムという名前では売れないので、似ているクロッサンドラの名前で売り出したことで、クロッサンドラとして購入する人が増えたようです。生息地である熱帯性の植物らしい、ワックスがかかったような葉のツヤツヤ感が気に入って、
花壇のポイントとして植える方も多いですが、どうしてもその葉のツヤツヤ感で熱帯の雰囲気が出てしまうので、温帯の淡い色の花との見栄えは悪くなりがちで、同じ熱帯の原色に近い花を一緒に植えてあげることで見栄えが増します。
クロッサンドラの特徴
クロッサンドラは、葉の付け根から茎をのばし、小さなうろこ状の花を重ね合わせたような花を咲かせます。大きな特徴はそんな特徴のある花の形ももちろんですが、そのツヤツヤの葉にあります。熱帯植物特有の葉であり、実際に育ててみると、花が目的であったのに、
花は思ったよりも小ぶりで、葉の方が目立ってしまったということが少なくありません。この花は個体差が大きく、変異することも多い花なので、花が小さく育ってしまったということが珍しくないのです。花が目的で育てるのであれば、
できれば大輪を咲かせるような種類のクロッサンドラもあるので、そちらを栽培する方が見栄えを気にする上では良いかと思います。また、花は基本的に日本で育てているのであれば、10度以下になると、枯れてしまうのですが、ビニールハウス内などの温度調節ができる場所で、
10度以上を保てば多年草であるので、年中花を楽しむことができるのもこのクロッサンドラの特徴です。一口にいっても、クロッサンドラの種類は豊富であるが故、それぞれ特徴も少しずつ違ってきます。たとえば、黄色の花を咲かせるアフリカ地方原産のプンゲンス種は、
葉に特徴があり通常深い緑色一色の葉をしているのですが、この種は葉脈部分が銀白色であり、通常のものよりも明るい雰囲気です。また、フラーバ種は、クロサンドラの中でも小型のもので、草丈は20cmほどで止まるので、あまり主張しすぎるような雰囲気が苦手な方にも扱いやすい品種です。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ケストルムの育て方
タイトル:ゲウムの育て方
-

-
シンボルツリーとしても人気の植物「オリーブ」の育て方
オリーブは常緑性のモクセイ科の植物で、原産国は中近東・地中海沿岸・北アフリカと考えられています。樹高は10~15mで、最...
-

-
スネールフラワーの育て方
スネールフラワーの原産地や生息地は中央アメリカから南アメリカの熱帯地域です。ベネズエラであるというのがよく言われているこ...
-

-
アガスターシェの育て方
アガスターシェは、初心者でも簡単に育てる事のできる、シソ科の花になります。別名が沢山ありまして、カワミドリやアガスタケ、...
-

-
より落ち着いた雰囲気にするために 植物の育て方
観葉植物を部屋に飾っていると、なんとなく落ち着いた雰囲気になりますよね。私も以前、低い棚の上に飾っていましたが、飾ってい...
-

-
チャボリンドウの育て方
チャボリンドウは、アルプスやピレネー山脈の草地原産の常緑の多年草です。チャボといえば、茶色を基調とした鶏の色をイメージす...
-

-
トキソウの育て方
ラン科トキソウ属の山野草です。和名は朱鷺草(トキソウ)で、別名には朱鷺蘭(トキラン)などがあります。日本の本州や北海道を...
-

-
フキ(フキノトウ)の育て方
植物というのは古来より、食用として育てられてきました。食べ物としてとることによって、人間の栄養になり体を作っていくことが...
-

-
ニオイヒバの育て方
ニオイヒバはヒノキ科 の ネズコ属に属する樹木です。原産国は北アメリカで、カナダの生息地です。日本では「香りがあるヒバ」...
-

-
ハベナリアの育て方
ハベナリアはラン科の植物で、草丈は15cmから60cmほどになります。洋ランの中でもその品種が非常に多い植物でもあります...
-

-
エゾギク(アスター)の育て方
中国や朝鮮が原産の”アスター”。和名で「エゾギク(蝦夷菊)」と呼ばれている花になります。半耐寒性一年草で、草の高さは3c...




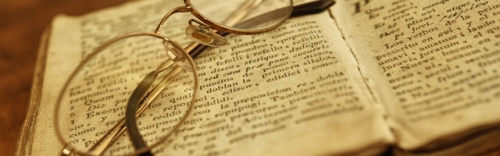





クロッサンドラは、促音を抜いたクロサンドラとしても呼ばれ、その名前の由来はギリシャ語で房飾りを意味する「Krossos」と雄を意味する「aner」が語源となっています。他にも夏のろうそくという意味でサマーキャンドルともよばれており、熱帯性の植物で原産は南インド地方です。